
『出前館—日本のフードデリバリー革命』後編調査ノート飲食業界編⑥全6話
「出前館は、日本のフードデリバリー業界の未来をどのように描き、実現しようとしているのか?その展望と課題を探ります。」
――前編では、「出前館」という日本発のフードデリバリーサービスが、2000年の創業以来“出前文化”をインターネットと融合させてきた歴史や、日本ならではの飲食店との結びつきを活かして、独自のポジションを確立してきた軌跡を紹介しました。さらに、海外勢(Uber Eatsなど)との競合が激化する中で、出前館が掲げる「食をもっと手軽に、もっと楽しく」という理念が、利用者・飲食店・配達員それぞれにメリットをもたらす仕組みを確立しているのだと見えてきました。今回の後編では、この出前館が未来をどのように描き、どのような戦略やテクノロジーを用いてフードデリバリーの新時代を切り拓こうとしているのかを深掘りしていきたいと思います。
前編はこちらから👇
●飲食業界編
①『食の未来を創る—飲食業界の全体像と代表企業』
②『ケンタッキー・フライド・チキン—11種類のスパイスが生んだ伝説』
③『タリーズコーヒー—シアトル発、日本流のコーヒーカルチャー』
④『サイゼリヤ—低価格×高品質を実現したイタリアンの魔法』
⑤『カゴメ—トマトの力で食文化を変えたパイオニア』
⑥『出前館—日本のフードデリバリー革命』
全6話でお届けします!
サイトマップはこちらから👇

私(ユキ)は夜ふかし続行中。いつものようにソファでうさぎの姿の“うさぎ先生”と一緒に、「ビジネスモデル調査ノート」の続きを書くために盛り上がっています。先生は闇の組織によってウサギの姿に変えられてしまった元大学教授で、飲食やマーケティングに詳しいときてる。「前編を読んだ人からは ‘出前館ってUber Eatsに押されてるって聞くけど、実際どうなの? 将来性あるの?’ って疑問もあるかもしれないね」と先生は耳をピョンと動かしながら笑顔を見せます。そこで後編では、AIやドローンといったテクノロジーの活用や、ゴーストキッチン・サブスクリプション型サービスなどを軸に、出前館がどう未来を描いているのか、そしてフードデリバリー業界全体の課題や可能性は何なのかを探ってみましょう。

1. テクノロジーの進化がもたらすフードデリバリーの未来
1.1 AIによる配達ルート最適化や需要予測の精度向上
フードデリバリーの効率とコストを左右する大きな要素が、配達ルートの設定と需要予測です。前編で、出前館は日本の昔ながらの出前文化をオンライン化することで支持を得てきたと話しましたが、海外勢が持ち込んだAI技術の分野では後れを取っているという指摘もありました。近年、出前館もこの分野への投資を加速しています。うさぎ先生はソファでまったりしながら、「AIが配達員の経路をリアルタイムで最適化し、渋滞情報や店舗の調理時間を考慮して複数の注文を効率良く配達する仕組みを導入し始めているんだ。これにより配達員の待ち時間や移動コストを減らし、ユーザーの待ち時間も短縮できるようになる」と解説します。
私が「なるほど、今までは配達員が店舗と配達先を行ったり来たりして大変そうでしたけど、AIの指示があれば ‘近所の複数注文をまとめて’ 配れるわけですね」と納得すると、先生は「そうさ。加えて需要予測もキーになる。何時頃、どの地域でどれくらい注文が入りそうかをAIが分析すれば、配達員の配置を事前に最適化できる。出前館はすでに莫大な注文データを持っているから、その解析を進めればUber Eatsに劣らない高度なシステムが組めるはずだよ」と語ります。
たとえば天候やイベント情報を踏まえて「今日は雨だから宅配需要が増える」「近くの花火大会の日は夜の注文が集中する」などを事前に予測し、配達員のシフトや在庫管理を最適化する。これが“AIによる需要予測”で、成功すれば労働環境の改善や売上の最大化に繋がるわけですね。先生は「現時点では完璧に機能しているとは言い難いが、出前館もデータサイエンス人材を積極採用し、この分野を強化していると聞くよ」と耳をピクピクさせています。

1.2 ドローンデリバリーの実現に向けた取り組み——可能性と課題を考察
フードデリバリーの未来像を語る上で外せない話題のひとつが“ドローン配達”。海外ではAmazonやGoogle子会社のWingなどがテスト運用を始め、日本でも法整備が進めば実現可能と言われています。出前館も過去にドローンデリバリーの実証実験を行ったというニュースが話題になりました。うさぎ先生いわく、「離島や山間部など、人力や車での配送が難しい地域にドローンを飛ばして届けるプランが検討されているんだ。だが、まだ規制や安全面のハードルが高いので、すぐに全国実用化とはいかないだろうね」と解説します。
私が「もしドローンが普及したら、都心の高層マンションに空からピザやお寿司が届く未来が来るんでしょうか…。それはすごくSF的でワクワクしますが、落下事故や騒音など課題もありそう」と指摘すると、先生は「そうなんだ。飛行許可や騒音対策、宅配ボックスの設置などクリアすべき問題は多数あるし、費用対効果をどう見るかも不明。とはいえ、出前館が積極的に参入する可能性は十分あるよ。 ‘日本一出前文化に根差した企業’ としてドローン技術を活かせば、離島や災害時の物資運搬にも貢献できるかもしれない」と語ります。
要するに、ドローンデリバリーは“地理的障壁を超える”利点がある反面、社会的合意や安全対策を伴うため、中長期的な課題として存在しています。出前館の実験的取り組みが成功すれば、フードデリバリー業界全体が一気に変わる可能性があるというわけです。
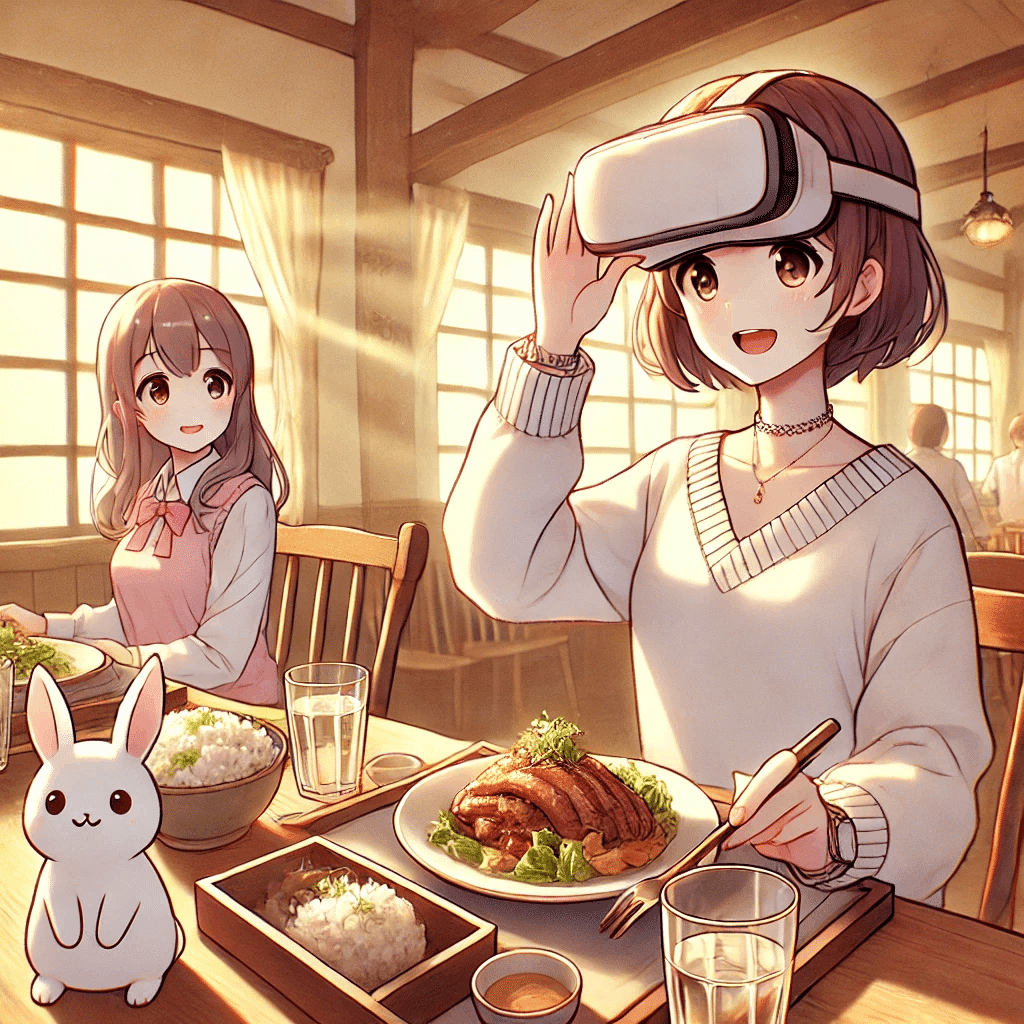
1.3 VRやAR技術を活用した新たな顧客体験の創出
フードデリバリーとVR/AR(仮想・拡張現実)は一見関係なさそうですが、“メニュー選びや飲食体験の拡張”として興味深いアイデアが議論されています。先生は「たとえば、VR空間上で飲食店の店内をバーチャル体験しながら注文したり、ARで料理の3Dビジュアルをテーブル上に投影してサイズや盛り付けを確認したりする仕組み。これが普及すれば、ネット注文の ‘写真だけ’ よりも実感を得やすいかもしれない」と教えてくれます。
私が「確かに ‘これぐらいのボリュームかな?’ とか ‘彩りがいいな!’ とか、VR/ARで見られれば選びやすそうですね。…でも、実用にはそれなりの設備やアプリが必要ですよね」と疑問を挟むと、先生は「そう。まだコストも手間もかかるし、現時点ではニッチな試み。だが、出前館や飲食店が協力して ‘ARメニュー’ を用意すれば、ユーザーはスマホをかざすだけで料理の完成イメージを見られるようになるかもしれない。そこが将来的な差別化要素になるだろうね」と耳を動かす。こうした先端技術がフードデリバリーに投入されれば、ますます“おうちレストラン”体験が深まることは間違いなさそうです。

2. ゴーストキッチンとの連携によるメニューの多様化
2.1 ゴーストキッチンとは何か? その仕組みとメリット
近年、コロナ禍を経て一気に注目されているのが“ゴーストキッチン”です。客席を持たず、調理場のみを備えてデリバリーやテイクアウト専用で運営する飲食店形態のこと。先生は「アメリカで一気に広まったが、日本でも都市部を中心にゴーストキッチンが増えている。こうした店舗は家賃や人件費を抑えられるため、低リスクでメニューを拡充しやすいメリットがあるね」と解説します。
私が「なるほど、実店舗だと席を用意したり内装を整えたりしてコストがかかりますもんね。ゴーストキッチンだと‘デリバリー特化メニュー’を複数ブランドで展開できるって仕組みでしたっけ?」と問いかけると、先生は「そうさ。キッチンスペースを間借りして、同じ調理スタッフが『ハンバーガーブランド』『タコスブランド』『和食ブランド』などを同時に運営する例もある。店舗名もオンライン上のブランドなので、実際どこで調理されているかはユーザーには分からない」と補足します。
ここで出前館が重要な役割を果たす。ゴーストキッチンは集客をすべてネット頼みなので、“プラットフォーム”となる出前館やUber Eatsに登録して顧客を獲得するわけです。先生は「出前館がゴーストキッチンオペレーターと連携すれば、メニューの多様化が一気に進む。利用者から見れば ‘また新しいブランドが登場した!’ と注文できるが、実は同じキッチンで作られているケースもあるという面白い構造さ」と語ります。

2.2 出前館とゴーストキッチンの連携による新たなビジネスモデル
日本国内でも大手不動産や外食チェーンが、ゴーストキッチン専用の施設を続々とオープンしている。出前館としては、こうした拠点と連携し、“ゴーストキッチン内での調理から配達まで”を手がけるパートナーシップを結ぶことで、メニュー多様化と配達コスト削減の両立を狙えるわけですね。先生は「たとえば出前館が『○○エリアのゴーストキッチン拠点』を囲い込み、そこで複数ブランドを展開すれば、配達ルートの効率が上がる。同じ施設から違うジャンルの料理をまとめて運ぶことも可能だから、ユーザーの注文が集中しても対応しやすい」と分析します。
私が「そうか、出前館側はゴーストキッチンと共同でメニュー開発するなんてこともありそう。 ‘和食×イタリアンの融合メニュー’ を期間限定で出すとか、遊び心のある企画もできそうですね」と想像すると、先生は「うん。従来の飲食店だと業態変更が大変だが、ゴーストキッチンならブランドを増やすのも比較的容易。出前館がプロモーションを支援すれば、『このブランドは出前館だけで頼める新作デリバリー専門店ですよ』みたいな形で差別化できる。ユーザーにとっては選択肢がさらに広がるわけだ」と語ります。

2.3 消費者のニーズに応えるためのメニュー開発と戦略
ゴーストキッチンとタッグを組む利点は、“消費者ニーズに素早く対応できる”こと。例えば、コロナ禍で健康志向メニューやおうち居酒屋セットの需要が高まったときに、ゴーストキッチンで新ブランドを立ち上げ、出前館で提供すれば短期間でヒット商品を作れる可能性がある。先生は「既存店だとメニュー変更には人員教育や仕入れルートの見直しがいるが、ゴーストキッチンは変化に対応しやすい。出前館がユーザーデータを活かして ‘このエリアは麺類が人気’ と分析して新ブランドを提案することも考えられる」と耳を動かします。
私が「なるほど、過去の注文履歴とかエリア別の売れ筋を見れば ‘こってり系ラーメンが足りてない’ とか分かるかもしれないですね。それをゴーストキッチンで即導入すれば、競合なしでバカ売れするかも…」とワクワクすると、先生は「そうさ。データドリブンでメニュー開発を行い、ゴーストキッチンで実験的に展開、出前館が集客と配達を担当する――そんな新ビジネスモデルが普及すれば、日本のデリバリー市場はまだまだ成長余地があるよ」とまとめます。

3. サブスクリプション型サービスの拡大と今後の展望
3.1 サブスクリプションモデルのメリットとデメリット――フードデリバリーへの適合性
近年、音楽や動画配信、ソフトウェアなど様々な分野で“サブスクリプション(定額制)”が流行っていますが、フードデリバリーにもサブスクを導入する動きが見られます。たとえば海外では、「月額いくらで配送料が無料になる」サービスを展開している例があります。先生は「出前館も ‘配送料定額サービス’ を試験的に行ったり、クーポンやポイントシステムでリピートを促したりしている。サブスクモデルが広がれば、ユーザーは一ヶ月の固定費で何度も注文できるから心理的ハードルが下がるかもしれないね」と語ります。
私が「なるほど、何度も注文すると送料だけで結構な額になりますもんね。定額で配送料がゼロなら ‘面倒だから今日はデリバリー頼もう’ という回数が増えそう。でも配達員の負担はどうなるのか気になります」と懸念を示すと、先生は「そこが難しいところだね。サブスクでユーザーはお得感がある一方、運営会社は収益を確保しつつ配達員への報酬をどう維持するかを考えなくてはならない。利用が多すぎると配達コストがかさむし、少なすぎるとユーザーが ‘割に合わない’ と感じるバランスが難しい」と解説します。
要するに、サブスクは“ユーザーの注文回数予測”と“配達コスト”をうまくマッチさせる必要があり、AIの需要予測や配達ルート最適化といった技術と組み合わせないと破綻する恐れがある。先生は「出前館が本格的にサブスクを導入するなら、データ解析で『平均注文回数が○回を超える層』をターゲットにプランを設計するなど、精密なマーケティングが必須だろうね」と耳を動かす。
3.2 出前館が提供するサブスクリプションサービスの内容と特徴
実際、出前館は“デリバリーパスポート”といったキャンペーン形式で一定期間配送料を割引にしたり、“使い放題” ならぬ形で配達手数料を何度でも無料にするプランを試験的に行っていたという報道もあります。先生いわく、「まだ大々的には普及していないが、将来的に定額サービスを本格導入するのは十分考えられる。特にリピーターが多いユーザー(例えば週3回以上注文するファミリーなど)はサブスクの恩恵が大きいからね。出前館としても ‘配達費収入’ の安定や、他社との差別化に繋がる可能性がある。」
私が「たしかに ‘毎回300円前後の配達料がかかるところが月1000円で無制限なら、3〜4回頼めば元が取れる’ と計算する人は多いでしょうし、そこに何か特典メニューやポイント還元があれば惹かれますね」と想像を膨らませると、先生は「うん。ただ、多すぎる利用があると配達負担が増して利益が出なくなるリスクもあるし、配達員の報酬体系をどうするかが課題。仕組みをうまくデザインしないと逆効果になりかねない。でも成功すれば ‘出前館ならサブスクでお得に頼める’ と話題になってシェアを伸ばすかもしれない」とまとめます。

3.3 今後のサブスクリプションサービス拡大に向けた課題と解決策
サブスク導入が進めば、出前館は安定収益と利用者ロイヤルティを得られる可能性がありますが、同時に以下の課題も指摘されます。
配達員の待遇・報酬問題:サブスク利用が増えれば配達数が増え、配達員の負担が過度にならないか。十分な報酬を支払うための収益確保が求められる。
飲食店の利益確保:サブスクで配送料無料になっても、飲食店の取り分は確保できるか? 注文が増えれば売上も増えるが、手数料や食材コストもある。
利用者の偏り:ヘビーユーザーが過度に利用して損益分岐を超えてしまうリスク。一定の制限を設けるかどうか。
キャンペーンの差別化:競合も同様のサブスクを導入すれば差別化が難しくなる。出前館ならではの特典や提携ブランドの強みをどう活かすか。
先生は「これらをうまくマネジメントするには、AI需要予測や配達ルート最適化、飲食店や配達員との密な連携が必要。出前館が日本の出前文化を深く理解している利点を活かして、他社とは違う ‘ユニークなサブスクモデル’ を実現できれば、競争の中で生き残る大きな武器になるだろうね」と語ります。

4. フードデリバリー業界が抱える課題と出前館の解決策
4.1 人材不足や労働条件、配達員の安全面への配慮
コロナ禍で急拡大したフードデリバリー市場は、“配達員不足” という問題に直面している。一時期はシフトの確保が間に合わず、ユーザーが注文してもなかなか配達員がいない…という事態もあった。先生は「出前館は独自の配達パートナー制度を用意していて、個人事業主やアルバイトを大量募集して対応しているが、Uber Eatsや他社との配達員取り合いが激化している。報酬やインセンティブをどう設定するかが大きな課題だね」と解説。
さらに、配達中の交通事故や安全管理の問題もある。大都市での配達は渋滞や自転車事故のリスクが大きく、配達員の保険制度や研修が必要だ。私が「Uber Eatsの配達員さんが事故に遭ったとかニュースで見ますけど、出前館は昔からバイク配達の文化があるから、従来から何か対策が整ってるんでしょうか?」と尋ねると、先生は「そう、昔ながらの出前の店が自己責任で配達するケースもあるから一概に比較は難しいが、少なくとも ‘出前館としての配達パートナー’ に対しては保険制度や安全教育を強化していると聞くよ。ただ、業界全体で見るとまだ不十分とも言われている」と耳を動かします。
4.2 環境問題、食品ロス、容器廃棄などへの取り組み
フードデリバリーは“使い捨て容器”が多用されることで知られ、環境負荷が懸念されている。Uber EatsやWoltも含め、プラスチックの削減やリサイクル容器の導入などが課題として浮上中。出前館はこの点で特別な施策を打っているのか、先生は「正直、まだ明確な大規模取り組みは公表されていないが、一部飲食店と連携して ‘返却可能なリユース容器’ を実験したり、 ‘フォークやスプーンを必要な人だけが選択する’ 仕組みをアプリに導入したりする例が出てきているね。環境に配慮した消費者が増える中、容器廃棄をどう減らすかは今後の大きなテーマだろう」と解説。
私が「確かに、毎回配達のたびにプラ容器が出るのは気になっていました。 ‘返却式’ は昔のそば屋の出前みたいに器を回収する仕組みだけど、現代の働き方でそれを維持できるのか…」と疑問を呈すると、先生は「そこが難しい点だよね。昔はご近所の店が器を取りに来たけど、現代はエリアが広がっていて回収が手間。出前館がどこまで介入してサポートするか次第だろうね。各自治体やNPOと連携する余地もある」と語ります。
一方、食品ロスの面でも、デリバリーは注文通りに作るためロスが少ない反面、キャンセルが出たりすると食材が無駄になるケースもある。AI需要予測や在庫管理の連携が進めばロスを減らせる可能性があり、先生は「出前館が飲食店の仕込み量をリアルタイムで管理できればフードロスを最低限に抑えられるが、そこまで踏み込むにはシステム開発と飲食店の協力が必要。今後の進展に期待したいね」とまとめます。
4.3 出前館が抱える技術面・運営面での課題
以上の課題を総合すると、出前館が今後も競争力を維持するにはデジタル技術と社会問題の解決の両方をバランス良く進める必要がある。先生は「技術面ではUber Eatsや海外企業が圧倒的に強い資本力を持っていて、AI開発やドローン実験なども先行している。出前館は日本ならではのネットワークが強みだけど、テクノロジー面の投資を怠れば将来的に遅れを取る可能性があるね」と耳を動かす。
運営面でも、配達員の労働環境整備や飲食店へのサポートを厚くしながら、サブスクやゴーストキッチンなど新事業を展開するには資金と組織体制が不可欠。私が「資金力は日本企業として限界あるかもしれませんが、ヤフー(Zホールディングス)と連携して資本増強も検討してると聞いたことがあります…」と話すと、先生は「そう、経営面ではいろいろと再編や提携が起きている。一時期LINEとYahooの経営統合もあり、出前館とも何らかのシナジーが期待されてる状況だよ。どんな形で安定基盤を築くかがカギだろうね」と言います。

5. まとめ:出前館が描くフードデリバリーの新時代
前後編を通して、出前館というサービスが“日本らしい出前文化をインターネットと掛け合わせる”という先駆的アプローチでスタートし、現在はUber Eatsなど海外勢との激戦区の中で地位を築いているさまを見てきました。老舗飲食店や地元の個人店などを幅広くカバーし、“地域の出前ネットワーク”として多くのユーザーを掴んでいる点が大きな強みです。さらに、今後はAI配達ルート最適化やゴーストキッチン連携、サブスク型サービスなど、テクノロジーと新ビジネスモデルで次のステージを目指すわけですね。
5.1 出前館の強みの再確認
老舗・個人店を巻き込むネットワーク
ピザやチェーン店だけでなく、寿司、そば、ラーメン、定食屋など、昔ながらの出前文化と強固な関係。
海外勢が苦手とする“地場店”の取り込みが得意。
“おうちレストラン”の実践
日本人が電話で頼んでいた出前をネット化し、“いつでも気軽に” を可能に。
寿司やそば、中華などを家で楽しむ従来の文化をアップデートした。
飲食店サポートとパートナーシップ
メニューの写真撮影やデリバリー用商品の提案などを行い、店舗を全面バックアップ。
電話対応不要で販路が広がるメリットを提示し、多くの飲食店とWin-Winを築いている。
5.2 課題と取り組み
技術面(AIやドローン)の追随: Uber Eatsや海外企業が先行するテクノロジーにどう立ち向かうか。
配達員労働環境: サブスクや配達数増加に伴う過労、報酬管理など問題を抱える。
環境・社会貢献: 廃棄容器の削減やフードロス対策、高齢者支援など社会的要請が高まる。
戦略的提携: 競争が激化する中、YahooやLINEなど大手IT企業との連携強化、もしくは資本再編も含めた動きが必要か。
5.3 “出前”から“フードデリバリー革命”へ――今後の展開
今後の出前館が描く“フードデリバリー革命”には以下の要素が入り込んでくるでしょう。
AIで配達網を最適化
需要予測と配達ルート統合により、効率的に多数の注文を裁く。待ち時間減・労働環境改善を目指す。
ゴーストキッチンとの連携でメニューを多様化
新ブランドを低コストで立ち上げ、ユーザーに飽きさせないメニュー開発。
サブスク型サービスの本格導入
定額制で配送料・手数料の割引を提供し、ヘビーユーザーの囲い込みと安定収益を実現。
ドローン・ロボットデリバリーの実験
規制緩和や技術進歩によって、離島や山間部、災害時などでの活躍が期待。都心部での商用展開も将来的に視野。
地域社会・環境への貢献
高齢者支援や地方創生、容器のリユース導入などで社会的価値を高める試み。
うさぎ先生は夜ふかしのリビングで、「ユキくん、出前館は確かに海外勢と比べるとブランドパワーやテクノロジー投資で弱点もあるけど、日本の老舗出前店との結びつきや社会への貢献姿勢は強い。後編で見たように、ゴーストキッチンやサブスクなど新分野に挑戦すれば、まだまだ面白い未来が開けるかもしれないね」と笑顔を見せます。私も「はい! 競合が激しくなってますが、出前館ならではの強みがあるし、日本人がずっと続けてきた ‘おうちで外食の味’ をどう次のステージに進めるか楽しみです」と共感します。

専門用語の解説
AI配達ルート最適化
配達員の経路をAIがリアルタイムで判断し、最適化する技術。渋滞状況や注文数、調理完了時間などを総合的に考慮し、配達時間短縮やコスト削減を狙う。ドローンデリバリー
無人航空機(ドローン)を使って商品を届ける仕組み。地理的・法規制・安全性など多くの課題があるが、将来的には離島や山間部、都市部でも活用が期待されている。ゴーストキッチン
飲食店の調理場のみを備え、客席を持たない業態。デリバリー専用のブランドを運営し、低コストかつ柔軟にメニューを展開できる。出前館などのデリバリーサービスと提携することで、幅広い顧客にアクセスが可能。サブスクリプション型サービス
月額・年額など一定料金を支払うことで、配達料やサービス料を定額化または割引にするビジネスモデル。フードデリバリーでは配送料定額プランなどが考えられている。デリバリーパスポート
出前館が試験的に行っているキャンペーン名称(あるいは類似の定額プラン)で、一定期間配達料を無料または割引にする仕組み。フードロス
消費されずに廃棄される食品。デリバリーにおいては注文キャンセルや在庫管理ミスなどで発生する。出前館などプラットフォームがAI予測を駆使すれば減らせる可能性がある。高齢者支援 / 買い物弱者
交通手段が限られる高齢者や地域住民に、デリバリーサービスが生活必需品や食事を届ける取り組み。自治体と連携して地域のインフラとして機能する例が増えている。
次回予告
「出前館—日本のフードデリバリー革命」後編をもって、飲食業界編第6話を締めくくります。前編では歴史や理念、国内老舗飲食店との関係を、後編ではAIやゴーストキッチン、サブスクなど未来指向の取り組みを中心に紹介しました。海外勢との競合が激化する中、出前館が“日本らしさ”を強みとして、どのような技術投資やビジネスモデルで新時代を生き抜くのか――大いに注目していきたいところです。
飲食業界編はここで一区切りとなりますが、私(ユキ)と“うさぎ先生”の夜ふかし対話はまだまだ終わりません。次のシリーズでは、あるいは新たなテーマや業界を取り上げ、また別の角度からビジネスモデルを探究する予定です。もし本記事を読んで「日本の出前文化ってすごい!」とか「カゴメやサイゼリヤみたいに、食が社会をどう変えるのか気になる!」と思ってくださったら幸いです。
うさぎ先生は夜のリビングで耳をピョコピョコ動かしながら、「ユキくん、今回もお疲れさま。出前館の話を通じて ‘フードデリバリーってこれからどうなるの?’ って視野が広がったんじゃない?」と声をかけてくれます。私も「はい、なんだかゴーストキッチンとかAI配達とか、面白い要素がいっぱいで驚きました! 次にデリバリーを頼むときは、その裏でどんな仕組みが動いているのか意識しちゃいますね」と笑顔で返事。そんなふうに、私たちの“ビジネスモデル調査ノート”はまた一歩進んだのでした。
次回はお悩み相談を挟んだ後、再び本編の『うさぎ先生とユキちゃん』マーケティングの週です!

サイトマップはこちらから👇

『うさ×ゆき』の支援をお願いします🙇
記事の購入やメンバーシップは余裕のある方だけで構いません。ストーリーで学べるコンテンツを幅広く使っていただける様にいいなと思っていただけた方はスキ❤️やシェアいただけると幸いです。
#眠れない夜に #歴史 #企業の歴史
#うさぎ先生とユキちゃん
#飲食業界 #学び #出前館 #UberEats #デリバリー
いいなと思ったら応援しよう!

