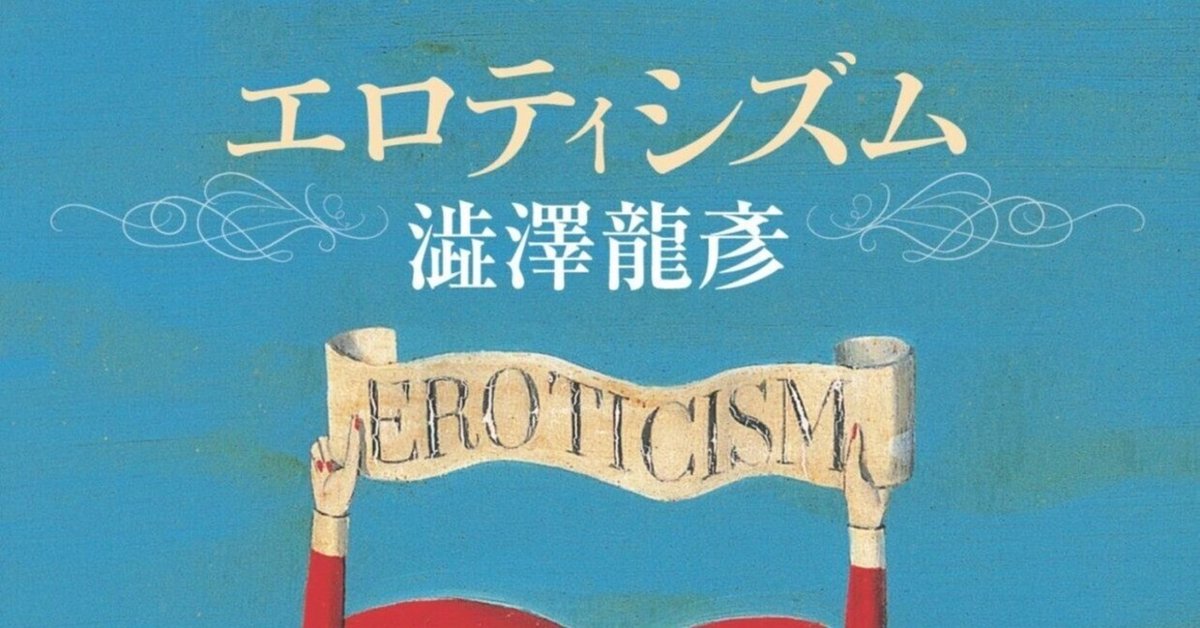
エロティシズムをセクシュアリズムから切り分けた男。澁澤龍彦。
「エロティシズム」 澁澤龍彦 (中公文庫)
弱さの打破
仏文学者・渋澤龍彦が著したエロティシズム三部作を代表する一冊。
「エロ」と「エロティシズム」はまったく異なるんだと、盟友の巖谷國士さんが巻末解説で強調されています。性産業としてのエロは、エロティシズムではなくてセクシュアリティの商品化でしかないというわけです。
澁澤龍彦の功績は、エロティシズムをセクシュアリズムから切り分け、精神性のものとして表の世界に堂々と持ち込んだこと。
江戸時代以来、性というものの真相が、陰湿な笑いやくすぐりや猥談にのみ語られて落とし込められてきた。そうした弱さ(=正面切って取り組まない)からくる偏見を打破したいのが澁澤の目的だといいます。
封が剥がれる瞬間
エロティシズムって、人間の「暗部」、つまり、考えてはいけないこととして、自分に封をしていることの表出。
この、自分に封をしているというところがエロティシズムの核。
だから「社会的に禁止されているものの露出」というだけではエロティシズムになりません。それはただの反抗であり、商材エロ。
自分に封をしているので、何に封をしているのか、本人自身もみたことがないもの。それがあるとき、偶然か、異性によって、その封がはがれて、姿を現す。
人間と動物の境が破れる瞬間です。その時、エロティシズムの本質が垣間見れるのです。
「スプートニクの恋人」にも
村上春樹の「スプートニクの恋人」の中に、まさにそれが描かれている有名な場面があります。
性欲がないと自認する主人公の若い女性が夜に遊園地のゴンドラに一人乗っている。そこから自分の部屋が見える。ある時、そこで男と艶めかしい姿態を繰り広げている自分自身を目撃します。
この世でないものに憧れるファンタジーであったり、禁じられているゆえに頭から離れないという、倒錯のエネルギーが本質であるエロティシズムに快楽を感じるのは、そこが解放の地であるから。
幼児期に持っていた甘美な世界への。
不機嫌の正体
近代社会は、動物である人間を、自我とかに押し込めてしまうのが本質であって、動物となんら変わらない存在なのに、人間を強く巧妙に「あるべき姿」にあくせくと追い込む。
ただ、それは常に達成されるわけではないので、誰しも鬱屈して不機嫌です。その不機嫌の原因でさえ自分で気がつかない。
澁澤はとにかくそういうのが大嫌いで、権威性がついちゃって「あるべき姿」に成り果てた不機嫌なメインストリームの芸術に対してのアンチの気持ちが強い。
人間の内面の自由を目指したこの反近代の人は、侠気あふれる、仲間思いの陽気な人情家でもありました。
あの黒サングラス姿と硬質な文体はそれとはまったく裏腹なイメージ。
それらは、少年のような風貌とそれに違わない純な内面を守るための、大切な装いだったのかも知れません。


表紙絵/金子國義


