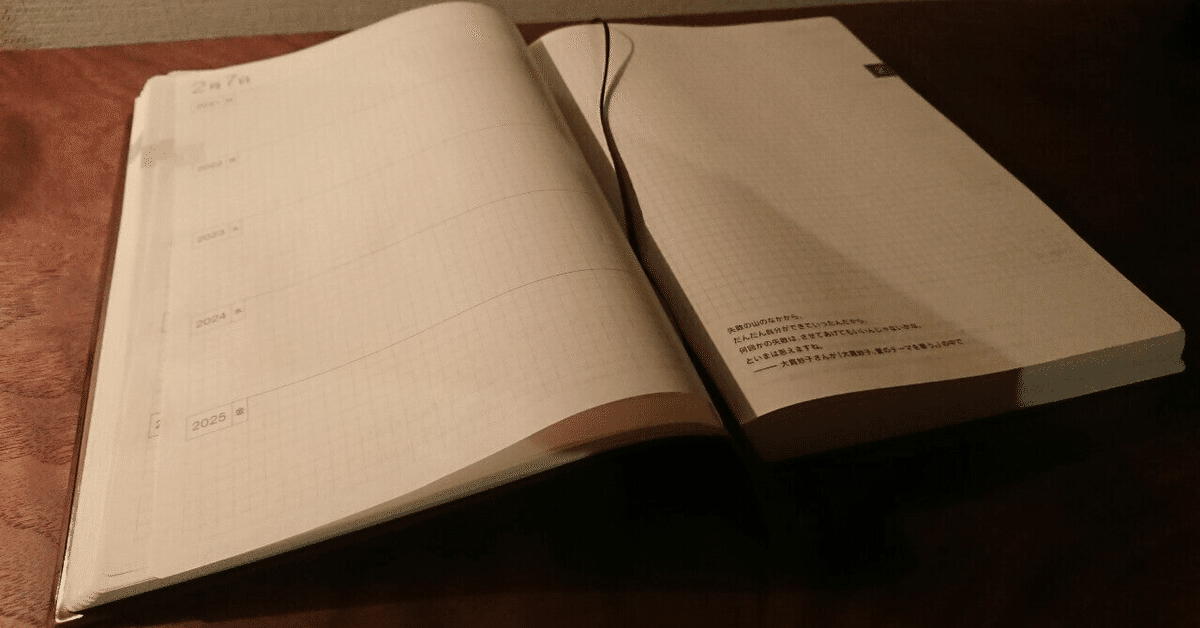
戦争論 ―体験と記憶、伝えるをカタチにしたとき―
レポート課題
「テレビ作品の『”ヒロシマ”が伝わらない』『ヒロシマの伝言』『赤い背中』をふまえて、原爆投下による被爆という出来事の『体験を風化させない』『記憶を伝える』ということについて、批評すること。」
今回のレポートの趣旨
レポート課題としてあげられてるテレビ作品はいずれも2005年8月に放映されたものであるが、この2005年という年は、戦後から60年、震災から10年にあたる節目の年であり、「体験を風化させない」・「記憶を伝える」といことが頻りに叫ばれた年であった。今回のレポートの趣旨はこれらについて批評するということである。
「体験」や「記憶」のもつ性質
「体験を風化させない」ことや「記憶を伝える」といったことを考える際には、まず「体験」や「記憶」といったものそれ自体について、その性質を考える必要があろう。様々な情報がデジタルデータとして保存・複製できてしまう現在において、まるで人々の体験や記憶がそのままの形で人から人へと伝達可能であるパッケージかのような錯覚を起こしているのではないだろうか。人の「体験」や「記憶」といったものは決してそのようなものではないと私は考えている。ある人の体験や記憶を他の人へと伝えようとする際に、必ず必要となるものが「情報媒体」である。おそらく「体験を風化させない」というときや、「記憶を伝える」といった際には、それらの体験や記憶を何らかの情報媒体を用いてカタチのあるものへと「表現」し、そのデータを後世に残し、伝えていくということが具体的な手法となるのであろう。今回講義で取り上げられた「テレビ作品」もその具体例の一つといえよう。情報媒体という言葉を用いた訳であるが、ここで更に考慮すべきことは「情報媒体」は、そのジャンルを問わず、何らかの「作品」であるということである。つまり私たちが「体験を風化させない」・「記憶を伝える」といった際には、それらに情報としての形式を与えてる「作品」というものの性質についても十分に理解しておく必要が生じてくるということになる。今回の議論においては「体験」・「記憶」、そして「作品」の3つがキーワードとなるのではないだろうか。
「作品」とは、体験や記憶に「加工」を通じてカタチを与えるもの
まずは「作品」というものの性質から考えてみることにする。私たちが人の体験や記憶を得ようとするとき、必ずと言っていいほどその仲介役を果たすのが「作品」というものである。あるできごとの体験や記憶を人に伝えようとする際の作品とは、何もテレビやラジオ、映画や著書といったものだけではない。口頭での講演や通常の会話ですら、ある種の「作品」であると私は考えている。それらには、必ず制作者や語り手の「出来事に対する加工」という作業が加わっていると見なすことができるからである。体験や記憶を他者に伝える第一段階は、それらを「言葉」或いは「文字」にのせることから始まる。体験や記憶といったものは、その「加工」という作業によって初めて他者に伝えうる「カタチ」を持ったものへとその姿を変える。まずはその過程を経なければ、その人の体験や記憶が他者にふれることはない。その加工に際して必要となるエネルギーには程度の差はあるであろうが、ここで私が強調しておきたいことは、体験や記憶は何らかのカタチを持ったものへと加工を施さない限りは他の誰かに伝えることが不可能であるという事実である。
作品を「加工」するとは?
では、「加工」するというのはどういうことなのであろうか。加工されたそれらの情報は当然のことながら整然とした形式を持ち、他者が理解しうるようにしっかりと整理されていなければならない。そのためには、加工を行うもの自身がまずはしっかりと自らの体験や記憶を整理した上で、深く理解をしておかなければならない。それはその体験の当事者=記憶の保持者にとっては、相当な負担であるはずである。多くの場合、戦争を肌で体験した人の記憶は「恐怖」と直結しているからである。ここで問題となるのが「記憶」というものの性質である。
記憶における「定義」と「再定義」
そもそも「記憶」とはどういうものであるのか。周知の通り日常におけるすべての体験がそのまま記憶として残る訳ではない。正確には、記憶として思い出せる訳ではない。記憶には何らかの強烈な「心象(イメージ)」を伴うことが多い。言い換えれば強烈な心象を伴って思い出されるものが記憶というものであり、その心象の意味を解していることによって、初めて思い出すことが可能となるものである。出来事を理解するということは、その出来事を「定義」するということと同義であり、さらに言及すれば、ある記憶を思い出すとき、そこには必ず「再定義」という過程が必要となる。当事者の体験や記憶を、情報媒体を通した作品という形式に置き換え、さらにそれを他者である視聴者や読者、或いは聴衆といった人々がそれぞれの「感性」によって受け取ることにより、初めて「伝える」という行為が成立したということができる。繰り返しになるが、人の持つ記憶というものはデジタルデータのように簡単に受け渡し可能であるようなパッケージではないということである。また、当事者の持つ心象と、それを加工された作品を通すことによって第三者の中に再定義・再構築された新たな心象とは、当然のことながらイコールの関係ではない訳である。
「記憶を伝える」という行為の残忍性
ここまで考察してきたときに、人々の体験や記憶を、風化させない或いは伝えようとするとき、人から人へと語り伝える過程には、常に「定義」と「再定義」が繰り返されていくこととなる。作品とは、深い理解の下に定義された体験や記憶を呼び起こし、再定義と再構築を行いながら、体験や記憶をカタチのあるものへと表現したものである。その作品を体験や記憶をカタチあるものとして表現されたものでると捉えた際に、受け手側による感覚と感性とによってその作品は再び定義される。これらの複雑なプロセスからも判るように「記憶」とは伝えることも困難であれば、受け取ることも困難なものであり、簡単に「記憶を伝える」という表現を用いることには注意すべきである。また、そもそも「記憶を伝えなければならない」、「体験を風化させてはならない」というときに、それらの視点は当事者からのものであるより、第三者からのものであることの方が多いような印象を受ける。特に体験の当事者たちにとって、その「記憶」というものを捉えたとき、それらは決して自由に操作可能なものではないということである。また、記憶の保持者にとっては決して過去の過ぎ去った出来事というだけではないことにも目を向ける必要がある。強烈な恐怖としての心象を伴うそれらの記憶は、今を生きる記憶の持ち主にとってはストレスを与えるものであるからである。日常の生活の中で受けたほんの些細な感覚によって、強烈な心象を伴う記憶が一瞬にして再生されてしまうこともある。「思い出したくない」或いは「話したくない」と記憶を封印している人々に対して、「記憶を伝えるべきである」とした際に、記憶の保持者たちに対するケアの視点が欠落しているのではないだろうか。記憶の保持それ自体が心理的な恐怖(ストレス)となっている人々にとっては、「記憶を伝える」という行為はあまりにも残酷な仕打ちであるのではないだろうか。「記憶」は決して引き渡せるものではない。それは同時に自由に消し去ることもできないということを意味しているとも捉えることができる。
「体験を風化させない」「記憶を伝える」とはどういうことなのか?
ここまでの内容をふまえた上で、「体験を風化させない」「記憶を伝える」ということは、なにをどうすることであるのかを再考してみたい。
1)人々の「体験」や「記憶」それ自体にはカタチは存在せず、それ故にそのままでは他の人々が受け取ることはできないということ。
2)それらを語り伝えるためには情報媒体を通じて、カタチを持つものへと再構築された「作品」として「表現」される必要があるということ。
3)記憶とは制御困難なものであり、デジタルデータのように完全な形を保持したまま複写や受け渡し、或いは消去できるようなものではないということ。
4)作品として体験や記憶を語り伝えるということは、語り手と受け手との間において、その出来事に対する「定義」と「再定義」を繰り返していくことであるということ。
ここまでに内容を端的に述べるのであれば、1)~4)のような内容へと概ね集約することができるのではないだろうか。ここまでは「体験」「記憶」「作品」をキーワードに「体験を風化させない」「記憶を伝える」ということについての議論を行ってきた。体験や記憶を語り伝えるためにはカタチあるものとしての表現が必要となる。ここでは表現されたものを作品と呼んでいる訳である。では、原爆投下による被爆という出来事にはどのような表現がふさわしいのか。原爆投下の体験と記憶を伝えなくてはならないといったとき、なにが伝えるべき出来事となり、それをどうカタチあるものへと表現するのか。この問いを考えなければ、今回のレポートの趣旨を満たしたとはいえない。
カタチある「作品」への加工と受け手における再定義・再構築の必要性
原爆投下についての議論は数多くあるといってよいだろう。しかしながら、その多くは投下に対する是か非かをめぐるものである。しばしば戦争は暴力であると定義されるが、多くの議論はその暴力が「必要な暴力」か「不必要な暴力」であるかという二元論によって論点を絞り込まれてしまう。しかし、私たちに本当に求められているのは戦争の善悪についてではなく、「戦争が何をもたらしたのかを考えるということ」ではないだろうか。そのためにはまず、真実、事実、真相を伝えようとする努力が必要であろう。ある出来事(ここでは原爆投下)が起こるまでの過程や直後の結果については比較的伝えられているが、現在とのつながりもたどった<その後>についてはなかなか知らされてはいない。また、戦争をめぐる真実は「悲惨」となりがちであるが、悲惨であるが故に目を背けられてしまうためになかなか伝わらないということも生じている。その一方で、真実の「悲惨さ」がそれを知ったものを動かす・変えるということもある。
原爆投下という出来事を端的に表現するならば「大量の人々が死んだ」「大量の人々を殺した」ということに他ならない。その真相を伝えるには「悲惨さ」抜きでは不可能である。悲惨さなくして戦争は語れないのである。しかし、直接的な表現を用いずともその出来事の意味を表現する手法もある。「奪われたもの・負わされたもの」を表現するというものである。直接的な暴力シーンが存在しない、小説『明日』や映画「TOMORROW/明日」などがその例である。
二元論では論じることのできない「体験」や「記憶」
ここまでをみてくれば、客観的な数値や善悪の二元論によってその結果を論じるだけでは「体験」や「記憶」を語り継いでいくことはできないといえる。人々にもたらした「恐怖」・「奪ってしまった過去と未来」、それらをカタチあるものとして表現すると同時に、表現された作品を受け手が自身の中にしっかりと再定義・再構築していくこと、それができたとき、初めて「体験風化の防止」・「記憶の伝承」が実現したといえるのである。
いいなと思ったら応援しよう!

