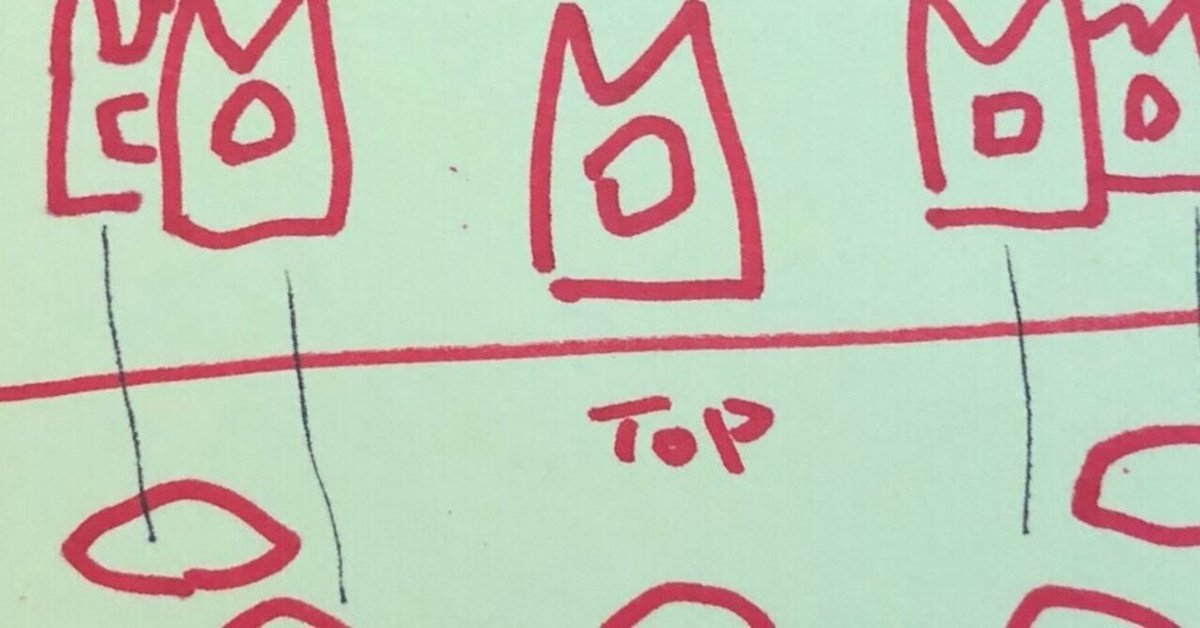
猫には猫の悩みがある
〜前回までのあらすじ〜
90年代のトイザラス(NY店)で、 商品陳列を不思議なルールで勝手に並べ替えてゆくプエルトリコの少年をみたワタシは…
そう、
端的にいいますと「三段オチ」です。
ユーザーは、
「a」を提示された後に
「b」を提示されると、 次の
「c」を予想することができます。
【例】
●ユーザーのココロの動き
――――――――――――
a:「あいう」
b:「あいうえ」
↓
c:「?????」
(次は 「あいうえお」 かな?)
――――――――――――
ここで
――――――――――――
c:「あいうえお」
――――――――――――
を提示してはデザインになりません。ユーザーは、自分の予想が当たることに、最初こそ喜びますが、それが続くようであると「ただの"予想確認"作業」と認識し、あっというまに興味を失ってしまいます。
この場合の
「三段オチ」をつかった
私が理想とするパターンは
――――――――――――
a:「あいう」
b:「あいうえ」
↓
c:「あいうえおかきくけこざじずぜぞ」
――――――――――――
となります。
何故か????
理由は3つ。
■その 1
・ユーザーの予想が当たる喜びをあたえるため
「あいうえお」
└ユーザー:ですよね。うんうん。
予想とおり。わたしさすが!
■その2
・ユーザーの予想を超える驚きをあたえるため
「あいうえおかきくけこ」
└ユーザー:え?一文字づつ増えるん
じゃないの???え?え?
■その3
・ユーザーの驚きに追い打ちをかけるため
「あいうえおかきくけこざじずぜぞ」
└ユーザー:まだあるの?えーーっつ!?
└ユーザー:文字は「清 音(せいおん)」だけ
じゃなく濁点も?!
このように
「ユーザーの予想」に対して「肯定」と「否定(裏切り)」をかぶせてゆくことが程よい刺激となり「作業」でなく「たのしい」が結実してゆくのだとワタシは考えています。
さて
これを拡張してゆきましょう。
A
――――――――――――
a:「あいう」
b:「あいうえ」
c:「あいうえおかきくけこざじずぜぞ」
――――――――――――
↓
B
――――――――――――
a:「かきく」
b:「かきくけ」
c:「かきくけこさしすせそだぢづでど」
――――――――――――
↓
C
――――――――――――
a:「さしすせそたちつてと」
b:「さしすせそたちつてと」
c:「さしすせそたちつてとたちつてとなにぬねのはひふへほ」
――――――――――――
ここでも 「三段オチ」をつかいます。
三つ目の"くくり"である「C」は、
「A」と「B」のパターンから、順当に想像されないものを入れます。
「A」と「B」
――――――――――――
・五十音が、ひとつづ、ずれて使われる
・最初は三文字。
・3セットあって、3つ目は違うパターンがくる
――――――――――――
↓↓
「C」
――――――――――――
【予想通り】
・五十音が、ひとつづ、ずれて使われる
・3セットあって、3つ目は違うパターンがくる
【予想と違う】
・最初は10文字
・”違うパターン”の内容がそもそも違う
――――――――――――
「三段オチ」を曼荼羅のように、ミクロからマクロに繰り返すことで、無限的に構成をまとめることが可能だと思います。
ところで、件のプエルトリコの少年はそのあと 奇妙な陳列をその場に残したまま 、とくにダイムを数えることなく去ってゆきました。
次回は「なまけもの歌」です
~つづく~
