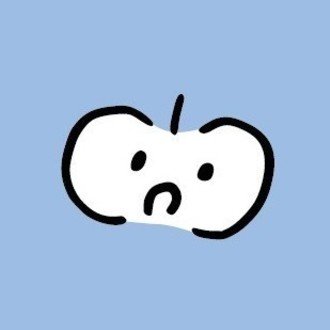書評:加藤雅俊著『スタートアップの経済学』 (経セミ2022年12月・2023年1月号より)
加藤雅俊[著]
『スタートアップの経済学――新しい企業の誕生と成長プロセスを学ぶ』
有斐閣、2022年、A5判、320ページ、税込2860円
評者:元橋一之(もとはし・かずゆき)
東京大学先端科学技術研究センター教授
最新の理論と実証研究を盛り込んだ完成度の高い教科書
我が国においてスタートアップ企業の重要性が指摘されてきて久しい。経済のダイナミクスを示す開廃業率の低さ、創業に対する意欲の低さなど、諸外国と比較した日本の遅れは1990年代から指摘されており、これまでさまざまな対策が取られてきた。その結果として、何らかの変化やその予兆でも見られるのであろうか? このような問題を考えるうえで、本書は時宜を得た好著といえる。
本書では、まず、イノベーションや雇用などの経済ダイナミズムの源泉としてのスタートアップ企業の特性について述べ、主に創業時に着目したアントレプレナーに係る諸問題について解説している。その後、スタートアップ企業を成長させるための組織やイノベーション戦略について触れ、企業の存続や成長についてミクロ経済学的な解説を加えたのちにスタートアップ企業に関する公的支援で締めくくっている。それぞれの内容について、これまでの学術的な研究成果、つまり科学的エビデンスに基づいて解説されており、個々の問題についてより深く考えるための手引きにもなっている。また、各章においては、最初にいくつかの質問が提示され、最後のまとめでこれらに回答を示すことで締めくくられており、教科書としての完成度も高い。
ところで皆さんはスタートアップ企業というと具体的にどのようなイメージを持つだろうか? 多くの人はGoogleやAppleといった技術を武器に急成長する企業を思い描くのではないだろうか? 本書もおおむねこのようなハイテクベンチャーを念頭に置いているといっていい。ただし、このような企業はごく一部であり、経済センサスにおける開業率にカウントされる多くの創業は小売業や飲食業、個人向けサービス業に属する。また、我が国において、スタートアップ企業に関する経営や政策は中小企業論として取り扱われてきた経緯がある。
また、著者も述べているとおり、スタートアップ企業の研究は経済学のみならず、経営学や社会学、場合によっては心理学的な理論を用いて分析されることがある。特に創業に関する研究は、個々人の職業判断を含めた人生設計に絡む問題を解きほぐす必要があり、幅広い背景知識を必要とする。本書のタイトルは「経済学」となっているが、これらの幅広い分野にまたがるイシューや文献についても取り上げられており、私のような研究者にとっても役に立つありがたい内容となっている。
ただ一つ難点をあげるとすれば、幅広い領域を過不足なく取り上げている一方で、個々の内容については独立した辞書的な印象を受けた。教科書として十分だと思うが、全体を貫く統合的な視点の提示があると読者としてもより腹落ちがするのではないだろうか。たとえば、日本におけるスタートアップ企業の問題について改めて考えてみるという応用的な視点を置くのはどうだろうか? スタートアップ企業の活動は国ごとの経済制度や文化的な違いに大きな影響を受ける。したがって、この分野の実証研究において、米国と欧州で異なる結論が導かれることは少なくない。長期的取引慣行や終身雇用制といった日本に特有の経済制度がアントレプレナーシップを阻害していることは間違いない。そもそもスタートアップ企業の目標を持つことが日本の経済政策として妥当なのかという問題もある。著者は国際的にも活発に活動されている新進気鋭の経済学者で、既にこの分野の第一人者の一人といっていい。今後の活動に対するエールも込めて注文の言葉で締めくくりたい。
■主な目次
第1章 スタートアップ:新しい企業について学ぶ意義は何か
第2章 スタートアップの経済効果:「企業の誕生」はいかなる恩恵をもたらすのか
第3章 スタートアップの個人要因:誰が「アントレプレナー」になるのか
第4章 スタートアップの環境要因:アントレプレナーを輩出する背景は何か
第5章 創業時に直面する課題:必要な資金を誰からどのように調達するのか
第6章 組織と戦略のデザイン:誰とチームを組み,いかなる策をとるのか
第7章 イノベーション戦略:なぜ「果実」を得るのが容易でないのか
第8章 企業の生存:退出は常にバッド・ニュースなのか
第9章 企業の成長:高成長のための特効薬はあるのか
第10章 スタートアップの公的支援:創業に対する「介入」はなぜ必要なのか
付録 「スタートアップの経済学」のための学習ガイド
*『経済セミナー』2022年12月・2023年1月号からの転載
いいなと思ったら応援しよう!