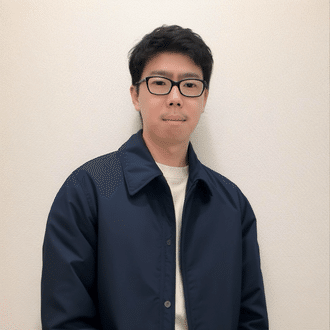なぜ審査員は同じ点数を付けてしまうのか?行動経済学からの考察
コント日本一を決める「キングオブコント2024」で、審査員が上位3組にほぼ同じ点数をつけたことが議論を呼びました。
本記事は、行動経済学の観点から、審査員が同じ点数を付けてしまう理由を分析します。
アンカリング効果
アンカリング効果とは、最初に提示された情報がその後の判断や評価に強く影響を与える心理的現象です。
例えば、商品を買う際に最初に見た価格が「アンカー(基準)」となり、その後の価格判断に影響を及ぼします。
この効果により、最初に提示された数値や情報が、その後の判断に引きずられてしまいます。
今回のケースで言えば、審査員が最初に評価した点数が、次の出場者の評価に大きな影響を与えたと考えます。
最初に高得点をつけた場合、その基準が他の出場者にも適用され、結果として点数の差が小さくなってしまいます。
これは、審査員が無意識に一貫性を保とうとする傾向があるためでしょう。
例えば、決勝1組目のファイヤーサンダーに95点以上をつけた後は、その点数が一つの基準となり、他の出場者に大きく異なる点数をつけるのは難しくなります。
審査員は、過去の点数と整合性を保つことで、自らの評価基準に自信を持とうとする心理的メカニズムが働いてしまいます。
社会的証明と同調バイアス
他の審査員の点数が公開される審査の場合、社会的証明や同調バイアスが強く作用します。
この場合、審査員は他の審査員の点数に影響されやすく、自分が大きく異なる点数をつけることに対する心理的抵抗が生じます。
この抵抗は「自分だけ異なる評価をして間違えるかもしれない」という不安感から来ています。
特に、審査が公開されている場では、自分の評価が他者と大きく異なると、その評価が批判されるリスクがあるため、より無難な点数をつける傾向が強まります。
たとえば、東京03の飯塚さんがファイヤーサンダーに高得点をつけた一方で、他の審査員は94点から96点の範囲内で採点していることを考えると、審査員間の評価基準は微妙に異なっているものの、大きな差をつけることを避けているのが見て取れます。
過去の評価や、他の審査員の評価と大きく異なる点数をつけないことで、一貫した評価が形成されやすくなりますが、結果として点数の差は縮小してしまいます。
リスク回避と損失回避
「キングオブコント」のような大きな大会では、審査員は自分の評価が結果に大きく影響することを意識します。
そのためリスクを回避する心理が働くのは当然です。
特に高得点や低得点をつけることは、その審査員が「責任」を背負う形になり、責任を分散するために同じような点数をつけるのは人間の心理として仕方がないかもしれません。
これを損失回避の心理と呼びます。
審査員は「自分だけが高い、あるいは低い点数をつけることで、優勝を左右してしまう」というリスクを避けるため、他の審査員と同じような点数をつけて責任を分散させようとします。
たとえば、決勝の3組とも、多くの審査員が94点や95点をつけたのは、審査員全体の評価に大きな差が生まれないようにし、自分の評価が過度に注目されることを避ける意図が働いている可能性があります。
審査員にとって、平均的な点数をつけることは、安全な選択肢であり、リスク回避の一環と考えられます。
審査基準の曖昧さ
エンターテイメントの審査において、明確な評価基準が存在しないことも、点数の均一化を助長します。
芸人の「面白さ」や「技術」を評価する際に、客観的な基準が不十分であるため、審査員は主観的な判断に依存せざるを得ません。
その結果、他の審査員と大きく異なる評価を避けようとする心理が強まり、点数の差がつきにくくなります。
具体的な基準がないため、審査員は自分の感覚に頼るしかなく、結果として点数の差が小さくなってしまいます。
ちなみに、これはビジネスにおける人事評価でも同様でしょう。
公正な審査のための改善策
行動経済学の観点から考えると、審査の公正さを保つためには以下の改善策が考えられます。
1. 評価基準の明確化
面白さや技術だけでなく、構成や独創性など、複数の具体的な評価基準を設け、それぞれに対して点数をつけることで、審査の透明性と公平性を高めることができます。審査員の主観的なバイアスが軽減され、より多様な視点での評価が可能になります。
2. 審査員の増員
審査員の数を増やせば、個々の審査員の評価が全体に与える影響を分散できます。5人よりも7人や9人など、複数の審査員がいれば、個々の好みやバイアスが影響を与えにくくなります。
3. 段階的評価
一度だけの評価ではなく、全コンビに対して複数のステージでの評価を行うえば、瞬間的な感情や一時的なバイアスが入り込むリスクを減らします。例えば、1回目の評価と2回目の評価の平均を取るなどが、公平な審査になるかもしれません。
まとめ
審査員が同じ点数をつけやすい理由は、行動経済学のアンカリング効果や同調バイアス、そして損失回避の心理に起因していると考えます。
これに対して、評価基準の明確化や審査員の増員などの改善策を講じることで、公正な審査が実現しやすくなるのではないでしょうか。
今回のキングオブコントを見て、賞レースについての審査プロセスを見直すのは、重要な課題と感じました。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
いいなと思ったら応援しよう!