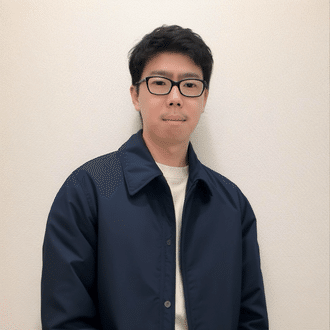政治家の経済知識は、実際どの程度なんだろうか?ー経済理論の誤解ー
読者の方から「ある政治家の発言について検証してほしい」という依頼がありました。
Xでの投稿らしいので、全体を読んで回答した方がよいだろうと思いましたが、この政治家のツイート数があまりにも多く、何を言いたいのか不明でした。
そこで依頼に対する回答ではなく「政治家の経済知識」についての記事にしたいと思います。
近年、「政治家の経済知識は本当に大丈夫なのだろうか?」といった声が、ネットやメディアで頻繁に聞かれるようになりました。
実際、国会での発言や選挙公約を見ていると、家計簿のようなイメージで国家財政を語ってしまい、通貨の仕組み等を十分に理解していないのではないかと思われる場面がよくあります。
本記事では、政治家にありがちな誤解を紐解きながら、いったいどれほどの経済知識が必要なのかを考えてみましょう。
家計簿と国家財政の違い
まず大前提として、家計簿(PL:損益計算書)的な考えと、国家財政(BS:貸借対照表)的な視点の違いを理解することが大切だと考えます。
家計簿的発想では、「収入があって、そこから支出を賄う」という順序を思い浮かべます。
たとえばサラリーマンの家庭なら、給料(収入)が入ってから家賃や食費など(支出)を払いますよね。
しかし、国家財政はこれとは仕組みが異なります。
PL的な考えの場合、以下のような問題が生じます。
異なる順序
国の予算支出は、税収を見込んで行われるのではなく、必要な支出額がまず決定され、その財源として税収や国債発行が計画されます。
貨幣の役割を無視
政府が支出を行うことで市場に通貨が供給され、後から税として回収されるという「貨幣の循環」が出来ません。
つまり、政府はまず支出(予算)を決め、必要に応じて税収や国債(政府の負債)でその財源を確保するのが、正しい順序です。
また、家計とは違って、政府には通貨を発行できる中央銀行との連携という仕組みもあります。
「支出→税収回収→国債発行→借換発行」といった循環で経済を動かすことができる点も、一般の家計簿とは違います。
ファイナンスの知識と経済理論を正しく理解していれば、簡単に分かると思います。
BS的発想が重要な理由
国家財政を理解するためには、BS(貸借対照表)的な視点、つまり「ストック(資産・負債)の動き」を中心に考えるべきです。
国債は負債だが資産でもある
国債発行によって政府の「負債」は増えます。
ただし、これは民間部門(主に国内の金融機関)の「資産」でもあります。
簡単に言うと、政府発行の国債を、金融機関が買うことで国にお金が入るという仕組みです。
国債は政府の借金ですが、銀行など金融機関にとっては資産になるということを覚えておいてください。
重要なのは、これが常に循環しており、償還や再発行によって管理されていることです。

政府の支出は通貨の供給
ようするに、政府が支出を行う際、その原資(税収や国債)は単なる「ストックの移動」です。
税収は民間から政府への資金移動を表し、国債発行は将来の税収や借換発行による資金調達の手段です。
これを数式で表すと次のようになります。
$$
\Delta G = \Delta T + \Delta D
$$
$${\Delta G : 政府支出の変化}$$
$${\Delta T : 税収の変化}$$
$${\Delta D : 国債発行額の変化}$$
つまり、支出額$${G}$$が先に決定され、それを満たすために税収や国債発行が調整されるという仕組みです。
この流れが財政におけるBS的な視点です。
貸借対照表を考慮した動的な視点
例えば、日本の国家財政の貸借対照表を簡略化すると以下になります。
資産:公共インフラ、外貨準備金など
負債:国債残高
ここで重要なのは、負債(国債)の増加が必ずしも問題ではない点です。
負債が増えても、その対価として経済全体の資産や所得が成長していれば、実質的な負担は軽減されます。
民間のバランスシート全体で見れば、政府負債が資産として蓄積されているからです。
国債は「現金で返さないとデフォルト」なのか?
「国債を返せなくなったらデフォルト(債務不履行)だ!」という主張もよく耳にします。
もちろん、国債は債権者から見れば「現金を受け取る権利」であるため、償還ができなければデフォルトとみなされます。
しかし、実際の財政運営では借換発行が常に行われています。
国債は償還時期を迎えたら、新しく国債を発行して金融機関に買い取ってもらい、その返済資金に充てています。
銀行は基本的に新規国債を引き受けます。なぜなら利息が確実にもらえるからです。
そのため国債発行=現金化です。
「国債は現金で償還されないといけない」と言われますが、実態は借換国債を発行して金融機関に再び買ってもらって現金化しているだけです。
政府債務(国債残高)について
政府債務の変化は簡単にモデル化すると、次のように表せます。
ちなみに、政府債務の変化は、税収や財政支出の収支結果も考慮する必要があります。
$$
\Delta D = G - T + D_{\text{借換}}
$$
$${D: 国債発行}$$
$${G: 政府支出}$$
$${T: 税収}$$
上記式は、以下の関係を示しています。
1. 税収 $${T}$$ が支出 $${G}$$ を超えれば、追加の負債 $${(D_{\text{新規}})}$$ は発生しません。
2. 税収が不足している場合、政府は追加の負債 $${(D_{\text{新規}})}$$ を発行して支出を賄います。
3. 借換国債 $${(D_{\text{借換}})}$$ は、元本返済のための負債であり、これは通常、毎年計画的に発行されます。
この式が示すとおり、国債は常に「現金」で返すわけではなく、国債の借換発行でつないでいくのが実態です。
さらに日本の国債の大半は自国通貨建て(円建て)であり、必要なら日本銀行が国債を買い取る(量的緩和)手段もあるため、他国通貨建て(例えばドル建て)の国債よりはるかにデフォルトリスクが低いといえます。
政治家に求められる経済知識
では、政治家が持っている経済知識はどの程度必要なのでしょうか。
国民にわかりやすく家計のメタファーで語るのも大切ですが、本当は貸借対照表(BS)的な視点が欠かせないと思います。
また、国家の支出と税収の関係は以下のように整理できます。
・政府支出は、まず必要な額が決定され、通貨が供給される。
・税収とは、政府支出によって供給された通貨の一部を回収するプロセス。
つまり、経済理論的にいえば、税収とは結果であって手段ではありません。
税収は経済活動の結果として得られるものであり、支出のための制約にはなり得ません。
この点は家計や企業とは決定的に異なります。
こうしたポイントを理解していないと、国会や政策立案の場で「財源はどうするんだ?」という短絡的なPL発想や、「国債を返せないからデフォルトだ」といった誤解を招いてしまいます。
まとめ
多くの政治家は、専門家ではないにしても国のかじ取りを担う立場です。
最低限、家計簿的な発想と国家財政を混同しないためのBS的な視点をもって議論を進める必要があるのではないでしょうか。
とくに経済政策においては、インフレや国債、税収などさまざまな要素が複雑に絡み合っていますから、単純化しすぎた発言は国民を誤解させるリスクが高くなります。
政治家に対しては、「どこまで経済理論を理解し、使いこなせるか」ということよりも、「国家財政を家計簿のように議論しない」という姿勢が重要だと思います。
そのためには、私たち有権者も家計簿的感覚とマクロ経済が違うということを理解し、政治家の発言や政策をしっかりチェックしていく必要があるかもしれません。
結局のところ、「政治家の経済知識は、実際どの程度なんだろうか?」という問いに対する答えは、ピンからキリまで様々でしょう。
しかし、誤った考え方を鵜呑みにしてしまうと、私たち自身の生活を左右する政策に重大な影響が出かねません。
だからこそ、経済を家計簿視点だけでなく、BS視点を含めた多角的な観点から見てくれる政治家の登場を強く望みたいところです。
ただ、最近の議論などを聞いていると期待はできそうにないですかね。
もう少し勉強してほしいものです。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
※「note」を利用する筆者のブログについて
当ブログは、 Amazon.co.jp のリンクによってサイトが紹介料を獲得できる「Amazonアソシエイト・プログラム」に参加しております。
紹介料は小児がんの娘のサポート費用に充当しております。
いいなと思ったら応援しよう!