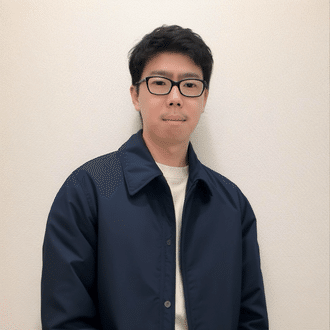なぜ政治家の立候補を「出馬」というのか?
自民党や立憲民主党の総裁選が始まります。
総裁選に関するニュースなどで総裁に立候補することを「出馬表明」と表現するのを、皆さん聞いたことがあると思います。
「出馬」という言葉は、日本の政治活動においてよく耳にしますが、その語源や意味について知っているでしょうか。
政治家が選挙に立候補する際、なぜ「出馬」という表現が使われるのか、その背景には日本独自の歴史や文化が深く関わっています。
明日の豆知識として、ぜひ最後までお読みください。
出馬の語源
元々、「出馬」は武士や貴族が馬に乗って戦場に出ることを指していました。
日本では古くから、馬は権力の象徴とされ、戦場において馬に乗ることができるのは、高い地位や名誉を示すものでした。
したがって、政治家が選挙に立候補する行為を「出馬」と表現するのは、彼らが自らの威信をかけて戦いに挑むという意味合いを持っているためです。
「出馬」という表現には、単なる選挙への立候補という以上に、政治家としての覚悟や責任感が込められていると言われています。
これは日本の政治文化が古くから受け継いできた価値観であり、現代においてもその影響が色濃く残っていると考えられています。
日本における「出馬」の歴史
「出馬」という言葉が政治の場で使われ始めたのは、江戸時代に遡ります。
政治が武士階級によって支配されていたこの時代、政治の場でも「出馬」が使われ、勇敢さや指導力を示す表現となりました。
明治時代に入ると、日本の政治体制は大きく変わり、選挙制度が導入されました。
「出馬」という言葉は消えず、いつしか政治家の立候補を表現するために使われ始めました。
これは、政治家が依然として国を率いる指導者としての役割を果たすべきであり、その覚悟を持って選挙に臨むべきであるという価値観が日本人に根付いていたからと考えられます。
出馬が持つ意味
つまり「出馬」には、単なる立候補以上の意味があるようです。
それは、政治家としてのリーダーシップや責任感です。
それを示すために、「出馬」という言葉が使われます。
また、有権者の支持を得るために政治家は多くの努力を重ねますが、実を結ぶかどうかは不確定です。
政治家にとって選挙の当落は、大袈裟に言えば「生きるか死ぬか」です。
まさに戦いの場と言えるのかもしれません。
このような背景から、「出馬」という言葉は、政治家がその責任を果たすために一歩前に踏み出す姿勢を表しています。
他国での立候補の言い回し
日本の「出馬」には、戦いに挑むという古い文化的意味合いが反映されています。
では、他国では立候補に対して、どのような表現が使われているのでしょうか。
実は、国ごとの文化や歴史により、政治家の立候補に対する表現は異なります。
アメリカの「ランニング」
アメリカでは、政治家が選挙に立候補することを「ランニング(Running)」と表現します。
この「ランニング」という言葉には、競争に参加するという意味が含まれており、選挙が競争の場であることを示しています。
アメリカの選挙も激しい競争が繰り広げられるため、「ランニング」という言葉が使われるのは適切と言えるでしょう。
また、「ランニング」にはスピード感や、動的なイメージがあり、政治家が積極的に行動し、選挙戦を戦う姿勢を表しています。
このように、アメリカでは政治家の立候補を「ランニング」と表現することで、選挙戦における競争の激しさや政治家の積極性を強調しています。
ヨーロッパにおける政治家の立候補
ヨーロッパの各国でも、政治家の立候補に対する表現は様々です。
例えば、イギリスでは「standing」という表現が使われます。
「standing」は日本語に直訳すると「立つ」という意味で、政治家が有権者の前に立ち、自己主張する姿勢を示しています。
この表現は、政治家が信念を持って選挙戦に臨むことを強調しています。
フランスでは「se présenter」という表現が使われます。
これは「自己を紹介する」という意味で、政治家が有権者に対して自らをアピールし、支持を得ようとする姿勢を表しています。
フランスの選挙では、政治家が自らの政策やビジョンを有権者に伝えることが重要視されていて、表現がその文化を反映していると言えます。
「出馬」という表現について
ただ、「出馬」という表現のイメージは、メディアの影響が大きいと思います。
メディアは「出馬」という言葉を通じて、政治家のイメージを作り上げる重要な役割を果たしていると考えます。
特にテレビや新聞などでは、政治家の「出馬」を大々的に取り上げ、その背景や意義を大げさに解説します。
このような報道によって、有権者は「出馬」という言葉が大きな出来事のように感じます。
また、メディアは「出馬」のイメージをコントロールする力も持っていると思います。
「出馬」を強調すれば、ネガティブなイメージを与えることもあります。
例えば、「出馬」には「野心的」や「権力志向」と結びつけられる場合があります。
元々、出馬は「戦いに出る」意味であるため、「手柄を立てに行く」イメージを持っています。
そのため、使い方によっては政治家のイメージに悪影響を与えるかもしれません。
まとめ
日本の選挙における「出馬」は、戦士が戦場に赴く行為から派生しました。
今日では、選挙に立候補する政治家の覚悟と責任を象徴する言葉として使用されています。
この表現は、日本の文化を反映しており、選挙の重要性と政治家の役割に対する国民の期待を示していると言えます。
ただ、最近の政治家を見ると覚悟も責任も無く、単に権威が欲しい人たちばかりではないか?という気がします。
「出馬」という言葉を使うからには、国民に対する覚悟と責任を示して欲しいですね。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
いいなと思ったら応援しよう!