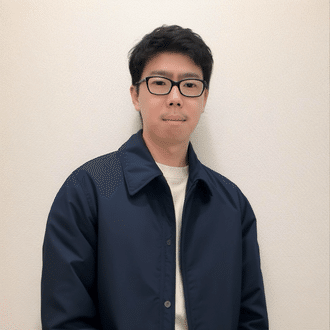増税・減税よりも大切だと思う議論:財政は投資の視点を持つべき
最近、ニュースやSNSを見ていると「増税・減税」といった税収の話題が非常に目立ちます。
政治家やメディアも「税収を上げるべきか、下げるべきか」という点を繰り返し取り上げるので、国民も税率にばかりに関心を向けてしまいます。もちろん税金は家計に直接影響しますから、これ自体は大切なテーマです。
しかし、その一方で「税収をどう使うのか」という肝心な部分が意外なほど語られていないようにも感じます。
増税・減税ばかりを追い求めるあまり、本来はもっと深く考えるべき「財政の使い道」が見落とされているのではないでしょうか。
本記事では、なぜ今の論争が増減税に偏るのか、その背景を振り返りつつ、大切な視点として「財政はファイナンスである」という考え方を提示します。
MBAや企業実務でファイナンスを学んだ者として痛感するのは、企業の資金調達・投資と同じように、国の財政も将来のリターンを生む投資として捉えるべきではないかという視点です。
それが政治家や官僚には欠如しているため、いつも増減税についてばかり議論するのではないかと感じています。
なぜ増減税ばかりクローズアップされるのか
まずは、どうして増減税の話ばかりが先行してしまうのか、その理由を整理してみましょう。
1. 家計への影響がわかりやすい
増税なら負担が増える、減税なら手取りが増える、こうした短期的な損得は家計に直接響くため、多くの人にとって切実なテーマになりやすいと思います。メディアや政治家にとっても、伝えやすい論点といえます。
2. 選挙の争点になりやすい
「増税反対」「減税賛成」といったスローガンは票を集めやすいため、政治家は税収に力を入れます。その結果、税金の使い道という本質的な部分は二の次になってしまうケースが多いと感じます。
3. 税金の使い道は複雑で地味
道路整備や教育投資など、財政支出の詳細は複雑です。しかも、その成果が長期的にしか現れません。よって短期間での評価が難しいため、メディア的にも扱いにくい傾向があるのではないでしょうか。
とはいえ、増税・減税が先行してしまうと、国の将来を左右する財政の使い道、すなわち「どの分野にどの程度のお金を投じ、将来の経済成長や社会的利益を狙うのか」が十分に議論されなくなるのが最大の問題だと考えます。
ファイナンスで考えると、資金調達の話に終始し、肝心の運用についての話が抜けているということです。
そこで注目したいのが「財政を投資として捉える」という発想になります。
財政は投資である:費用と投資の違い
支出をネガティブに捉えすぎていないか?
私たちは普段、税金を支払うとき「お金が減ってしまう」「何の役に立つかわからない」という感情を持つと思います。
医療・福祉・防衛・公共施設などに対する支出は、家計簿で見るとただのマイナスに見えてしまいます。
一方、企業の観点でいうと設備投資や研究開発、教育研修などは「将来の利益を生むための投資」です。
たとえ金額が大きくても、長期的には会社の利益や競争力につながると考えて投資するケースはよくあります。
同じように、国の財政支出にも「将来的にリターンを生む」可能性があるはずです。
たとえばインフラ整備(道路・橋・通信網)はビジネスの活性化や物流の効率化につながる可能性があります。教育投資はイノベーションや生産性向上の土台を作ります。
こうした支出は、短期的に見れば大きな支出でも、長期的に国民生活の質向上や税収アップをもたらす投資と位置づけることが適切といえると考えます。
投資対効果を見極める
投資である以上、当然「どれだけのリターンが期待できるのか」を測り、効果が乏しい施策には資金を注がない判断が必要です。
企業であれば設備投資を決定する際、ROI(投資収益率)を計算し、リスクとリターンを精査します。
一方、公共事業や行政施策では透明性がなく、十分なエビデンスがないまま予算が組まれていると感じます。
政治家にとっては選挙への影響を考え、短期的な成果をアピールしやすい事業への投資に傾く可能性もあります。
だからこそ、国民が「税金がどんな分野に投資され、どのようなリターンが期待されるか」をチェックできる分かりやすい制度が必要です。
財政のリターンは多様
また、財政投資のリターンを考えるとき、企業のように金銭的リターンで判断するのは不適切かもしれません。
例えば、国の財政におけるリターンは、以下のように多面的に定義できると思います。
1. 経済成長(GDP増加) → インフラ投資・企業支援・教育改革
2. 雇用の創出と安定 → 公共事業・職業訓練・スタートアップ支援
3. 生活の質(QOL)の向上 → 医療・福祉・交通インフラ・文化政策
4. 社会の安定と安全保障 → 貧困対策・防災・治安維持
5. 環境・持続可能性の向上 → 再生可能エネルギー・公共交通整備
6. 技術革新・イノベーション → 科学技術・AI・医療研究
7. 国際的な影響力の向上 → 外交政策・国際協力・文化発信
このように、国の財政投資のリターンは多様であり、「単に税収が増えるかどうか」だけで判断するのではなく、社会全体への影響を踏まえた総合的な評価が必要でしょう。
しかし、根本的には「リターン=収益」の視点は必要です。キャッシュの垂れ流しは企業に限らず、国も破綻に追い込まれてしまいます。
今後、財政の議論が「増税か減税か」にとどまらず、「どのようなリターンを生み出すべきか」にシフトすれば、より建設的な議論ができるようになると考えます。
私たち国民も、財政の使い道について投資対効果を意識し、政策を評価する視点を持つことが求められると思います。
「将来世代へのツケ」論は本当に正しいのか?
「財政拡大は国債依存になり、将来世代にツケを回す」と言われることが多いですが、これは一概に正しいとも言い切れません。
国債の利払いが膨れるリスク
確かに国債を無制限に発行しすぎれば、利払いが膨らみ、将来の財政に大きな負担となる可能性があります。
投資は未来を助ける
しかし、企業の社債発行と同じように、調達した資金を適切な投資を行えば国力が向上し、結果的に税収が増えます。国債は「将来世代へのツケ」どころか、むしろ未来に恩恵をもたらすものとも言えます。
大切なのは「どのプロジェクトにいくらの予算を投じるか」「そこから得られるリターンをどのように測るか」という、あくまで使い道の部分にあります。
つまり、国債や増税・減税といった資金調達の方法を論じるだけではなく、「それを使って何をするのか」こそ議論の中心に据えるべきではないでしょうか。
企業会計で考えると見えてくる財政投資の本質
企業ならば、調達(社債や株式発行)→運用(設備投資・研究開発)→回収(収益獲得)という流れがクリアで、投資家へ説明責任を果たさなければなりません。
一方、国の場合は通貨発行権を持ち、かつ納税義務のある国民から強制的に税収を得られるため、企業のように「利益が出せるか?」という指標がないままに資金を調達できます。
そこで見落とされがちなのが「税収も、国債発行も将来の経済成長や社会発展といった形で回収するための調達である」という視点です。
もちろん、企業のPL(損益計算書)のように明確なキャッシュフローや利益が可視化されにくい点は難しい部分ではあります。
しかし、だからこそ投資対効果を評価する仕組みを強化し、インフレリスクや利払の増大をマネジメントしながら、計画的に財政を運営することが必要です。
「将来を見据えた投資か、単なるバラマキか」を見極める観点は企業も国も基本的に同じだと思います。
この視点が欠落すると、財政支出を短期的な費用としてしか考えず、政策が短期的・部分的なものに終わってしまいます。
財政こそが未来の成長エンジンになりうるという発想は、まだまだ一般に浸透していないように思えます。
まとめ
最後にもう一度強調したいのは、「増税か減税か」という議論に終始せず、本当に重要なのは「どう使ってリターンを生むか」ということです。
たとえば教育・インフラ・研究開発といった分野に効果的に投資すれば、長期的な税収増や国民生活の向上につながるかもしれません。
1. 増減税論争の盲点:使い道が語られない
増税の負担感、減税の喜びばかりが注目され「投資としての財政」が見過ごされている。
2. 無制限ではなく、投資効果を見極めるバランス感
国債や財政拡大にはリスクもある一方で、使い道次第では大きなリターンを生む可能性もあることを意識する。
3. 私たちにもできること:チェックと声を上げる
結局、政治家だけで財政運営は変わりません。私たち一人ひとりが「どんな未来を創る投資なのか」をチェックし、議論に参加することが欠かせません。
もちろん、実際の政策には社会保障費の拡大や少子高齢化といった複雑な要因も絡んできます。
しかし、だからこそ短期的な増減税の是非だけに流されず、「財政を未来への投資と考える」という大局観を持つことが必要ではないでしょうか。
もしこの記事をきっかけに「もっとファイナンスを学んでみたい」と思ったら、ぜひ書籍やセミナーなどを活用してみてください。
あなた自身が投資の視点を獲得すれば、日本の財政議論をさらに建設的に捉えられるはずです。
今後、メディアやSNSで増税・減税の話が盛り上がっていても、ぜひ「そのお金、何に使うの?」「どうリターンを生み出すの?」という問いを自分にも、そして周りにも投げかけてみてください。
それが「税金=費用」という固定観念から抜け出し、「財政=投資」という未来志向を手に入れる第一歩になるかもしれません。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
よろしければフォロー頂けると、大変嬉しいです。
またコメントもお待ちしております。
※「note」を利用する筆者のブログについて
当ブログは、 Amazon.co.jp のリンクによってサイトが紹介料を獲得できる「Amazonアソシエイト・プログラム」に参加しております。
紹介料は小児がんの娘のサポート費用に充当しております。
いいなと思ったら応援しよう!