
Photo by
mikaruma
有価証券報告書から考える会計処理ー資産除去債務、割引率ー
ちょろ助@経理の人です。
経理の方向けに情報発信して行きます。
資産除去債務の割引率について
はい。割引計算、みなさん大嫌いですね。
先日は、履行による減少の共有でしたが、関連してご参考までに。
資産除去債務の計上に際しては、割引計算が必要となります。
では、その割引率は何を使うのか・・・?
日高屋さんは、以下のように記載ありです。
(使い回しでごめんなさい。今回は、上のアンダーライン)

「国債の利回り」とありますね。
これは、
「資産除去債務に関する会計基準」第6(2)に
以下のように規定されているからですね。
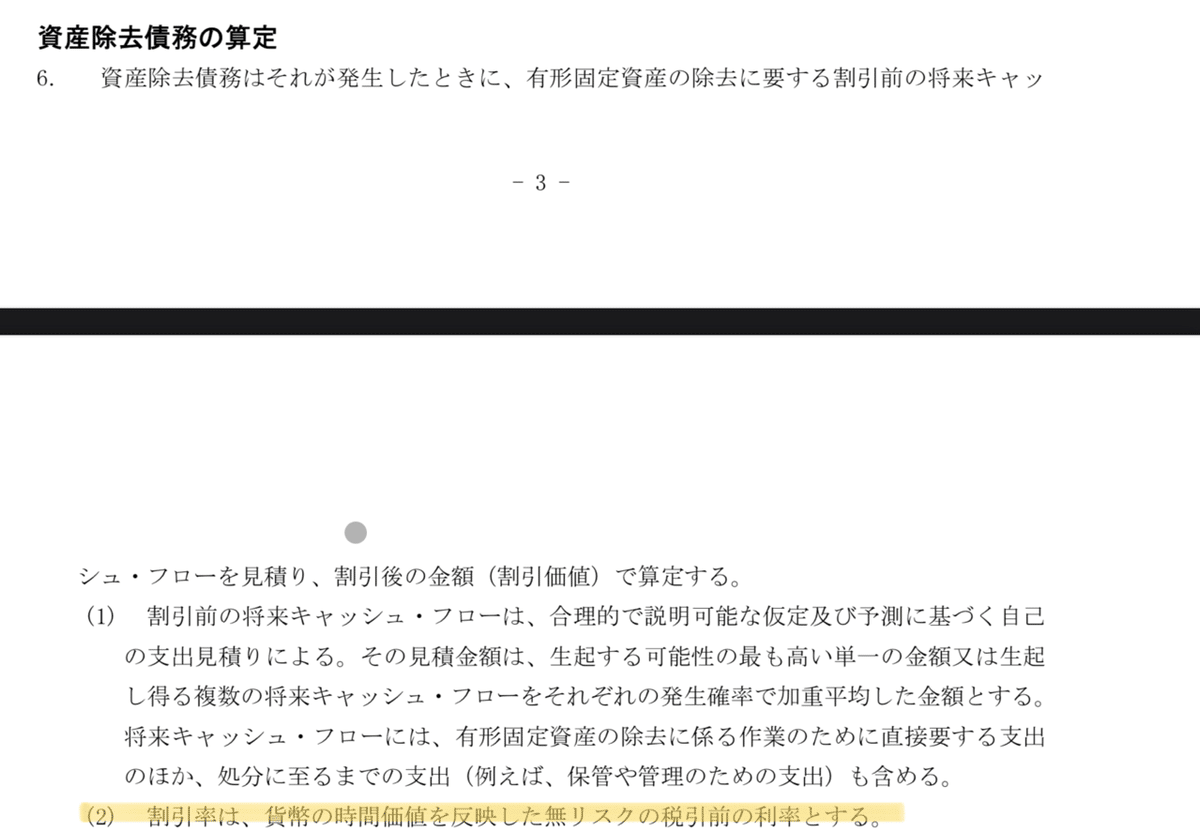
無リスクの利率とは
話がぐるっっと戻ってきました。
これが国債の利率ですね。日高屋さんも国債で行っていますね。
少なくとも日本国内の事業については、以下のリンクの情報で
よろしいかと。
文句言われたら、監査人と話し合って決めてください。
財務省のホームページです。
オレンジのアンダーライン箇所をクリックするとCSVでダウンロードできます。
(もちろん無料)

1974年からの金利が見れるので、「低金利時代」への変遷を
何となく感じられます。笑
以上、実務的な資産除去債務の割引率のソースの共有でした。
