
脳内イメージ出力アプリ「脳啜(ノズ)」についての覚書
随時更新
電子書籍用端末向けアプリ「脳啜(ノズ)」は、テクストを読んで脳内に刻まれた視覚的イメージを正確に出力することができる
読了時、それぞれが脳内で無意識裡にイメージした通りの画像(イラスト・写真)が出力されるので、答え合わせの要領で読書モチベーションが高まると一部で人気である

脳啜で活用されている主な技術は超高度なアイトラッキング機能である。読者の視線が文字を追う速度の差、単語理解までの時間、叙述関係の整理をする時間、反芻の有無、瞳孔の微動などの変数を総合的かつ高速で演算し、テクストの内容と合わせて画像へと落とし込む作業を、読書中絶え間なく行っている。
その他に利用する使用者のパーソナルな情報は、これまで読んできた電子書籍のデータに依存する。

脳啜が得意とするのは、高度な読解や解釈が必要となるテクスト群である。単純な単語の羅列、生成AI技術で扱われたようなプロトコルの入力といったものでも画像の出力は可能だが、それではほとんど脳啜を使う意義を感じないだろう。
脳啜はテクストに沿って新たに画像を生成しているのではなく、読者の想像を再現しているのである。

脳啜と生成AIによって出力されたイメージの大きな違いは、利用者の既視感の違いである。はじめ、本当に想像通りである、という驚きはあるが、その内容自体に驚きは少ないのが特徴だ。

脳啜によって議論の対象になったのは、「無意識」に関する領域についてである。こと小説や詩を読む場合、無意識というのはそれほど突拍子の無いものでも、不可解なものでもないのではないか、という認識を持つものが増えた。
意識的に言語化、意識化できていなかったとしても、現れる画像を見るにごく理性的な文脈で理解している。
無意識は膨大だが理性的だと納得する人々と、脳啜では無意識の思考を捉えれないと断ずる人々とで大きく二分された。

脳啜によって出力されたイメージは本人の頭の中にあるそれそのものである。
もちろん、人によりイメージは大なり小なり異なるが、いずれもテクストと矛盾しない、破綻のない画像である。
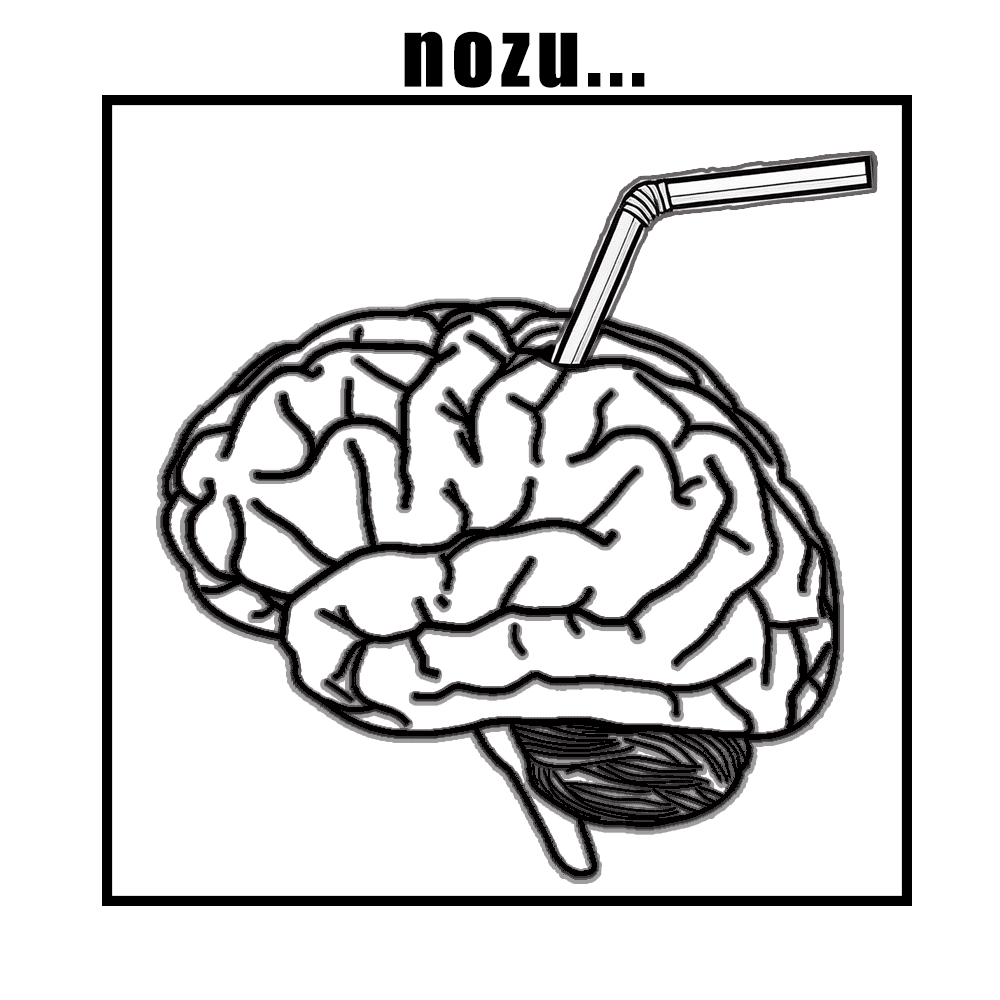
脳啜開発チームは、脳啜アプリのロゴについて悩んでいる。
英字表記したとき、[nozu…]と表しているが、多くの国で日本語式に発音されるためには[noz…]とした方が誤解が少ないのではないか、という議論が社内で四度ほど巻き起こった。
ノズゥ、ノォーゥズと発音されるのはもうごめんだ、最初のOにアクセントがあるのか、後のUにアクセントがあるのか聞いてくるのはやめろ、と脳啜開発チームリーダーがアメリカ人の友人にぼやいているメールが公開されている。
公開主はこのアメリカ人である。良かれと思って公開したという。

写真のように出力するか、イラストのように出力するかは設定画面で選べる仕様になっているが、これも基本的には読者が写実的に想像したか、デフォルメされたものを想像したかにより出力結果が異なる。
よって写真かイラストかを選ぶのは、単に好みに合わせたカスタマイズであり、正確性は多少犠牲にされることがある。

脳啜によって出力された画像を小さく印刷し、読書ノートに貼る。データをダウンロードし読書ブログやSNSで使うなど、用途は様々である。
当然、一冊のノートにまとめればその人自身の個性というものが如実に現れる。
子どもの読解力を確認する目的で使われることもある。

作品によっては、十八禁画像が出力されてしまうことがある。
無論これらは規制されており、人によっては脳啜をいくら使っても、モザイク画面しか出力されない、という事態に陥る。
この場合、読む本の傾向を換えるか、思考回路や嗜好を変える他ないだろうと開発陣はコメントしている

年会費12,000円の有料版では出力された十八禁画像のモザイク除去が可能であるとまことしやかに囁かれたが、実際の有料版は1200円の買い切りであり、開放される機能の主なものは出力画像の複数枚化である
また、印刷時などに使えるオリジナルフレームがニ十種類開放される。

脳啜によりモザイク画像を出力し続けるある男の読書ブログは一部の紳士に大変人気である。
一つには、そういうイメージが生じ得る作品であることの証左であるし、ブログ主でなければ見逃してしまう性的思想・嗜好についての啓蒙の場となっている。
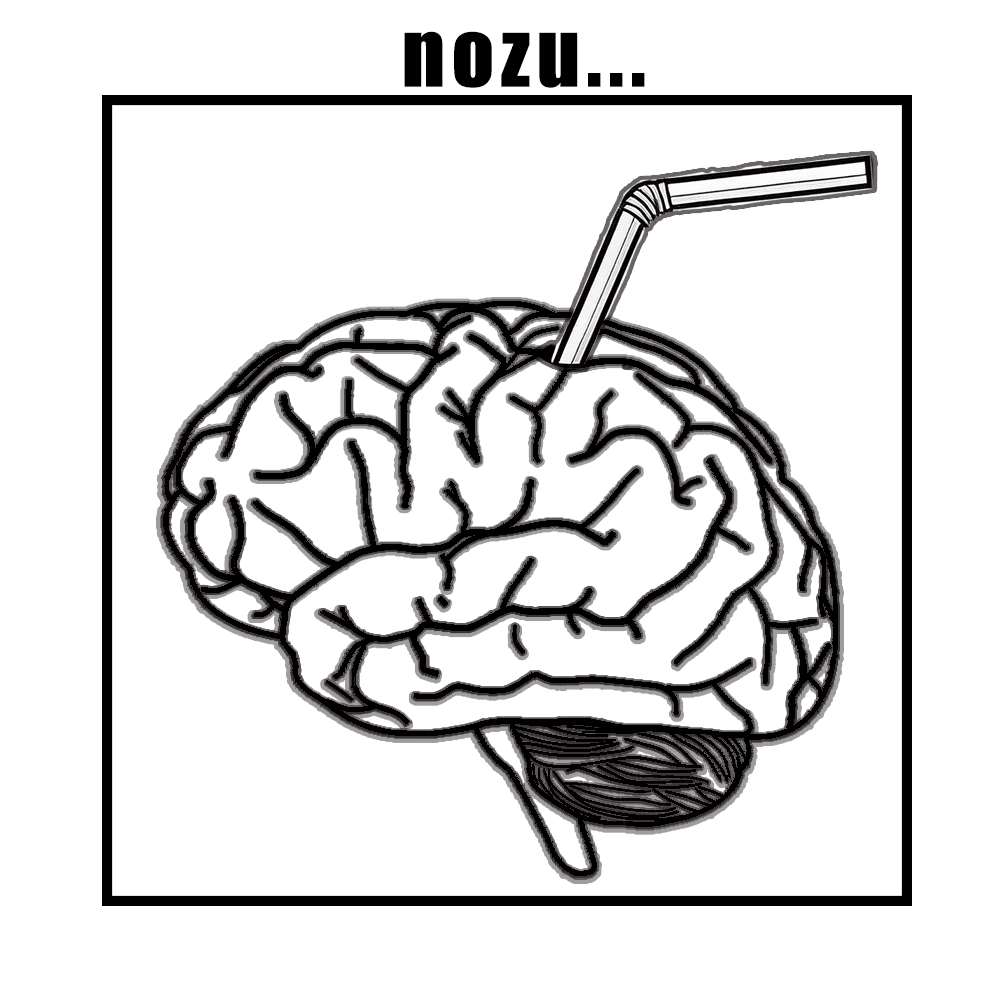
脳啜にたいする批判的な意見として、誰もが読み飛ばしや誤読を経験しているはずだが、その点が反映されれば破綻のある画像が生成されることもあるはずだ、というものがある。
開発陣もこの点は少し疑問に感じていたが、読み飛ばした部分はどうせイメージとなって表れないから良いだろう、と放置してのリリースとなったことを明かしている。
誤読に関しては普通に反映され生成されると反論している。
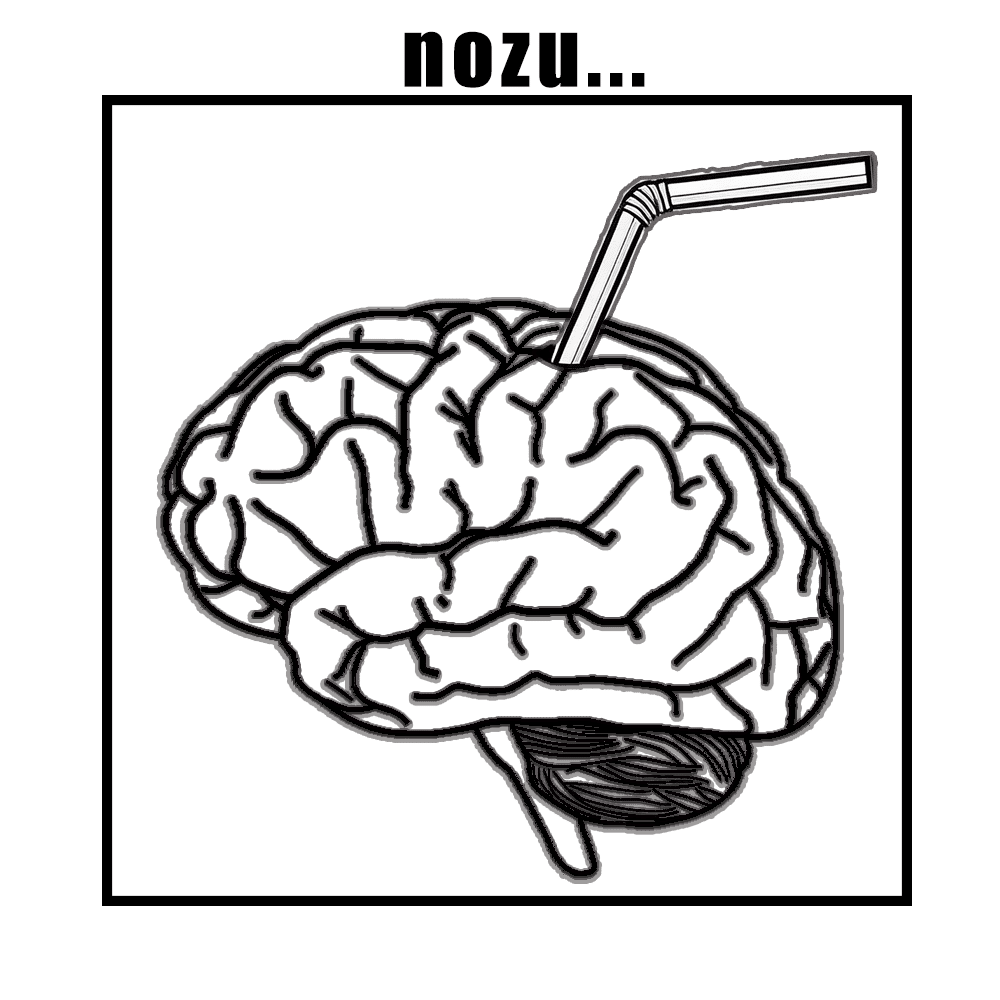
(公的にではないにせよ)教育の現場で使われることもある脳啜だが、読解力や語彙力が未熟な児童・生徒が使用した場合、誤読、誤解が手に取るように分かる。
例えば「井戸」がうまくイメージできず、マンホールの穴のようになっている。老婆と書いてあるのに大人から見るとやけに若い、などの齟齬が浮彫となる。
ただし、それこそがありのまま子どもたちが文字から受け取り見ている世界である。
指導後、イメージの再構築をすることで学習効果の確認が可能となる。
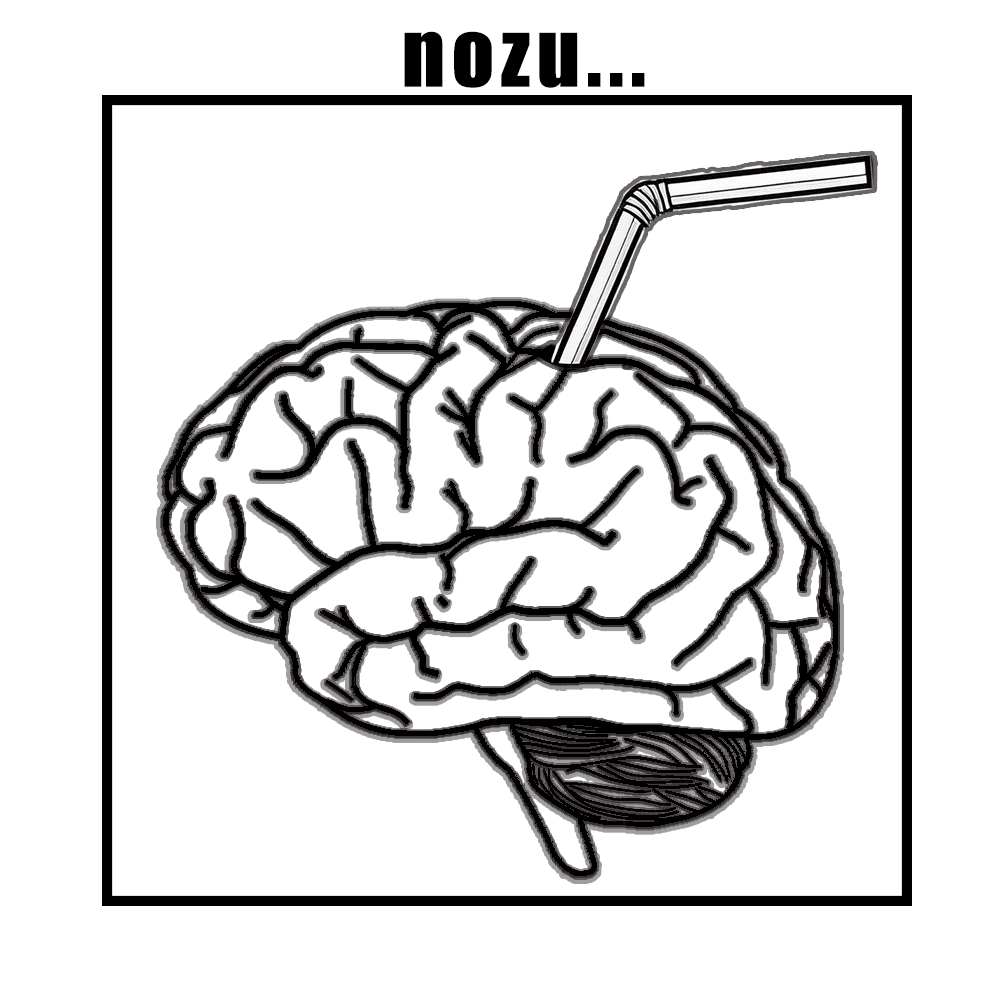
読解学習の応用として、大人も難解な書物や第二、第三言語の読解を客観的にテストするために脳啜を利用する場合がある。
母国語でない言語で脳啜を用いたとき、出力される画像が急激に陳腐化、単純化してしまうのはよくあることで、これがある種の人には言語学習のモチベーションになるようである。

語り手が実は男ではなく女だった、のような、叙述トリックが仕掛けられたミステリ小説を読んだ場合、その驚きがイメージに表れるということもあるはずだが、その点はどういう風に出力されるのか、という疑問、もとい、サービスの信頼性を訝しむもあった。
基本は無料アプリなのだから試してみれば良いじゃん、という主旨のコメントを開発陣はしている。

叙述トリックを読んだときに脳啜を使用していた場合、多くはどのシーンもネタバレ後の映像として出力されることが多い。
例えば語り手が男ではなく実は女だった、というような叙述トリックであれば、アニメであるような人工皮膚を破り正体を現す画像が出力される、というようなことがあったようだが、これは誤読の結果である。

誤読の結果が反映されるのであれば、テクストと矛盾がない、という脳啜のイメージ生成システムの信頼が根幹から揺らぐのではないか、という指摘もあった。
回答としては、脳啜も読者の視線と共にテクストを読み、内容を理解している、という点を前提として、誤読が反映されるのは読者と脳啜との間に交わされる異種間同調、経験値の共有というプロセスがあるからだというものだった。
ならば脳啜が集めている情報というものは、もっとプライバシーに関わる部分のものも含まれているのではないか、という指摘に対し、開発者は断固否定、その後は沈黙を貫いている。

あらかじめ作品のテクストに沿った画像を複数枚作成しておき、読了後、いくつかの視覚的情報を元に、もっとも想像の蓋然性が高いものを弾き出しているのではないかという指摘が一部からあった。
中には指紋の違い程度のもの生じるが、やはり指紋のように一つとして同じ画像ができないことが現段階では断定されている。集合知を利用しても結果は同じである。
リリース後同じ画像がないことが一応確認されているが、無論これは悪魔の証明に類する議論である。

出版前の作品を読む機会がある編集者、校正者、装丁家などが脳啜を使用した場合にも当然イメージは出力される。
同じイメージが一枚もないのかどうかを証明することはできないが、脳啜があらかじめ画像を用意しているという指摘はこの点などからも否定されている。
もちろん宣伝や表紙制作の目的で、個人的に書いた小説や詩などにも利用されている。

脳啜を使用し再読・三読しても同じ画像が出ることはない
これは簡単に、想像力の不可逆性を示していると言われている
同じシーンであることは多いが、一般的に再読・三読すると解像度が上がる傾向がある。
解像度とはこの場合、背景や登場人物に対する情報の正確さである。
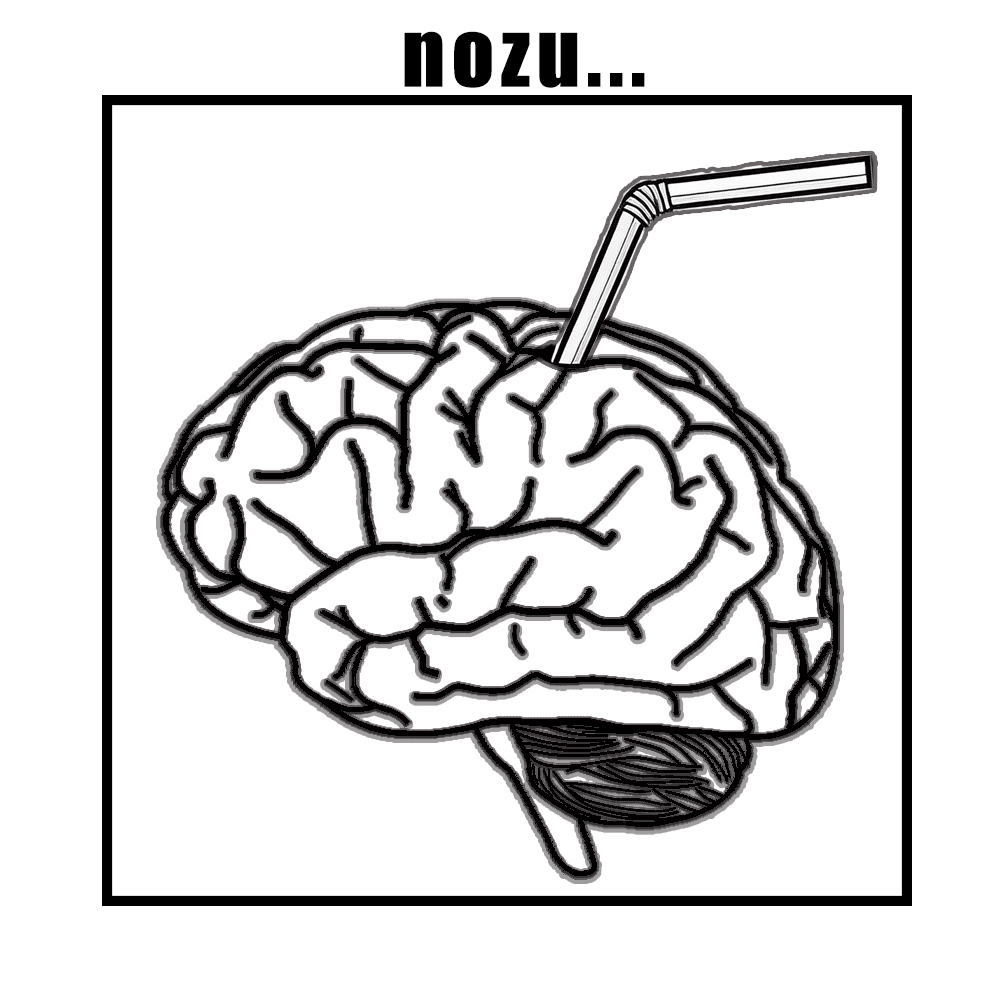
読者の基本知識を大きく上回る画像は出力されない。
異国の、隔たった時代の背景イメージや服装は、如実に読者の知識に依存する。
児童生徒に対して脳啜を利用し読解力を確認することがあるが、第二、第三言語を用いたり、少しテクスト内容の時代や場所に隔たりがあれば、誰であれ理解力は十代並みになる可能性がある。
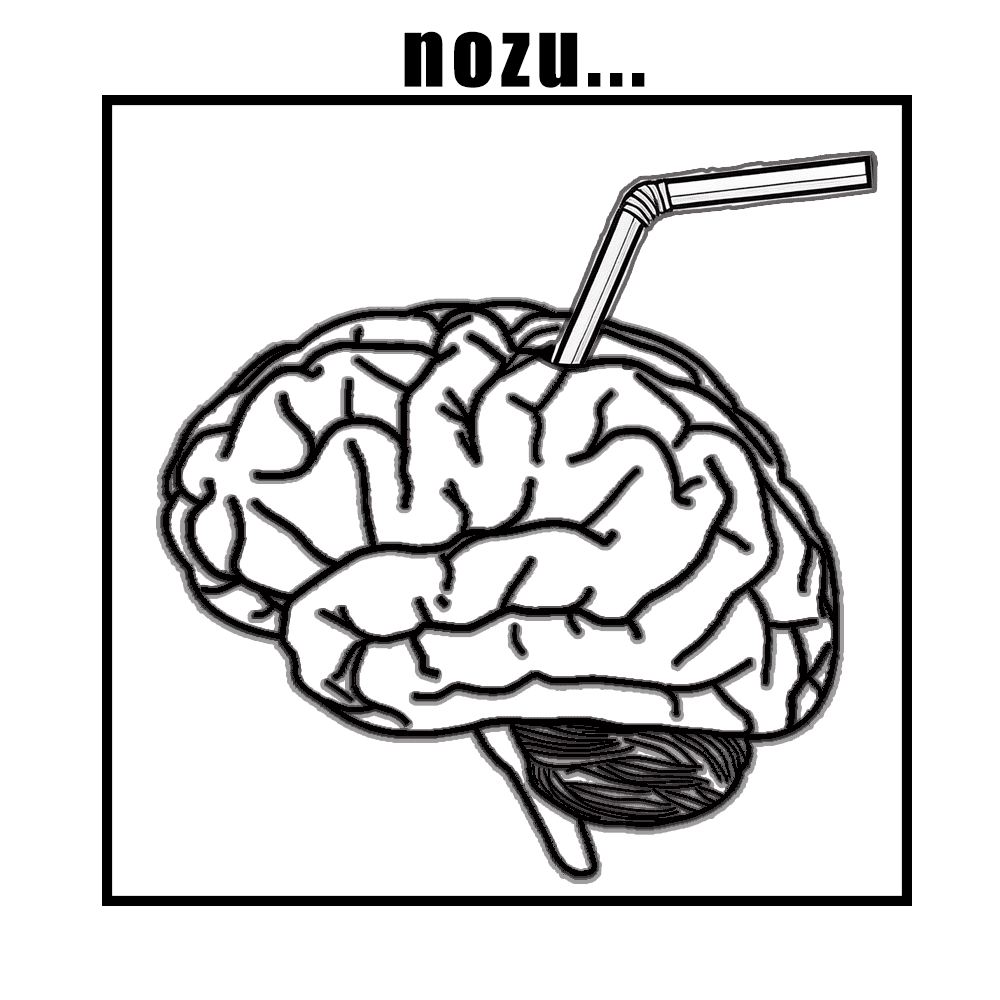
脳啜で出力された画像に登場する人物は、読者の個人的な知り合いの顔を持っていることも少なくない。
有料版の肖像権フィルター機能により、画像内の人物の顔を無個性なものにすることは可能である。

無意識は我々が思っているよりずっと理性的だ、という主張もあるが、脳啜により読者の深層意識が画像として顕在化するという側面も確かにあり、一部医療の現場、司法の現場などで利用されるケースもある。

犯罪捜査に利用されることもある。脳啜を使い捜査情報など読み込ませることで、犯人しか知り得ない事柄が明確に出力されることがある。
ただし、リリース以降絶え間なく脳啜の信ぴょう性に疑念が付きまとう以上、決定的な追及ができるケースはあまり多くない。
言い逃れ不能な画像を出力する詰め方が構築できる捜査官で組織された特別部署が某署にはあるらしいが、噂の域を出ない。

積極的に知り合いや著名人をイメージに反映させる術を開発した使用者が存在する。
その手法は販売されるや否や、4000部の売り上げを達成する。
とは言え、この作者自身が調べたところによると再現率は良くても30%に留まり、言うは易し、行うは難しの秘儀であったため少なからず批判も出た。
作者は再現率を上げるべくアップデートを繰り返しており、購入者には無料で配布し続けている。
またこの作者は、脳啜の健全な利用と発展のため、肖像権の侵害、プライバシーの侵害等には十分配慮することを各種SNSで訴え続けている。

想像力豊かな読者が脳啜を用い詩を読んだとき、非常に美しいイメージが出力され、それ自体が作品として機能することがある。
画像が美しく、それ自体が詩に対する解釈の解説となるので読み手として人気となり、出版部数の伸びに貢献するが、ときには原作者より影響力を持つこともあった。
原作者と読み手の主従が入れ替わる逆転現象が散見されたが、経済合理性の観点から、これを問題視するのはナンセンスであるととあるインフルエンサーの発言に文学評論家が反論したことで、脳啜と作家の関係は少々剣呑なものとなった。

読み巧者が見ている世界を見せることができる脳啜が微かな読書ブームの火付け役となったことは事実だが、一部の作家からは自作がイメージの限定、過度な美化に繋がりかねないという不満が出ている。
今までも実写映画化などはあり、そこに文句は言わなかったじゃないか、などと反論されているが、要は原作へのリスペクトが、という点に言及されると、議論は平行線を辿り自然に消滅した。

脳啜の台頭により、イメージ的な美しさを意識して書かれる傾向が高まるという側面もあった。
表面的には読み手の想像を上回るべしという積極的な創造行為と見なされたが、半ばは創造的空白のない視覚的な美に迎合する行為であることを作家自身が認めており、文章表現の敗北と捉えられる創造行為でもあった。

積極的に視覚的な美を出力するための文章を書くノズ派と称される派閥と、反ノズ派と呼ばれる、文は論理であると主張する派閥が登場した。
いずれもノズの周りにいるという点で多くの作家は彼らを冷ややかな目で鑑賞していたが、どの作家も少なからずノズというアプリの小さな地場の影響を受けていた。
自覚があるかないかの違いであった。

小説の世界は奥深く、必ずしも論理展開が明確であるとは限らないという声は脳啜リリース直後から上がっていた。
正確に読めば読むほどコラージュ的な画像が出力されるはずであるとか、語り手の意識の歪み、非連続性、はたまた流れと言ったものを反映させることができるのか、という点は、脳啜が標榜する矛盾や破綻の無い画像というものを真っ向から否定するものであり、かつこの場合、矛盾や破綻があることこそが正しい出力である、という。
開発陣は、だから、疑問に思うことがあったらまず使ってみれば良いじゃん、という趣旨のコメントをしている。

ノズグラスが発売された。脳啜の機能を実装したウェアラブル端末であり、これを利用すれば紙の本においても脳内イメージの出力、保存が可能である。
ノズグラスのリリースによって次第に明らかになったのは、日常を厳然たるテクストとして把握している人間が少なからずいることだった。
見たものの中で、特に注意を凝らしたある部分がテクストとなり認知され、ノズグラスがそれを反映し日常が一枚絵になる。それはつまり徹底的な写実なのではないかと思われたが、実体は言語を越えた知覚とその処理の痕跡だった。
つまり人は、見たもの以上に多くのものを見ていることが、第三者が視覚的に認知できるようになった。

ノズグラスによって出力された日常の一枚絵はいわば、整合性を保ちながら圧縮された意味と感覚の情報塊だと主張する文学者・脳科学者などの一団が現れた。
彼らの要請に応じ、テクスト外から出力した画像をテクストの形式で展開する方法を脳啜開発チームは四年かけて開発し、実行した。すると、非常に明敏でかつ感情豊かなエッセイもしくは私小説らしきものが出来上がった。
それはある種の作家に見られる文体の傾向、描写の完成度に近い質感のものであり、熟練を思わせる文字列だった。
このような流れで作家として活躍する人々が現れ始め、彼らは文字を書かない小説家として新しい時代に迎えられた。

ノズグラスの台頭により、まず世界を厳然なるテクストで捉えている人々がいることが浮き彫りとなり、これを画像化、さらに実際のテクストへと還元することで作品となる流れが生じた。
当の作者連中は出来上がったテクストの方に新鮮味は感じないが、画像には親しみと共に驚きがある、という旨の発言をしている。
本当にこういう風に世界が見えてるんだ、と関心する大衆がいる一方で、ノズグラスは反応しないものの、自分の世界認識もこれに近いと感じる人々の存在も目立った。
どうやら世界はレイヤー構造を成して重なっているようであることが、客観的な視点で云々され始めた。

文字を書かない小説家と呼ばれる人々はノズグラスを用いて華麗で鮮烈な画像を弾き出しがちだが、この中にもわびさびの美、空間の哲学を表現する人々もいた。
世界がレイヤー構造だとしたら、もっともベースとなる、基本的で本質的な一部分だけを残し、印象や気分といったものを見事に削いだ画像、及びテクストが弾き出される。
それは野生生物の洗練された肉体を思わせる文体で、もとよりあるミニマリズムの手法とは一線を画すネオミニマリストの一団として扱われた。

文字を書かない小説家と、文字を書く小説家とでは、生産性に大きな差が生じた。
無論、多くの作家が書かない小説家へと転向しようとしたが、才能の差、感度の差が浮き彫りになるだけで、特に熟練と評価されている作家ほどこれには難儀し、ペンを持たずに何が小説家かと言った捨て台詞を吐き筆を折る者が増えた。
これら作家が、捨て台詞まで凡庸との誹りを受け、筆を折る際にどれだけ気の利いたことを言えるかという部分まで批評を受ける始末となった。

現在、脳啜開発チームは、想像を映像にして出力する技術を開発中である
