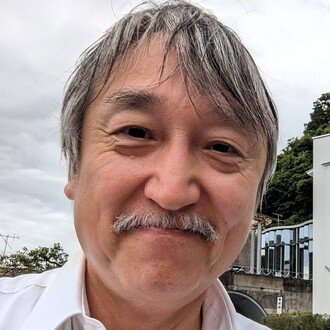大学の講義 - 2年目が無事に終了
先日、期末レポートの採点も終わり、すべての学生の成績もつけ終わり、無事に2年目の大役も終えることが出来ました。そうなんです、実は某大学で非常勤講師を引き受けることになりまして後期の1コマだけですが情報の講義でC言語を教えていたりします。
今年でまだ2年目の新米ではありますが、昨年と同じシラバスのままでしたし、講義資料の使い回しが出来たので、時間的にも気持ちの上でも少しだけ余裕も出てきました。何せはじめての年はシラバスに沿った資料を作るのと、その内容をこなすだけで精一杯のところもあり、教室で学生ひとりひとりの顔を見回しているような余裕も無かったんですよ。今年は昨年の反省点もあったので、より手を動かすことに集中できるように資料を工夫したり、プログラミング環境を整える説明にも時間を割くようにしました。
そうなんです。普通は最初に資料を作ってしまえばずっと同じものが使えそうなものですが、ソフトウェアの世界アルアルで、全てのコードが最新の環境で同じように動作するかは確認し直さないといけないのです。実際、参照しているWEBページが変更になっていたり、ライブラリとして組み込むコードのバージョンが上がっていてほんの少し修正が必要な場所がありました。それにMacユーザが増えていて特にMシリーズのCPUの場合、些細な部分ですが挙動が微妙に違う部分があったようで、学生に指摘されてしまいました。今はMacを持っていないので前もって確かめることが出来なかったんですよね。やはり動作検証の為に新しめのMacが欲しくなっているところです。
まあC言語自身の話は良いのですが、どちらかというと今の学生はシェルでコマンドを打って文字が出力されるというCUIの経験が無く、特に階層化ディレクトリの概念に慣れないようで、何かとファイルを見失ったり違う場所にある同じ名前のファイルと取り違えることが見受けられました。操作している手元を見ていると繰り返し同じコマンドを打つのに毎回キチンとタイプしているようで、シェルのヒストリ関連の使い方もちゃんと教えたほうが良さそうだと反省もしました。
全体的に物事の理解がデジタルというか「わかる」と「わからない」のどちらかのことが多く「なんとなくわかる」というのがあまりいないのだなと昭和なアナログ時代は思ってしまうのです。出来る学生はそれこそAIも駆使して自分なりの答えを導き出すのですが、そもそも自分が何をしているのかもなかなか理解していない残念なケースもあるにはありました。これはそれまでのPC経験とはあまり関係は無いようで、どちらかというと学業への取り組み方というか姿勢なような気もしました。これはプログラミングとは直接関係ないことではあるんですが。
どうやらクビにはならなかったようで、来期も講義をすることにはなりそうですがシラバスの微修正もあるようですし、高校で情報を習ってきた子達が入ってきます。世の中も進みますし「AI時代に必要なC言語の知識と経験って何だろう」と自問しながら、内容をアップデートしたいとは思っています。
昨年に講義について書いた記事はこちら。
大学の講義をやってみて
ヘッダ画像は、この記事をAIに要約してもらい、それをプロンプトに与えて生成しました。
いいなと思ったら応援しよう!