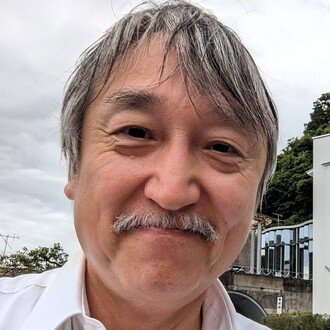MS-DOSの進化と国際化対応 - Version 2.x
16ビット時代のPCを使っていた方にはお馴染みのMS-DOSが登場した時の話は以下の記事に書きました。
MS-DOS(PC-DOS)の登場
MS-DOSは8086ベースのPCでもCP/Mのような使い勝手で使えたことが好まれました(アプリも移植されたものが大半でした)。8086向けにはCP/M-86もあったのですが、細かいところはともかく見た目と使い勝手は似たようなものでした。
IBM-PC向けに用意されたPC-DOSは、XT登場に合わせて階層化ディレクトリなどをサポートしたVersion2となり、IBM(および互換機)以外にもOEM供給されるようになりました。こちらはIBMと関係ないのでMS-DOSという名称が使われました(機種依存する部分を除けば中身は同じです)。最初は供給先ごとに個別にカスタマイズしていたようですが(その名残がコードページの定義に残っています)、ヨーロッパやアジア向けの文字やキーボードの取り扱いを共通化したVersion2.11が作られ、日本ではシフトJIS(厳密にはMS漢字コード)という文字コードが一般的となりました。
MS-DOSを使う時に意識することが多いのがドライブレターで、まだハードディスクは一般的ではなかったので、1台目のフロッピードライブが”A”で、2台目が”B”として使われました。起動時にはDOSのシステムが入ったディスケットを1台目に入れる必要があって、ですから起動後は”A>”というプロンプトが出て使い始めるというスタイルが一般的でした。アプリは”A”に入れ、自分のデータなどを保存するのが”B”というのが普通でしたが、中には3台目、4台目を接続している人もいたので、それらを使う時は”C”であったり”D”となる訳です。これはなかなか直感的で目的にあわせてディスケットを入れ替えて使っていた時代にはわかりやすいものでしたが、入れ替えることのないハードディスクの時代になっても互換性を保つために今でもこの呪縛から逃れられないのが困ったものです。MS-DOSのコマンドを処理する”COMMAND.COM”には必要最低限の内部コマンド(他のプログラムを呼び出さずに実行できる命令)を持っていましたが、多くのコマンドは実行ファイルとしてフロッピーに置かれている必要があり、Aドライブは入れっぱなしで使うのが流儀です。
ところで日本語に関しては、当初はDOSに組み込まれていて各メーカーが用意した日本語変換を使うしかありませんでした。PC-9801の場合、1983年にリリースされたバージョンでは熟語変換しかサポートしておらず頻繁に変換と無変換のキーを押して単語ごとに同音異義語の選択をしなければなりませんでした。これが1986年のバージョンになると文節変換、連文節変換となり使い勝手が上がったのですが、この時代には既に日本語変換処理をデバイスとしてCONFIG.SYSに登録することで好きな日本語変換プログラムを登録できるようになっていて、純正の日本語変換を使う人は少数派でした。
PC98版MS-DOSのバージョン一覧 [PC98]
日本においては少なくともMS-DOSを使っている機種の間では、文字コードは同じでしたし、2DDとか2HDなどのフロッピーの種別さえ合わせればいろいろな機種の間でのデータ交換には不便はありませんでした。もっともアプリは機種ごとに違いましたし、プリンタなどのデバイスもPCの機種ごと、プリンタの種類ごとにちゃんとドライバをインストールしないとなりませんでしたけど。
MS-DOSの普及に日本で一役買ったのが、アプリにDOSをバンドルすることが許されていたことで(その後、この特典は無くなった)、わざわざDOSを購入しなくてもアプリさえ買えば黙ってもDOSが使えました。もちろんアプリを使うのに必要なものしか入っていませんでしたが、単独で使いたいときにはアプリごとDISKCOPYして不要なものを消せば充分なので、開発をするのでなければそれで間に合いました。その中でアスキーのアプリを買うと同梱されてくるMS-DOSは少しカスタマイズされたものが入っていて(確かVersion2.11vと表示されたと思う)、微妙に使い勝手が良かったのを覚えている(コマンドオプションの記号が”/”ではなくて”-”が使えるとかだっけ?)のですが、詳細について書かれているものが見つかっていません。
まだハードディスクも滅多に接続されずネットワークも無い時代、使いたいアプリのフロッピーを入れて起動し、データもフロッピーの単位で目に見える形で管理していた、不便そうに見えて実はとてもシンプルで使いやすい時代でした。OSもアプリに合わせて使い分ければ良いだけでゲームをするならN88のシステムディスク(ゲームはDOSを使わないものが多かった)を入れれば済みました。これが次の時代になると便利にはなったとはいえなかなか面倒なことになってきたんですよね。
ヘッダ画像は、この記事の本文を元にAIに頑張って貰いました。
いいなと思ったら応援しよう!