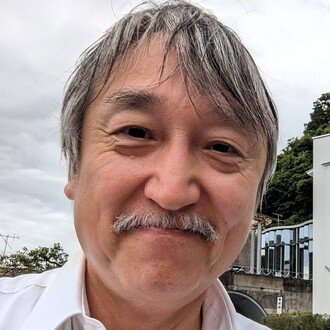ダイナブック大作戦 in 秋葉原
アキバのイベント会場で有名なベルサール秋葉原で東芝ダイナブックのイベントをやっていたので、ちょっと様子を見てきました。

そんなに混んでいるわけでもなく並んだりする必要はありませんでした。中に入るとダイナブックの歴史コーナーや、現役のダイナブックを使ってAIなどを体験するコーナーなどがあり、ステージでも何かやっていたのですが、そこは見そびれました。

こうしてみると1989年のPCって、もうかなりカスタムチップばかりとなっていてあまり古さを感じません。とはいえ今の基板に見えるのはもう豆粒のような部品ばかりで、印象的なのはバッテリーがペラペラとなり、排熱が大変でファンばかりが目立つというところでしょうか。こうしてみるとマイクロフロッピーがとても大きなものに感じます。

残念ながら電源は入っていなかったので(説明の人によるとちゃんと電源は入るよとのこと)、あのオレンジ色のプラズマ画面を見ることが出来なかったのですが、これが高くて重くて持ち運べるけど電源が必要と三重苦なPCだったのですが、とても丈夫に出来ていてデスクトップのように設置をしなくてもすぐに使えるのが当時は魅力だったんです。

どちらというと、このJ-3100SSが周囲では大人気でした。重さも3キロを切りA4サイズで価格も手の届く感じ(約20万)でした。もちろんバッテリでも動作して授業や会議の時間くらいなら持つという感じでした。ノートPCもPC9801勢が強かったのですが独自色が強く、Dynabookの方がちょっとだけ海外製ソフトの互換性が良くて「俺は国際対応した環境なんだぜ」という雰囲気を醸せました。

そしてみんな大好き小型ノートの元祖、Librettoです。実は初代はメモリもディスクもCPUパワーもいろいろ無理があって、私が使っていたのは2代目の30です。これで普通にWindowsが使えるので、ちょっとしたテストをしたり、PCMCIAモデムを差し込んで通信も出来たので、どこでもメールやネットサーフィンが出来たのはとても重宝しました。何せ邪魔にならないので晩年は机の隅に立てかけてパソ通の自動巡回や軽いサービスのサーバとして活躍していました。
まあ、その後もいろいろな機種が出たのですが、ある意味、標準的なものになっていったので、あまり記憶がなかったりします。
最後に開発中というARグラスを体験してみました。特徴的なのがメガネの上部に画面を置いてプリズムで眼の前に投影している構造が多いのに対し、レンズの一部を線の形でプリズムと同じ効果を持たせて投影しているところです。この方法を採用したことでメガネの形状が普通のメガネに近いものとなるそうです。真ん中と左右にカメラも仕込んでいるようですが、まだ活用するアプリは無いそうです。日本の会社は技術力が素晴らしく高品質なものを作れるのですが、よほどうまくやらないとびっくりするコストになりがちで、普及せずにせっかくの技術が活用されないことが多いので、その辺りをどう解決するつもりなのかは気になります。

沢山の写真を撮らせてもらったので、レトロPCシリーズが、その時代まで追いついたら活用させてもらうつもりです(まだパソピア時代なんだよな)。
サクッと見て回った割には密度の濃いイベントでした。
dynabook 35th Anniversay Thanks! (公式)
いいなと思ったら応援しよう!