
文学の意義と作用

はじめに
この記事で取り上げる「文学」とは、飽迄も芸術性重視の「純文学」であり、娯楽性重視の大衆文学は含まないものとする。
途中、現代的な手法への批判も交えるが、直ちに全てを否定するのではない。実験的、前衛的、新しさに目を奪われるがあまり、軸心を失っているのではないかという再考である。
作品執筆の動機

執筆へ至る直接の動機としては、三島由紀夫の文化防衛論の影響がある。日本の文化、謂わば芸道は、死して美術館や博物館に寄贈され、大事に展示され続ける物ではない。今現在この瞬間に、生きた形で心身に継承し、人伝に保存し続けるのである。彼の主張をなぞるに連れて、自身の茫漠とした存在の意味が、少しずつ輪郭付けられてゆく感覚を抱いた。自身も和の心を継承し、次世代に繋ぐ手立ての一つとして、文学を選択した。
三島由紀夫の修飾と表現の多彩さ、精神と肉体の乖離に踠きながらも、統一を目指す姿は痛ましくも美しく、その脆くも強靭な思想と文体の原点を、古典文学や日本文化に据えた。三島由紀夫は晩年、当時から現代までの、日本人としての在り方、日本国家としての在り方を憂い、執筆活動へ励む。彼を完全には踏襲しないが、日本の文化と文学への心緒は、本物であると感じた。
作風としては川端康成の沈静的な日本の美に惹かれた。川端康成は戦後から顕著に、日本古来の美しさと哀しみを作品に反映させる。彼は終わり行く物に美を感じる日本人の感性、花が散る間際に抱く美しさと哀しみ、その相剋を表現する事で、永遠の美に辿り着こうとする。作品の展開が細流のようで、水面に浮かぶ言葉が時に汀へ嵩み、また静かに流れてゆく。川端康成の作風は、日本人特有の美的感覚に触れ、喚起する作用があると感じた。
文学性では夏目漱石の苦悩を基盤に、西洋思想と東洋思想の衝突、過度な個人主義、人と自然の調和、それらの文学観を反映させ、一歩先へ推し進めようと考えた。他所から思想や文化が流入する度に、先人は和魂の重要性を幾度も説いてきた。外来思想と日本の折衷を為すための千辛万苦は、現存の有形文化財や無形文化財の中に、その片鱗が垣間見え、和魂漢才、和魂洋才などの言葉に、先人の精神性が宿る。
文学で成せる事は淡く、手掛かりを作るに限られるが、以下に述べる文学の意義と作用、それらが読者に与える影響を信じ、筆を執るに至った。
文学の意義

文学の意義は曖昧だが、仮に当てはめるのであれば、歴史的意義、文化的意義、精神的意義の三種に枝分かれする。作用については後述するが、意義が作用を喚起し、作用が意義を補填する。そしてその基盤を担う物が文体となる。
•文化と歴史の保存
歴史書が客観的な記録を重視する一方で、文学は主観的で感性的な側面から記録する。文学は人々の生活や、感性の機微を保存する精神史の役割を担う。
松尾芭蕉の『奥の細道』は、江戸時代の旅や自然観を詩的に記録し、随所に鏤められた和歌の抒情から、その時代の精神文化を現代に伝えた。文学の精神表現により、歴史と文化に立体性が付与される。
文化の変容という意味では、近代化による西洋思想の流入に対峙し、日本の伝統や東洋思想を再解釈した夏目漱石の、精神的葛藤と文化的葛藤が示されている。
•精神的救済と自己形成
漱石は東洋思想(儒教や禅)と西洋哲学(英国文学や個人主義)を深く学び、その統合を通じて自己を形成を試みる。西洋の個人主義と日本の伝統的価値観の間で葛藤し、両者の統合を目指す中、物質的な近代化による疎外感を覚え、それらが社会的な調和といかに共存し得るかを模索した。結果、漱石は精神衰弱の境地に陥るが、彼の文学はこの統合の産物と言える。
片や太宰治のような破滅型の作家は、人間関係の構築に励むものの、常に欺瞞や虚偽に陥る。結果、人間としての尊厳を喪失してゆく。一方で斜陽では、没落貴族の精神的革命を美しくも危うく描いている。精神的救済の失敗、自己形成の失敗もまた、文学の産物となる。
文学の作用
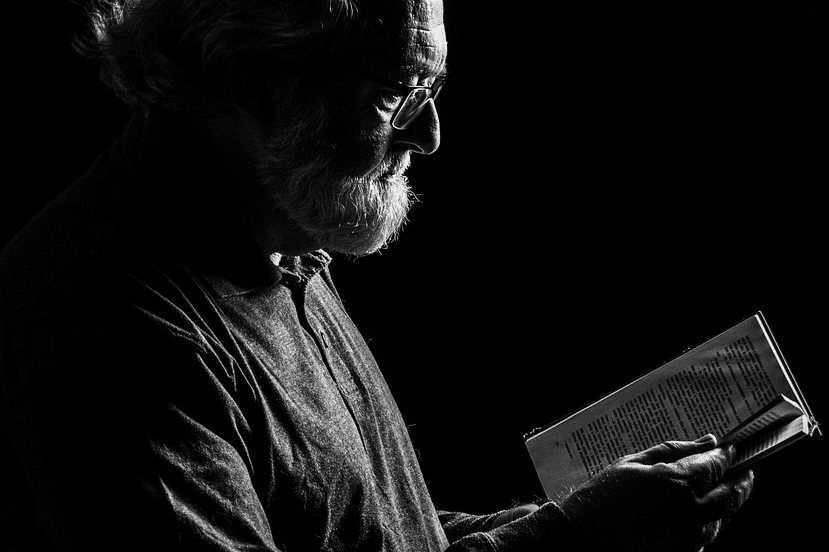
•感性の喚起
絢爛華麗な言葉の連続性が、作品と読者の内的空間を紡ぎ、その独自の精神探求を追体験する事で、作品を通した自身の感性が呼び起こされる。文学作品の言語表現が、読者の中で視覚的、聴覚的、触覚的な心象を形成し、象徴的な表現に留め仄めかす事で、個人の感性は刺激されてゆく。
•認識の変革
一切の存在が物として現れる以前の「道」には名状が無く、言語以前であり分節以前となる。言語により無分節の「存在」が分節され、形而上から形而下へ遷るこの転換点を担うものが言葉である。言葉は事物を明示する道具ではなく、混沌から実在を呼び起こす物である。言葉は事物を輪郭付け、物あらしめる。花という個が在るのではなく、存在が言葉の分節を受け、花の輪郭を帯びている。
或る現象が一定の名を得て、一定の物として凝固するためには、それを他の一切から識別する必要がある。精神現象、物体現象の相反する実在があるのではない、一方より見れば全てが主観に属す精神現象となり、もう一方では全てが客観的物体現象となる。
我々の認識対象は少なからず個性を含んでおり、個々人の経験や思想と智慧が反映されてくる。同一の花を眺むにしても、商人、学者、華道家、芸術家で心象が異なり、心緒の匙加減で美しくも哀しくも、多様な精神現象を想起する。ある存在を花と言う言葉で輪郭付け分節する場合、或いは華や葩卉と定めた場合、それぞれの言葉から想起される認識には差が生じ、そこから形成する現実世界の解釈へ変化を齎す。
文学はこの様な言語作用の連続性を保つ。虚構世界は実像へ投影されてゆき、個々人の認識と行動を癖付ける可能性を秘めている。
文体論

•文体とは
文体とは、作家が用いる言語表現の特徴や形式を指し、語彙の選択、文の構造、律動、比喩など、多岐にわたる要素から構成され、作家が自身の精神性や思想を具象化するための表現形式である。精神の深奥にある情動や理念が、詩的な比喩や独特な語彙を通じて表現され、作家の精神状態や世界観が文体の特性を纏う。
文学作品における文体は、単に作家自身の表現に留まらず、読者の精神性にも作用を及ぼす。文体の美しさや独創性が、読者に深い感動や気づきを与え、読者自身の認識を深め、内的世界を拡大させる。
•文体の形成
自身の文体を輪郭付けた発端は、意外にも文学作品からではなく、西洋画のシュルレアリスムである。「シュルレアリスム」は日本語訳で「超現実主義」となり、「とても現実的な」という表現では無く、現実を超えた現実、ある種の真理に近しい現象を指し示すものとなる。
絵画であればダリの時計が有名だが、原点は詩人のブルトンによる自動記述法であり、自身の純粋な精神作用に働きかけるため、浮かび上がる言葉や情景をひたすらに書き綴るという方法である。その際、事物の連関はなく、脈絡を欠いている作品が出来上がり、宛ら夢の中を漂うかの様な奇怪を極める。
ここで一度、言葉の定義に立ち返って頂きたい。超現実主義とは、現実を超えた現実、或いは過剰現実、過飽和、などとする。であれば「脈絡を欠いた夢のようなもの」を生み出す西洋の描写法や筆記は、端から現実に即していないため、「超現実」の定義に当てはまらず矛盾を抱えている。文学でシュルレアリスムを反映させた作品もあるが、ある種の子供騙しのようで、単に奇抜な前衛性に陥る。
西洋芸術を経た末に辿り着いたのは、伊藤若冲の日本画である。彼の作品はまさに超現実と謳うべき作品であり、自身の文体を輪郭付けた。若冲の仔細な観察による精巧な描写、視野角を超えた緻密な表現、それらが織り成す日本画は、現実を過剰に描写する事で、返って夢幻に至るかのような、夢と現の境を暈す作用を感じた。
具体的な文体形成の成り行きの前に、自動記述法の性質に立ち返る。ブルトンが探った領域は禅や禅問答に近しいと考える。言葉の外郭を剥がし、具象を抽象化してゆく様が似ており、その末には全ての事物の輪郭が剥がれ、一塊の存在へと還るのだろう。しかし、ブルトンの生み出す作品自体は、雑多な意識の塊でしかなく、当の本人は禅に触れたかもしれないが、その詩を読む読者や鑑賞者には、何ら影響を与えない。
文学や小説で禅問答を行い、言葉の意味を剥奪してゆくと、その後何一つ言葉を扱えなくなり、ただ白紙が続くのみになってしまう。であれば発想を逆転すればよい。言葉の外郭、意味を剥がすのではなく、寧ろ過剰なまでの描写による言語と認識の飽和を起こす。その飽和により個々人の言葉と、認識の網目から漏れ出した何かは、逆説的ではあるが意味と外郭が剥奪された「禅」に至ると考える。この作用を読者に体感させる事が、自身の文学と文体により表現され得るかもしれない。
「禅」、「道」、「悟り」の三種は換言可能な類似性があり、文学による言語認識と、芸道や日本文化の精神認識により、これらの境地への手掛かりとなり、失われた精神の復古へ繋がると信じる。
あとがき

このように、読者の心身性へ訴えかけ、作用を及ぼす物が文学たり得る。文学の質は作家自身の精神的な質に直結しやすい。昨今の文学界隈では、文体に拘る作家や読者が減り、平易な言葉を好む傾向がある。作家の色が全く無いとまでは言わないが、表現は中心に寄っており、それにより与える作用も、浅薄な共感に留まる作品が多い。
言語認識の凋落は文化の衰退を招く。読者の皆様はこの事を心に留めて頂きたい。作家がどれほど表現を尽くしても、寧ろ表現に精魂を込めるほど、現代の商業主義を破る事は困難を極め、表に出ることさえ難しい現状に陥る。
作家一人、ただ言葉を紡ぐだけでは、何も成し得る事ができない。行動し続ける作家に、支えて下さる読者の皆様の力が必要となる。
