
大学で学ぶ起業家マインドセット
はじめに
2016年(白鳥,学部2回生),学生ロケット団体RiSAや草津天文研究会に加入したり次々と新しいことに挑戦し始めていた.
専門ゼミ「イノベーションと起業家」
白鳥は物理科学科の専門講義に加え,一般教養科目を取る必要があった.
そこで,興味本位で取った講義が一般教養科目にカウントされる専門ゼミ「イノベーションと起業家」であった.
この講義では,1934年のヒューレット・パッカードのガレージ創業から始まったシリコンバレーの誕生,1968年創業のIntel,1976年創業のApple,そしてスタートアップを囲むエンジェル投資家やベンチャーキャピタルなどの環境を外観した.
白鳥はこの授業ではじめて「イノベーション」や「スティーブ・ジョブズ」について知り,大企業を目指すだけが必ずしも社会的成功の指標ではないことを学んだ.
この講義の担当のK先生には,講義後に何度かランチをご一緒して,白鳥がおこした学生団体SOIL&SOULについて相談に乗っていただいた.
SOIL&SOULの活動は,この講義のメインテーマである「起業家マインドセット」に影響をうけていた.
EDGE+Rプログラムとは
「イノベーションと起業家」の講義に大いにインスパイアされた白鳥は,続く秋セメスターで立命館大学の起業家育成プログラム(EDGE+Rプログラム)に申請した.
このプログラムでは,様々な学部からの参加者でチームを組んで,経営学部の先生方とのメンタリングや起業家セミナーを参考に,ビジネスプランの構築と発表をする.
EDGE+R3期生となった白鳥は唯一の2回生であり,少し寂しかったことを覚えている.
EDGE+Rは文部科学省から支援を受けたプログラムであったため,チームで必要なものは自由に購入でき,見学が必要な場合は,旅費を負担してくれた.
またEDGEの学生らが活動するEDGE+Rルームには,イノベーション関連の書籍や使い放題の3Dプリンターがあった.
さらに,びわこ・くさつキャンパス(以下、BKC)で出会うことのない文系学生や経営学部の教授と議論を交わす機会は視野を広げる貴重な経験となった.
このプログラムでの出会いがきっかけで白鳥はSustaianble Weekに参画していく.
3期生での挫折と学び
デザイン思考とは
EDGE+Rプログラム3期が開始する直前の2016年9月に,大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学(APU)で開催された「デザイン思考ワークショップ」に参加した.

このワークショップでは,デザイン思考の基礎を学び,チームを組んでそのプロセスをすべて英語で体験した.
デザイン思考とは,行動分析やヒヤリングを通して立てた仮説をプロトタイプ製作などにより検証や改善を繰り返すことで,イノベーションを起こす問題解決方法である.
デザイン思考については,EDGE+R3期プログラムでもたびたびとりあげられたため,自然と習得することができたと思う.
このように,一見不可解で急進的な起業家マインドセットをゆっくりと体系的に理解し実践することは刺激的であった.
ちなみに,ワークショップ後は「鉄輪(かんなわ)温泉」「明礬(みょうばん)温泉」「地獄巡り」など,はじめての大分観光を存分に楽しんだ.
APUのおかげで,在学中に合計で3回も別府に行くことができた.
チームの崩壊
2016年10月にK先生のお誘いで,白鳥は「Startup Weekend Osaka」というイベントに参加し,幸運にも最優秀賞をいただいた.

この成功体験は,白鳥に大きな自信を与えてくれたが,同時に少し天狗になっていたのかもしれない.
同時期に始まったEDGE+Rのチーム活動では,自分の意見を棚上げにして,相手のアイデアに難癖をつけるような独善的な振る舞いをしてしまった.
その結果,APUでの発表会において「レゴブロックのようにカスタマイズ可能なバックパックの製作販売」のビジネスプランを1人で発表し,チームメンバーとの関係も疎遠になってしまった.
チームで取り組むことの難しさや他者と協働するための姿勢について多くを学んだ.
ちなみに,「Startup Weekend Osaka」でお会いした立命館大学MOTテクノロジーマネジメント研究科の学生から「ZERO to ONE」を借りて読み,感銘を受けたことを覚えている.
白鳥がアメリカという国を意識し始めたのはこの時からかもしれない.
4期生での挑戦と失敗
デザインドリブンイノベーションとは
デザイン思考がユーザー中心の考え方(outside→in)である一方で,デザイン・ドリブン・イノベーションはユーザーが使いたいワケに注目をして,製品に新しい「意味」を与えることで,ビジョンをデザインすることから始める考え方(inside→out)である.
2017年7月17日にデザイン・ドリブン・イノベーションの提唱者であるミラノ工科大学のロベルト・ベルガンディ教授の講演が立命館大学大阪いばらきキャンパス(以下,OIC)で開催された.
白鳥は,事前に先生の本「突破するデザイン」を読み,あるアイデアを講演後の学生ポスタープレゼンにおいて発表した.
そのアイデアは「ゴミをターゲットに当てることで流れる電力により生じた光で植物を育てる」というもので,本来は面倒な「ゴミ捨て」という行為にストレス解消しつつ植樹をするという新しい意味づけを行うことを目指した.

また,多少英語が話せると思われたか,経営学部の八重樫教授からベルガンディ教授を関西空港まで送り届ける役目を白鳥は仰せつかった.
ここで発表したゴミ箱のアイデアは2017年2月に参加したインド留学での「ゴミ箱改良を通したゴミ発電の提案」にインスパイアされており,「IoTを駆使したスマートビン開発プロジェクト」(現在加筆修正中)につながっていく.
ちなみに,経営学部がOICにあるためEDGE+R関連のイベントはOICで開催されることが多く,白鳥はOICに行く機会が多かった.
立命館大学はOICに加え,滋賀県草津市にあるBKC,そして京都市北区にある衣笠キャンパス(KIC)の主に3つのキャンパスで構成されている.
キャンパス間移動のシャトルバスが毎日でており,電車で行くよりも早く安く移動することができ,小旅行気分を味わうことができる.
また,KICにはオナーズプログラム(現在加筆修正中)で頻繁に行くことになる.
地域活性化コンペ〜奈良〜
2017年6月から始まったEDGE+R4期のテーマは「地域活性化」であった.
今回のEDGE+Rイベントでは,セブン銀行が協賛しており,プレゼン指導やメンタリングをしていただいたうえに,「セブンプレミアムシリーズ」のおにぎりやハンバーグなどが懇親会で振る舞われた.
白鳥が所属したチームのターゲット地域は「奈良県」であった.
京都の影に隠れがちだが,奈良は,東大寺,法隆寺,春日大社などの霊験あらたかな寺社仏閣に加え,鹿サファリパークである奈良公園などの観光資源を有している.
しかし,京都駅から奈良線で奈良駅に向かう途中の車窓を見ると,思ったよりも田舎であることを認識した.
また,奈良公園周辺に主要な観光地が集まっているので,徒歩でも1日でほとんどに行くことができ,さらに寺社仏閣は5時にしまってしまうため,奈良での滞在時間が少ないという問題があった.
当時はSNOWやポケモンGOなどの仮想現実(AR)アプリが流行していることもあり,奈良公園を昼夜問わず動き続ける約1000頭もの鹿をターゲットに鹿せんべいで捕まえるといった内容のゲームを提案した.
しかし,思ったよりも評価されずに,またしても「自分のアイデアに酔っていた」ことを自覚し,恥ずかしい気持ちになった.
ただ,修学旅行を最後に奈良には行っていなかったので,2度も行く機会を得たのはよかった.
ちなみに,地域活性化つながりで,白鳥の故郷を舞台にして「もしサウナを作るなら」という妄想記事を紹介しておきたい.
EDGE+Rの影響
EDGE+R3期と4期での経験を通して学んだ起業家マインドセットを実践するために,白鳥はビジネスコンテストや社会貢献活動などに挑戦し始めた.
Macbook Airを買う
2017年10月17日,iOSアプリを作ってみたくて白鳥はMacbook Airを購入した.

同時に封筒のような見た目のPCケースも購入した.
この封筒のデザインは2008年にスティーブ・ジョブズがMacbook Airの薄さを強調するために用いた小道具とほぼ同じである.

このケースはアメリカの大学院進学して,Macbook Proにアップグレードさせた後も使い続けている.
ビジコンへの挑戦
2017年2月に参加したハワイ大学留学プログラムでの最終プレゼンとして,「キャンパス内でのボードシャアリングサービス」を提案した.
2017年11月には,立命館大学ICT創作コンテスト「あいちゃれグローバル2017」にて,友人たちと作った「読書アプリ」でアイデア賞と副賞でドローンをいただいた.

この読書アプリは「読書記録SNSであるShociety(書斎とSocietyをかけた造語)」を作るために「スマホを置いて読書に集中すること」に特化している.
また,プログラミングだけではなく,デザインの重要性も認識していたため,草津天文研究会の同期でデザインが得意な人に協力してもらっていた.
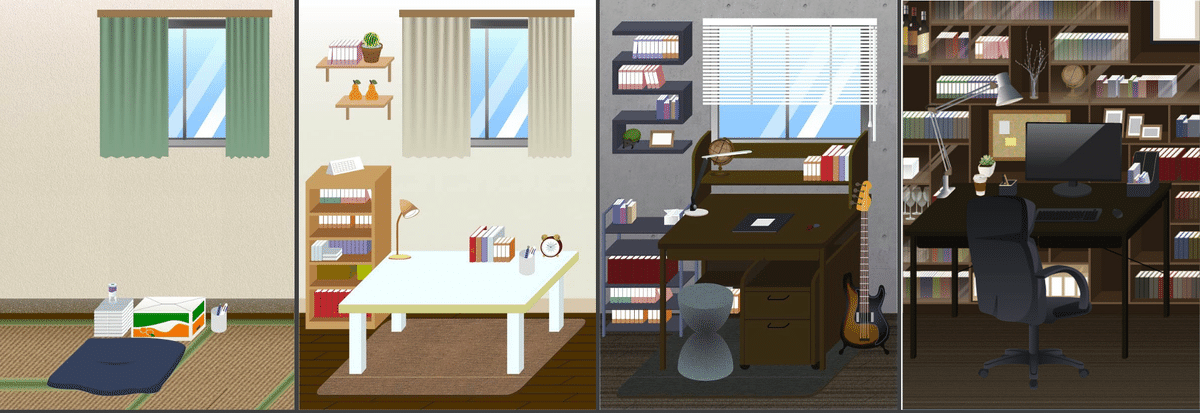
残念ながら,「絶対に挫折しない」と謳ったアプリ教本で,白鳥が挫折してしまったため,リリースには至らなかった.
しかし,自分が良いと思ったことに他者を巻き込み,足りないところを補いながら,さらに良いものにしていく過程は面白いと感じた.
社会起業家への興味
ビジネスによる社会問題解決に興味を持ち始めていた白鳥は,ちょうどキャンパス内でSustainable Development Goals (SDGs)を目指した大きなイベントSustainable Week実行委員会に招待された.
SDGsの「誰一人取り残さない」という目標に共感し,Sustainable Weekでできた「学生」「大学」「地域」の間を自然とつなぐ機能を持ったアプリを開発しようと考えていた.
都合の悪いことは忘却される白鳥の機能により,提案内容はあまり覚えていないが,かなり抽象的で小さなスケールの事業であったことを覚えている.
2017年10月に大阪イノベーションハブで開催された「ミライノピッチ2017」において,日本スタートアップ支援協会の方にメンタリングをしていただく機会があった.
「で,どうやってお金を稼ぐの?」というごもっともなダメ出しに自信を持って答えらることができず,とても落ち込んだのを覚えている.
でも,メンターの方の説明を聞いて逆に納得できてしまい,そのレベルの自信だったということを悟った.
また,2度のインド留学を通して肌で感じた「ゴミ問題」を「ゴミ箱」から解決するべく,プロトタイプ作成にも勤しんでいた.
そして,これらの試行錯誤がスマートビン開発プロジェクトに繋がっていく.
最後に,白鳥がそれまでに構築したコネクションをフルに活用して,「マイボトル促進」と「フードロス減少」を目的に掲げて,スムージーをレシピから開発し,マイボトルと共に学生に販売した.
おわりに
身の回りを見渡すと,かつて誰かが起業して生産したプロダクトやサービスで溢れていることに気づく.
新しい仕事を作り出し,自分の生活だけでなく,他の人の生活を支えながら,社会にインパクトを与え続ける職業に憧れる.
こられの経験から得られた起業家マインドセットは,以降の正課外活動で十分活躍した.
今後将来,ビジネスのみならず,研究などの問題解決にも力を発揮するだろうと信じている.
白鳥もいつか何かでイノベーションを起こせるように頑張りたいと思うであった.
To be continued.
