
【創作童話】おらんだ
ぼくは、かずま。小学四年生。春にはムラサキツメクサが咲きほこる河原づつみの途中に、一人暮らしのばあちゃんの家がある。
今日は、母ちゃんにたのまれて、ばあちゃんの様子を見るために寄ってから家に帰った。
「おかえりなさい、かずま。おばあちゃん、どんな様子だった?」
「おらんだ、だって・・・」
「は? オランダ?」
かあちゃんは、首をかしげた。
「ばあちゃん、風邪で食欲ないみたい。母ちゃんの伝言、伝えたよ。なんでもいいから、食べたいもの、おしえてほしいって」
「ありがとう。でも、オランダって、なにかしら? 聞いたことがないわ」
「それがさ、商品名は確実じゃないんだ。
ばあちゃんの子どものころのお菓子だから、はっきりおぼえてないみたい。
でも、国の名前にはまちがいないって」
「そう? パパが帰ったら聞いてみましょう」
父ちゃんに聞いてみたけど、オランダというお菓子は、父ちゃんも知らないということだった。
「ニューヨーク・チーズケーキかしら? それとも、ベルギー・ワッフルとか?

母ちゃんが言った。
ばあちゃんのことはもちろん気がかりだ。
でもそれ以上に、ばあちゃんが子供のころに食べたという、謎のお菓子を推理することに、ちょっぴりワクワクするボクらだった。
父ちゃんが、うで組みをして言った。
「昭和初期。商品名は国の名前。かずま、おばあちゃん、他に何か言ってなかったか?」
ボクは、思い出しながら答えた。
「子供のころ、みんなあこがれたって」
「駄菓子とか、おまんじゅうでないことは、たしかだわね。高級な洋菓子かしら?」
母ちゃんが言った。
ばあちゃんは、なんとかゲッチューとか言っていたから、ボクはそのとおりに伝えたんだけど、母ちゃんから
「和洋せっちゅうじゃない? かずま」
と、笑われた。
でも父ちゃんが、さらにとんちんかんなことを言い出した。
「タイやきだ! カスタード・クリームの!」

「タイの意味がちがうわよパパ・・それともうなぎパイかしら?」

答えがだんだん遠のいてゆく。この二人からは、答えをみちびき出せないとさとった。
ボクは、ばあちゃんに電話で聞いてみた。

「もしもしばあちゃん、具合どう?」
「ああ、かずまかい? だいぶいいよ。ありがとう」

「ところでさ、ばあちゃんの食べたいお菓子のとくちょう、おしえてくれない?」
「いいんだよ。そんなこと・・・」
「えんりょは無用だよ。ボクも興味あるしさ」
ばあちゃんによると、カステラにようかんがはさんであるという、夢のようなお菓子だ。
もしかしたら、同じクラスのまことに聞けばわかるかもしれない。まことのおじいちゃんは、若いころ、菓子職人をしていたと聞いたことがある。
翌日、ボクはさっそく、まことにたのんで、一人ぐらしのおじいちゃんの家につれていってもらった。
あごヒゲのにあう、ダンディなおじいちゃんだった。
「それはたぶん、シベリアだよ」
まことのおじいちゃんがおしえてくれた。
「どこに行けば買えますか?」
「この辺ではもう、売っていないよ。なんなら、ワシが作ってあげよう」
「えっ? いいんですか?」
「なあに。困った時は、おたがいよ!」
それからボクと、まこともてつだってくれて、シベリアを作ることになった。
鍋に水、かんてん、さとうをくわえて火にかけ、こしあんをとかす。これをおじいちゃんの焼いたカステラの上に流し、さらにカステラでサンドして、冷蔵庫で冷やす。
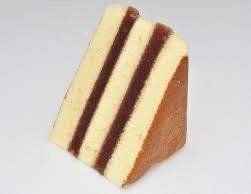
出来上がったシベリアの断面は、雪原に線路が走っているようだ。そう。まるで、シベリア鉄道のように。
ボクのばあちゃんと、まことのおじいちゃんは、玄関先で昭和の話に花を咲かせていた。
「まあ、立ち話もなんですので。
ささ、どうぞお上がりくださいな。まことくんも、さあ。かずま、座布団を出しておくれ」
「おじゃましま~す!」
まことが元気よくあいさつすると、おじいさんもあとにつづいた。
「今、おいしいコーヒーをいれますからね」
「それにしてもばあちゃん、オランダはないよなあ・・・」
ボクが言うと、ばあちゃんは言った。
「かずま、恥かかすんじゃないよ!」
ぼくは、シベリアの甘さをたよりに、はじめてのブラック・コーヒーにちょうせんした。

コーヒーはほろ苦く、ボクはちょっぴり、おとなになったような気がした。
おわり
