
知識0経験0からつくれる/売れる遊廓本の造り方
『遊廓文学マーケット』を告知しました。関心のある方は是非ご参加下さい。
グッズ製作はSUZURIなど簡易的に作れるサービスが一定以上普及し、ノウハウも蓄積されている印象ですが、いっぽう本については、まだまだノウハウが共有されていないようです。
本稿では、日頃慣れ親しんでいる活字でありながら、いささかハードルが高い本づくりについて、知識0経験0でもつくれる方法と売り方について、ご提案します。
なお本稿は『遊廓文学マーケット』への参加を検討中の方に向けた内容です。商業出版やその他自費出版を想定したものではないこと、加えて分かりやすさを重視して意図的に単純化していることを予めお断りします。
まず結論から
見た目が良くても売れるとは限らない
安くても売れるとは限らない。
いささか先走り過ぎですが、行き着くところ以上の2点になります。天邪鬼のようですが、裏を返せば「デザインに自信がない人でもチャレンジできる」「安くつくるノウハウがない人でもチャレンジできる」のが、マーケットの魅力です。具体的に提案していきます。
プロ向けツールを使わずとも本はつくれる!
以下、難易度別に2パターン用意しました。本来もっと選択肢はありますが、選択肢が多いほど迷いも増えるので、敢えて絞っています。ツール選定に時間を消費するほど、肝心の製作に割ける時間が減っていくので。
一定クオリティのある本を作りたい人向け(パソコンいじりが好きな人、HTML程度なら触ったことがある人向け)
一番楽につくりたい人向け(その他ビギナー向け)
一定クオリティのある本づくり
プロ業界ではDTP関連ソフト(Adobe社のIndesign、Illustrator、Photoshopなど)を用いるのが標準ですが、近年では必ずしも専門的な知識や経験がなくとも、一定水準のクオリティを保った本をつくれるツールが提供されています。
BCCKSがおすすめ
サブスクといえども、Adobe製品は安くはない月額料金。これを払わずとも、ブラウザからテキスト入力して、そのまま本を作れるサービスに「BCCKS」があります。利用料は掛からず、無料で使い始めることができます。(当然ですが、印刷・製本には料金が掛かります)
他にも同種のサービスがありますが、文字組み(紙面デザイン)のセンスや紙の質感など、「本を持つよろこび」を叶える仕様をもっとも備えていたのがBCCKSです(独断です)。

つくることができる判型サイズ
文庫・新書・10インチ・A5変型と多様です。サイズ選びの目安は以下です。
活字主体・文芸→文庫 or 新書
図版や絵を多用した内容→10インチ or A5変形
豆本やカードブック(切り離して使える絵はがき本)などグッズと本の中間アイテムもつくることができます。写真を撮る人ならカードブックと相性が良さそうですね。


コスト感
文庫サイズ・モノクロ48ページで500円+税、1部からの注文も可能で、余剰在庫を抱える心配からも解放されます。つくる前は単価に目が行きがちですが、実は在庫管理がとても重要です。
縦書き対応も嬉しいです。資料を引用する際などに多用するルビ(読み仮名や註)や異体字にも対応しています。
実はこれを書いているカストリ書房の店主も、時間を掛けてあれこれ選定した結果、BCCKSでスタートしました(現在はAdobe利用)。Indesignなどを用いた方が完成度が高い書籍を作ることができることは自明でしたが、大事なことは「情報提供」と「コスト回収までのスピード」であって、「どれだけ時間が掛かっても見栄えの良い本をつくること」がゴールではありませんでした。(見栄えの良い本が沢山並んでいる出版・書店業界が大不況である事実を忘れないでください)
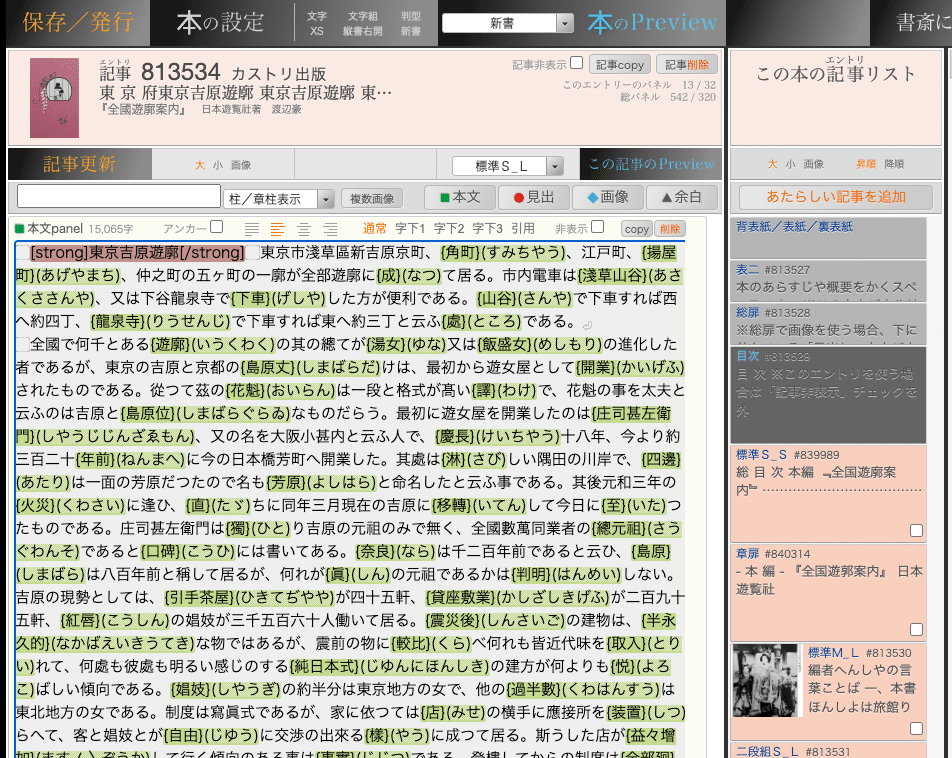
2014年に、幻の奇本とされていた『全国女性街ガイド』を復刻して販売したところサラリーマン時代の月収を超えたため、前職を辞める踏ん切りがついたというのは個人的余談ですが、復刻したことで著者のご家族と縁ができ、私的な資料などもお借りして、次の本をつくることができました。「どれほど優れた内容を頭に蓄えていても、世間に知って貰えない限り、次に繋がらない」「後々ブラッシュアップの機会はあるが、スタートの機会はそうそうない」という当たり前のことを再確認したのでした。
一番楽につくる方法
既製品をうまく使おう
極論を言えば「本」とは背を綴じられた複数ページからなるものです。したがって「本」であるためには、本屋さんで売られているような本(無線綴じ中綴じ&カバーつき)である必要は必ずしもありません。一番楽につくるには、コピー用紙にプリントアウトした紙をスライドファイル(レールファイル)を使って綴じるのも一案です。以下はキングジム製で単価60円ほどです。
強調したいのは「大切なのは中身」です。実際、私はスライドファイルで綴じた論考を頂戴したことがありますが、類書がなく、一番大切にしている本の一つです。
ちょっと手間を掛けるなら、表紙代わりに厚紙で挟んで二つ折りの真ん中を手縫いで綴じれば本が出来上がり。厚紙の種類や縫い糸の色を変えるだけでも無限の組み合わせができます。
「折本」で豆本をつくるのもいいですね。
本である必要さえない?
更にもっと言えば、本である必要さえないのかも。コピー用紙に手書き(手描き)し、コンビニで必要な部数だけコピーするだけでも。カラフルな半透明のグラシン紙と重ねてOPP袋に入れてもいいですし、巻物のように好きな色の紐で真ん中を縛っても。
実例を示すと、オリジナルの地図を作画し、家庭用インクジェットプリンターで厚紙に印刷したペライチ(冊子ではなくチラシ状のもの)をOPPに入れて1,000円で販売。飛ぶように売れているクリエイターさんが実際にいます。
いずれの方法でも、一番のメリットは「最小限つくって、売れた分をすぐに追加生産できる」こと。
大量生産より、少量生産&高サイクル
つい最初は「いかに安く生産できるか」に目が行きがちですが、基本的に「安さと生産量は比例関係」です。ほどほどの価格を保ちながら、「少ない数量(ロット)で、安価な再生産のサイクルが構築できるか?」が重要になってきます。
売り方
実のところ一番悩むのは値段ではないでしょうか? さまざまな考えはありますが、一つ間違いなく言えることは「安さが理由で売れることは、ほぼ100%ない」です。「自信がないから安くしよう…」という声をまま聞きます。もちろん値づけは自由なので、高価・廉価に良し悪しはありません。ただし、自信がないものを安くしたからといって売れる可能性もないのです。
10万円単位の作品がやすやすと売れることもありませんが、敢えて極論を申せば、2,000円以下の本であれば、1,300円でも1,800円でもほぼ売れ行きは変わりません。マーケットという場がある種の非日常的なイベントなので、数百円の差はあってないものです。
コスト計算は「3:3:3」
製造コストと販売価格のバランスは、まずは製造コストの3倍近辺が適当です。ざっくり小売店側の利益に3割、製造コストに3割、残り3割が作り手の利益です。例えば製造コストが1部500円なら販売価格は1,500円になります。もちろんコストカットできるほど作り手側の利益率は良くなります。手売り前提にするなら、小売店側の利益は不要なので、原価コストを上げたり、作り手の利益UPが望めます。ただし、最初はそう考えていても、在庫が余ってしまったが、原価割れしてしまうので卸すに卸せない=在庫を死蔵しつづける人の存在を仄聞するので、いったんは「3:3:3」で考えてみるのがおすすめです。
おわりに
作り方と売り方(値付け)は以上です。まずは手を動かさなければ何も生まれません。事前にあれこれ悩むよりも、トライ&エラーで学んでいけることが沢山ありますし、なによりも作り手になることで見える景色が変わってくることが得られる大きな一つ。本をつくり始めると、これまで読み飛ばしていた文章や本に興味を覚えることも沢山あります。
マーケットで売れる本は、必ずしも「見栄えの良い本」「安い本」であるとは限りません。一言で言い表すなら「作り手の動機が見える本」です。解釈は人ぞれぞれですが、「自分が面白い」と感じるテーマを、「自分のできる範囲」でつくる。売るタイミングでは「商業流通のマーケティングを過信しない」ことが大切。
『遊廓文学マーケット』は同好者が集まるので、みな暖かく迎え入れてくれるはずです。気後れせず、是非チャレンジしてみて下さい。
