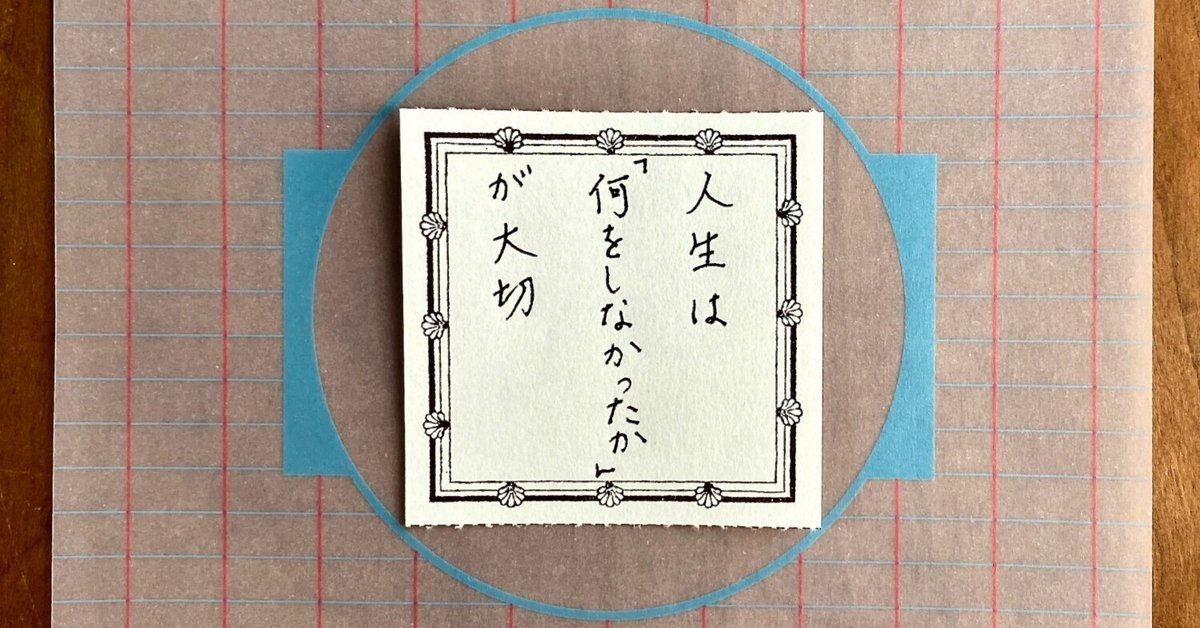
人生は「何をしなかったか」が大切
今年最初のエッセイです。
少し長いですが、もしよろしかったら。
新しく始めたエッセイの連載です。
毎月、15日と30日の夜に、アップする予定です。
バックナンバーは、『人生は「何をしなかったか」が大切』というマガジンに入れていきます。
人は「人生で何をしたか?」で判断されがちです。
でも、「何かしなかったか」を誇りにしてもいいのではないでしょうか。
何かを成しとげてこそ、人生を生きたと言えるのか?
人は「人生で何をしたか?」で測(はか)られがちだ。
私も10代のころは、「自分は将来、何をするんだろう?」と夢見ていた。
夜、眠る前のふとんの中などで。
たくさんの人たちが、いろんなすごいことを成しとげている。
アインシュタインが相対性理論を考え出したり、ダ・ヴィンチがモナリザを描いたり、始皇帝が中国を統一したり。
もちろん、そんなすごいことは自分にはできない。
そんなことはわかりきっている。
それでも、もっと小規模でいいから、何かをしたいと思っていた。死ぬときに、「自分は人生でこういうことをした」と思えるようなことを。
逆に言うと、何もない人生をおそれていた。
死ぬときに、「何もできなかったなあ」とガッカリするとしたら、それはすごくつらいことではないかと思っていた。
ダ・ヴィンチがこんなことを言っている。
あたかもよくすごした一日が
安らかな眠りを與(あた)えるように、
よく用いられた一生は
安らかな死を與(あた)える。
私は「いやなことを言うなあ」と思ってしまった。
夜、寝るときに、ものたりなさを感じることがほとんどだからだ。なかなか一日を「よくすごす」ことなんてできない。
だとすると、人生の最後にも「安らか」ではいられないということだ。
なんていやな予言だ。
これが一生か、一生がこれか
それでも10代のころは、まだ未来がたっぷりあると思っているから、「まあ、人生に何かあるだろう」と楽観していた。
たしかに〝何か〟はあった。
でも、思っていたものとはまるでちがっていた。
20歳で難病になったのだ。
そこからは20代はまるまる、そして30代になっても、ずっと闘病生活だ。人生は闘病一色。
これが「野球しかやっていなかった」とか「絵しか描いていなかった」とかならいいのだが、「闘病しかしていなかった」では、じつにむなしい。
人生が空っぽどころか、マイナスだと感じた。
何もしていないどころか、ずっと溺れかけているのだ。
トイレに行ったりしたとき、ふと「自分の人生はこれだけなのか、これが自分の人生なのか」と思うと、ふいに涙が頬を流れたりして、自分でも驚いた。
樋口一葉の「これが一生か、一生がこれか、ああ嫌(いや)だ嫌だ」という言葉が身にしみた(「にごりえ」『樋口一葉 ちくま日本文学13』ちくま文庫)。
最近、雑誌「BRUTUS」のNo.1008で「一行だけで。」という特集をやっていて、穂村弘さんがこういう短歌を紹介していた。
眠らむとしてひとすじの涙落つ きょうという無名交響曲
大滝和子『銀河を産んだように』砂子屋書房
解説にはこう書いてあった。
何事もない一日が過ぎて、何者でもない自分が、誰にも知られないまま、世界の片隅で眠ろうとする。その時、不意に「ひとすじの涙」がこぼれた。悲しいとか淋しいとかは、よくわからない。ただ、今日という日を生きた命の雫のような涙。「むめいこうきょうきょく」の中には「きょう」の響きが隠されている。
「何者でもない自分」
「誰にも知られないまま」
「世界の片隅で眠ろうとする」
ということが、私もひどくこたえていた。
「何をしなかったか」の大切さ
でも、今はまったく考えがちがう。
2022年2月28日に私はTwitter(現X)にこうツイート(現ポスト)した。
「何をしたか」で、人を評価しすぎだと思う。
— 頭木弘樹📕UC『カフカ断片集』『口の立つやつが勝つってことでいいのか』『食べることと出すこと』 (@kafka_kashiragi) February 28, 2022
「何をしなかったか」も、とても大切。傷つけなかった、人の上に立とうとしなかった、差別しなかった、欲に溺れなかった……。
人生を振り返って、「あれをやった」と感慨にふけるのもいいが、「あれをやらなかった」と誇りするのもありだと思う。
どうしてそう考えるようになったかというと、最初はこんなきっかけだった。
昔の知り合いと久しぶりに集まったときに、ある女性が再婚を報告して、こう言った。
「わたしの今の夫、すっごく素敵なの!」
どんなのろけを聞かされるのかと思ったら、
「お酒をぜんぜん飲まないの!」
と、それだけで終わった。
(えっ、それだけ?)と内心、思った。
まあたしかに、大酒飲みよりはいいかもしれないけど、素敵と言うほどの長所だろうか。むしろ、お酒をいっしょに楽しめないのは欠点と思う人も多いのでは。そんなふうに思った。
でも、あとから知ったのだが、彼女の前の夫は、アルコール依存症になり、暴力暴言その他、さんざん苦労したのだそうだ。なんとか別れることができて、それでもしばらくは男性恐怖症にもなっていたらしい。
だから、お酒を飲まないということは、彼女にとっては大変な長所なのだ。
「大酒飲みよりはいいかもしれないけど」などと軽く考えた自分を反省した。大酒飲みの夫がどれほど大変か、リアルに想像できていなかった。
リアルに体験した彼女にとって、お酒を飲まないということは、光り輝くほどの美点なのだ。
このときまで私は、人の長所というのは「何かができる」ことだと思っていた。「仕事ができる」とか「親切にできる」とか。
しかし、「何かをしない」ということも、また長所になりうることに、このとき初めて気がついた。
カフカが"書いていなかった"こと
もうひとつ、こういう出来事もあった。
私は以前から、カフカと2回も婚約した恋人のフェリーツェが、どうしてカフカを好きだったのか、不思議だった。
カフカはこんな手紙を送ってくる人だ。
将来にむかって歩くことは、ぼくにはできません。
将来にむかってつまずくこと、これはできます。
いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです。
神経質の雨が
いつもぼくの上に降り注いでいます。
今ぼくがしようと思っていることを、
少し後には、
ぼくはもうしようとは思わなくなっているのです。
こんなことをラブレターに書いてくる人と、つきあいたいだろうか?
1回目の婚約はまだしも、それが破棄になったあとも、再度婚約しているのだ。カフカのどこをそんなにいいと思ったのか?
その答えがわからないまま、私は『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)というカフカの伝記本を書いていたのだが、カフカの友人の医師で作家のエルンスト・ヴァイスが、フェリーツェのことをこんなふうに評したというのだ。
「相手のベルリン女性はただ実務だけの人間であって、『時代の毒』にもっとも染まった女であり、生活をともにできるはずはない」(池内紀『フランツ・カフカの生涯』新書館)
フェリーツェは当時はまだ珍しかったキャリアウーマンで、10代でタイピストからスタートして20代前半で大手企業の管理職まで出世した人だ。
そういう女性には、こういう反応を示す男性のほうが当時は多かっただろう。未だにそういう男性が少しはいるくらいなのだから。
しかし、カフカはまったくちがう。そんなことは思いもしなかっただろう。
そこでハッと気がついた。
カフカの日記や手紙には、「男らしく」とか「女らしく」とか「男だから」とか「女だから」とか、そういう言葉がまったく出てこない!
出てくる言葉には気がついても、出てこない言葉には気がついていなかった。
盲点だったと思った。
その人が何を書いたかだけでなく、何を書いていないかにも注目しなければと、このとき肝に銘じた。
ともかく、カフカには、そういう魅力があったわけだ。
男性社会の中で、周囲の男性たちからの批判的な目につねにさらされていたフェリーツェにとって、そういう批判を思いつくことさえないカフカは、どれほど素敵に見えたことだろう。
他にはなかなかいない、かけがいのない存在であったはずだ。
なるほど、これは2回婚約してもおかしくないなと思った。
カフカの魅力もまた、男女差別をしないという、"しない魅力"であったわけだ。
もちろん、これは推測で、フェリーツェが本当はどう思っていたのかは当人にしかわからないが。
ヴィヴェカナンダ師の言葉
その後、ネットでこんな言葉に出合った。
もっとも偉大な人々は、人に知られることなく死んでいった。
人々が知るブッダやキリストは、第二流の英雄なのだ。
ロマン・ロラン
おおっ、こんな言葉があったのかと思って、感激した。
ぜひラジオで紹介しようと思って、出典を調べたのだが、これがなかなかわからない。
困り果てて、図書館のレファレンスの方に相談したら、なんとロマン・ロラン全集をすべて調べてくれた。
でも、出てこなかった。
ついには、ロマン・ロラン協会に問い合わせてくれて、その答えは「ロマン・ロランにそういう言葉はない」というものだった。
詰んでしまって、けっきょくラジオでは紹介できなかった。
じつは、名言にはこういうことがよくある。出典を見るとちがう言葉だったり、そもそもそんなことは言ってなかったり、別の人の言葉だったり。名言紹介の難しさは、ほぼ出典探しにあると言ってもいいほどだ。
あとでわかったのだが、この名言は「別の人の言葉だった」というパターンだった。
ヘンリー・ミラーが『冷房装置の悪夢』という本のエピグラフで、ヴィヴェカナンダ師の言葉を紹介している。
この世のもっとも偉大なる人々は、無名のまま消えて行った。われわれの知っている仏陀やキリストごとき聖人も、世人が知らぬそれらの偉大なる人々にくらべるなら、二流の英雄にしかすぎない。
ヴィヴェカナンダ師というのは、インドのヒンドゥー教の出家者で、ロマン・ロランは彼を強く支持していたそうだ。それでこういう混乱が発生したのだろう。
出典はわかったが、宗教家の言葉というのは、たとえば「右の頬を打たれたら、左の頬も差し出しなさい」のように、素敵だけれども、一種の理想論なので、少し残念だった。
もっと日常的な実感から語っている人はないものかと思った。
自分がしなかったことを誇りに
シオランの本を読んでいたら、こんな言葉にぶつかった。
自分がしたことを誇るのもよかろう。だが、それよりも私たちは、自分がしなかったことを、大いに誇るべきではなかろうか。その種の誇りを、ぜひとも創り出すべきだ。
ずばりの言葉だ。
しかもシオランは、「若い人たちに教えてやるべきことはただの一事、生に期待すべきものは何ひとつとしてない、少々譲ってもほとんど何ひとつない、ということに尽きる」(『生誕の災厄』新装版 出口裕弘訳 紀伊國屋書店)などという、みもふたもないことを言う人なので、決して理想論でもない。
さらに、このシオランの言葉について、山田太一がインタビューでこう語っていた。
ルーマニアの哲学者エミール・シオランが、「みんな何かをなしたことで表彰されるけれども、もしかすると、しなかったことでほめることが必要かもしれない」というようなことを書いていますが、ぼくは、そこにすごく共感しています。
————しなかったことでほめる、というのは?
たとえば、戦争をしなかったとかね。それはすごいことだと思います。しなかったことでこの世を潤(うるお)したとか、そういうことも考えたほうがいいと思うんです。しなかったことを探すと、たくさんありすぎて、表彰するのに困ってしまうかもしれませんが……。それでも、しなかったことで表彰してもいいんじゃないかという考え方自体、ぼくはとてもいいセンスだと思いますね。そういうのがいいなあと思ってしまう。
私は山田太一の大ファンで、今ではスタジオジブリの『熱風』という雑誌で「山田太一といっしょに山田太一ドラマをすべて見る」という連載もさせてもらっている。
それなのに、まず真っ先にこの発言に気づかなかったとは!
あるいは、山田太一のこうした考え方に感化されて、私もそういうふうに考えるようになったのかもしれない。
シオランも、「理念は、私たちの腸(はらわた)から立ちのぼってくるものではない」「掛け値なしに私たちのものであることなど、絶対にない」と言っている(『告白と呪誼』)。
「何をしなかったか」という目で、あらためて周囲の人を見てみる
上の山田太一の言葉にあるように、もし「戦争をしなかった」としたら、これはものすごいことだ。
もしヒトラーが虐殺をしなかったら、どんなに多くの人が助かっただろう。
きっとそういう「しなかった」人たちもたくさんいたはずだ。
しなかったから、誰も知らないだけで。
誰も知らない——。
ここに「何かをしないこと」の問題点がある。
ヒトラーが虐殺をしなかったら、ただの無名な画家だったかもしれない。
ヴィヴェカナンダ師も「この世のもっとも偉大なる人々は、無名のまま消えて行った」と書いている。
せっかくいいことをしたのに——いや、ひどいことをしなかったのに、誰にも気づいてもらえないのだ。
これはものたりないことだと思う。
人にはどうしたって、自分のやったことを評価してほしい気持ちがある。
「しないこと」だって、それは同じだろう。
「したこと」には気づいてもらえるが、「しないこと」には気づいてもらえない。
何かをしなかった上に、それを評価してもらうこともあきらめなければならないのだ。
これはそうとうの精神力を必要とする。
シオランの言うように、「自分がしなかったことを、大いに誇るべきではなかろうか」。
やったことを自慢する人は多いのだから、やらなかったことも自慢していいだろう。
自慢はいやだとしても、せめて自分の中では、「大いに誇るべきではなかろうか。その種の誇りを、ぜひとも創り出すべきだ」と思う。
そして、周囲も、なるべく気づいて上げるよう、心がけたいものだ。「この人は何をしたか」だけでなく、「何をしなかったか」という目で、あらためて相手を見て見るのだ。
そうすると、今まで気づかなかったよさに気づけるかもしれない。
したこととちがって、しなかったことは、意識しないとなかなか気づけない。私のカフカの場合がそうだったように。
しかし、意識すればかなり気づける。そのちがいは大きい。
老子とクマのプーさん
しなかったことで有名な人も、世の中にはいる。
たとえば、老子だ。
なにも為さないということを為し、
なにも事がないということを事とし、
なにも味がないということを味とする。
などと述べている。
無為自然な生き方をして老子は尊敬された。
また、先のツイートをしたときに、クマのプーさんが、
何もしないをする。
と言っていることを教えてもらった。
本の中でではなく、映画「プーと大人になった僕」の中のセリフだそうだ。
プーさんのこの言葉も素敵で、プーさんはとても愛されている。
老子もプーさんも、特別な存在で、マネをするのは難しい。
でも、こういう2人(ひとりと一頭?)がいることも、頭の片隅においておくと、何もしないことを、より楽しめるし、誇りにできるのではないだろう。
「もっとも輝かしいもの」
モンテーニュの『エセー』は、私が今書いているようなエッセーの源流のようなものだが、そこにこう書いてあった。
われわれは大馬鹿者である。だからこんなことを言う。
『あの人は生涯を無為のうちに過ごした。私は今日何もしなかった。』
——なんだと。あなた方は生きたではないか。それが、あなた方の仕事の根本であるばかりでなく、もっとも輝かしいものではないか。
私には、この言葉がとてもしっくりきた。
「何もしなくも、人生を生きたと言えるのか?」という問いへの、ひとつの答えだと思う。もちろん、「言える!」という答えだ。
生きているだけで、もう充分にすごいことだ。
さらに「何かをしなければ」と思う必要はない。
もしさらに何か心がけるとしたら、「何かをしない」ことも意識してみる、というのがいいのではないだろうか。
「◯◯をしない」を新年の目標に
新年の目標を決めた人も多いだろう。
それはきっと「◯◯をする」というかたちをとっているだろう。
もしよかったら、そこにもうひとつ、「◯◯をしない」という目標を加えてみるのはどうだろうか?
それも面白いのではないだろうか?
私はまず「その人が"何をしないか"で評価する」を今年の目標のひとつとしてみたいと思う。
いいなと思ったら応援しよう!

