
「色彩に着目して絵画展を楽しむ」(上級編)【鑑賞力向上のヒント③】
こんにちは!
今回は、前回の記事「色彩に着目して絵画展を楽しむ」【鑑賞力向上のヒント②】の続編として、展覧会で「色」に注目しながら展示を楽しむためのヒントをいくつかお送りします。
★前回記事「色彩に着目して絵画展を楽しむ」(初級編)
https://note.com/karubi7799/n/nb65c9a5450d6
今回は少しだけマニアックになりますので、後半部分は購読者のみ限定公開とさせていただきますね。
着眼点④:反対色に注目する
さて、「色」のチェックに慣れてきたら、色の組み合わせで画面を見てみるのも面白いです。その切り口として、色相環上の反対色(補色)を見てみるのがオススメです。
17世紀の科学者アイザック・ニュートンは、太陽光線をプリズムに通して分光し、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫が連続的に含まれていることを発見します。この色のグラデーションを、円環状のチャートに並べ直したものを「色相環」と呼びます。

この「色相環」上で、ちょうど対角線上にある色同士を「反対色」「補色」と呼びます。たとえば、「藍色」と「黄」、「赤」と「緑」、「オレンジ」と「水色」などの組み合わせですね。
この色彩の特徴は19世紀に入って学術的な研究が進み、高度に理論化されていくことになりますが、画家たちはそれよりもはるか以前から、反対色同士を近づけて置くと、互いの色が鮮やかに引き立つ効果を直感的に解していました。特に油絵が普及したルネサンス頃から、カンヴァス上に反対色を意図的に並置した作品が目立ちはじめます。

近代になると、もはやこの「反対色」の活用は基本公式のような状態になっていきます。「色彩の魔術師」と呼ばれたロマン派の巨匠ドラクロワをはじめ、ゴッホ、マティス・・・と色彩を得意とした多くの画家が反対色を活用することで、メリハリのついた画面づくりを図っています。


作品をパッと見て、画面から「あざやかな絵だな」という印象を受けたら、ぜひ一度、画面上に反対色が使われていないかどうか探してみて下さい。大抵の場合、どこかで採用されているはずです。
着眼点⑤:絵画の「背景」に使われた色彩に注目する
ところで、私達は絵画を見る際に、宗教画でも風景画でも、たいていは手前に大きく描かれた人物などを目で追ってしまいがちです。もちろんそれは自然なことであり、全く問題ないのですが、時折「背景」に意識を向けてみるのも面白いです。主題を引き立たせるために、それぞれの画家がどのように「色」に工夫をこらしては背景を描いているのか見ていくと、意外な気づきが得られます。
たとえば、ルネサンス以前の作品では、描かれた聖人たちの背後は「金」一色で覆われました。薄暗い教会内でも、一際高い祭壇の上に設置されると、まるで聖人の姿が光り輝いて見えたかもしれません。

ですが、もう少し時代が下ってルネサンス期に入ると、背景には「金」ではなく、屋外の風景が描かれるようになります。油彩技法の普及とともに、ダ・ヴィンチが「空気遠近法」「スフマート」を開発するなど、立体感をもって対象を描く技法が発達していったからです。

さらに17世紀以降になると、同じ屋外でも、金色の光に包まれた夕暮れが背景に好まれるようになっていきます。遠方の背景を見て、夕暮れのグラデーションが美しく表現されていたら、「これはバロック期の作品かな?」とあたりを付けても良いかも知れません。

一方、バロック時代は、室内画の背景も大きく様変わりします。つい300年ほど前は「金」で表現された背景が、今度は「黒」で表されるようになるんです。
例えば、この時期に活躍したカラヴァッジョ、レンブラント、ベラスケスらの作品の「背景」を注目してみましょう。


ネット上の画像で見ると、彼らが描いた背景はみな漆黒の闇に包まれているように見えますね。ですが、実物を見ると、「黒」ではなく、微妙に藍色やグレー、焦げ茶色が含まれた「黒」なんですね。
オンラインの画像上ではこうした微妙なニュアンスは全部消えてしまうので、展示室で実物を見る時ならではの「ぜいたくな愉しみ」でもあります。
ちなみに、自分はエル・グレコの背景描写が特に好きで毎回注目して見てしまいます。

銀と茶、銀と紫を混ぜたような複雑なニュアンスの背景や、聖人達をとりまくオーラの描き方も個性的です。人物の聖性を高め、演出効果を高めるため、気を使って入念に色彩を選んでいることに気付かされます。
着眼点⑥:聖母マリアはなぜ「青」のケープを羽織っているのか
西洋美術の絵画展を繰り返し見ていくと、もっともよく目にする人物が、聖母マリアです。幼子イエスとセットで描かれた「聖母子像」、天に昇っていく「聖母被昇天」など、様々なバリエーションがありますよね。

ところで、聖母マリアはなぜみな一様に「青」のケープを身にまとっているのでしょうか?着ている服は赤や白などバリエーションがみられますが、その上から羽織るケープは、必ずといっていいほど「青」と決まっています。
これには、何か理由があるのでしょうか?
こういうときは、まずググったり、AIに聞いてみるといいでしょう。便利な時代ですよね。
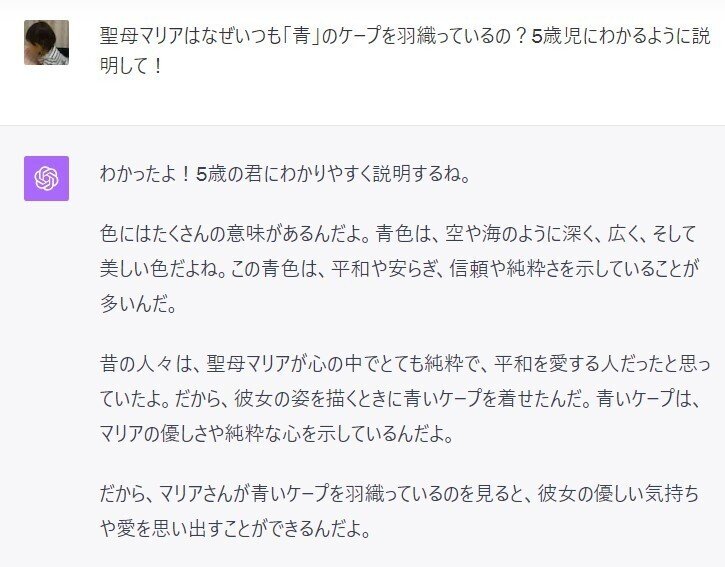
なるほど、わかりやすい。chatGPTのお陰で、鑑賞が本当にはかどる時代になりました。出先で気軽にパパッと検索して聞けるのがいいですよね。
このように、繰り返し見かける人物や風景の中に共通の色が見いだせれば、そこから鑑賞を深めるきっかけにしやすいんです。ぜひ、同じモチーフや画題の中に、似たような色彩がないかどうか、じっくりと観察してみてくださいね。
さて、ここからは有料となります。もし読んでみたい方は、ぜひご購読くださいね。今なら100円/月とワンコインで読めるようになっています!
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

