
美術館でのメモの取り方(実践編)
過去3回、「メモの取り方」について書いてきましたが、今回はより私の実際に即して説明したいと思います。
なお、今回紹介しているのは現時点の話で、心境の変化で全く違う方法を採用することもあります。絶対こうすべき、というような方法ではないこと、あらかじめご了承いただけたらと思います。
メモの道具
メモ帳
現在使用しているのは、どこにでもある普通のノートです。

小さすぎず、大きすぎずとういことで、現在はA6の小さなノートを使用しています。用が済んだらほとんど振り返ることはないため、ブランド等には特段のこだわりはありません。方眼・罫線・無地などもこだわりはありませんが、個人的には方眼が好みでしょうか。
以前はスケジュール帳のウィークリーページを使ってメモを取っていた時期もありますが、美術館内における軽量化の観点で再び別途ノートを準備する形に戻りました。
鉛筆

こちらもどこにでもある、消しゴム付きのタイプ。ボールペンと勘違いして近寄ってくる監視スタッフが過去にいたため、その名残で消しゴム付きのものを使っています(基本的に消しゴムは使いません)。写真のようなペンケース(1本だけ入るやつ)を持参していたり、そうでなかったりもします。
鉛筆はいちいち受付にお願いするのも気が引けるので、自分の鉛筆を携帯するようになりました。もちろん美術館・博物館で貸出してくれますし、鉛筆を持つと鉛筆削りも買わないといけないので、使用頻度が高くなければわざわざ買う必要はないかもしれません。
メモの書き方
見た目よりスピード
公開しておいて我ながら恥ずかしいですが、私のメモはかなり汚いです。

本来人に見せるためのものではないですし、見た目重視で丁寧に書いていると時間がかかりすぎてしまい、周囲に迷惑を与えてしまうことも考えられます。大事なことは作品を観賞すること、そしてそれをもとに感想を書くことであり、メモをとること自体が目的ではありません。
もともと高校〜大学の頃から『書きなぐり』方式でノートをとっていたこともあり、私のメモはだんだんと効率・スピード重視のものへとなっていきました。
「乱雑すぎて後で振り返っても思い出せない」ということも稀にあるのですが、その時はスパッと諦めることにしています。それが明らかに展覧会、もしくは自分の感想にとっても重要な内容、意味不明のメモしかないということであれば話は変わってきますが、大部分のメモが取れていれば「それで忘れてしまったらしょうがない」というスタンスです。
ただし、以前も書いた通り、振り返りはなるべく同日中に行います。『書きなぐり』方式のメモは見た目上ロジックとして繋がっていないこともあるため、適宜加筆したりしてその部分を補うことにしています。
書くのは文字だけじゃない
メモは基本的には文字で書き進めていきますが、書いていくうちに絵や図が混ざっていくこともあります。

これは紙メモ派ならではの発想と言えるかもしれません。スマートフォンであれば文字を打たなければいけないところ(スマホでイラストメモをやっている方はそう多くないと思います)、絵であれば言葉で説明するより具体的に描けますし、記憶も引き出しやすくなります。
メモの内容
基本はネタ探し
最後に一番肝心な、メモに書く内容についてですが、私の場合は「文章を書く」というのが最終目標であるため、基本的には「ネタ探し」ということになります。
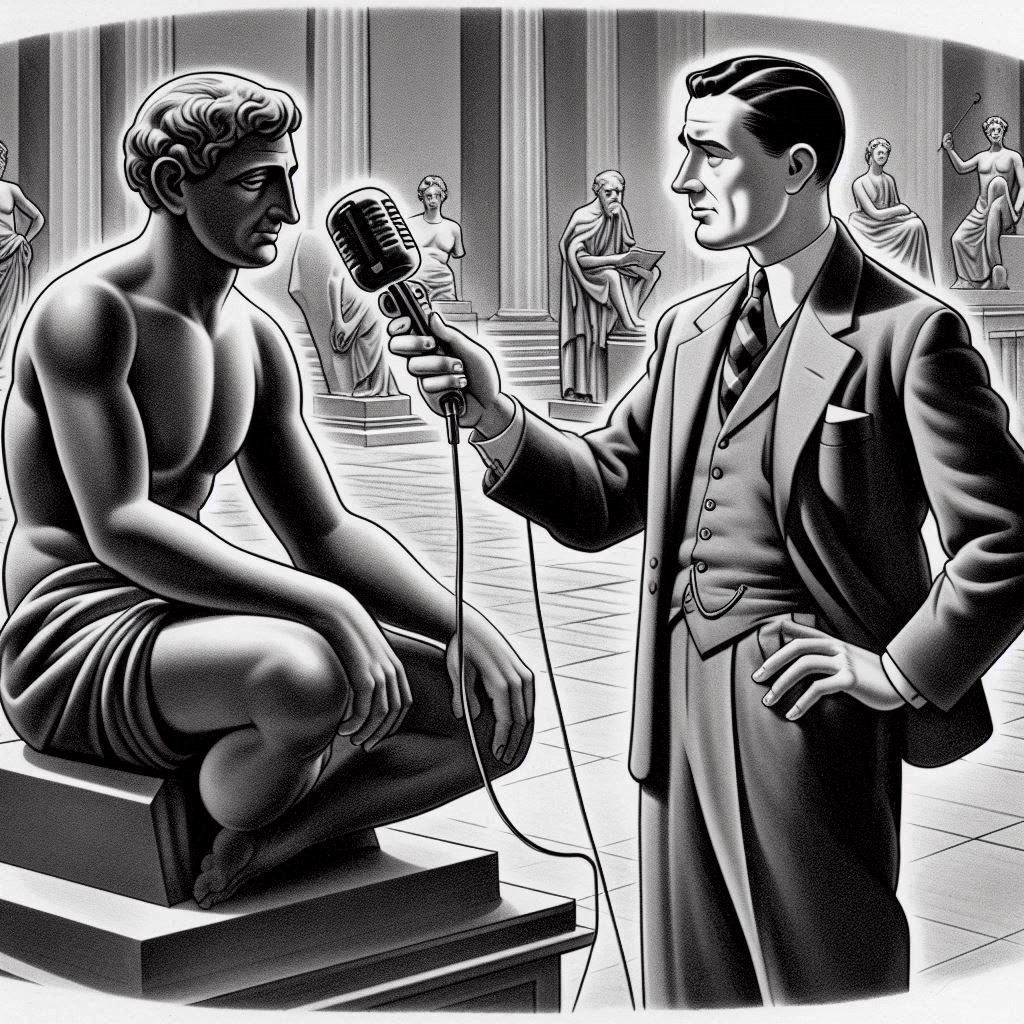
もちろん個別の作品を見て気づいたこともそうですし、展覧会全体としてのキーワード、キーフレーズやポイントなども記述していきます。基本的には思いつくままに書いていきますが、感想文としてある程度取捨選択することもあります(とはいえ基本は『なぐり書き』です)。
文字情報からは要点だけを
以前も書いた通り、キャプションや解説文の文字をそのまま書き取るということはほとんどしません。ただし単語やフレーズ程度を拾っておくことはあります。

打ち消し線は文章に起こす際に引いたもの。
論文として作成したり、学校等に提出する場合は別として、日常レベルで正確な引用が求められることは稀ですし、どうしても正確なものが必要な場合は図録を入手したほうが無難です。
「感想」のための「鑑賞」にしない
最後に"そもそも論"ということにはなりますが、「感想文を書くために美術鑑賞をする」となると、少なからず通常の鑑賞とは違う部分もあるかと思います。以前ある劇評で、「暗がりの中でパンフレットの端にメモを取りながら劇を見るのは本来の観劇ではない」というような文章をお見かけしたことがありますが、同様の指摘は私にも該当するものでしょう。
一言で言い切れるものではないんですが、通常の鑑賞のようにまっすぐ作品に観られているか…となると、多かれ少なかれ「歪み」があることは否定できないと思います。

私の場合、基本的に企画展・特別展の類の展覧会は2周することが多く、その2周目では1周目ほどにメモは取りません。その2周目はある意味では「本来の美術鑑賞」に近い…のかなぁと思っています。
メモの有無に関わらず、美術鑑賞の「2周目」はサプライズの要素がなくなり、作品・展覧会の印象が変わることがあります。最初に書いたメモが陳腐なものに見えてしまうこともありますし、反対に1周目とは違う気づきを得ることもあります。
個人的に「2周する」というのは習慣というか、深い意味も考えずにやっているのですが、そこで多少のバランスを取っている…のかもしれません。
おわりに
私の場合、メモをとる理由は一つ、感想を書くためです。記憶力も良いほうではなく、単に人に話すだけだったらそこまで細かいメモは要りませんが、そこそこ長いボリュームで「書く」となるとどうしてもそれなりのメモが必要となります。
メモがないと曖昧な記憶に頼りすぎてしまい、特に長文の場合はあやふやな部分を自説で埋める、悪く言えば独善的な内容にもなりがちです。評論は観念の彫刻という言葉もありますが、自説のために相手を歪めるというのも本来、道義的にも褒められたものではないでしょう。
メモを取るということは、より正確に相手を理解し、自分の意思を伝えようとする、ひとつの意思の現れだと思います。
とは言いつつ、究極的に相手を完全に理解することは難しいし、自分の意思だっていつも正しく伝えられるとは限りません。しかし、できる範囲でいいからベストを尽くそう、相手に誠意を尽くそうという気持ちが、よりよいメモ、よりよいアウトプットに繋がるのかなとも考えています。
自分の書いているこの文章が、何かしらのヒントにつながれば幸いです。

