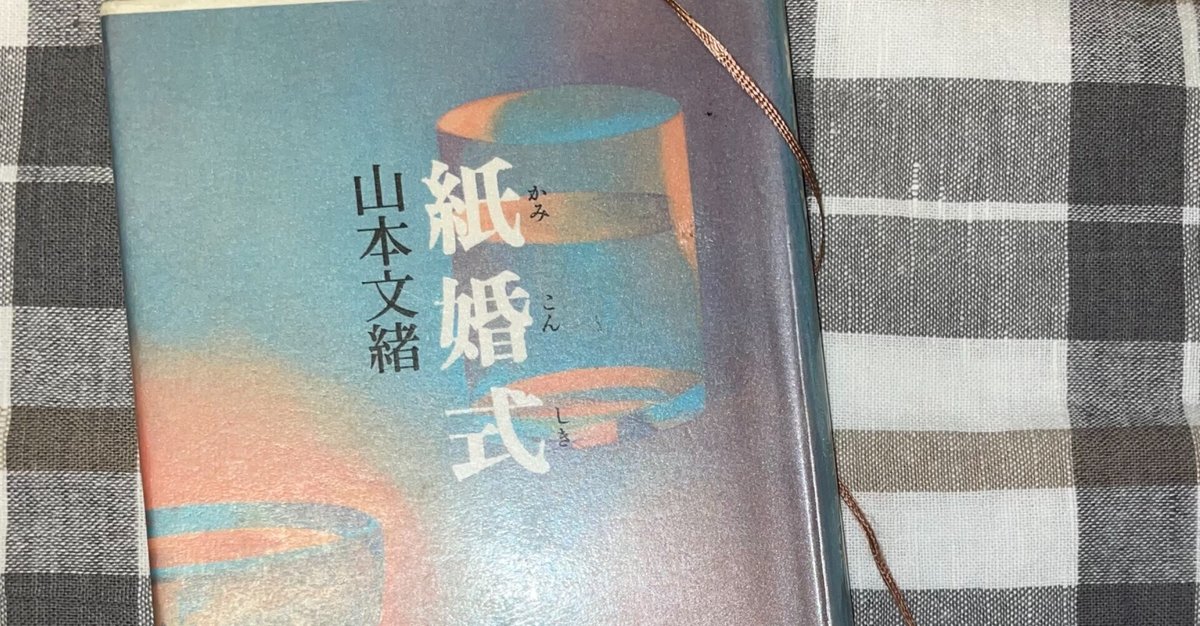
一番近い他人
『紙婚式』山本文緒著:徳間書店
紙婚式という言葉があるそうだ。なんでも、結婚一年目の記念日のことをそう言うらしい。「白紙の状態から将来の夢を願う」という意味があるそうだ。
表題作「紙婚式」を含め、様々な夫婦についての物語が書かれた短編集である。本作は刊行は1998年。今から23年ほど前。昨今のコロナ禍のソーシャルディスタンスなどが叫ばれているなかで読むと、この夫婦関係やまた恋愛の密な関係性が、いい意味で、時代的に古びていて懐かしい気がする。
たとえば、夫婦間の生活上での優位性とか、価値観のズレ、違い、そこからの争いと仲直り、子供を持つ、持たないとか、浮気(プラトニックも含め)やがて離婚、子供の親権問題、舅姑との二世帯住宅問題など多彩なテーマが短編ごとに物語に盛り込まれている。
しかし、改めて思うのが、夫婦というのはいわば一番近い他者であり他人であるという事実だ。他人であるからこそ、分かり合おうと努力したり、また逆に、分からなくて絶望したりもするのだろう。
表題作にもなっている最終話「紙婚式」では、いわゆる現在では、事実婚と呼ばれるであろう同棲十年の夫婦が登場する。一緒に暮らしてはいるが、互いに一切干渉することなく互いが独立して暮らしている夫婦(みたいなもの)の話だ。 いろいろすったもんだがあるのだが、最終で出てくる言葉が逆説的に真理を突いていて、興味深い。『婚姻届けの紙切れ一枚が何をしてくれるとも思えない。手をつなぎつづけることはこんなにも困難で、断ち切ってしまう方が百倍やさしい。けれど、いつかどうせ終わるのなら、ひたすら続けつづけるということもあるのではないか』みたいなことを、妻が考える場面が出てくる。
それこそが、希望なのだと思うし、そういった希望的観測を持ち続けることで他人同士の夫婦は、夫婦たりえるのではないだろうかと思うのである。そんなことを思わせられる短編集だった。
