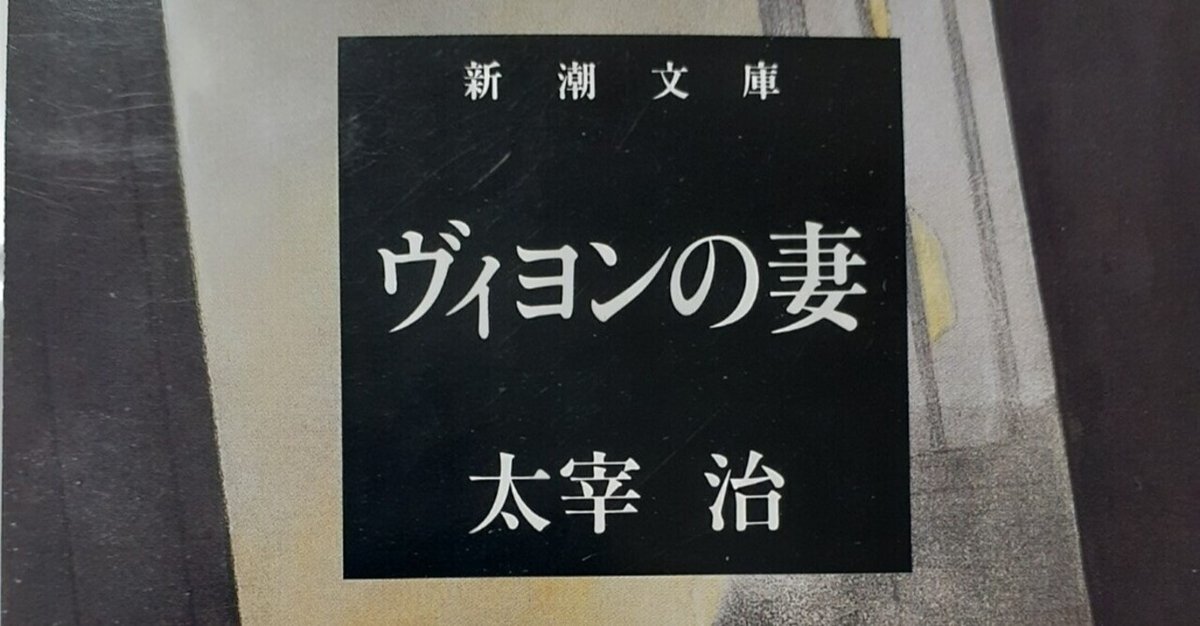
私の読書●小説家志望の読書日記㉓ 『ヴィヨンの妻』太宰治
小説家志望と言いながら、こんなのはどうかと自分で思ってしまうのですが、太宰の作品をじっくり読んだことってあまりないんです。
めちゃくちゃに文章がうまいのもあって、つい流れるように読み、かつストーリーテラーでもあるので、さらさら読んでもなんとなくわかったような気になってしまう。
良くも悪くも太宰の才能。
そのなかでこの『ヴィヨンの妻』はわりと分かりにくい部類に入る短編なのではないでしょうか。太宰治の最晩年に書かれた作品ですが、そこには『人間失格』のような暗さはなくむしろ奇妙な明るさと軽さにあふれています。
タイトルのヴィヨンとは、15世紀のフランスでならず者の生涯を送った詩人フランソワ・ヴィヨンからつけられています。
この場合ヴィヨンは、主人公(私)の夫である酒飲みでだらしない詩人の大谷を指していますが、ここには太宰治本人の姿が投影されています。
最初は何が言いたいのか、よく分からなくて、もう一度読みました。私」の変化に意味があるのは分かるんですけど。
はじめはろくに家にも帰らない夫を、坊やを抱えてただ待つだけだった「私」。
ところが夫の盗みをきっかけに小料理屋「椿屋」を訪れるところから変化が現れます。
小料理屋で生き生きと働くうち、彼女は店の客や出入りの商人を見て、「我が身にうしろ暗いところが一つも無くて生きて行く事は、不可能だ」と思いいたりるのです。
そしてとうとう、「私」は、店の客である工員風の若い男と関係を持つことによって自らも罪を抱え込むことになるのでした。
情事の翌朝、大谷に「人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすればいいのよ」と言いはなつ「私」。そこで物語は終わります。
大谷は「男には、不幸だけがあるんです。いつも恐怖と戦ってばかりいるのです」と言い、神を恐れる男。それに対し、「私」は罪を抱えこんだ結果、人間的に強くなります。
「私」が店の客である工員風の若い男を家にいれ、その結果汚されてしまった経緯は、一見不可解です。
だって大谷のいない家に、明らかに自分に気がある男を泊めるのは正気の沙汰ではないでしょう。
ある意味で、彼女は確信犯だったでしょう。
それは「神がいるなら、出てきてください!」という言葉に示されています。
大谷から「神はいるんでしょうね」と問われた「私」は、自分自身も罪を背負った人間となることで神を求めようと考えたのではないでしょうか。
それは大谷への愛であったのかもしれませんね。
細かく読み解くと太宰の実に緻密なストーリー構成にもやられた! と思わされる一冊です。
いいなと思ったら応援しよう!

