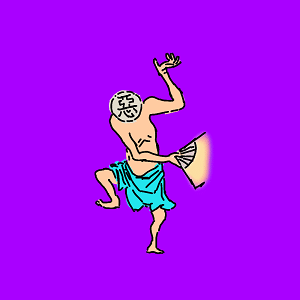もっともっと「誹風柳多留」四篇①
江戸庶民の日常生活を伝える古川柳も次々作られた。その紹介をしているこの「誹風柳多留」も第4編となった。
5 女湯へ おきたおきたと だいて来る めいわくなことめいわくなこと
赤ん坊が泣いて、どうしようもなくなった時は、「起きた、起きた」と女房をさがす。妻にすれば「迷惑なこと」だなあ。
52 あいそうも男へすれば疵になり おしひことかなおしひことかな
愛想のいい女性はいいもんだが、あまり男に愛想よくしてばかりいると失敗することもある。ストーカーは、女性に愛想よくされたのを、自分が好かれていると勘違いしたものが多い。
57 見せもせず無筆は文を もてあまし おしひことかなおしひことかな
寺子屋があったものの文字が読めない人(無筆)はいる。せっかく恋文をもらったのに読めない。誰かに読んでもらうには内容が気になるので見せない。それが「おしいこと」なのだろう。
63 武士の けんくわに後家が二人出来 わかれこそすれわかれこそすれ
武士のケンカでは死人が出る。刀を抜いたケンカで両方死んだら、未亡人(後家)が二人できるという。ブラックジョークではなく、本当にそんなこともあったのだろう。のんびりした時代とはいえ、武士は刀を持っている。アメリカの銃社会と一緒だ。持っているから使うこともある。
64 弥陀しゃか(釈迦)の違ひ 不縁の元となり わかれこそすれわかれこそすれ
阿弥陀仏の南無阿弥陀仏、日蓮宗の南無妙法蓮華経、阿弥陀、釈迦の違いで宗派が異なると。、そこから別れが起きたりする。いろんな宗教が混在する日本でも、ちょっとした違いから溝が大きくなる。
132 あの女房 すんでに おれがもつところ (前句不明)
あの女房、もうちょっとで俺と結婚するはずだったんだ。その女房をうらやましがっているのか、それともホッとしているのか。
26 麦ばたけ小一畳ほどおったおし めいわくなこと めいわくなこと
麦畑がいっぱいあった時代。「迷惑なこと」は麦を倒されること。ちょうどベッドのサイズで倒されている。二人で麦を敷き布団にしたのだ。「♪誰かさんと誰かさんが麦畑~」(「誰かさんと誰かさん」詞・なかにし礼)で、イチャイチャしているのだ。麦の句が多いが、麦はそれほど一般的だった。
34 海あん寺 真赤なうその つき所 めいわくなこと めいわくなこと
品川の海晏寺は真っ赤な紅葉の名所。紅葉を見に行くとウソをついて、品川へ女郎を買いに行く。「真っ赤な嘘」から「真っ赤な紅葉」。海晏寺といえば紅葉、品川といえば女郎。こういう共通認識があった。
182 なりひらの かさをかかぬも ふしぎ也 本望なこと本望なこと
「なりひら」は、平安時代のプレイボーイ在原業平。「かさ」は梅毒のこと。あれだけ女遊びをしていて梅毒にならないのは不思議。江戸時代は梅毒の患者が非常に多かった。
梅毒は南アメリカの風土病で、コロンブスがヨーロッパに伝えたといわれる。コロンブスは1492年~1502年にかけて航海をしている。1500年代にはすでに日本にも梅毒は伝わっている。性病も煙草も伝わるのが早い(煙草も南米原産)。
けれど800年代(平安時代)の業平の生きた時代には、まだ梅毒は日本に伝わっていなかった。
193 ほれたとは 女のやぶれかぶれなり あまりこそすれあまりこそすれ
女の方から「ほれた」というのは、破れかぶれの思いだろう。
175 御袋の やうだと かげで けちをつけ あつまりにけりあつまりにけり
母親みたいだ、と陰で女性の文句を言う。直接は言えないから、あくまでも陰口となる。
古川柳作品は、「誹風柳多留四篇」より。その通し番号を記載。
見出し画像は、山東京伝作・北尾政美画「心学早染草」の模写。