
『1973年のピンボール』村上春樹 「雰囲気を味わえば良い」と、ビールを飲みながら
このnoteは、本の内容をまだその本を読んでない人に対してカッコよく語っている設定で書いています。なのでこの文章のままあなたも、お友達、後輩、恋人に語れます。 ぜひ文学をダシにしてカッコよく生きてください。
『1973年のピンボール』村上春樹
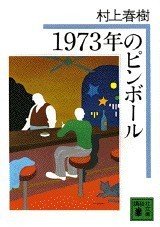
【村上春樹の作品を語る上でのポイント】
①「春樹」と呼ぶ
②最近の長編作品を批判する
③自分を主人公へ寄せる
の3点です。
①に関して、どの分野でも通の人は名称を省略して呼びます。文学でもしかり。「春樹」と呼び捨てで語ることで、文学青年感1割り増しです。
②に関して、村上作品は初期は比較的短編が多く、いわゆるハルキストの中には、一定数短編至上主義者が存在します。そこに乗るとかっこいいです。
③作品に共通して、主人公は「聡明でお洒落で達観しててどこか憂鬱で、女にモテる」という特徴を持っています。その主人公に自分がどことなく似ていると認めさせることで、かっこいい人間であることと同義になります。
○以下会話
■「なんとなく」好きになれる小説
「夢中になる小説か。そうだな、そしたら村上春樹の『1973年のピンボール』がおすすめかな。これは村上春樹が31歳の時に書いた作品なんだ。処女作の『風の歌を聴け』と、2作目の『1973年のピンボール』、そして3作目の『羊を巡る冒険』の3つは、「鼠三部作」と呼ばれているんだよ。「鼠三部作」は共通して「僕」と「鼠(というあだ名の男)」の二人が主人公になっている小説なんだ。3作品とも「長編小説」という枠組みではあるんだけど、短い文章が途切れ途切れに、時系列はバラバラで、重なり合ってできている作品なんだ。だから正直読みやすい小説ではないんだよね。だけど、なんだか面白くて夢中になって読んじゃうんだよ。
村上春樹の作品、特に「鼠三部作」に関しては、小説のストーリーよりも小説の雰囲気を楽しむのがポイントなんだ。時系列がバラバラな短文と何か暗喩めいた言い回しを、分解して、分析するのも一つの楽しみ方だと思う。だけど、そういった難しい作業は文学者とかコアなファンに任せて、僕らは軽い気持ちで楽しんでいいと思うんだ。例えば恋人と美術館に行った時、絵画の見方とか、芸術家の歴史といった「美術の知識」なんて持たずに鑑賞してるよね。それでも充分楽しいよね。色がかわいいとか、迫力があって良いとか、「なんとなく」好きという気持ちで楽しめるんだ。
村上春樹の作品は、なんとなく難しいとか何言ってるか分からないって感じて避けている人もいると思う。でもゴッホの「ひまわり」とか、フェルメールの「真珠の首飾りの少女」は別にその絵の意味をしっかり理解して、感動してる訳ではないよね。陰影がしっかりしてるなとか、色彩が強烈だなとか、「なんとなく」の感覚で、無意識下でその絵を自分なりに理解しようとしてるよね。その「なんとなく」の感覚で、村上春樹の小説を読めばきっと楽しく作品の世界に入り込めると思うんだ。
■あってないようなストーリー
ストーリーはあってないようなものなんだよ。
友人と翻訳の事務所を開いた「僕」は、それなりの量の仕事をこなして、現状に適度な満足感を持って生活していたんだよ。ある朝、目を覚ますと両隣に双子の女の子が寝ていたんだ。散歩の途中で「僕」の家に入り込んで、そのまま寝てしまった双子は、そのまま「僕」の家で生活を始めるんだ。そんな「僕」は、かつてジェイズ・バーで熱中したピンボールの「スペース・シップ」を思い出して、そのピンボールを探しにいくんだよ。そして同時並行的に、「鼠」も大学を辞めて空虚な生活を送っているんだ。一人の女性からタイプライターを購入し、それがきっかけで頻繁に会うようになって、時々ジェイズ・バーで酒浸りになっていたんだ。そしてある日思い立って街を出て行くんだよ。
こんな感じの話。これが、時系列はバラバラに展開されていくんだよ。なんだか不思議な話でしょ。
■肯定する孤独と、否定する孤独
この作品のテーマをひとつ挙げるとすると、「孤独の肯定」なんだ。僕と鼠は二人とも「孤独」を抱えているんだよ。だけど違う点は、僕は孤独を肯定しているのに対し、鼠は孤独を否定している点なんだ。
僕は双子の女の子や仕事の仲間など、ある程度人と関わりがあるけれど、どこか孤独感があるんだよ。話していてもちゃんと目が合わないというか、ひたむきがちで、自分の本性を腹から見せてない、ガッツリと仲良くはなれない雰囲気があるんだ。だけど「僕」は、その孤独を受け入れて、孤独をつまみにビールをガブガブ飲んでいる。
一方、鼠は一人の女性を失い、大学生の頃から同じ街に居続けて、ジェイズバーで酒を飲み続けている。鼠は孤独を受け入れられず、誰かに理解されたい一心で、街を飛び出して、「何か」を探しに行くんだ。
孤独を受け入れるべきか、受け入れないべきか。どちらが正解とは言えないけれど、少なくとも『1973年のピンボール』では、「僕」の方が魅力的に描かれているんだ。すなわち「孤独」を受け入れていることが、生きていく上で大切なことだって読み取れるんだ。
だけど、僕と鼠でどちらがより「人間らしい」かと言ったら、鼠の方だと思うんだ。現実を受け入れて、その範囲で生きていくことも一つの生き方だけど、現実にあらがって、理想を追い求めて、がめつく生きていくのも良い生き方だよね。そして後者の方が、本当は魅力的なはずなんだよ。
■カッコ良い描写
僕がこの作品で好きなのは、ストーリーではなくて「情景描写」なんだ。たくさんカッコ良い描写はあるんだけど、特に気にってるのは2つあるんだ。
ひとつ目は、鼠取りを仕掛ける描写。
アパートの流し台の下に鼠取りを仕掛けたことがある。餌にはペパーミント・ガムを使った。部屋中を捜しまわった挙句、食べ物と呼び得るものはそれ以外に見当らなかったからだ。冬もののコートのポケットから映画館の半券と一緒にそれをみつけた。
三日めの朝に、小さな鼠がその罠にかかっていた。ロンドンの免税店に積み上げられたカシミヤのセーターのような色をしたまだ若い鼠だった。人間にすれば十五、六といったところだろう。切ない歳だ。ガムの切れ端が足下に転がっていた。
つかまえてはみたものの、どうしたものか僕にはわからなかった。後足を針金にはさんだまま、鼠は四日めの朝に死んでいた。彼の姿は僕にひとつの教訓を残してくれた。
物事には必ず入口と出口がなくてはならない。そういうことだ。
カッコ良すぎるよね。文学史上、こんなカッコ良く鼠取りを仕掛けた人はいるんだろうか。こんなカッコ良く仕掛けられたら、捕まるネズミも本望だよね。
もうひとつは、「僕」が友人と共に翻訳の仕事を始める時の描写なんだ。
僕と僕の友人は渋谷から南平台に向う坂道にあるマンションを借りて、翻訳を専門とする小さな事務所を開いていた。資金は友人の父親から出た、と言っても驚くほどの金ではない。部屋の権利金の他にはスチールの机が三つと十冊ばかりの辞書、電話とバーボン・ウィスキーを半ダース買ったきりだった。余った金で鉄製の看板をあつらえ、適当な名前をひねり出してそこに彫りこませて表に掲げ、新聞に広告を出してしまうと二人で四本の足を机に載せウィスキーを飲みながら客を待った。七二年の春のことだ。
カッコ良すぎる。肩の力が抜けた、汗なんて全くかかない、サラリとした感じ。村上春樹の作品から受け取れる、退廃的で幻想的な雰囲気はこういった丁寧な描写の積み重ねから感じ取れるものなんだ。
こんな感じで、読めば読むほど夢中になれる小説だから、是非読んでみて。」
いいなと思ったら応援しよう!

