
運動が苦手な子どもたちを輝かせる「4つのプログラム・コンテンツ要素」 ~子ども運動チャレンジ教室を視察して②〜
一番の驚きは、5時間もの運動プログラムを、集中を切らすことなく、全員がやりきったことです。
このプロジェクトは「運動が苦手な子ども」を対象にしています。
普段はそれほど積極的に身体を動かす方ではないかもしれない子どもたちが、5時間ものプログラムを嫌な顔をすることなく運動し続け、先生とお別れする瞬間まで、笑顔をキラキラと輝かせていたのです。
運動の得意・不得意に関わらず、5時間の運動をやりきること自体、並大抵のことではありません。
いったいなぜ、こんなことが実現できたのか。
私は、7つのポイントがあると考えました。
さらに分類すると、ハイクオリティな4つの「プログラム・コンテンツ要素」と、3つの「コミュニケーション・アプローチ要素」が影響していると考えました。詳細は以下です。
【プログラム・コンテンツ要素】
1 「遊び」を基本としたプログラム構成
2 「できるようになる」ことを保障する、科学的知見に基づいた支援
3 夢中になれるアイデア教具の活用
4 敢えて「勝ち負け」を競うタスクゲームや運動会の設定
【コミュニケーション・アプローチ要素】
1 子どもたちに安心感を与える、先生方の温かさ
2 臆することなくチャレンジでき、自己肯定感を育む先生方の指導
3 憧れの元プロ選手による明るく元気な、ハツラツ全力プレー
取組の全てを紹介することはできませんが、子どもたちが生き生きと運動に親しむための7つのポイントを、このPert②では、4つの「プログラム・コンテンツ要素」について、次回のPert③では、3つの「コミュニケーション・アプローチ要素」について、私の個人的な見解をお示しします。

1 「遊び」を基本としたプログラム構成
大まかなプログラムは以下のような内容でした。
<午前> ・ アイスブレイク活動
・ 基礎運動能力向上タイム
<午後> ・ 苦手な子が輝く運動会
アイスブレイク活動では、すぐさま、面白おかしく変装した先生が、元気よく登場して、早速みんなでひと笑い。場の空気を和ませてみえました。
「ワン!、ツー!、スリー!、・・・」の英語のかけ声に合わせて、ジャンプ、ジャンプ開脚、屈伸運動、捻転運動・・・などの全身ほぐしや、「言うこと一緒やること一緒」、「言うこと逆やること逆」などの頭と体と心をほぐす遊びを、先生とペアになって行う活動を行いました。
「言うこと逆やること逆」では、大人たちの方がよく間違えてしまい、子どもたちに引っ張ってもらう場面があるなど、活動を通して、先生と子どもたちの心の距離がみるみるうちに近付いていくのを感じました。

基礎運動能力向上タイムでは、「投動作」「走動作」「多様な動き」「操作系動作」、の4つのカテゴリーをエリアで分けて、ローテーションで活動を行っていました。
各カテゴリーとも、いわゆる練習とかトレーニングという色をできるだけ出さずに、遊び的な課題の提示やゲーム、言葉がけなどを意識されていました。
例えば投動作では、「あのゴムバーを越せるように投げてみよう」、「玉入れのカゴ横向きバージョンだよ」とか、走動作では、「カメラで連続写真を撮った時に2種類の写真しかないように、同じポーズを繰り返すことを意識してみよう、はいっカシャ!カシャ!」、「このボードに膝を当てると音が出るよ。膝の音と、逆足が地面に着いた時の音が、同時になるように脚を動かしてみよう、トン!トン!」などの遊び的な課題提示や言葉がけがありました。
多様な動きでは、「先生が転がしたフラフープをタイミングよくジャンプして3人一緒に跳び越そう」、「マットの上を2人で手をつないで寝転がって進もう」、「10人で手をつないでコロリンっぱ、で一斉に立ち上がろう」とか、操作系動作では、「上空にボールを投げて、10回手をたたいてキャッチ」、「先生の指示で、頭、肩、膝などを触って、ボール!と言われたら、真ん中のボールを取り合うよ」などの遊び的な課題提示やゲームを行っていました。
運動を楽しく行い、楽しみながら動きが身に付くようなプログラムの構成であったため、子どもたちは失敗を恐れることなく、安心して伸び伸びと、自ら進んで運動に取り組めていました。
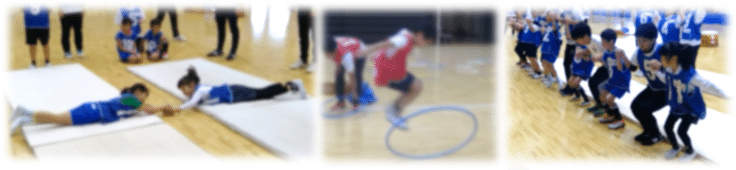
苦手な子が輝く運動会は、以下のような種目を行っていました。
・ ゾンビしっぽ取り
・ ボール投げ合戦
・ ドッヂボール
・ 元Jリーガーとのミニサッカー
・ リレー対決
運動会の始まりは、かっこいいバックミュージックに乗せて、盛大な拍手の中で入場行進をして登場です。そして各チームで考えた決めポーズで記念撮影。審判長からフェアプレーの精神を教えてもらい、チームごとで円陣を組んで元気よく「がんばるぞー!」のかけ声。この時点で、子どもたちの表情は輝き、期待感で溢れていました。
遊び的な種目を設定しているため、そもそも種目を行うこと自体へのワクワク感もありますが、午前中のプログラムで経験した動きと午後の運動会の種目設定がリンクしているため、午前中に自信をつけた動きをゲームで発揮してみたいという自分自身への期待感もあったと思います。

2 「できるようになる」ことを保障する、
科学的知見に基づいた質の高い支援
投動作エリアでは、指差し姿勢から投動作を開始し、ステップマットに足を合わせて投げることで効率的な投球姿勢や滑らかな身体重心移動の習得を図ったり、投方向にゴムバーを設置してよりよい投射角度の感覚をつかませたりという工夫がなされていました。元来、投動作のバイオメカニクス的な動きは、口頭での説明ではなかなかイメージできないため、難しい解説などは一切ない中で、より遠くへ投げるための身体の使い方のコツを楽しみながら感覚的につかむことを促していました。
走動作エリアでは、地に足が常に着いているのが「歩く」で、宙に浮いている瞬間がある、つまりジャンプの連続が「走る」であることに気付かせた上で、より力まずにしっかりジャンプができる姿勢作りを意識した様々な手立てが講じられていました。「空気の入ったボールと空気の入っていないボールの弾み方を比較してみよう」、「頭から足まで一本の棒になるように意識してそのまま前に倒れてみよう」などなど、様々な面白い手立てで上体のぶれない走りを感覚的につかむことができるよう促していました。

多様な動きエリアでは、「ペアで背中を合わせて座り同時に起立してみよう!」、「カラーのリングを両足を揃えてジャンプして進もう!次は腕を後ろで組んだまま跳んでみよう!」、「フラフープを上手く回して、輪の中にジャンプイン!」、「ぶらぶらリラックスして連続ジャンプ~からのギュッと固まる!」など、活動の場や用具を工夫しながら、多様な動きを経験していました。これらは、「体のバランスをとる運動」「体を移動する運動」「用具を操作する運動」「力試しの運動」であり、小学校の学習指導要領に示されている運動とリンクされています。楽しく活発に運動する中で、動きのレパートリーを増やしながら、基本的な動きの質が高まることを促していました。
操作系動作エリアでは、新聞紙を丸めて作った柔らかサッカーボールを使用し、ボールへの恐さを軽減させた上で、両手投げ、バック投げ、股下通し投げ、インサイドキック、インフロントキック、インステップキックなどの多様なボール操作を行っていました。テンポよく運動を展開し、次々に新しい運動課題を提示することで、頭で難しく考えて体を動かすのでなく、繰り返しチャレンジをしながら動きのコツを感覚的につかむことができるよう促していました。

とても印象的なシーンがありました。
跳び箱運動の開脚跳びにチャレンジした女の子の話です。
女の子は、私の勝手な見立てですが、学校の体育授業において開脚跳びを成功させた経験が一度もないのではないかなと想像するほど、まだまだ身のこなしが未熟と言わざるを得ないレベルでした。しかし、跳べるようになりたいという強い気持ちが伝わってくるほど、失敗しても失敗してもチャレンジを続けていました。
そこに先生がやってきました。先生はじっくりと観察し分析を始めます。もう一人の先生も近付いてきて観察し始めます。二人は考察を伝え合い、ある手立ての一手を講じます。
女の子は、先生たちの手立てに素直に粘り強くチャレンジします。3回、4回…、そして5回目に、何と見事に開脚跳びを成功させることができたのです。盛大な拍手と歓声の中、先生方は誰よりも喜びを露わにし、すかさず女の子に近寄って笑顔でハイタッチ。先生方同士も「やったな!」と互いにハイタッチ。
女の子は、ずっとできなかった悔しさを晴らすかのように、何度も何度も繰り返し跳び続け、完全に開脚跳びの技能を定着させることができました。その自信に満ち溢れた喜びの笑顔が、実に輝かしかったです。

3 夢中になれるアイデア教具の活用
「楽しくなる」「やってみたくなる」「やりやすくなる」「感覚を身に付ける」「積極的にチャレンジできる」「恐さがなくなる」「自信がつく」などのねらいで、様々なアイデア教具が活用されていました。
全てを紹介することはできませんが、簡単に手作りできるものや学校や家庭にあるもので代用できるものもあり、たいへん参考になると思うので、その一部を紹介します。なおタイトル枠には、教具の用法やねらいを鑑みて個人的な私見でのネーミングを記載しました。




4 敢えて「勝ち負け」を競う
タスクゲームや運動会の設定
運動の苦手な子どもたちの中には、「負ける」ことで自身の無力感や劣等感に苛まれ、運動嫌いになってしまったという子も多いのではないかと想像します。いつしか「負ける」ことへの抵抗として、勝ち負けのある運動や遊びから逃げてしまったり、チャレンジをしなくなったりして、どんどん運動から遠ざかってしまう、そんな子どもたちもたくさんいるのではないかと思います。
今回のような運動の苦手な子どもたちを対象にした教室では、運動嫌いを誘発するかもしれない「勝ち負け」を競う活動はタブーなのでは、と思いきや、何と驚くことに、そこを敢えて「勝ち負け」を競うゲームで、勝負にこだわり、逃げずにチャレンジさせるプログラムを数多く設定していました。
そして、「負ける」ことへのアレルギーを解消するための、いくつかの考え方をしっかりと伝えていました。
①フェアプレーの精神をきちんと伝える。
②負けることは恥ずかしいことではないことを伝える。
③負けた時の悔しさが、心の成長には欠かせないことを伝える。
④「勝ち」の価値より「負け」を素直に受けとめ、課題を発見し、次のチャレンジに臨むことの方が価値があることを伝える。
⑤結果としての勝ち負けよりも、習得した動きを、ゲームの中で発揮することを意識しようと伝える。そして自分や仲間が見事に発揮できた時には、相手や味方に関係なく、大げさなくらい認めようと伝える。
⑥自分は負けても、チームメイト(同じチームの先生)を応援して、心を晴れやかにしようと伝える。

「勝ち負け」をジャッジされることから逃げてきた子どもたちには、「負ける」ことへの抵抗感を失くしてあげることが必要です。
運動への苦手意識を解消するためには、「勝ち」も「負け」もたくさん経験する必要があるのです。高い壁を乗り越えてこそ得られる「勝ち」の喜びも、「負ける」悔しさから生まれる新たなるチャレンジ精神も、どちらも味わうことが重要なのです。だからこそ、勝負にこだわって向かっていく機会を敢えて設定しているのです。
運動が苦手な子どもたちだからこそ、通らなければならない道なのだということに気付かされました。

Pert②では、4つの「プログラム・コンテンツ要素」について、私なりの見解を述べてきました。
次のPert③では、3つの「コミュニケーション・アプローチ要素」について、考えを述べたいと思います。
