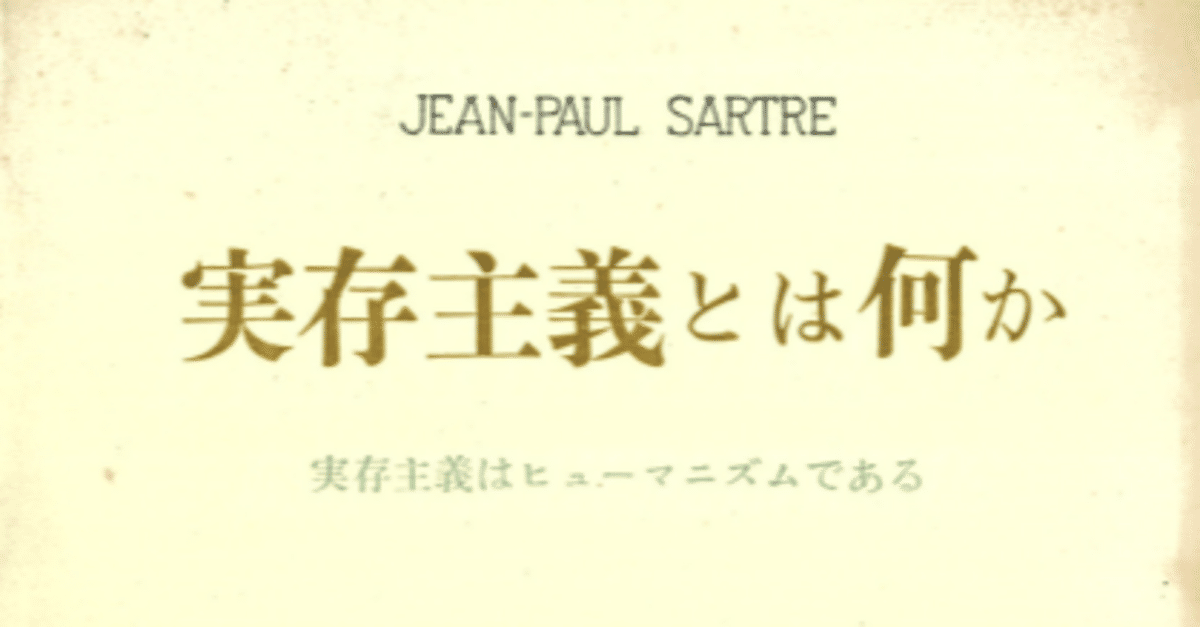
本の風景「実存主義とは何か」サルトル(1940年)
ジツゾール

「ジツゾールしてる?」「今日はとてもジツゾールできないな」こんな会話を交わした日々があった。「元気?」程度の意味だったが、「実存してる」を日常化する、その会話が秘かにカッコよかった。実存は青春の重要な断片だった。
1966年9月、ジャン、ポール・サルトルがパートナーのボーヴォワールを伴って来日した。「実存が第二の性を連れてきた」と、日本中が湧きたった。
実存主義とは何か

サルトル(1905~1980年)は語る。「実存は本質に先立つ」と。ペーパーナイフを例にとる。ペーパーナイフは、作るべきモノのイメージ(概念)を「頭に描いた職人」によって作られる。その際職人は作ろうとする概念(本質)にそって材料(実存)を選ぶ。つまり、本質が実存に先立つ。一方、これに対し、かつて人間とは「土の塵」で創られた神の被造物として、それが人間の本質とされていた。しかし、神なき後、人間は「ふいに姿を表し、そのあとで定義されるもの」となった。人は「この世界に投げ出され、その後に、私を選ぶことによって、私が人間を選ぶ」のである。つまり、私の存在(実存)が人間という本質に先立つのである。
サルトルはそこから第二のテーゼ「投企」について語る。「人間は何より先に、みずからかくあろうと投企したものになる」、人は自ら選んだことに自分を投げ出していくのである。選ぶということ、それは天使の声ではなく、自身の声で投企していくことで、サルトルはそれを「アンガージュマン」(参加する人)と名付ける、アンガージュによる投企において人間は自由となる。それ故、「なされつつある創意が果たして自由の名においてなされるかどうか」に実存の意味がある。更に語る。「実存主義はヒューマニズムである」と。人間は絶えず自分自身を失い、投企によって、乗り越えていき、この世界に「主体的」にとどまる。これをヒューマニズムと呼んでいる。
時代、混迷の日々
この時代、社会は混沌としていた。若者たちにとって、現代もそして未来も迷路のようだった。日本では60年安保闘争のあと、70年安保闘争を控え、さらには65年アメリカのベトナム戦争へ本格的な介入が始まり、反米機運は高揚していた。一方、キューバ危機を発端に米ソの冷戦が深刻化する中、ソ連は61年、65年に核実験を行った。アメリカやヨーロッパもこれに対抗して核実験を再開した。こうした中、日本共産党は「原水爆禁止日本協議会(原水協)」において、ソ連の核実験を擁護し、それを「きれいな核兵器」と評した。それは更なる混迷を招いた。若者たちの一部はより先鋭化した。しかし多くは迷路から脱出できないでいた。
その迷える魂に直接語りかけてきたのが「実存は本質に先立つ」の言葉だった。声高に攻撃してくる「主義主張」という怪物、周囲は「のっぺらぼう」の世界、こうした世界に対して、たとえ意味もなく投げ出された存在であっても、実存から出発する「君は希望なんだ」と背中を押された気がした。
幸福な錯覚
しかし70年安保闘争の破壊的な混迷が収束し「髪を切った」若者たちが、社会に組み込まれた時、「実存主義」は静かに消えていった。加藤周一は記す。「戦後実存主義が流行したが、五、六年しかつづかなかった。…つまり、思想ともイデオロギーとも関係のない、一種の気分の流行」(『雑種文化』)で、それは「不幸な錯覚だった」と。
半世紀が過ぎた。それは「錯覚」だったかもしれない。しかし「不幸な」ではなかった。「幸福な」錯覚だった、サルトルの小説「嘔吐」で、主人公が存在の重みに耐えかねて、マロニエの木の根に嘔吐する。74年初めてパリを訪れた際、シャンゼリゼ通りのマロニエの木々の美しさは、今も忘れることはない。(大石重範)
(地域情報誌cocogane 2023年12月号掲載)
[関連リンク]
地域情報誌cocogane(毎月25日発行、NPO法人クロスメディアしまだ発行)
