
1/13-1/19 ~経験に学びのアンカーを打つ~
練習日誌
気管支炎のためALL OFF
こんなに長引いたことはいつぶりだろうか?
丹後ウルトラ走った2016年以来かもしれない。
あの時も2週間くらい走れなかったが、なぜか福知山では自己ベスト出たから、この咳が長引かなければ、おそらく1ヶ月後には戻るだろう。
一休さんのごとく慌てない慌てない。
といっても内心、2週間を棒に振るのはかなり痛手だと思っている。
練習は焦らず戻していこうと思うけど、精神的に焦らないように自分に言い聞かせたい。
雑記
我が子にいつも「今日は保育園で何が楽しかった?」と聞く。「ブロック!」といつも答える我が子。楽しいことがあるだけましか。と思いつつ、ふと、経験について考えてみた。

「経験の差がものを言う」という言葉を聞いたことがあるが、本当にそうか?ぼくはそれは違うと思う。もちろん経験が成長を支えていることは間違いないが、経験の差が直接的な成長の差になるとは思えない。そうであれば、小学校で同じ学習をしている子どもたちは、同じだけ成長をしていかないといけないから。しかし現実は、成長は人それぞれ異なる。それはなぜだろうか?ぼくは、「経験に学びのアンカーを打つ」ことができる人が、大きく成長していける人だと考えた。
一卵性の双子がいて、2人は同じ経験を積んでいくと仮定しよう。同じことを経験していてもAは何をやってもうまくいかないいわゆる「できない人」。一方Bは、どんなこともうまくやるいわゆる「できる人」となった。(ここでは、関わる人などの環境要因は考慮しない)この差は、どこから生まれるのか。それは、「経験から学びを得ているかどうか」ではないかと思う。
例えばテストでAとBが同じ80点をとったとする。「よしよし80点か。これでオッケー。」と考えるA。「80点か。まずまずだな。20点はどこを間違えたんだろう。自分は何に躓いているんだろう。」と立ち止まって考えるB。Bはテストで80点を取ったという経験から、不足しているものは何かを考えることで学びを得ていると思う。荒木博行さんが、「学びは、経験前と経験後の差分」と言われるが、自己分析することから差分が生まれている。Aは経験という港についても、何も得ずに次の港に向かって進んでいるが、Bはその港でアンカーを打ち、船を停泊させ学びを得ている。
このアンカーを打って、立ち止まって思考し、学びを得ることが成長につながるのではないかと思う。そのために書くことは非常に有効な手段だと思う。最近こうやって気づいたことを書くことが多いが、これからも続けていこうと思う。
我が子の話に戻るが、たまに「今日は工作で、料理を作った!ほら見て。」と興奮気味に話すことがある。「ほ〜そうなんか!どんなものを作ったん?これはどうやって作ったの?」と聞くと、「ここはハサミで〜。」などと制作過程を伝えてくれる。こういったやりとりが次への意欲につながるだろう。子どもの経験を学びに変える役割は、周りの大人にあるのだと思う。
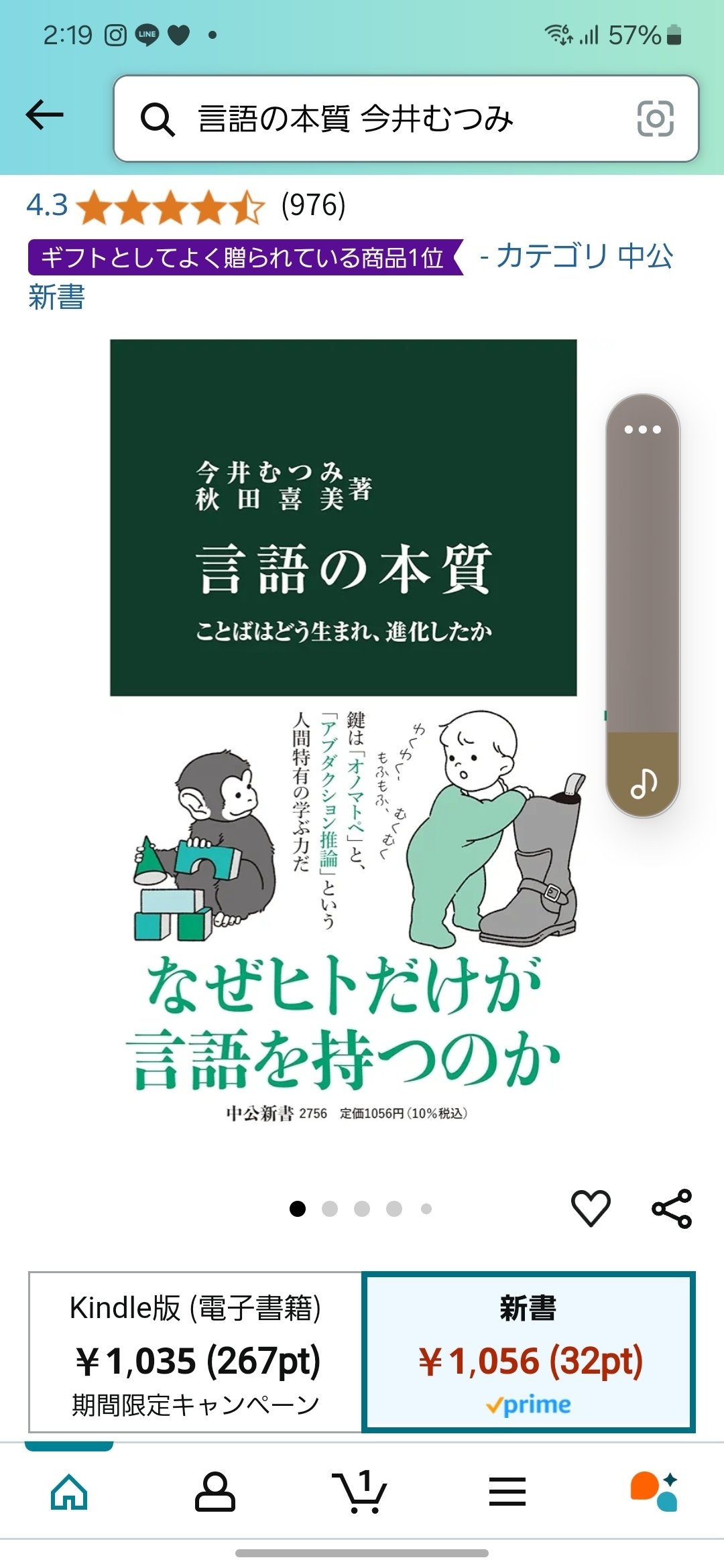
仕事に関係する話となってしまったが、競技にも同じことが言える。日常生活にも。この体調不良からどんなことを学んだか。冬は特に免疫力を高める生活を送ろうということだ。
療養中にトップガン、トップガンMAVERICKと見た。
かなりエキサイティングでまた自転車乗りたくなった。
あと、ダンダダンがおもろい。
