
【博物館レビュー】東京都現代美術館(MOT)「MOTアニュアル2022 私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみ」
施設としてはあまり好きじゃないのだが東京都現代美術館(MOT)に行ってみたところ,「MOTアニュアル2022 私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみ」が面白かったのでレビュー。施設としてはあまり好きじゃないが。

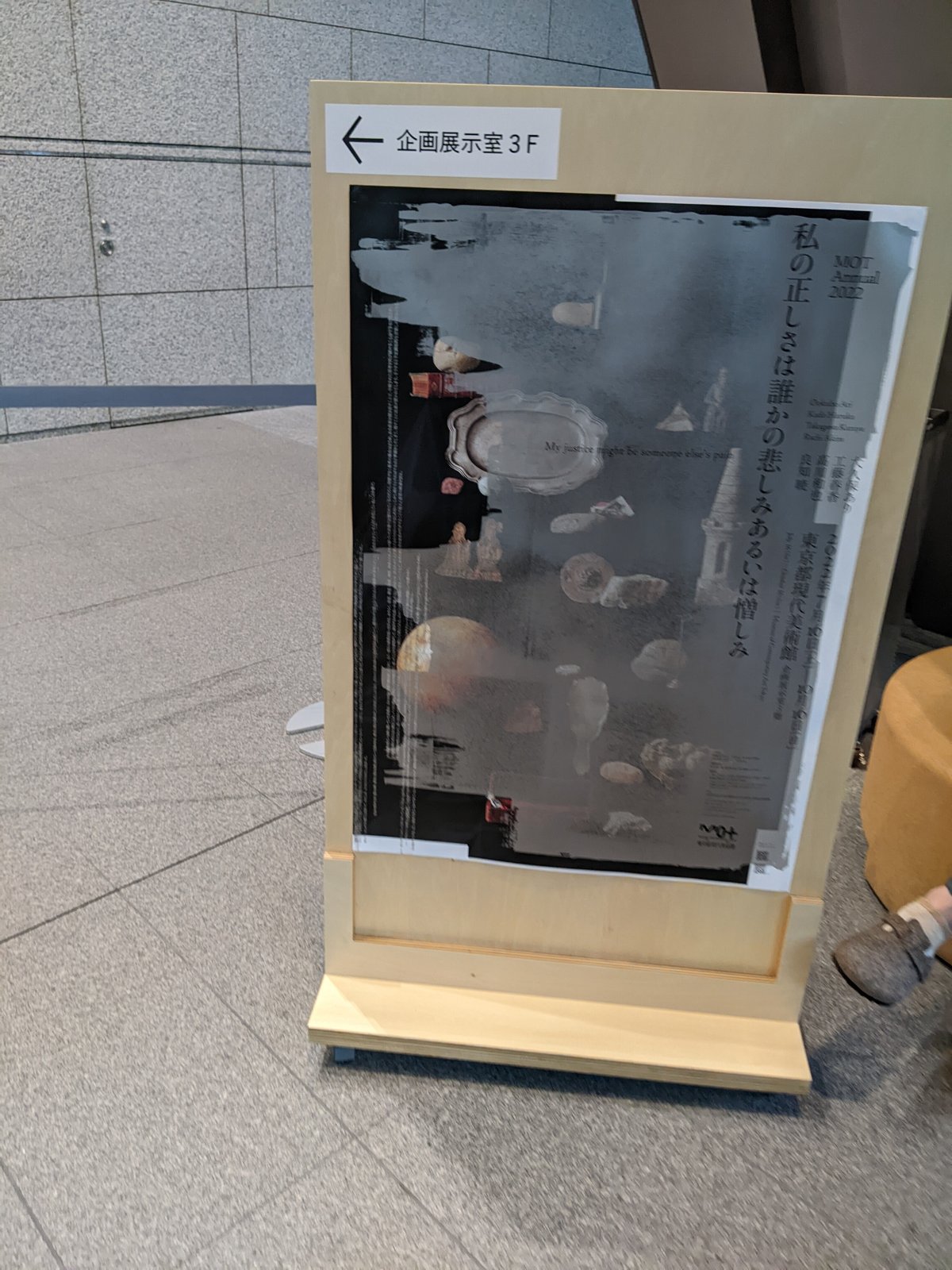
はじめに
参加している作家は4人。タイトルの「私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみ」から私が得るのは主に「弱者」と「権利」のイメージだが,そこにほぼ直に関係する「障害者の権利・女性の権利」を扱う作家から記号論やメディアの話をしたいであろう作家までいる。なにかひとことで特定できるようなテーマをもって集めたという感じはしない。それでも4人の作品全体を貫くような問題関心は,タイトルに現れているように感じられる。
高川和也
そもそもの扱われているテーマが興味深いのはもちろんとして,おそらく展示の順番もよく計算されている。
(私はつい癖で,込みがちな映像作品をはじめ飛ばしてしまったが)順路的に最初に案内されるのが,高川和也による思考をラップとして表現しようとする過程のセルフドキュメンタリー映像。
頭の中に渾然としていることばがラップという媒体を取りながら表現されるとき,そこにはリズムやテンポ,ライムという独特の制限により捨象されてしまう部分が生まれる。しかし反対に,それら制限があるからこそ「本心」からくる「純粋」な表現が生み出されることもある。そこで高川が出した表現の結末は,「青姦したい」「犬のように交尾したい」というまったくもって利己的な願い(念のため作家の名誉のため付言しておくが,ここでの「青姦」の想定相手には性的同意を得ているという文脈である)。
そもそもラップという文化・表現が社会的に弱い立場にいる者の素直な意見の表明を大事にしているから,本展覧会のタイトルがすでに思い起こされる。しかしそれだけではない。高川というひとりの男性による「本心」が語られることにより,本展覧会における「私の正しさ」の裏にありうる「誰かの悲しみあるいは憎しみ」(高川のラップの場合は,ある意味で暴力的に性的対象とされる女性たち)に目を向ける準備が鑑賞者はできることだろう。そういう意味で,本映像作品が冒頭に置かれている細かさが光る。
工藤春香

順路として二つめに出会うのが,工藤春香による障害者の権利獲得運動,とくに相模原障害者施設殺傷事件を題材にしたインスタレーション等からなる作品群。もっとも目をひくのは,「優生思想」をめぐる法制度の歴史と,それに抗するかたちでおこなわれてきた障害者その他にかかわる権利獲得運動の歴史が時系列順に裏表にまとめられたインスタレーション作品。作品の特性上,裏面が縦書きでありつつ右方向へ進んでいく文章は読みにくいが,その読みにくさこそが多くの人たちに知られることなく進められてきた権利獲得の動きのインパクトを示す。その他には障害者施設殺傷事件の被害者に直接取材した作品,その事件が起こった地に実際に出向いて作成した映像作品などが続き,これらも興味深い。障害者の権利運動について調べたいときにはこの作品群を参考の一つにしてもいいレベル。
大久保あり

順路的に3つめとなるのは,大久保ありがこれまで発表してきた美術作品・詩を集めつつ新たに展覧会場全体をひとつの作品として再構成したかと思われるもの。これまでの作品を時系列順に並べたものかと思いきや,会場全体を見ればそれぞれの作品,またそれにかかわったであろう出来事が交錯していることがわかる。中には隠れミッキーならぬ隠れ「黒い円」のように,全体を見回していなければ気づかないものもある。会場内の光の反射を利用した作品があることや,祖母から教わったというパンのレシピを示す作品の文字がおそらく刺繍でなされていることなど,芸が細かいのも面白い。
良知暁

そして最後の4つめには,良知暁による「シボレート / schibboleth」を題材とした作品群。シボレートとは,ある特定の共同体において仲間意識を作り出すために用いられる合言葉。この合言葉によってどのような人びとが周縁に追いやられてきたかについての文章を,展覧場冒頭に置かれている機械が映写する。辺野古ゲートで座り込みをしている人たちに対してひろゆきが「沖縄の人ってあんまりスムーズに標準語喋らないんですよ」と発言したことが話題になっている時代を生きている私たちにとっては,悲しいことにあまりにタイムリーすぎる作品。
その後,標準的な学校教室2.5室分はあるだろうスペースに展示されているのは,3時50分を示したまま止まった時計と,「rάɪt」の形に象られたネオン菅があるのみ。キャプションもなしで多くを語らない。しかし先に置かれていた映像作品をふまえれば,そしてなによりも本展覧会にてそれまでに目にしてきた「私の正しさ」とそれに伴う「誰かの悲しみあるいは憎しみ」があることをふまえれば,これらふたつの展示は雄弁にものを語るメディアとなりうる。
良知の展示室が終わった後,出口に出向くにはまた冒頭の高川の映像作品を通らなければならなくなる。つまりここまで巡ってきた鑑賞者たちはまた新たな発見をするべく2周目3周目の鑑賞に誘われているということだ。あえてそうしているのか,または施設の設計上そうするしかなかったのかは不明だが,最後まで展示設計の面白さを感じさせられた。
まとめとして
それぞれの作品としても,各作家の演出する展示空間としても,そしてひとつの流れをもつ展覧会全体としても楽しめるものであった。
満足感のまま,珍しく図録(というよりは作家による作品解説)も買ってしまった。
おすすめしたいところだが本日最終日のところに滑りこんできたので,いまさら感。気になった人はぜひこれからの4人の作家の活躍に期待していただきたい。私自身もそのひとり。
気になったのは,展示風景の撮影のみが認められている割には接写する人たちが多いこと多いこと。そこだけは残念さが勝つ。
