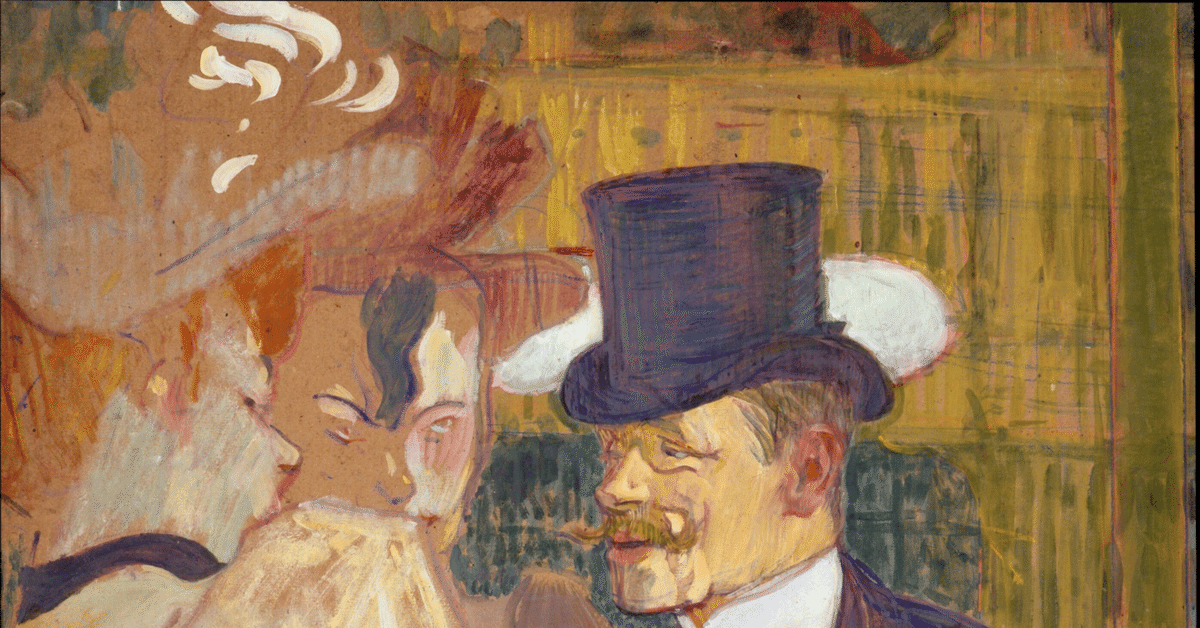
死に至る病 (講談社学術文庫)鈴木祐丞訳の解説が非常によかったので一部大幅抜粋
死に至る病、本文自体は、キリスト教的信仰心を持たない立場の私からしたら、ちょっと何を言ってるのかさっぱりわからない感じだった。だがキルケゴールが著作を作るうえで、念頭に置いていたこと、彼自身の思想的な背景に対する解説が、やたらと面白いというのか、これはキルケゴールを読む際に抑えておかないと、誤読の種になるだろうなと感心したので大幅抜粋。
死に至る病本文の解説や信仰者キルケゴールと死に至る病の関係の解説も面白いので、続きが気になる方はぜひ買ってみてちょ。
キルケゴールにとって著作とは何か。
改めて言うまでもなく『死に至る病』はキルケゴールの著作である。キルケゴールにとって著作とは、実は普通の哲学者にとってのそれとは異なる独特な位置付けを持った媒体なのである。
普通の哲学者の場合、基本的には自分の考えたことの表現のための場が著作であろう。だが、キルケゴールの場合、彼の著作にはもちろん彼自身が考えたことが書かれてはいるのだが、それは彼自身が考えたことの表現のための場ではなかったのである。
以下、この辺りの事情を説明し、キルケゴールにとって著作とは何であったのかを明確にしよう。キルケゴールにとって終生、最重要であり続けた問題、それはキリスト教の信仰を巡る問題だった。急いで言い出さなくてはならない。彼が追い求めたのはキリスト教に関する客観的な真理ではなかった。
彼を実存主義という思想潮流の源に位置付けることで有名な「ギレライアの手記」。22歳の若きキルケゴールが旅先のコペンハーゲン北方の小さな町ギレライアで書き残したとされる日記の言葉がある。
重要なのは私にとって真理であるような真理を見つけること。そのために私が生き、そして死ぬことを望むような理念を見つけることだ。いわゆる客観的真理なんてものを見つけ出すとして、そんなものが私にとって一体何の役に立つというのだろう。
キルケゴールはキリスト教に関する客観的な真理を求めて考察し続けたのではないのだ。そうではなく、彼はキリスト教の信仰を巡る主体的な真理を探求し続けたのである。
罪深いこの私はどのようにすれば救われるのか。この私に向けられている神の意志とは一体どのようなものか。そして、この私はどのように生きればそれを体現していることになるのか。このような問題に彼は終生向き合ったのである。
このことは、キルケゴールという人を理解するにあたって極めて重要であるにも関わらず、実に看過されやすいポイントである。つまり、このような実存主義者キルケゴールが著作活動にも携わったのだと捉えるべきなのである。
彼は自分自身の信仰のあり方をめぐる主体的な思索や苦闘を絶えず生きていて、その上で自分の能力、溢れるほどの想像力や境遇(父が資産家だったのでお金のために働く必要がなかったこと)などに鑑みて、著作家として活動したのである。
キルケゴールはいわば信仰者キルケゴールとして生き、その上で著作家キルケゴールとしても生きたということだ。ところで、キルケゴールが書き残したものは著作と日記に大別される。キルケゴールが書き残したものをできる限り余すところなく収録することを目指した最新版の原典全集(全28巻)のうち、16巻が著作であり、9巻が日記である。
キルケゴールは自らの信仰のあり方を巡る思索と苦闘を日記に記録した。日記は信仰者キルケゴールの思索、苦闘の表現のための場だったのである。日記にはもちろん他にも様々な内容、著作のアイデアや時事問題についての雑感などが書きつけられているが、彼の信仰を巡る実存的な思索、苦闘は日記をその表現のための場としたということである。
付け加えると、キルケゴールの日記には後世の読者の目を意識した様々な脚色が施されており、その内容全てを純然たる事実の記録と見ることはできないのだが、それでも日記には自らの生き方に思い悩む等身大のキルケゴールが姿を現していると見て間違いない。そして、信仰者キルケゴールが著作家として読者の方を向いたところに生み出されたのが著作だったのである。
とはいえ、この点はもう少し正確に捉える必要がある。つまり、信仰者キルケゴールは一体何を意図して著作家として読者の方を向いたのかということだ。普通の哲学者は何らかのテーマについて客観的な真理を考察するものであり、著作とはそのテーマについての施策の表現のための場であろう。
だが、信仰者キルケゴールは自分自身の救いのためにこそ思索と苦闘を行ったのであり、彼にとってはキリスト教についての客観的な真理の考察などどうでもいいことだったはずだ。そして、そうした実存的な思索と苦闘は日記の方をその表現のための媒体としている。そうしてみると、果たしてキルケゴールにとって著作とは一体どのような媒体だったのかよくわからなくなってくるだろう。
キルケゴールからすれば、およそキリスト教に関わるものにとって最重要なのは、一人一人の人間がそれぞれの具体的な生の現場でただ一人、単独者として神と向き合うことである。
その時に初めて、そしてその時にのみ、人間は自分に向けられているはずの神の意志を求めて耳を澄まそうとするし、そこに神の意志に忠実な生、すなわち信仰が形を取りうるのであって、罪意識という苦しみからの救いが実現しうるのだ。だから、著作家キルケゴールがなすべきこと、彼が成しうる最大かつ最善のことは、一人一人の読者を単独者として絶えず神と向き合って生きるように導くことなのである。
神学や哲学やらの客観的な真理に関する考察の成果を提示するようなことは、少なくとも彼にとっては意味のないことだし、また自分自身の信仰のあり方を巡る思索や苦闘をこれ見よがしに読者に披露しても仕方ないだろう。
むしろ、信仰のあり方を巡って絶えず思索や苦闘を重ねて生きるように読者を導くこと、これこそがキルケゴールにとっての著作という媒体のアイデンティティなのである。
確認しておこう。キルケゴールにとって著作とは一体何だったのか。それは端的に言えば、読者をキリスト教の信仰へ導くことを目的とした媒体だったのである。
もちろん、信仰者キルケゴールが著作家の姿をまとって読者の前に現れる以上、彼自身の信仰のあり方を巡る実存的な思索や苦闘が著作の方にも顔を覗かせることは多々ある。
ポイントは、彼の著作はそうした思索や苦闘の表現を目的とした場ではないということ。あくまで、読者をキリスト教の信仰へ導くことを目的とした媒体だということである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
