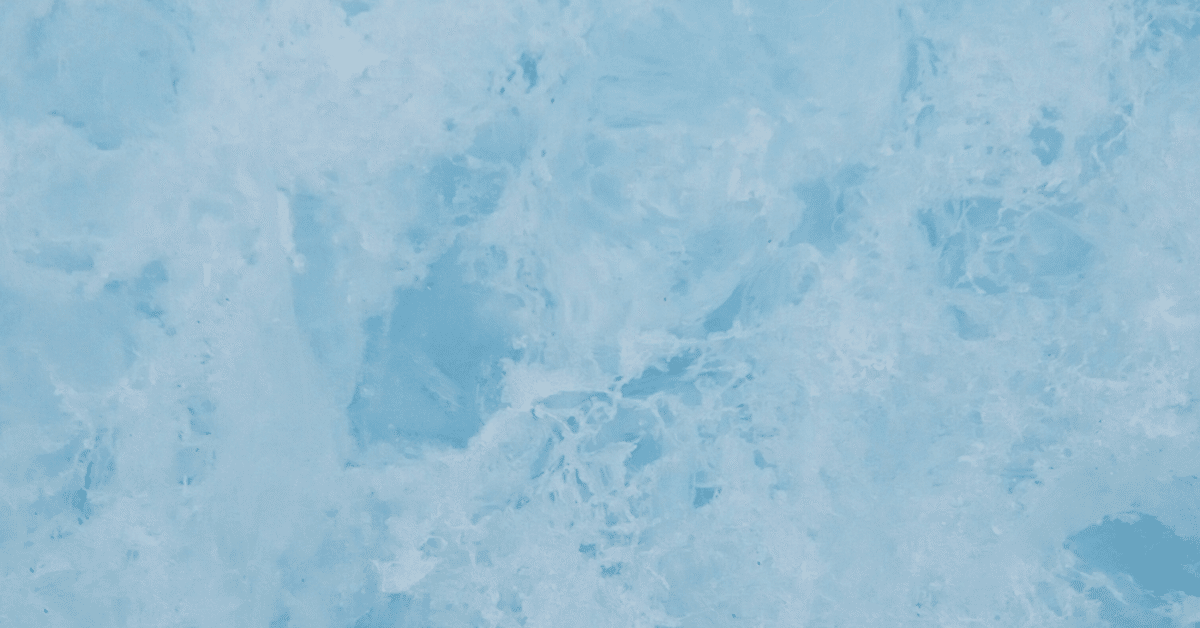
日本哲学史 藤田正勝 学習ノート
目次
序 章 日本の「哲学」と「哲学史」
1 「哲学」をどう捉えるか
2 哲学史とは何か
■第一部 受容期――明治の哲学
第一章 明治前期の哲学
1 「哲学」受容前史
2 西周による哲学の受容
3 福沢諭吉と近代日本の学問
4 中江兆民――「理学」としての哲学
第二章 大学という制度(アカデミズム)のなかの哲学
1 東京大学におけるフェノロサの哲学講義
2 現象即実在論――井上哲次郎・井上円了
3 哲学史の著述を通しての哲学受容――三宅雪嶺・清沢満之
4 批判的・合理的な知の形成――大西祝と狩野亨吉
5 フェノロサと岡倉天心の美学・美術史についての理解
6 ブッセ・ケーベルの日本における哲学研究への寄与
第三章 明治中期・後期における国家社会への関心と個人の自覚
1 近代化の歩みへの反省
2 個人の自覚
3 社会の矛盾や平和へのまなざし
■第二部 形成期――大正・昭和前期の哲学
第一章 大正・昭和前期の思想状況
1 大正という時代
2 昭和前期の思想状況
第二章 西田哲学と田辺哲学
1 西田幾多郎の前期の思索
2 田辺元の思想形成と西田哲学批判
3 後期西田哲学
4 田辺元の「種の論理」
第三章 西田・田辺と同時代の哲学のさまざまな展開
1 高橋里美
2 九鬼周造
3 和辻哲郎
4 美学研究の発展
5 宗教の哲学
第四章 西田・田辺の弟子たち
1 禅の伝統――久松真一・西谷啓治
2 現象学・歴史哲学・社会存在論――山内得立・高坂正顕・務台理作
3 構想力の論理――三木清
4 マルクス主義への接近――戸坂潤・梯明秀
5 多様な分野への展開――木村素衛・高山岩男・土田杏村・下村寅太郎
第五章 京都学派
1 京都学派とは
2 近代の超克
■第三部 展開期――終戦後の哲学
第一章 敗戦からの出発
1 「近代」と「主体性」の問題
2 平和の実現に向けて
3 戦後の相対化
第二章 戦後の京都学派
1 田辺哲学の展開
2 無(空)の哲学の展開
3 京都学派の多様な展開
第三章 戦後の日本の哲学の多様な展開
1 存在と知識
2 自己と他者
3 言 葉
4 身体へのまなざし
5 比較という視座
後 語
序 章 日本の「哲学」と「哲学史」
1 「哲学」をどう捉えるか
(1)哲学とは
日本哲学史を語るにあたってまず問題となるのは哲学とは何か?
古代ギリシア以来の西洋の伝統に立てばそれは自明な問いであるかもしれない。
だが日本という立場から哲学を問題にするときそれは自明ではない。
日本は明治維新後、政治や学問といった領域において西洋に倣う形で根本的な変革を行った。
哲学はその時受容された学問のうちの一つ。
その受容は完成したものを別の場所に移す作業ではなかった。
新しい哲学は、それ以前の世界観を基盤にして、それと交じり合う形で受容された。
そうなると次のような問いが生まれる。西洋で営まれた哲学という営みと、日本で行われた哲学は果たして同じものか?
受容の際、基盤になった世界観を構成する思想たちは哲学と呼びうるのかそうでないのか。もしそうでないのなら何なのか?
受容をした側には、何が哲学かという問いは簡単に答えられない問題と切り離しがたく結びついている。
哲学の受容は、それ以前に定着していた思想的基盤の上でなされた営み。
当然その思想の伝統も哲学の受容と展開の歴史の中に入り込んでいる。
西周
2 哲学史とは何か
