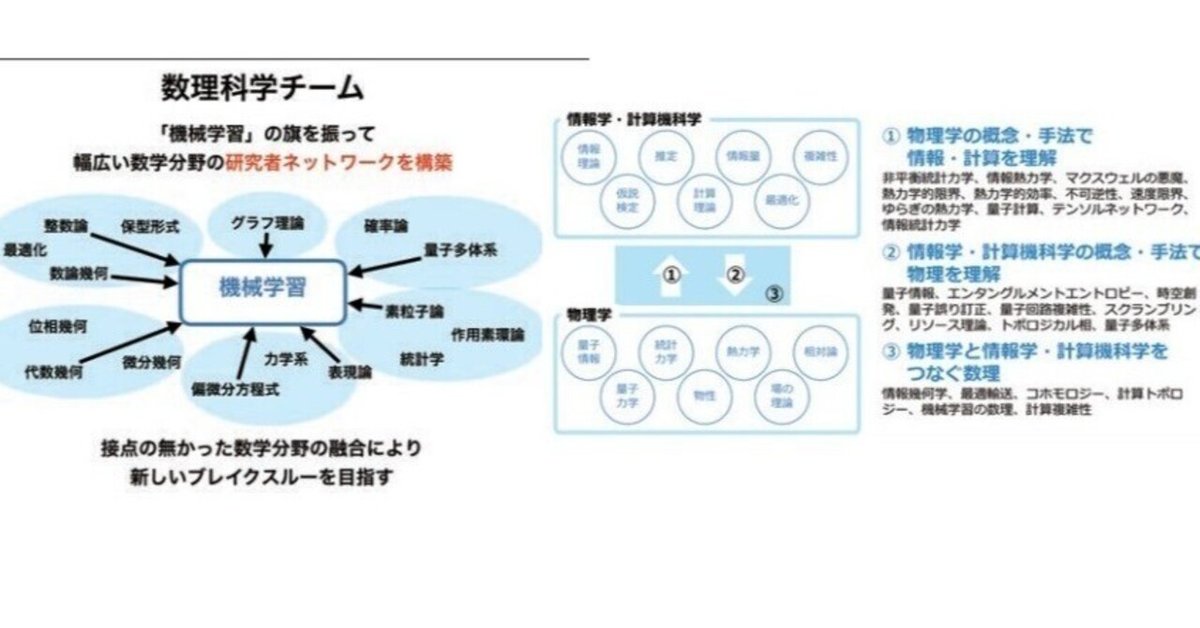
(量子力学の記事まとめ)東北大学 堀田助教のNote記事 {2024/09分まで}
Noteで量子力学や相対性理論についての様々な解説記事を書いてくださっていて、確率統計・情報理論ベースからの量子力学の本も書いてくださっている
「東北大学 大学院理学研究科 物理学専攻
量子基礎物理学講座(素粒子・宇宙理論分野)
堀田 昌寛(※)」
先生のNoteの記事をまとめました(自分用のメモもかねて)(ง'̀-'́)ง
どなたかの参考になりましたら、とっても嬉しいです( *ˊᵕˋ* )
※極限宇宙(学術変革領域研究A)
C02班量子ホール系による量子宇宙の実験
・記事中の書籍のご紹介
第1章 隠れた変数の理論と量子力学
第2章 二準位系の量子力学
第3章 多準位系の量子力学
第4章 合成系の量子状態
第5章 物理量の相関と量子もつれ
第6章 量子操作および時間発展
第7章 量子測定
第8章 一次元空間の粒子の量子力学
第9章 量子調和振動子
第10章 磁場中の荷電粒子
第11章 粒子の量子的挙動
第12章 空間回転と角運動量演算子
第13章 三次元球対称ポテンシャル問題
第14章 量子情報物理学
第15章 なぜ自然は「量子力学」を選んだのだろうか
第1章 量子情報と量子状態
1.1 量子ビットと量子情報
1.2 量子状態が導く頻度主義的確率と単発測定における客観情報
1.3 量子状態トモグラフィ
1.4 混合状態の純粋化
1.5 量子情報のアイデンティティ
第2章 量子測定
2.1 ポインター基底測定
2.2 量子測定における現代的コペンハーゲン解釈のいくつかの本質的側面
2.3 一般化された量子測定
第3章 量子操作
3.1 一般的量子操作としてのTPCP写像
3.2 LOCC:局所的操作と古典通信
3.3 連鎖する測定過程としてのLOCC
3.4 LOCCのユニタリー化
3.5 TPCP写像と量子状態の間の双対性
第4章 量子エンタングルメント
4.1 量子エンタングルメントの操作論的定義
4.2 量子エンタングルメント解析における局所性の定義の重要性
4.3 エンタングルメントエントロピー
4.4 2体系の状態変化と量子エンタングルメント
4.5 確率的LOCCによる状態変化と多体系の量子エンタングルメント
4.6 混合状態に対するエンタングルメント測度の一般論
4.7 ネガティビティと対数ネガティビティ
4.8 ガウス量子状態に対するネガティビティ
4.9 基底状態のエンタングルメントと局所強受動性
4.10 量子テレポーテーション
第5章 連続測定と量子ゼノン効果
5.1 直接測定によるゼノン効果
5.2 間接測定での量子ゼノン効果の実現不可能性
5.3 一方向性量子ダイナミクスと崩壊時刻の確率分布
5.4 一方向性条件を厳密に満たすモデル
第6章 ウンルー効果と量子情報
6.1 一様加速度運動をする測定者と等価原理
6.2 慣性系での量子場
6.3 一様加速度系での量子場
6.4 ウンルー効果とエンタングルメントエントロピー
6.5 真空状態のネガティビティ
6.6 ウンルー効果とブラックホール
第7章 ホーキング輻射と量子情報
7.1 ブラックホール形成と動的鏡モデル
7.2 2次元動的鏡モデル
7.3 ホーキング輻射の量子縺れ
7.4 量子縺れのモノガミーとホーキング輻射
7.5 ブラックホールの情報喪失問題
7.6 場の理論におけるパートナー公式
第8章 量子エンタングルメントと負エネルギー
8.1 基底状態の量子エンタングルメントが生み出す負エネルギー密度
8.2 量子場の負エネルギー密度
8.3 ブラックホール時空での負エネルギー密度流
第9章 量子エネルギーテレポーテーション
9.1 基底状態の量子エンタングルメント破壊と局所冷却問題
9.2 ミニマルQETモデル
9.3 一般スピン鎖系におけるQET
9.4 QETにおけるエネルギーと情報量の関係性
9.5 量子場を用いたQET
9.6 ブラックホールとQET
・確率分布と情報量・情報理論
〇確率分布と情報量・情報理論
・波動関数とは何か?
そもそも波動関数や量子状態は、単に「確率分布/確率密度関数の ”集合(束)”」に過ぎない、というお話。とっても重要( ˊᵕˋ )
状態ベクトルや、密度行列、演算子なども、単に表記方法の違いだけで、本質的には確率分布のこと。
量子力学は、情報理論の一種です。
量子状態は、任意の物理量を測定したときのその観測値の確率分布を与えます。
また逆にある物理量の確率分布が分かると、量子状態は一意に定まります。
つまり「量子状態」=「物理量の観測値の確率分布の ”集合”」ということです。
※確率分布の集合 = 確率密度「汎」関数
波動関数とは、物理的には量子状態と同じものです。
ただ数学的には観測量に影響を与えない位相因子exp(iδ)の自由度が波動関数には出てきますが、基本的に両者は同じものです。
右辺の項全体にかけられているexp(iδ)という因子は、量子力学では任意の物理量の観測結果に影響をしません。
そんな要らない因子を数学的表記から追い出したい場合には、下記のような密度行列表記をとれば良いです。
この密度行列表示は大変便利で、確率的に混合した量子状態ρも記述できます。
その特別な場合として、使用される確率分布のある1つの成分が1であって、他成分は零のとき、その状態は純粋状態と呼ばれます。
そうでないときは混合状態と呼ばれます。
直交座標系を任意固定して、その各軸方向のパウリ行列に対応する以下の3つの物理量を考えましょう。
するとその3つの期待値を実験で測定することで、元の量子状態ρは一意的に下記のように決定されます。
このように実験から量子状態を同定することを、量子状態トモグラフィ(※)と呼びます。
(注:推定統計学での「母集団(母確率分布)の推定」のこと)
従って、今度は物理量の確率分布が状態ρを与えられることがわかりました。
数学の確率論や情報理論では、確率分布はその系に関する情報とみなされるので、量子状態は系に関する情報の集合そのものであると、この量子状態トモグラフィから自然に理解されるのです。
このことから量子状態は確率分布の「集合」に過ぎないと、ご理解頂けたと思います。
波動関数も状態ベクトルの特定の基底での成分表示に過ぎませんので、同様に物理量の確率分布の「集合」がその正体です。
さて波動関数の収縮ですが、ある確率分布をしている物理量の理想測定をして、ある結果を得た時、その後の確率分布はその値に局在したものに置き換わりますよね。
例えばσ=+1が出る確率がp(+)=1/2で、σ=-1が出る確率がp(-)=1/2となる一様分布(注:ミクロカノニカル分布)の元で、測定したらσ=+1が観測できたとしましょう。
するとその確率変数の測定後の確率分布はp(+|σ=+1)=1, p(-|σ=+1)=0という新しいものに更新されます。
これが従来波動関数の収縮と呼ばれていたものです。
量子力学が確率論に基づいた情報理論である限り、「波動関数の収縮」は極当たり前のことなのです。
波動関数は飽くまで情報の集合であり、決して物理的な実在ではないので、測定した瞬間にそれが変化しても、系の知識の増加による情報の更新に過ぎないのです。
また粒子系の量子状態トモグラフィについては、教科書「量子情報と時空の物理【第2版】」(サイエンス社 電子版)の第1章で解説をしています。
・量子的な混合状態が現れるのは、人間の無知のせいか?
「主観」確率と、「客観」確率のお話です。
また主観確率と客観確率の区別がおかしくなっている議論も散見します。
物理学では、主に客観確率としての頻度的な確率を採用しています。
しかしその頻度的な確率でも、観測者依存性はあるのです。
このように確率には観測者依存性があるのですが、同じ実験を何回繰り返しても成り立つという意味で、これは客観的でもあります。
つまり頻度的な確率は観測者依存性があっても、再現可能性の観点からは飽くまで客観確率なのです。
アリスにとってはボブの結果を知らないために、彼女にとってのAの確率1/6を「人間の無知のため」と表現することは可能です。
しかしそれはサイコロ自体が決定論的な運動をすることが起源ではないことに、注意を払ってください。
しかし量子力学になると、この状況は大きく変わります。
そしてこの確率混合による純粋状態への分解の仕方も、無限種類あるのです。
この事実から、古典統計力学のように量子系の混合状態の起源を人間の無知のせいにしてしまうことは不可能なのです。
つまり混合状態は本当は1つの確定した純粋状態であるという理解は間違いなのです。
しかも量子力学の混合状態には純粋化可能性という性質があります。
その量子系の他に外部系を考えると、その合成系全体としては1つの純粋状態としての記述がいつでも可能なのです。
それは1つの純粋状態(注:環境系、第三者、フォンノイマン鎖の各鎖などとのテンソル積状態など)なので、そこには情報の欠如は全く無く、人間の無知が入り込み余地はありません。
ですから混合状態は人間の無知によるという説明は、根底から間違っているのです。
・量子ベイズ主義
「主観確率」というよりも、
「確率分布の変化(事前確率分布から事後確率分布への変化)」
という情報幾何的な解釈についてのお話。
1回でも頻度主義に則った実験や観測で確認をしておけば、後は未来予想としてQビズムの人々が「主観確率」と呼んでいるものを使う合理的な理由にはなります。
その意味でQビズムの理論から「主観確率」の誤解を取り除いたバージョンを考えるべきだと、私は思っています。
量子力学は確率だけを扱う理論だという、本来どの分野の人とも共有できる事実を認めれば、Qビズムや標準的な確率解釈を極端な認識論だという批判も出てこないはずなのですが、
現実にはまだ「確率だけを扱う理論」だと信じていない研究者がおかしなことを言うわけです。
量子ネイティブ育成のために、「量子力学は情報理論である」という現代的視点での教科書を書きました。
・物理量が作用素になるのは、古典力学でも同じ。
ポワソン括弧とハミルトニアン形式のお話。
ポワソン括弧はフィッシャー情報量/フィッシャー計量/共分散行列と同じ、「計量の定義」に使われる形式によく似ていて、
ハミルトニアン形式は、シンプレクティック構造と関係しているので
超弦理論や量子計量・情報計量による情報幾何とも関係してきます。
ある時刻でpとqの値を決めて、この方程式を解くことによって、未来(と過去)のp(t)とq(t)が一意に定まるのです。
また運動量演算子を定数倍して指数関数の肩に乗せると、その演算子は粒子の位置と運動量に関する確率分布関数ρ(p,q)に対して、下記のように位置座標の値に定数を加える作用を与えます。
つまり運動量演算子は、古典力学でも位置座標の推進演算子なのです。
同様に位置座標演算子から作られる演算子は、運動量の値に対する推進演算子になっています。
このような変換の生成子として、位置演算子と運動量演算子は理解できます。(※)
このように古典力学でも指数関数exp(・)を通じて、この物理量の演算子は状態変化を生み出す「生成子」であると理解できるのです。
演算子という表記を使えば、古典力学や量子力学、更にその2つとも異なる一般的な確率理論に対してさえも、この生成子と対称性の関係は普遍的な形で論じることが可能です。
量子力学を学ぶとき、しばしば物理量が「演算子」になるということが強調され過ぎて、学ぶ人はそこにある種の神秘性を感じてしまうかもしれません。
でもここで述べたように、実はそれは古典力学でも普通に起きていることであり、特に不思議でも何でもないのです。
なおこのような枠組みから、量子力学を操作論的な情報理論として正しく扱う下記の教科書を書いております。
※注:(指数型分布族、特に純虚指数関数で定義されている場合の)波動関数に対するフーリエ変換で、座標表示と運動量表示を入れ替えることができる、ということとも関連しています。
「座標」と「波数(物理量や状態変化の速度。
座標とは逆の物理次元を持つ)」の関係性ですね。
フーリエ変換によるスペクトル分解(空間座標に限らず、何らかの物理量の「座標」を変化させる要因・原因・因子としての波数)と、量子調和振動子、複素平面波の「集合」としての、確率分布・確率密度行列、という解釈です。
指数関数の「肩に乗せる」という操作をすると、
「指数型分布族として特徴づけられる」確率密度関数・確率分布になる、というときには
「指数写像 ⇔ 対数写像」の双対性になっている、ということなので
「確率量(確率測度の空間)
⇅
(確率事象に対しては「自己」、確率分布に対しては「平均」)
情報量(の空間)」 ※平均情報量=シャノンエントロピーのこと
「確率統計 ⇔ 情報理論」
ということでもあり、
「肩に乗せる」 ”前” の値・関数・数式は、
「情報量を表している」
(なのでexpをとる/指数写像すると確率分布に戻る)
という解釈も可能だと思います。
※「演算子」も「作用素」も、中身は「テンソル」なので、
ある意味では「確率密度行列」と同じなので、
単なる表記上の違いに過ぎない、
ということでもあると思います。
「プロセス-状態の双対性」ですね( ˊᵕˋ )
・ニ重スリット実験: 量子力学では、意識を向けると電子は粒子になり、向けないと波になるのか?
波動関数とは「物理量の確率分布の集合をまとめて1つの数式に表したもの(物理量/確率変数ごとに、確率密度関数が異なっていて、それを集めたもののこと)」だよ、というお話。
2重スリット実験とデコヒーレンスについてもわかりやすいです(. ❛ ᴗ ❛.)
量子力学の「波動性」は、波動関数の重ね合わせが作る干渉実験などから、そう呼ばれたりしますが、「波動関数」という物理的な波が実在しているわけではないのです。
波動関数は下記の記事にあるように、物理量の確率分布の集合をまとめて1つの数式に表したものに過ぎません。
また量子的な測定が対象系に起こす量子ゼノン効果でも、観測者の意識は何も対象系に影響を与えません。これについては下記記事をご覧ください。
では二重スリット実験で干渉縞が消える原因は何でしょうか?それは観測者による測定結果の読み出しのためではなく、「デコヒーレンス」のためです。
つまりスリットを通過した電子が他の系との間に量子もつれを作ってしまうためなのです。
ところが、スリットとスクリーンの間に電子と量子もつれをつくるものを入れるだけで、この干渉項は無くなってしまうのです。
でも上の計算では、Dは測定機である必要もありませんし、それを見る観測者を置く必要もありません。この点が重要なのです。
つまり測定機に限らず、SとDの間に量子もつれを作ってしまうものであればどんなDでも、スクリーンから干渉縞を消してしまうのです。
電子を見ようとする観測者の意識は、二重スリット実験の結果に何も関係ありません。
・量子力学のベリー位相と密度行列
確率分布(確率密度関数)として記述しても、
波動関数として記述しても、
状態ベクトルとして記述しても、
確率密度行列として記述しても、
単なる表記の違いに過ぎない、というお話です。とっても重要(∩ˊᵕˋ∩)
※個人的には、非可換な物理量の組み合わせ(行列の非対角項)や、干渉項を扱う都合上、確率密度行列(テンソル)表示の方が便利かな、と思っています。
また「確率事象」自体が「離散化※※ & 直交化(排他的・i.i.d.)」されているので、その点でも「連続的な」関数形式よりも、「離散的な」行列/テンソル形式の方が、イメージしやすそうです。
ただ、ブロッホ球のイメージも(ヒルベルト空間を)理解しやすいので、「状態ベクトル」形式も良いですよね(˶ˊᵕˋ˵)
※※量子速度限界や不確定性原理によって「実験的に区別/識別可能な物理量」は連続ではない。
一方で、現代測定工学の技術では、精度の桁数が足りていないので、連続として扱っても差支えない。
なので、連続でも離散でも、どっちでもいい。
私の教科書では、実験で観測できる物理量の確率分布こそが量子力学の基礎であり、状態ベクトルや波動関数や密度行列はその1つの表記に過ぎないことを強調しています。
これは電磁気学のマクスウェル方程式を4元数や外微分形式でも表すことができるのと同じ意味であり、ベクトルや行列や演算子は量子力学の表し方の1つでしかありません。
最初に物理量の確率分布の集まりから量子状態は定義されます。
教科書では、その後で量子状態トモグラフィ法によって、量子状態が密度行列で表示される流れになっています。
そしてその密度行列の特別な例として、その行列のスペクトル表示が1つの状態ベクトルだけで書ける量子状態を採り上げて、それを純粋状態であると定義します。
波動関数は点粒子の純粋状態での状態ベクトルの1つの成分表示に過ぎません。
ですから状態ベクトルや波動関数のみならず、密度行列も、確率論で量子状態を定義した後に導入された「記述の便法」だという内容になります。
立川さんは数理物理学の観点から「密度行列が先」派と「状態ベクトルが先」派という名前を記事で導入されていますが、私自身はそのどちらでもなく「観測される物理量の確率分布こそが先」派ということになります。
まとめると、私の教科書で扱われる「確率分布」に基づいた定式化では、その表記として密度行列および特別な場合としての状態ベクトルの2つが出てきますが、その2つの差は飽くまで見かけだけだということです。
純粋状態にある量子系の物理現象は、そのどちらでも漏れなく記述することが可能です。
ただし密度行列で扱われる混合状態については、下記の記事にある注意は必要となります。
量子力学では、混合状態にも古典統計力学にはなかった性質が現れるのです。
・量子力学の物理量は複素数では駄目なのか?
その物理量の定義の本質は、基準測定の
”複数の状態を区別” する「名前」に過ぎない
(注:複数の状態 ≒ 確率分布{確率事象の集合}
区別する名前 ≒ 確率事象)
というものです。
これは前世紀の量子力学教育からすると、ギャップを感じさせるものかもしれませんが、現代的な量子力学の定式化において非常に重要な点です。
基準測定でk番目の結果が出たときに、物理量Aは実数a_kであると定義した場合には、下記のエルミート行列が物理量Aに対応します。
しかし同じ基準測定で、物理量に対応するユニタリー行列を定義することも可能です。
例えば基準測定でk番目の結果が出たときに、下記の位相因子が観測されたと定義すれば良いのです。
この複素数である物理量の実部(cosθ_k)と虚部(sinθ_k)も、
それぞれ量子測定で計量できます。
例えば実部は、下記の相互作用でフォンノイマンのポインター基底測定装置と相互作用をすれば、正確に測定されます。
(ポインター基底測定に関しては、拙書『量子情報と時空の物理【第2版】』(サイエンス社, 電子版)第2章を参照してください。)
虚部を測りたければ、上の相互作用においてユニタリ行列とそのエルミート共役行列の和の部分を、ユニタリ行列とそのエルミート共役行列の差に置き換えて、更に純虚数であるiをかけておけば可能です。
ですから任意の物理量にはエルミート行列も対応しますが、
同時にエルミートではない行列を対応させることも可能です。
ただ普通は面倒なだけですし、エルミート行列だけでも十分なので、
そのエルミート行列を使って量子力学の物理量は通常議論をされています。
なおエルミート行列で定義される物理量は、
基準測定での状態区別をする名前ではありますが、
合成系のハミルトニアンに特定の対称性と物理量の保存則がある場合には、一部の部分系だけで勝手にその名前を変えることはできません。
保存則が表現できるように、全ての部分系でその物理量を定義する必要があります。
(注:テンソル積状態{合成系}になっているときには、同時確率分布/同時確率事象になっているため、各確率変数を「独立 / i.i.d.」として扱うことはできず、必ずセットで扱う必要がある)
・物理量の相関の強さと物理操作の多様性
相関は強すぎても弱すぎてもダメで、「人間原理」のように、
「可能な物理操作の ”種類が最大” になるように」
絶妙な調整をされているのが「量子力学」
というお話。
科学哲学的には、最大エントロピー原理や、自由エネルギー原理や、
変分原理などの情報理論的アルゴリズムの側面も絡めて、
非常に興味深い・奥深いお話です(*'▽')
※ここに「自然界のすべての物理量
(何らかの数学的空間・パラメータ空間中の ”座標”)には、
必ずシンプレクティック構造を成す、もう一つの対の物理量
(シンプレクティック共役な物理量:”波数”≒”座標”の物理次元の逆数)
が存在する」という条件(ルジャンドル変換による双対な空間の存在)や、
「自然界のすべての物理量の確率分布は、
必ず指数型分布族(またはそれらの混合分布)である」
という条件が加わった場合に、
相関や物理操作の多様性がどのように関係してくるのか
についても、(情報幾何学的な観点からも)興味深いと思っています(˶ˊᵕˋ˵)
※シンプレクティック構造によるシンプレクティック共役な2変数が、複素構造を持っている場合についても。
量子力学の本当の面白みは、演算子の非可換性というよりも、
物理量の相関が理論のユニタリー性とも強く結びつき、かつ、
情報因果律を通じて相対論的な時空構造にまで影響を与えている点です。
量子力学自体を作るときには相対論は入っていないのに、
因果律についての興味深い性質を既に内在していたのです。
また物理量の相関量自体についても、独特の性質が量子力学にはあります。
量子力学を理論として構築するには、ベル不等式の破れを説明するような、古典相関より強い相関がもちろん必要です。
しかし『入門現代の量子力学』第5章5.4節を読めばわかりますが、
相関が強すぎてもユニタリ性が壊れてしまい、
この現実の世界を説明できなくなります。
程よい強さの相関が量子力学の量子もつれ
(注:相互情報量、エンタングルメント、量子相関)なのです。
そしてこの量子もつれという相関が実現する時に、
可能であるユニタリ的な物理操作(つまり物理過程)の多様性が
最も強く現れます。
原理的に一番多様な種類の物理操作が可能となる世界こそが、
量子力学の法則に支配をされたこの世界だと分かるのです。
物理操作の多様性が物理量の間の強い相関の出現によって
抑制されてしまうのです。
物理量の相関は強すぎても駄目なのです。
この世界では、まるで可能な物理操作の種類が最大になるように、
相関の強さが調整されているようにも見えます。
そして量子力学の自然法則が選ばれたとき、
それがきちんと実現をしているという不思議さがあるのです。
この事実を逆の視点で考えると、次のような考察も可能です。
我々のような生命を生み出した進化の多様な物理操作(物理過程)の世界が実現するためには、この量子力学の物理法則でなければ駄目だったという面白い可能性が理論的にはあるのです。
相関が無駄に強い世界では、進化に必要な多様な時間発展も生まれなかったことでしょう。
思わぬところで、生命や人類の進化と量子力学の理論的構造が互いに深く結びついているのかもしれません。
なお量子力学に限定しても、量子相関としての量子もつれが強すぎれば、この世界の状態を記述できなくなる場合があります。
たとえば時空は量子もつれ(エンタングルメント)から創発する可能性が真剣に理論物理学で論じられているのですが、
場の量子揺らぎの相関が弱すぎても、そして強すぎても、
時空はブチブチにちぎれてしまいます。
滑らかな時空が現れるには、
程よい大きさの量子もつれが必要とされるのです。
物理量の相関と物理操作の多様性の間には、
このように深淵で不可思議な関係性があります。
今後の研究の発展によって、この関係性に関しても更に多くの事実が発見されていくことが期待をされます。
・量子テレポーテーションは、送信者から見たらモノの本当の瞬間移動である
量子テレポーテーションによって移動する量子情報は、
外部の系(環境系・世界全体など)から見れば、
異なる歴史の間の干渉(干渉項)によって転送されている、
というお話。とっても重要(. ❛ ᴗ ❛.)
そして、各観測者ごとに「(物理現象についての)描像」というものが、全く異なっているように、(局所的な、部分系でしかない、我々からは)「見かけ上は」そう見える、というお話。
この『入門現代の量子力学』(講談社サイエンティフィク)では、量子力学はなんらかの実在論ではなく、情報理論つまり認識論的な理論であるということを強調をいたしました。
物理量の確率分布の集合に収納された量子情報を扱う理論であるという意味です。
これは実に意味深長な内容を含んでいます。
物理学とは、「物(モノ)」の「理(コトワリ)」の学問ですが、
情報理論としての量子力学では、この「モノ」も観測者にとって情報に過ぎないのです。
例えば様々な個性をもつ猫や人間や、
ブラックホールに落ちるコーヒーカップも素粒子の集まりですが、
それらを構成しているその1つ1つの素粒子自体には個性が全くなく、
どこでどのように作られたのかという記憶も各粒子は持ち合わせません。
「モノ」を区別できるその個性や特徴は、素粒子の集合の量子状態に収められている量子情報が生成をしているのです。
その意味で個性を持った「モノ」の正体は、
量子情報という「コト」だとも言えるのです。
またアリスとボブ以外の外部観測者を置けば、その観測者にとって、転送される「モノ」の量子情報は異なる歴史の間の干渉によって転送されていることも分かります。
一知半解の理解で「量子テレポーテーションは瞬間移動ではない」と簡単に言い切ってしまう方もいますが、それは正しくありません。
量子力学は情報理論であり、情報は観測者依存性のある概念です。
これをきちんと踏まえると、少なくとも送信者での立場では、確かに瞬間移動になっているのです。
そして更に測定結果を得た受信者が過去を振り返る立場では、アリスの測定時刻以前に既に量子情報が届いていたとも言えるのです。
このような量子情報物理学の深い、そして面白い理解が広まることに期待をしています。
このアリス領域の状態の重要な特徴は、未知状態|ψ〉の依存性が全て干渉項のみに現れていて、対角成分のどこにもでてこない点にある。
アリスの測定後にその領域から消えたように見えていた|ψ〉の情報は、マジックの舞台裏のクリスから見ると、マクロ系の量子もつれの中へ巧妙に隠されていたのである。
この他の場合でも量子もつれを使うと、各部分系には情報をまったく持たせないまま、情報を壊すことなく完全に隠すことは可能だ。
ブログ記事「量子エンタングルメントと時間の矢 」の中でも、そのような他の例が紹介されている。
アリス自身が参加している異なる歴史どうしの干渉であるため、決してアリスはこの干渉項を観測することができないという、量子力学の原理に則った究極のトリックである。
(アリスは、4つの歴史のうちの1つだけしか、意識できないため。)
舞台裏からこの過程を見れば、アリスのところから送られた信号にもその干渉項部分に|ψ〉の情報が隠されており、因果律に則った光速度以下のスピードでスピン3にそれは届けられ、こっそりと受け渡されていたのだ。
クリスにとっては、図14の操作はスピン3への情報書き込みだけでなく、スピン3と他の系の間にあった量子もつれを解消する「dis-entangler」の役目もしている。
ただ強調しておくと、普通の手品とは違い、クリスの視点が正しくて、アリスやボブの視点での描像が間違いだとか、不正確ということではない。
アリスがみる量子状態、
ボブがみる量子状態、
そしてクリスがみる量子状態は、
観測者のもつ系の知識量の差によって、一般には全て違う。
量子力学は観測者毎に定式化されており、
どの視点での描像も互いに矛盾を起こさない。
クリスにとっての量子力学では、
まったく異なる歴史の間に生じる「干渉項」に隠されて
量子情報は空間を伝達し、
アリスにとっての量子力学では、確かに
アリスが測定した瞬間に、量子情報は既にボブのスピンに飛んでいる。
アリスの見方でも、クリスの見方でも、
量子テレポーテーションの描像は日常生活とかけ離れているものだが、
それぞれ間違いではない。
これが、量子力学自体の深さを示しているところなのだ。
・量子力学の線形性はどこから来たのか?
量子力学の線形性は、確率論的なもので、量子論固有のものではない、というお話(専門的です)。
これまでの流れを振り返りますと、線形性が現れた原因は確率分布に対する物理操作のアフィン性にあることに気付けるかと思います。
そしてそのアフィン性は、決して量子力学固有の性質ではなく、
全ての確率論が持つ一般的な性質に過ぎません。
この意味で量子力学のダイナミクスの線形性は、確率論を認めさえすれば、特に不思議なことではないのです。
前世紀には波動関数のシュレディンガー方程式に波動関数の3次の非線形項を加える理論なども研究されていました。
しかしその密度行列表示ではアフィン性は露わに破れています。
現代的観点からは、このような非線形的拡張がうまくいかなかったのは、状態ベクトルや密度行列の操作論的定義(量子状態トモグラフィ)とアフィン性を入れてなかったからとも言えます。
区別できる状態の離散性と連続的物理操作を同時に考える必要性が、状態ベクトルの線形重ね合わせを必然的に招く構造になっているのです。
ただしここで注意が必要なのは、そのような構造を持つ理論は量子力学に限定されていない点です。
古典力学は他の理論と比べてむしろ特殊であり、1回の実験で区別できる無限個の純粋状態が隣接して、それが連続的に分布をしている性質があります。
つまり相空間上の各点(x1,x2,x3,p1,p2,p3)の全てが1回の実験だけで互いに区別できる純粋状態になっています。
このおかげで純粋状態の線形重ね合わせが出現せずに済んだのです。
なお量子力学は物理量の確率分布に基づいた情報理論であることをしっかりと押さえれば、所謂「観測問題」はそもそも量子力学には存在しなかったことも、明確に理解できます。
ですので量子力学でもっとも驚くべき事実は、状態の線形重ね合わせではなく、また測定における不可避な他の物理量への擾乱でもなく、ベル不等式の破れの実験で確立をした「局所実在の否定」だと、私は考えています。
・無限に深い量子井戸に潜む、物理学徒の数学への隷属とその開放
「純粋数学」としての性質と、
「現実・自然界」での性質(物理学)は、
(基本的には)別物だよ、というお話です。
とっても重要(. ❛ ᴗ ❛.)
結局物理学に出てくる関数は全て連続的であるべきかどうかさえ、実証科学としては確定をしていないのです。
今回は多くの教科書に出てくる無限井戸を考察し、数学の関数論を知らなくても、その物理は正確に扱えることを論じてみましょう。
また物理学として考えるとき、問題の設定の物理的妥当性を検証することも大事です。
たとえば明らかなように、この世界には理想的な無限井戸などは存在しません。
十分に高いポテンシャルを持つ有限井戸型ポテンシャルは実験で近似的に作ることはできますが、その高さを無限大することは決してできません。
その物理として達成できない奇妙な極限を考えたことが、変な解を出す原因ではないかと目星を立てる能力も大切なのです。
重要なのは、物理学徒が数学の関数論を知らなくても、物理自体に集中をして考察を深めれば、これらの問題点は気づける点です。
またハミルトニアン、つまりエネルギーの確率分布の期待値や分散や高次モーメントの全ても必ず有限になります。
そのような量子状態を実験で作ることは、エネルギーコストの観点からも問題はなくなります。
また2乗可積分性で定義をされるフォンノイマン流のヒルベルト空間の状態も、任意の精度でこの状態空間の元で近似をできることが保証をされています。
ヒルベルト空間とは異なり、この状態空間には完備性はないのですが、必ず生成には誤差を伴う物理的量子状態ならば、任意に小さくできるこの誤差は問題になりません。
ここで和を一応無限和にしています。
しかし実際の数値計算や現実の実験では、有限個数の固有関数の和にします。
和の無限大を有限のカットオフΛに置き換えて、上で作った状態空間の元として扱えば、何も問題は起きないのです。
また物理理論の厳密な数学化は物理学者の仕事ではないと、私は思っています。
物理学者を例えるならば、下記記事にも書いたように「探偵」なのです。
・「確率0%」は、その事象が絶対起きないことを意味するのか?
「確率0%」の「測度零事象」についてのお話。
とっても興味深いです(ง'̀-'́)ง
人間のようなマクロスケールな構造
(遺伝子配列や、超マクロな分子構造など、
パリティ・キラリティ/カイラリティ・トポロジーなど、
トポロジカルな情報/位相幾何情報が存在する系や、
生体内に蓄えたネゲントロピーを消費することで、
変分原理/自由エネルギー原理/最大エントロピー原理などが規定する
「測地線」から乖離した「運動/行動」をとることができる生命系など)
については、そのユニークな性質
(【ミクロな】素粒子には【個性がない】のに対して、
位相幾何情報は【マクロな個体】ごとに【個性が存在】する)
から見て、個々の存在自体が「測度零事象」と言える場合、
個々が持っている自己情報量は「無限大」ということになり、
情報熱力学的には無限のエネルギー(のポテンシャル)
を持っていることになるので、ますます興味深いです(. ❛ ᴗ ❛.)
もちろん、そのエネルギーがポテンシャルから汲み出されるためには、
シラードエンジン(マクスウェルの悪魔)として
「具体的な物理操作」を行う必要があるので、
その「ネゲントロピー・情報量を消費して行う物理操作」に応じて
「確率分布から、ある単一の確率事象が選択される」
「その確率事象が持っている自己情報量に相当する、
ネゲントロピー・相互情報量を、確率分布/量子状態へ供給することで、
確率事象を励起している」
みたいな解釈の仕方もできるのであれば、
それもとっても興味深いと思っています(∩ˊᵕˋ∩)
量子力学は起き得る事象の確率分布を与えるものです。
ある物理量を測ると、その許される値が何%で観測されるのかということを予言し、実験でそれを確認できます。
測度零事象とは、量子力学での観測確率が零である事象(現象や出来事のこと)を指します。
普通の感覚だと0%とは「起き得ない」事象です。
しかし「その現象が起こる確率は0%」、つまり
「ある現象は100%起き得ない」ことと、
「本当にその現象が起きない」ことの間には、
微妙な概念のずれがあることに気づきます。
確率の普通の頻度主義的な定義では、ある事象が起きる確率とは、それが起きた回数を、観測したトータルの回数で割った比(※)を考え、その比の試行回数無限大極限とされます。
※注:状態和・分配関数によって定義される「ギブス測度」を確率量/確率測度とする。
このギブス測度による定義の場合、確率量は温度・(平均「情報量」としての、シャノン)エントロピーと結びつく。
宇宙の寿命は無限に長いと仮定して、その宇宙の歴史の中でその事象がたった1回だけ起きた場合、「その事象が起きる確率は?」と聞かれれば「0%」と答えることでしょう。
起きた事象の回数である1を、無限大の試行回数で割るためです。
中には信じてくれる人も居るかもしれませんが、
実証科学的にはその人を未来人であるとする根拠を持てません。
Nを大きな自然数として、N回中にその事象が起きる回数の期待値をn(N)としたとき、N無限大極限でその比 n(N)/Nが零になっていれば、それは測度零事象になります。
このような測度零事象に対しては、量子力学を含む全ての実証科学的な立場からは何も言えません。
測度零事象は統計学に基づく科学がイエスともノーとも言えない対象です。
科学で扱える対象外ということなので、それが仮に起きても、否定も肯定も科学ではできないのです。
科学の本質的な境界を考える上でも、このような測度零事象は面白い概念だと思います。
ちなみに測度零事象は出現確率が零となることだけが条件なので、無限回の試行の中でただ1回だけ観測される事象に限定されません。
2回でも3回でも良いです。
無限回試行をした実験結果のリストの中で、その事象の出現の仕方が測度零の分布であればよく、トータルの試行データ上の測度零事象の位置分布は複雑なものでもOKです。
〇マクロとミクロについて
・量子力学におけるミクロとマクロの境目
量子力学におけるミクロとマクロの境目は(おそらく)無いよ、というお話。
今まで量子力学がマクロ系で破れる兆候は、実験では全く見えていません。
部分としては量子で、全体としては波動関数が収縮をしている古典だという考え方には、粒子間の距離や多体相互作用の強さに閾値の存在が必要です。
そしてその概念も、自由度の勝手な数え方に依らない定義をしないといけません。
どの部分を見れば、それは量子だとか古典だとかをいちいち定義しないとならないのです。
しかし現時点では、その辺りの定義も合理的にクリアして成功している理論はありません。
粒子が何個に増えようと、それは量子力学に従う対象なのです。
マクロ的な古典的な振る舞いも、量子の法則で創発している2次的な概念だと考えます。
厳密には近似的な存在に過ぎません。
ただしその創発概念である「マクロな実在」はとても良い近似であって、そのため古典力学は日常でも十分に有効なわけです。
たとえば空に月があると確認した後、しばらく月から目を逸らして、次に自分が目を向けるときに、空のどこにその月が観測されるのかは、
近似理論の古典力学でも完全に無視できるくらいに小さな誤差の範囲で、答えを与えてくれるのです。
・「シュレディンガーの猫」の現代的な量子力学での理解
上の記事と同じで、マクロ系でも干渉効果はあるよ、
でも現代技術では、干渉効果が小さすぎて測定できないよ、というお話。
より重要な認識は、猫の体も素粒子の集まりにすぎないという点です。
「量子力学の法則に従う粒子の集まりなのに、シュレディンガーの猫についてだけは量子重ね合わせが起きないなんて、不公平だ」という感覚は、多くの人とも共有できるのではないでしょうか。
φを変えることで、このマクロな物理量の期待値は確かに変化をしています。
この物理量を測る実験さえできれば、マクロな猫でもこのような干渉実験が可能なのです。
日常体験ではそれをしていないので、猫の干渉効果が見えていないだけなのです。
「測っていないから見えていないこと」は、「あり得ないこと」とは大きく違うのです。
現実の実験技術ではそのマクロな物理量の測定がまだできていないのが原因であり、原理的にその物理量や干渉効果が存在していないわけではありません。
〇観測/測定・意識
・量子力学における「直接測定」と「間接測定」
「観測」「測定」という言葉についての「定義」のお話。
とっても重要です( ˊᵕˋ )
概念として基準測定を含む理想測定がまずあり、それを包含する正確な測定、更にそれを包含する一般測定があります。
理想測定とは、基準測定で定義をされた物理量の確率分布を正しく再現し、そしてかつ測定後状態が観測された物理量の固有値に対応する固有状態になる測定です。
正確な測定とは、物理量の確率分布を正しく再現するが、測定後状態がその物理量の固有状態からずれてしまう可能性がある場合の測定となります。
つまり測定後状態には誤差が一般には伴います。
そして一般測定では、得られる物理量の確率分布と測定後状態の双方に誤差が出てくる可能性がある場合に対応をしています。
またあらゆる測定において、直接その対象を「見る」ことはできません。
その対象やその測定結果を表示する測定機のモニターから出てきた光子が観測者の眼に入り、それが持ち込んだ情報を観測者の脳内で処理をして、
「スピンz成分は上向きである」「エネルギー準位は○○である」等と認識をしているだけです。
つまりこの意味では、あらゆる測定は対象を直接認識しない「間接測定」だと言えます。
つまり対象系の自由度ではなく、測定機の自由度を観測するという意味で、その測定を間接測定と呼ぶ場合があるのです。
一方でSG実験では、スピンの情報を得るために、この粒子のスピン自由度にSG装置という測定機が直接的に磁場を及ぼしています。
対象物の情報を得るために、直接その対象物に相互作用を加えるという能動性があるのです。
この意味ではSG実験は「直接測定」であると表現して問題ありません。
ある1つの量子測定が「直接的」か「間接的」であるかは、このようにその文脈を正しく指定しないと意味がとれないことに、まず注意をしてください。
測定がスピン自由度の時間的な運動を止めてしまう量子ゼノン効果は、この直接測定のときのみ起きます。
つまり対象に直接かかる相互作用が引き起こす物理的効果こそが、量子ゼノン効果であるという、極めて常識的な理解が可能なのです。
一方で『量子情報と時空の物理【第2版】』(サイエンス社)の第5章では、間接測定における量子ゼノン効果の不可能性定理を証明しています。
情報を得たい対象系に、その測定のための余計な相互作用を直接加えることなく、その対象系の元のダイナミクスによって放出される信号をただ受動的に外部で受け取り、その信号を測定をする間接測定の設定で成り立つ一般的な定理です。
崩壊したかどうかを実験で知りたい対象であるこの原子核には、その測定のための余計な相互作用を全く加えていませんし(光子は勝手に原子核の元のダイナミクスで出てきます)、
そしてその原子核が出したガンマ線を原子核に影響を与えないようしながら測定をして、原子核自体が崩壊したかどうかを決定しています。
そして教科書第5章で述べられているように、このような間接測定の場合には、決して原子核の運動に量子ゼノン効果は起きないことが証明されるのです。
・擾乱の存在のために、量子力学における測定による変化は、単なる情報取得による変化とは考えられないのか?
「観測問題」など最初から無い、
単に「確率分布から、単一の確率事象が排他的に選択される」という、
確率論の基礎的なお話。
擾乱は、量子力学に限らず、古典力学にもあるよ、というお話も。
そして波動関数や状態ベクトルの収縮は、
測定によって得られた系の情報に基づいた、
物理量の確率分布の単なる更新に過ぎません。
その意味で、観測によって古典的なサイコロの目の確率分布が更新されて、特定の目に分布が収縮をするのと本質的な違いはないのです。
その意味で、量子力学には「観測問題」など最初から無かったと言えるのです。
そもそも古典力学ですらも、他の物理量への擾乱は有りがちなことです。
他の物理量への擾乱は、対象系と測定機との相互作用が原因であり、
古典力学が良い近似で成り立つ領域での多くの実験ですらも、
そのような擾乱は頻繁に起きています。
或る粒子の位置を測ろうと粒子にレーザービームをぶつければ、
古典力学でもその粒子の運動量には擾乱が起きます。
ただ古典力学ではその擾乱の原理的な下限はないとされ、
いくらでも擾乱は小さくできると考えられていましたが、
古典力学や古典確率論にも「擾乱」という概念自体は自然に入っていて、量子力学特有のものではありません。
波動関数は「誰にとっての」を指定しないと定まりません。
ですから測らない他の物理量への擾乱が起きるタイミングと、
粒子の波動関数が収縮するタイミングは、異なります。
ですから物理過程としての擾乱の存在が、波動関数や状態ベクトルの収縮に対して特別な意味を持つわけではありません。
まとめると、測定中に起こる他の物理量への擾乱の存在も、また状態の線形重ね合わせも、そして観測による状態ベクトルの収縮も、量子力学固有の性質とは全く言えないのです。
観測における状態ベクトルや波動関数の収縮は、
観測者にとっての単なる情報取得による変化です。
・古典確率とフォンノイマン鎖の「意識」の話
量子力学に限らず、確率論・確率統計全般において、
「確率分布から、単一の(排他的な)確率事象が選択される」
という事象/過程について、(数学的には未定義なので)
「”意識”によって引き起こされる現象」である
とする「公理」として出発する、というお話です。
とっても重要(˶ˊᵕˋ˵)
量子力学は情報理論であるため、
所謂「観測問題」というものもそもそも無い
ことが、下記のように現在では分かっています。
粒子の位置や粒子数などは素朴な実在ではなく、
その確率分布だけで記述される情報的な対象であるのです。
実はこのような情報理論的な考え方の萌芽は、
前世紀初頭にフォンノイマンやウィグナーが既に持っていました。
しかし彼らの話の中には、観測過程の終端として、
観測者の「意識」が含まれていたために、多くの研究者がそれに反発をし、「量子力学は情報理論」という理解に至ることは当時ありませんでした。
その後、多数の量子力学の精密実験がなされ、特にベル不等式の破れの実験的検証にも成功をしたために、量子力学は素朴な実在論的理論ではなく、実在を伴わない情報理論であることが現在では明確になっています。
特に重要なのは「可能な様々な事象の候補の中から、波動関数で定まるある確率で、ただ1つの事象が選択されて、時々刻々と認知、体験をしていく意識を持った自分は存在している」という前提です。
これを実証科学を始めるための1つの公理として認めるのです。
そもそも確率を考えるときには、いろいろな前提が必要です。
これは量子力学に限らず、古典確率論を含む一般的な話となります。
まず決して同時には起きない事象(例えば表に出るサイコロの各目)の集合を考えて、各事象に何%かという数字を割り振ることで得られるのが、確率分布です。
ではそれらの事象が同時には起きないと誰が判断をするのでしょう?
それは人によって違うかもしれません。
色彩に限らず、「これ」と「あれ」は同時には起き得ず、
その2つは1回の試行で区別可能であると判断することは、
原理的には観測者毎に異なっていても良いのですし、
そして実際あり得ることなのです。
すると関数とみなした確率分布の引数に当たる独立事象は、
各観測者、もっと端的に言えば観測者の認知と、
その主体である「意識」が決めていることになります。
どんな事象が同時には起き得ないと判断をし、
そのような独立な事象の集合の中のどの1つの事象が、
今の時刻に起きたのかを認知する「意識」の存在は、
確率を論じる上で普段はあまり目立ちませんが、
不可欠な要素と言えます。
太郎君には、裕子さんが知った自分のコインの表裏はわかりません。
太郎君にしてみれば、情報が伏せられたままの「裕子さん+花子さん+花子さんのコイン+自分のコイン」の合成系全体を考えるしかできません。
その系が表の状態にあるのか裏の状態にあるのかは、50%の確率でしかわかりません。
花子さんや裕子さんにはもう太郎君のコインの裏表は確定していても、
太郎君にとっては確定的なことは何もないのです。
これが古典的な場合のフォンノイマン鎖の例です。
今は意識をもった花子さんや裕子さんを仮定しましたが、
代わりに意識をもたないであろうAIを考えても、
太郎君にとっては全て同じ結果を与えます。
この意味で、フォンノイマン鎖の終端である観測者(今の場合は太郎君)の「意識」以外は、花子さんや裕子さんなどの
他の部分系に意識の有無を仮定する必要は、太郎君にとって無いのです。
しかし太郎君にとっては、ただ1つの事象を各時刻に体験認知する
自分の「意識」の存在は不可欠となります。
これが意識の終端としての「意識」であり、
フォンノイマン=ウィグナー的な理解の仕方になります。
確率分布を扱うときにフォンノイマン=ウィグナー的な観測者の「意識」は不要であると主張する人も居ますが、
確率分布の引数となる独立事象を定義し、
そしてその観測者自身にとっての対象の確率分布を収縮させている、
フォンノイマン鎖の終端としての「意識」の存在は、
前提として不可欠なのです。
・何色でもない量子情報が作っている、この世界 -It From Qbit-
It From Qbit的な世界観と、
「意識」<私>「クオリア」を公理・原理・出発点とした、
「外部世界の情報解析」が科学であって、客観性にも限界がある、
というお話。
物理学・化学などの低物理レイヤーでもこのような主観性がある上に、
心理学・社会学・クオリア構造学のような高物理レイヤーも
「プロジェクションサイエンス」として、主観性が存在するので、
情報ベースの世界観であれば、それは必ず
「局所主観世界だけしか存在しない」ということになります(. ❛ ᴗ ❛.)
※リーマン幾何の空間や統計多様体などでの、
原点(座標系)選択の自由性とも関係しているのかも?
素粒子の集まりである「モノ」を区別するその個性や特徴は、
その多数のブロックで組み上げられた量子状態に収められている
量子情報そのものだと言えます。
つまり現代的物理学の理解では、
個性を持った「モノ」つまり「存在」の正体は、
量子情報という「コト」だとも言えるのです。
この世界のあらゆる存在(英語ではIt)は、
量子情報の基礎単位である量子ビット(英語ではQbit)
から生まれているという思想を
It From Qbit(イット フロム キュービット)と呼びます。
これは現代物理学を表す1つの象徴的なワードになっており、
現在世界の多くの物理学者が取り組む研究テーマになっています。
もともとは量子情報である「素粒子」の1つ1つには、
色というものはありません。
人間の眼に届く光にも色はありません。
「色」は量子情報を基にして人間の脳が作ったイメージです。
色のない量子情報である「光子」や「素粒子」を記述するには、
波長という数字に基づいた数式を用いるしかありません。
その数学を通じて、物理学はこの世界のバックヤードに人々を案内してくれるのです。
自分がこの世界の像の中に見ている色を他の人も見れているかは、
原理的に回答不能な問題なのです。
哲学ではそれを「クオリア」と呼んだりもします。
色を見るという行為でも、飽くまで観測者としての意識、
つまり<私>こそが主体であり、見えているこの世界は、
その<私>が認識する量子情報を基にして創発しているものなのです。
どこまでも客観的であるはずと言われている科学ですが、
それでも科学をする主体の<私>の存在は大前提です。
「我考える、故に我在り」、「我感じる、故に我在り」。
これを否定してしまうと、科学の活動を始めることさえできないのです。
でもこの<私>の存在を、他者は客観的事実としては実証しようがありません。
自身は確かにこの<私>であると思っている自分を、
プログラムによってうまく会話している機械としてのAIと、
外部の他者は原理的にそして客観的に区別しようがないのですから。
つまり<私>の存在は、他者にとって「確かめようのない」事実とも言えます。
それでも科学という営みは、この<私>の存在を真実として全肯定するところから始まります。
公理(原理)としてまず<私>がいて、
その<私>の五感やその先にある様々な機械装置も使って、
<私>にとっての外部世界に刺激を与えてその応答を収集し、
その情報を解析するのが、科学なのです。
・量子力学における基底選択問題とフォンノイマン鎖の終端の「意識」
フォンノイマン鎖の終端である「意識」についてのお話。
括弧付きで「意識」となっているように、
必ずしも人間の意識に限定されません。
量子力学では環境系を含めた全系では、
純粋状態(部分系のテンソル積状態・テンソルネットワーク)しかとれない
ので、部分系である私たちが日常的に感じている
「(多世界ではなく)単一の世界(デコヒーレンス)」
を説明するためには、必ず
「意識(どの部分空間・部分座標からの視点なのか、
どの量子力学的な数式の項なのか、
どの確率事象なのか、
どの並行世界の枝なのかを指定する、
「ポインター」のようなもの)」
が必要不可欠ということですね。
※個人的には「意識」という言葉は、
臨床医学や脳神経学や心理学的な側面を帯びてしまうので、
科学的な定義・ニュアンスがまだ乏しい「クオリア」という用語を使って、
【クオリアポインタ】
(自己のクオリアが
並行世界の枝/確率分布/数式上の項/情報幾何空間中のうち、
どの枝/どの確率事象/数式上のどの項/どの部分空間にいるのかを、
指定する・指し示す・ポインティングするもの)
という呼び方をしています。
量子力学は確率分布に基づいた情報理論の一種であり、
またその確率は指定された観測者にとっての対象系の情報
を意味しています。
観測者たちが持っている対象の事前情報に応じて、
対象系のその確率は変わります。
ですから観測の主体である観測者の<私>という視点が、
情報理論には極々自然に入ってきます。
その観測者は、互いに同時には起き得ない対象系の事象の候補(注:確率分布のこと)の中から、
各時刻にただ1つの事象が選ばれる背反的な体験(注:確率事象のこと)を常にしています。
多数の事象から1つの事象が観測で選ばれることにより、
その観測者にとっての対象系の確率分布、そして
その確率分布の集合である状態ベクトルや波動関数が収縮を起こします。
この収縮を起こさせる観測者の<私>が、
フォンノイマン鎖の終端である「意識」なのです。
この観測者Sは外部の観測者Oにとっては、所詮素粒子の集まりです。
そしてOにとっては、Sの状態ベクトルをこの「意識基底」系ではない、
他のどの基底系でも展開することも可能です。
つまり同じSの状態ベクトルを、Oは元の意識基底系で展開もできるし、
この別な基底系で展開することもできます。
この外部観測者Oにしてみれば、
こっちの基底系でこの観測者Sの「意識」が働いていても、
別に不思議でないのです。
つまりOにとっては、Sの基底系を選ぶ原理は特に存在していません。
Sの1つの基底系が選ばれることなく、基底系の避けがたい選択自由度が依然として残っていることを「基底選択問題」と呼びます。
でも繰り返し強調しますが、対象の観測者Sにしてみれば、
自分ははっきりとした「意識」を持っていて、
どの状態でもグーかチョキかのどちらか一方しか出していない
と思っているのです。
このことは確かに他の基底系に比べても特殊な、ただ1つの「意識基底系」がこの観測者Sの素粒子群には存在をしていることを意味しています。
また「意識基底系」の存在は、その前提としての「意識」の存在を意味しています。
結局、Sを「意識」のある観測者だとすると、
意識基底系が元々Sの素粒子群に与えられている必要があるのです。
環境系が自動的に意識基底系を指定するという事実はありません。
互いに排反な事象のうちの唯1つだけを感じている、この「意識基底系」の存在こそが、フォンノイマン鎖の終端に「意識」を置く必要性を与えているのです。
事前にこれが「意識」の基底であると指定をするということは、
その「意識」の存在も事前に仮定しなくてはいけません。
従って、どうしても観測主体である「意識」の存在を、
量子力学の公理の中に入れておく必要があるのです。
ここまで説明しても「意識」は要らないという人がまだ居れば、
この基底選択問題にきちんとした解答を与えないといけませんが、
これまで広く認められた合理的な解答は存在していません。
結局、上のSとEの話と同様に、状態ベクトルの収縮を起こさない「意識」を持たない観測機モデルでは、どの基底で対象系Cを測ったのかが決まりません。
ですから、排反事象から1つの事象を取り出す観測には成っていないのです。
本当の観測を考えたいのならば、観測機Tの結果を読み出して認知をする「意識」を持った外部観測者を仮定するか、もしくは観測機Tが|0>と|1>の基底に基づいた「意識」を持っていて、Cの状態に収縮を起こすとするしかありません。
結局フォンノイマン鎖終端の「意識」が出てくるのです。
・量子力学におけるウィーラーの参加型宇宙
It from Qbit/qubit、すべては情報理論的な起源を持つ、というお話。
量子情報による時空の創発についても少しだけ。
彼のこの思想は、現代では「It From Qbit」、
つまり量子情報の基礎単位である量子ビット(Qbit)から
世界は創発をしているという思想へと拡張され、
世界中の多くの物理学者によって、その研究が進められています。
量子力学では、測定前にいかなる「実在」も存在をしていません。
測定をすることで、
その測定をした観測者にとっての「実在」や「現実」が創発をします。
私たちが日常で「現実」や「実在」と呼ぶものは、
イエス・ノーの1ビットを基礎とする質問を、
観測者である私達が量子的な対象に投げかけ、
測定装置によって引き出されたその質問に対する応答の記録から生じる
のです。
要するに、すべての物理的なものは情報理論的な起源を持ちます。
つまり観測者である自分以外の外部を指す「世界」または「宇宙」は、
私達の観測で創発をしているという考え方です。
これがウィーラーの参加型宇宙の思想です。
量子力学によると、初期の宇宙の歴史は量子的な重ね合わせ状態になっています。
後の時代の我々が眼の前の宇宙を観測をすることで、
その中の1つの過去の歴史がピックアップされ、
それが「現実」だと我々に認識されるのです。
これが彼の言う「宇宙は私たちから独立して『あそこに』存在しているわけではありません。
私たちは、起こっているように見えることを引き起こすことに
避けられない形で関わっています」の部分の意味です。
そして私たちは単なる観察者ではなく、
宇宙の「現実」や「実在」を創発させる参加者だと、
ウィーラーは強調するのです。
ただし彼も、また現代の量子力学でも、
観測者の意識が対象に物理的な変化を与える
と言っているわけではありません。
歴史の線形重ね合わせの中に既にあった
1つの歴史を選択するだけのことです。
このあたりが、スピリチュアル系の方々との考え方とは大きく異なる点です。
彼の「It From Bit」、そして現代の「It From Qbit」という思想は、
現代的な量子力学の情報理論としての理解の進展や、
時空が量子情報から創発する具体例として研究が続いている
AdS/CFT対応理論などを通じて、
現代物理学にしっかりとその根を下ろしつつあるのです。
・量子的重ね合わせ状態を1回で区別できるならば、その人はユニタリー性を破る存在である。
タイトルそのまま。
量子的重ね合わせ状態を1回で区別できるならば、
その人はユニタリー性を破る存在である、というお話。
素朴な実在を扱う古典力学とは異なり、
量子力学は実在概念をその中に持たない情報理論です。
その理論の主役は、
観測者が1回の試行で区別できる背反的な事象に対する確率分布です。
「それらの事象は同時には起き得ず、背反的である」
と観測者の意識が知覚認識する事象xと
その集合Δに対して確率分布p(x)が導入されます。
例えばサイコロの目が1であるならば、
そのサイコロの目は同時に6にはなれません。
このことを踏まえてΔ={1,2,3,4,5,6}として、
サイコロの目x∈Δの出現確率をp(x)と数学的に表現できるようになり、
そしてその合計確率は(1)式のように
1(注:”1 = 100%"のこと)になります。
この「排反的な事象」は観測者の認知によって指定をされます。
サイコロの目が1であり、同時に6であるとことはないという
経験則に基づいて観測者は目が1から6までの事象を区別されると判断をして、その確率分布を考えるのです。
区別する能力が観測者になければ、そのような確率分布を導入することはそもそも無理なのです。
量子力学に従っている我々には、この(5)式の4つの事象を
背反的とすることはできません。
1回の試行だけではスピンx成分が+1の状態とスピンz成分が+1の状態を区別できないのです。
区別するには無限回の実験の繰り返しが必要となります。
もしその区別をただ1回の実験だけで可能にする異星人が居れば、量子力学のユニタリー性を破っている存在だということが、以下のように分かります。
ですから、もし量子的な重ね合わせ状態にただ1回の試行をして100%の成功確率で区別できてしまう異星人がいたら、その異星人は量子力学のユニタリー性を破る存在であると言えるのです。
量子力学でも、その確率分布の引数である互いに排反的な事象は、
観測者の意識が本来設定するものですが、
シュレディンガーの猫の状態のような量子重ね合わせ状態を
1回のチェックだけで区別できる観測者は存在しないのです。
この結論は、今後いくら量子コンピュータや量子AIの技術が進んでも、
量子力学が正しい限りにおいて変わりません。
古典力学が破れていたように、
量子力学も将来破れていることが実験で分かれば、
逆に量子重ね合わせ状態を1回のチェックだけで区別できる観測者が居る
可能性も残ります。
このように最終的には観測主体である観測者の「意識」が、
独立な事象を実証的に決定するのです。
〇実在性の否定・「量子力学での」状況依存性("量子力学での"コンテクスチュアリティ)
・超選択則と隠れた変数:量子力学における「実在」の否定について
タイトルのとおり「量子力学における「実在」の否定について」のお話です。
「超選択則」と「ホログラフィ原理」についても。
「そこにモノがある」という局所実在性の考え方は、
下記記事のようにベル不等式の破れが見つかった実験で
現在では否定をされております。
そしてその局所実在性否定の成果は、
2022年のノーベル物理学賞の対象となりました。
そしてこの「実在」の否定の実証により、
量子力学は実在論的理論ではなく、情報理論の一種であることも、
よりはっきりとしてきたのです。
現在までの実験でも精密に成り立っているものに
チレルソン不等式というものがあります。
この不等式は量子力学の理論的な予言です。
ですから実験は非決定論的で、非実在論的な量子力学
という理論の正確さを同時に示しているのです。
物理学での実在性の否定とは、
隠れた変数が存在しないということを指しています。
この「隠れた変数」とは、あらゆる物理量の背景には、
実現可能な複数の値(多くの場合は連続的な値)の中から、
各時刻にはっきりとした値をとる実在的な何かがある
とする前世紀の理論で論じられていたものです。
そしてその変数の値の時間的変化は決定論的な法則で決まっていて、
過去の初期条件だけから決まると考えられていました。
つまり隠れた変数とは、古典力学での粒子の位置座標や速度などのような「実在」と呼びたくなる対象です。
ところがベル不等式の破れが実験で確認されたことにより、
「そこにモノがある」という考え方の根拠だった
局所的な隠れた変数の存在が否定をされたのでした。
一方で、量子力学自体を使わずとも
情報因果律(※)という局所性の性質だけから
チレルソン不等式は導けることが知れられています。
この事実をごく当たり前に受け止めれば、
局所性こそが自然界の重要な法則であり、
その結果として実験での局所実在性の否定は、
そのまま実在性の否定であると理解できるのです。
ある状態において、光子などのモノが存在するしないは、
観測者や測定方法に依存するのです。
それが情報理論としての量子力学の本質的な性質なのです。
でも我々は生まれてから現在まで
「実在」というものを肌で感じてきました。
量子力学はそれが「幻」だと言っているわけですが、
それでは何故我々は「実在」を感じているのでしょう?
それは原子数などの物理量の保存則の経験からきています。
でもそれは先のnote記事の中で述べたように、正確なものではありません。
多くの物理量の保存則はミクロの世界や高エネルギー領域では壊れています。
しかしそれは少なくとも局所的な隠れた変数、
つまり「或る値をもった電荷がそこに存在している」
という局所的実在にはなれないことは、
先のベル不等式の破れの結果から明らかになっています。
ある有限空間領域の中にどれだけ電荷が入っているのかは、
観測前には決まっていないのです。
それは単に「知らない」のではなく、
その測定前の電荷の値がそもそも存在していない(注)のです。
これが量子力学の帰結です。
(注:物理時空中には「存在していない」が、
確率空間中(ヒルベルト空間や情報幾何空間)においては
(確率分布・統計多様体として)「存在している」。
ただし人間には確率空間を実験的に直接的に測定できず
あくまでも測定できるのは物理時空・確率事象のみ。
「(物理時空に)存在していない」 ≠ 「完全な無」。
しかし宇宙全体での全電荷量の値は保存しているはずです。
電荷密度を全空間で積分した値は、はっきりとした値を常にも持ち続けます。
それは確かに隠れてもいない「実在」とも言えます。
そしてこの電荷保存則から、量子状態の線形重ね合わせに関して
超選択則(superselection rule)という性質が導かれます。
素粒子標準理論に現れるゲージ理論では、
物理的な観測量は全てゲージ変換の下で不変なものに限られます。
すると全ゲージ電荷量の値が異なる量子状態の重ね合わせ
の干渉効果を測定できる実験は存在しないことがわかるのです。
電場を生む電荷ならば、宇宙全体の電荷量の合計が或る値、たとえば零となる状態だけで量子場の状態は記述可能だという意味です。
例えば量子電磁力学(QED)という理論においては、下記の式のように、電子と陽電子の全電荷数が零の状態は書けます。
全電荷数が異なる状態との重ね合わせを考えてももちろん良いのですが、
その効果は単に物理的には観測不能なのです。
測定において全電荷量が特定の値をとる状態の重ね合わせだけが
「選択をされる」というこの事実を、
物理学の業界では超選択則と呼んでいるのです。
このような状況では全電荷を実在的存在と見なしても良いのですが、
その値は変えられないので「変数」とは実質的に見なせません。
ですから超選択則を導くこの全電荷量は、
いわゆる「隠れた変数」とは異なるのです。
宇宙全体に与えられる、動かしようのない固定されたその1つの値を
「実在」と呼んでも、特にそれ以上の意味は何もありません。
「そこにある」というモノの実在性とは本質的に違うものです。
(記者疑問:不確定性原理の下限、
クラメールラオの限界/クラメールラオの情報不等式の下限を、
ある物理量を示す「座標」と、
その逆数の物理次元を持つ「波数」で構成した場合、
この下限は無次元量になり、フィッシャ情報量の逆数で与えられるので、
これを「負の情報量 ≒ エントロピー」と解釈した場合、
このエントロピー量自体は超選択則を導く「実在」と呼べて、
情報空間中(確率空間中)にのみしか「実在」が存在しない、
物理時空中には「実在」が存在できない、
とも解釈できる?)
古典的な電磁気学や一般相対論でも既に成り立っていたのですが、
境界だけで全電荷量や全エネルギー量などが分かってしまうこの性質は、
現代物理学では「ホログラフィ原理」と呼ばれています。
全空間の情報はその境界に集まっており、
そして逆にその情報を基にして低次元空間の中で意識をもった存在が広がる高次元空間を想起しているだけと言っても良いのだというのが、
この原理の意味するところです。
これは境界に溜まる量子情報が時空全体やその中の世界を創発している
という『万物は量子情報である』、つまり
『It From Qbit』の考え方と非常にうまく整合をしているのです。
現在では『It From Qbit』という考え方に基づいた様々な理論が世界中で多くの物理学者により探求をされています。
なお量子ビットから量子力学の理論を現代的に構築していく現代的な教科書を、講談社サイエンティフィクから出しております。
It From Qbitの精神がその構成の背景にある教科書です。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpsgaiyo/74.1/0/74.1_2904/_pdf/-char/ja
(※)情報因果律とは,「遠隔地の物理系との ”相互情報量” が,
エンタングルメントなどの物理相関を用いたとしても,
送信された古典的な ”通信量” を超えることはない」
という物理原理で ある.
(注:1bitしか送信していないのに、受信側で受け取った情報量を
1bit超の情報量として扱うことは決してできない、の意味。
どのような通信路を用いても、情報量を増やすことはできない。
小熊 貴大 A,松尾 弘貴 A,木村 元 A
・マーミンの魔法陣と量子力学での実在性の否定
GHZ状態、コッヘン=シュペッカーの定理、マーミンの魔法陣のお話。
個人的には「ベル不等式の破れ」、EPR状態よりも、
GHZ状態(※)・マーミンの魔法陣の方がわかりやすかったので、
こちらの方がオススメです( ˊᵕˋ )
物理量に対して古典力学では、測定によらない真の値の存在と、
その値の正確な測定の存在を無根拠に仮定をしていました。
ところが量子力学は、その物理量の真の値は実在しておらず、また不可避な測定誤差や物理量への擾乱が出てくるという性質を持ちます。
この物理量の中には、光子などの素粒子の数も入っており、
その真の値が存在しないということは、
その素粒子自体が実在として存在していないことを意味します。
2022年には「そこにモノがある」という局所実在性を否定をした、
ベル不等式の破れの実験に対してノーベル物理学賞が与えられました。
古典力学では異なる複数の物理量にそれぞれの真の値があり、
その物理量の真の値の積も物理的な実在だと考えられてきました。
ところが量子力学ではその性質が成り立たないことが、
コッヘン=シュペッカーの定理などを通じて現在ではよく知られています。
ここでは、その最も簡単な例となる、ディヴィット・マーミンが見つけた「魔法陣」というものを紹介してみようと思います。
ところがこの性質を満たすように、
測定前の9つの物理量に+1かー1の値を割り振ることは、
どうやってもできないのです。
つまり測定前に各物理量が+1かー1のかの値をはっきりと持っていて、
かつそれが擾乱なく測定できると仮定をすると矛盾が生じるのです。
つまり古典力学のような素朴な実在としての物理量の値は、
量子力学にはないのです。
量子力学では
どの物理量をどの順番で測定をするかで、結果は変わる
のです。
何を測定するのかという選択と、その測定をする順番を決めることを、
一般に量子力学では「文脈」と呼んだりします。
※「量子力学での文脈依存性・状況依存性・コンテクスチュアリティ」
マーミンの魔法陣は、そのような
文脈によらない測定前の物理量の値は実在していない
ことをはっきりと示しているのです。
※GHZ状態の名前に含まれている「ツァイリンガー」さんは、
「ベル不等式の破れ」によって「ノーベル賞」を受賞したご本人です。
・「万物は量子情報」と「万物は素粒子」との整合性について
私たちが日常的に感じている「実在」というのは、
「物理量の保存則を基にして、近似的に想起しているもの」
に過ぎない、というお話です。
「万物は量子情報」という認識論的な理解と
「万物は原子分子、そしてそれらは素粒子標準理論に出てくる
素粒子やまだ発見されていない素粒子からできている」
という原子論的な還元論の理解との整合性で混乱する人もいます。
それは原子論が前世紀に実在論として語られていたことが原因だと思います。
でも21世紀の現在ではその「実在論」は下記記事にあるように否定をされてます。
電子、ニュートリノやクォークなどの素粒子を記述する標準理論も、
「実在」という概念が実験的に既に否定をされている
量子力学の中の1つの理論に過ぎません。
しかし体を貫通し続けても我々に何も感じさせないニュートリノを、
現場でその実験をする研究者が「実在」であると
無意識に感じてしまう理由は、
素粒子反応のデータから各種物理量の保存則を読み取る、
彼らの経験そのものにあります。
データを解析する現場の物理学者は、そのような保存則を満たす対象に対して、なんらかの「実在」を感覚として自然に想起してしまうのです。
彼らにとってのこの「実在」の本性は、このような物理量の保存則に過ぎません。
しかしその「実在」は、量子力学では厳密には否定をされている、
単なる近似的概念に過ぎません。
2022年のノーベル物理学賞となった有名なベル不等式の破れの実証により、「そこにモノが在る」という局所実在性が実験で否定をされているのです。
天動説が観測によって覆ったように、我々にとって当たり前な感覚でもある「そこにモノが在る」という思い込みも、既に現代物理学の実験によって覆っているのです。
また標準理論を超える高エネルギー領域での新しい物理においては、
バリオン数やレプトン数などの保存則も、
実際には破れているだろうと予想をされています。
素粒子標準理論を実在論的に教えてしまう前世紀スタイルの講義は、
今世紀後半には消えていると、私は思っています。
教員の世代交代の中で、実験的に確定をしている
「量子力学は情報理論であり、局所実在はそもそも存在しない」
という事実が、当たり前に広く浸透しているはずだからです。
「ありありとした実在」としてではなく
飽くまで「量子情報としての素粒子」であるニュートリノを、
教壇に立っている量子ネイティブ世代は教えていることでしょう。
なお量子力学は実在論ではなく、情報理論であることを強調をした
下記の現代的な教科書を、講談社サイエンティフィクから出しております。
・ベル不等式の破れに与えられたノーベル賞
「局所実在性」のうち、
「局所性」がおそらく重要なので(因果律・マルコフ性と関係するため)、「実在性」の方を否定して考える、というお話です。
注:「実在性」の否定といっても、
「量子状態 ≒ 確率分布自体は存在している」ので、
「無」というわけではありません。
「決定論」を否定していて、
「量子確率論」を肯定する
(「無知」を原因とする「古典確率」
{つまり本質的には決定論} ではなく、
「本質的・根源的・自然界が持つ性質としての確率性」
を持っている「量子確率」)、という趣旨です。
「測定するまで値が存在しない/決定していない」というのは、
あくまでも(古典確率ではなく)「量子確率」による確率分布
になっていて、「(古典確率的な)決定論ではない」ということです。
2022年にノーベル物理学賞を与えられたベル不等式の破れの実験結果は、
実在論を信じることを不可能にはしないですが、
実在論を信じないことは可能にします。
つまり量子力学は情報理論であるということです。
仮に実在論を信じたい場合には、「陰謀論的実在論」というかなり変わった理論しか生き残りません。
量子力学は操作論的な意味で、完全に局所的理論です。
無信号条件のみならず、情報因果律まで満たすという
驚異的な局所性を持っています。
量子もつれは非局所性を示すというアインシュタイン以来の古い見方は、
実証のみに基づいた現代的な量子力学で、
もう意味を失っていると考えています。
このような陰謀論を信じれば、ベル不等式が破れることも「まあ問題ない」と強弁できるわけですが、今度はなぜ実験でも確認されているチレルソン不等式(量子力学の結果)を満たすのかが分かりません。
どうせベル不等式を破るのなら、ついでに量子力学臭いチレルソン不等式も宇宙はなぜ破らないのかの合理的説明がないのです。
ちなみにこのチレルソン不等式は、量子力学を考えなくても、
情報因果律という局所性の考え方だけから導くことができます。
素直にこの事実を受け止めれば、局所性こそが量子力学の本質であり、
ベル不等式の破れが意味するのは実在性の否定であると考えられます。
日常感覚で慣れていた「実在」というものは、
飽くまで局所的実在だったはずです。
そのような局所性があるからこそ、
長い時間の経験を踏まえて「自然だな」と人類に思わせてきたわけです。
ベル不等式の破れの実験がこの局所的実在を否定した段階で、
(注:「局所性」の方ではなく)「実在」自体を放棄する
のが最も合理的な思考ではないかと思います。
量子力学はその背後に決定論的実在論を持たない情報理論
であるという観方を実験結果は後押しをしたのです。
同じ年にノーベル賞をとられたザイリンガー(ツァイリンガー)さんは
「量子力学は情報理論である」という思想をお持ちです。
現代的視点からは、ザイリンガーさんの同時受賞は大変良かったことだと、個人的には思っております。
(注:ザイリンガーさんは、GHZ状態{マーミンの魔法陣・コッヘン=シュペッカーの定理}の「Z」の人です)
・物理学における「情報」と「実在」
(かなり専門的なお話です)
ホログラフィ原理や、
双対性のある空間同士での「見た目」の違い、
「見た目」上での物理量・物理現象は局所座標系の取り方
(観測者の視点・状態や、観測者にとっての環境系の状態)
ごとに異なる
(エネルギー密度は無限遠方でのみ意味を持ち、
局所的には座標変換次第でいくらでも「見た目」上の値は変化し得る)、
などの重要なお話です(∩ˊᵕˋ∩)
量子力学は実在論ではなく、情報理論の一種です。
でもこう言われても、
「情報は情報のみで存在し得るのか?」
「量子力学が情報を扱う理論であるなら、実在を表す本当の理論を。」
と素朴に感じてしまう方も多いと思います。
「実在」というものが日常生活であまりにも当たり前のように刷り込まれているから当然の反応でもありますが、それは幻想なのです。
まずはよく考えてみて下さい。
睡眠から覚めて目に入る世界は、
光(つまり素粒子である光子の集まり)が持ってくる情報に過ぎません。
例えば錯視は意識の現象的研究に役立ちますが、
更に人間が見ている世界は最終的に脳内で加工されたものであることを教えてくれています。
皮膚や服の領域に色は付いていないという情報を、
それぞれの光子は自分の網膜まで届けていたはずなのに、
脳内では斜線部分の情報を採り入れて、錯視として皮膚や服に自動的に彩色してしまいます。
我々が見ている世界は、決してそのまま実在しているわけではないのです。
では、その情報を運んでくる「光子」は実在でしょうか。
これについても、普通の意味の実在ではないことが分かってます。
例えば光子が存在しないはずの真空中を一様加速度運動する測定機や観測者は、加速度に比例した温度の光子の集まりとしての熱浴を観測するのです。
(注:環境系・真空場の温度が上昇したように見かけ上、そう見える)
(注:ウンルー効果のこと。一般相対論・強い等価原理によって、
{自身の座標系を、加速度のあるリンドラー計量から、
静止系であるユークリッド計量[ミンコフスキー]へ
変換することによって}
”自身の加速度を環境系へ押し付ける” ことになるため。)
光子があるかないかは観測者に依存しています。
真空中を慣性運動する観測者にとっては、光子は存在しない。
ところが一様加速度運動する観測者にとっては、光子は存在するのです。
現代物理学の基礎である場の量子論において、
素朴な実在概念では光子すらも説明がつかないのです。
眠りから目覚めた人が見る世界の光景は、
世界が素朴に実在していることを証明してません。
情報が脳の中で処理され、それからイメージを作り出しているだけ。
ただ毎日起きるたびその世界の風景に再現性がある(☆)ため、
素朴な実在という感覚を生み出して、
日常の範囲でそれを長く利用してきただけなのです。
量子力学は素朴な実在を扱う理論ではなく、情報を扱う認識論的理論です。世界は量子情報からできている。
量子重ね合わせにある自分自身を認知できない古典性がある意識を持った
観測者としての私が、独立でかつ互いに背反な事象の中から、
各時刻に唯1つの事象を確率的に体験するという事実
があるだけです。
「情報は情報のみで存在し得るのか?」
これには情報自体を記憶させる物理的実在は必要ではないのか
という疑問も内包しています。
でも「情報が物理的な何かに記憶されている」ということ自体も
情報に過ぎません。
本当に実在的な何かに情報が書き込まれているのかは、
永遠に分かりません。
でも場の理論には双対性というものがあり、
見かけが全く異なる場の量子論が、実は同じものだったりすることが分かっています。
理論物理学分野で広く研究が続いているAdS/CFT対応という理論は、面白い性質を持っています。
時空の理論であるAdS量子重力理論が、重力を全く含まない、
そして空間次元も1つ小さな物質場の理論(CFT)に等価だという話です。
例えば、空間次元が1つ高い曲がった時空に住んで、その宇宙の空間的な広がりを感じている人間も、実は次元が1つ低い平らな空間の別な場の理論の中の存在であって、その意識が空間の広がりを量子情報からイメージしているだけと言っても、それは原理的に区別ができないのです。
また実際の実験で使う電磁場だって、エネルギー的な観点から本当に実在かと言われると怪しいのです。
電磁場のエネルギー密度は任意の時空点において、
観測者に依存せず、客観的に存在しているように見えますが、
それも実は観方次第です。
超弦理論のように高次元空間のコンパクト化で考えると、
電磁場だって元は高次元重力場の一つの成分に過ぎません。
そして重力場のエネルギー密度はテンソルの成分ではないことは昔から分かってます。
ある点を中心とした近傍で座標変換すると、
その点での重力場のエネルギー密度は常に零にさえできます。
重力場のエネルギー密度が座標変換で零にできるという性質は、
一般相対論の指導原理である「等価原理」からの直接の帰結
でもあります。
ある点近傍で自由落下を表す局所慣性座標系をとると、
そこの重力は消えるのです。だからその場合には、
その重力場のエネルギー密度もその点では零であるべきなのです。
電磁場を含む高次元重力場のエネルギー密度は
座標系や観測者に依存する概念です。
ただエネルギー密度を空間積分した全エネルギーは、
漸近的対称性(ポアンカレ群や反ドジッター群)の座標変換で
ベクトルとして振る舞うことは分かってます。
つまりエネルギー総量だけは、物理学的な意味があるのです。
重力場の空間的なエネルギー総量にだけは意味があるのですが、
この総量は興味深いことに、空間無限遠方の境界領域だけで評価できる
のです。
エネルギー密度がある量の空間微分で書けるためです。
局所的な密度には意味がなく、
無限遠方の境界だけで評価されるその総量だけに意味がある重力場のエネルギーは、最近議論されるホログラフィ原理と非常に整合しています。
空間無限遠方の境界に全ての情報が存在しているというその描像とマッチしているのです。
「情報は情報のみで存在し得るのか?」
「量子力学が情報を扱う理論であるなら、実在を表す本当の理論を。」
と思う人は、もう一度より深く現代物理学における「実在」を
批判的に考え直して頂ければと思います。
「世界は量子情報でできている」という事実が
きっと腹の底から理解できてくることでしょう。
ホログラフィ原理については以下の書籍がオススメです。
専門書としては以下の書籍がオススメです。
pdf資料は以下がオススメですが、超本格的な資料なので、
研究者の方向けの内容です。
https://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~tadashi.takayanagi/Nambu.pdf
☆再現性については以下の著作がオススメです。
物理学などのような低物理レイヤーの「科学」は
「再現性」を確認しやすいですが、
心理学・社会学などのような高物理レイヤーの「科学」は
「再現性」がほぼ確認されず「科学ではなくフィクション」
の可能性がありえる、という趣旨の書籍です。
また、「再現性」については、確率統計・推定統計学において
標本数・サンプリング数・データ数などなど
とにかく「数」が必要になりますが、高物理レイヤーの「科学」においては
「数」を揃えるためには(実験環境を一律に揃えなければ、データとしての意味がなくなってしまうので)、非常に高額な研究費を必要としますが、現代の経済主義社会においては、実績が伴わない場合、研究費を得ることが難しく、結果として「統計学的な再現性のある実験」を行うことが、そもそも不可能という「科学 vs 経済性」のジレンマが存在する、という背景です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
