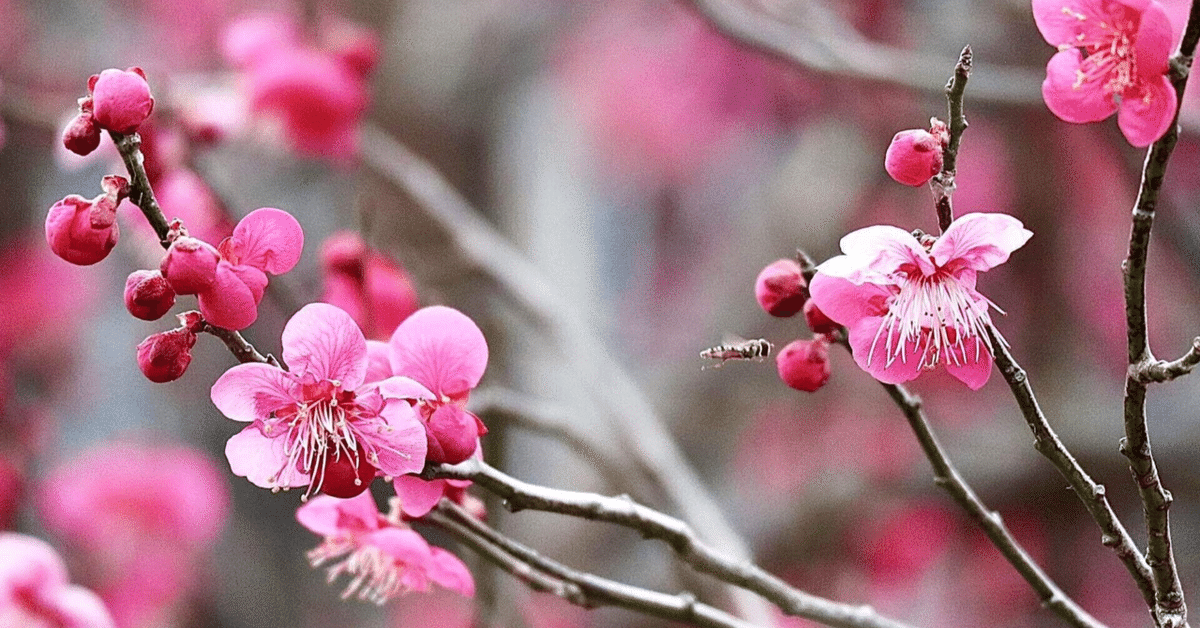
嵯峨野の月#5 讃岐から来た少年
第一章・菜摘
第五話、讃岐から来た少年
昔、ある少年が故郷から都へと旅立った。
少年が一族の中でずば抜けて学問に秀で、都に居る叔父にその才を見出されたからである。
この子の才は故郷で朽ちさせる訳にはいかない、是非都に上って大学寮に行かせるべきだ。
ゆくゆくは官吏か博士になり、朝廷にお仕えするのだ。
それが、一族の為になるのだから。と叔父は主張し、故郷に迎えの者を寄越した。
「しっかり学んで、多くの人を助ける人に成って下さいね」
という母の見送りの言葉を涙ぐんで受け止める少年に、迎えの者は、
もうすぐ十五になられる大人なのに、この少年は大丈夫なのだろうか?
という印象を受けたのだという。
少年の名は、佐伯真魚といった。
父親は四国讃岐の国(香川県)で郡司を務める地方豪族、佐伯善通。
母は阿刀氏の娘で玉依といい、弟に学者、阿刀大足がいる。都にいる大足に真魚の書写を文に添えて送ったのもこの母であった。
大足は、真魚の書写を一目見るなり脳天に雷を喰らう程の衝撃を受けたのだという。
…十一の子供が、王羲之の書をほぼ完璧に写せるなんて!
これは自分以上、いや、育て方次第ではどの博士たちよりも優れた学者になるに違いない!と思って、
真魚が十五になったら迎えの使者を寄越します。地方豪族の子が中央に出て出世するまたとない機会です。
と姉玉依に返事の文を書いた。
延暦七年(788年)、平城京は春。
中央佐伯氏の氏寺、佐伯院で大足は「貴物」と呼ばれる甥の到着を楽しみにしていた。
さてさて、どのような利発な少年か…とほくほくして待っていると、やがて、
「甥御さまのご到着です」
と使用人が報告に来ると大足は早足で自ら入口まで出迎えた。
さて、「貴物」の第一印象は…
この子本当に我が甥なのか?
と思うほど十五の少年にしては小柄で、顔を見ても自分の目線から逃げるような、頼りない少年だった。
辺りでは梅の花が咲きほこり、ほうほけきょ、と鶯が鳴いた。
「…まあ、長旅ご苦労だったな。中に入って、体を洗って休むのだ」
と言って真魚を使用人に任せて中に入れると
早速、真魚を迎えに行って帰って来た使用人に「甥は旅の途中どんな様子だった?」と声をひそめて聞いた。
それが…と使用人が言いいにくそうにするのを無理に言わせると、
「途中までずっと泣いておいででした。お母上との別れが相当哀しかったようで」
どうやら甥は貴物と呼ばれて甘やかされて育てられてきたのではないか?
と話を聞いて大足は急に心配になった。これでは大学寮受験以前の問題ではないか!
「しかし、讃岐を抜けて船に乗られた時には落ち着いたご様子で。お父上が海運豪族だから、船には慣れておられますね。
目に見える小島や風景にいちいち、あれはなんという地名なのだ?
と我にも答えられぬ質問を次々ぶつけ、答えられぬと周りの旅人を捕まえて質問攻めにする始末で…ほとほと困りましたよ」
と疲れた顔で笑って答えた使用人を下がらせると大足は、知的好奇心が貪欲なのだな。
と少しは安堵して、用意された部屋で赤子のように丸まって眠る真魚を覗き見た。
翌朝早く目覚めた真魚は顔を洗って朝餉を済ませ、叔父が与えてくれた新しい衣に袖を通して整えた髪の上に烏帽子をちょこん、と載せた。
「ここにある書は全部目を通していい」
と叔父に連れられて通された部屋の棚には、巻物が数十本ほど積まれていた。
ああ…新しい墨の匂いだ!叔父の制止の声を横に真魚は走り出して巻物を一本取り、漢文の文章をがつがつと読んだ。
「有難し…叔父上!故郷では古ぼけた書を繰り返し読むだけで飽いておりました」
「そうだろうな」
と大足は初めて真魚が嬉しそうな顔を見せたので、それだけでこの子を都に来させた甲斐があったと思った。
「ここに慣れたら少しずつ明経科の書を持って来させる。入試は厳しいから覚悟するんだな」
大学寮とは現代でいうと官僚養成校で、大足が薦める明経科では主に儒教を教える。
「しばらくは退屈はせぬだろう、その書の多さではな」
とにやりと笑って言い置き、それから十日後、大足が新都長岡京から戻って真魚の様子を見に寺に来ると…
真魚の顔から表情というものが消えていた。明らかに物事に倦んだという様子で書を読んでいる。
一体何があったのだ?
「叔父上、新しき書は?もう退屈で退屈で…」
「しかし書はこんなにあるではないか」
「もう全部目を通してしまいました」
地方の秀才が都の凡才に陥りがちな慢心だな、と大足は思って注意した。
「読んだだけでは駄目だ。暗記しないと試験には答えられないぞ」
「もう暗記してしまいました」
「なんだと!?」
確認のために大足が巻物の題だけ言って、真魚には内容を暗唱させた。
全て…全ての巻物の内容を一字一句間違えも淀みも無くすらすらと暗唱してのけた真魚に、
この子は…!!と空恐ろしいものを大足は感じたという。
姉玉依が「貴物」と呼ぶ理由が、やっと大足には解ったのだ。
「本日は書は携えておらぬよ…お前がこの量の巻物を読破してしまうなんて思わないからな」
実はな、真魚。と大足が長岡京に建てさせている自分の家が完成し次第、真魚もこの寺から移り、本格的な受験勉強に入ること。
ここにある書も貴重なものが多く、少しずつ新都に移す予定を告げた。
話し終わると真魚は結構がっかりして肩を落としていた。
「ああ叔父上…それはもうここに書を持ってくる気はない、という意味ですね?」
「そうなのだ、申し訳ないが遷都から四年、全てのものが長岡京に移っていくのだ…」
仕方のない事なのだ。そんなに気を落とすな、と大足は真魚に声を掛けて
「人間学問ばかりで体がなまってもいけない。
都見物をして気を晴らすといい。今度来るときは必ず書を持ってくるから」
と慰めた。
但し、従者は必ずつけるのだ。平城京は物騒になってきているからね、と注意して大足は寺を後にした。
大足自身、職場である大学寮の新築に関わっているし、自宅の完成も急がせなくてはならない。
学者として帝の話し相手をしたり、担当している貴族や親王様がたの教育など長岡京での用事に忙殺され、甥っ子一人に構っている余裕が無かったのも事実である。
さらに十日後、今度は明経科の教書を二本携えて来た大足は、真魚の頬や目元に痣が付いているのを見つけた。
「何があったのだ!?」と問いただすと、
「市場で僧侶に殴られ、蹴られました」
と瞳に冷たい怒りを宿して真魚は答えた。
「詳しく聞かせてもらえまいか?」
四日前のことである、真魚が市場の或る店で見た光景とは…
「市場の食糧を売っている辺りで酒と干し肉を金を払わず強奪する二人組がいて、さらに、慰み者にするために店の娘を連れ去ろうとしたのです」
さすがに見て見ぬふりはまずい!と思って真魚は二人組に注意すると、逆に、
「我らは何をしても許される身だ。生意気ながきだな!」
とへらへら笑うその二人組に袋叩きにされたのだという。
従者が間に入って財布の金を全部渡すと二人組は帰って行った。
「娘さんの身は助かりましたが…店主から訳を聞くと、その二人は変装した東大寺の僧だというのです!
定期的に市場に来てはやりたい放題をするというではありませんか、
叔父上、私は僧侶が飲酒、肉食、果ては女犯をやらかそうという横暴をこの目で見てしまいました。
…東大寺の僧は、一体どうなっているんですか!?
国家鎮護の祈りために僧とは、仏教とはあるものなのではないんですか!?」
と話しながら内にどんどん怒りを燃やしていく甥に大足は、
ああ、この地で一番見て欲しくないものを真魚に見せてしまった…
と恥ずかしい思いになり、同時に、よし!と肚を決めた。
「まさに、お前を打ち据えた者たちが中央仏教の正体なのだよ。
仏教伝来から二百年、仏の尊い教えも扱う者が腐ると、教えも腐るのだ。
権力におもねる僧侶たちを今上帝は厭い、寺だけをこの平城京に留め置かれて長岡に都を移された。
政と仏教に距離を置き、全てを刷新する。それが現朝廷の方針だ。
実に果敢な決断であるよ…真魚、お前も勉学に励み新しき都づくりをお助けするのだよ」
じっと叔父の話を聞いていた真魚は「はい!」と背筋を伸ばし、叔父が大学寮の博士に無理を言って借りて来た巻物を手に取って広げると、
「うわあ、難しい!…でも、実に興味深い」と経書の文に目を凝らした。
「おいおい、原本だけでは読解は難しいよ」と大足は笑って注釈が書かれた巻物を経書の上に広げた。
やはり、この子は学問をしているが一番いいのだ。
長岡京に引っ越して大学寮に入れば、忌まわしきことも忘れてくれるだろう…
翌年、真魚は叔父に連れられ長岡京に引っ越し、新築された叔父の家で受験に向けて猛勉強を始めた。
論語、孝経、史伝、文章など、実に膨大な量の文をわずか三年足らずで暗記する、という非常に厳しい受験勉強であるが、
真魚はまるで砂が水を吸うように楽しんで学習した。
学問で頭が疲れると、真魚は気晴らしに外出をよくした。
街では建築中の住居が真新しい柱をさらして軒並み連なっている。
こんこん、と木工座(大工集団の祖)の者たちがたてる槌音が実に小気味良く、時を忘れて建築現場を眺めているのが真魚の楽しみとなった。
「そんなに木工が好きなら大学寮入るの辞めてこっちに来ないか?学者の若さま」
「私は新しき建物が出来上がっていく過程が好きなのです。木の匂いもいいですね」
と会話をし、真魚も木工を習うほど職人たちと仲良くなった。
「前の都よりこっち(長岡)の方が便利はいいね。でっかい河が三本も流れているから、筏で木材を運びやすいんだ」
三本の河とは、桂川、宇治川、淀川のことである。
平城京ではすべて陸路で荷を運ぶしかなかった不便さを、三本の河は一気に解決した。
長岡京ではほぼ全ての家庭に井戸が掘られ、道路脇の流れる水を家の中に引き込み、排泄物を流すという下水対策も行われていた。
「へえ、お上は街の細かい所まで考えられているんですね」
と真魚がいたく感心して若い職人の話を聞いていると、
「そうさ!この素晴らしき都で仕事が出来るのは誇りなのだ」と木工座の男たちは胸を張って言った。
平城京から移り住んだ人間にとっては長岡京はまさに住みやすい理想の都で、延暦八年(789年)のこの時期は、新都建設のために庶民はいくらでも仕事にありつけた、
はずであった。
翌年、天然痘が大発生するまでは。
延暦九年の秋から冬にかけて(790年8月~791年1月)、当時「わんずかさ」と呼ばれる天然痘が長岡京の畿内で発生した。
随分蒸し暑い日の午後であった。
叔父、大足から外出を止められていたが、真魚はいてもたったもいられず仲良の良かった職人が働いているという河原まで行った。
わんずかさで下々の者には死者が続出し、骸の処理に都中の人足が回されているという噂を聞いた。
なんでも骸の処理法も、河原に棄てて犬に喰わせるだけ、という杜撰なものらしい…
やはり、河原を見下ろせる所まで行くと、見覚えのある職人の後ろ姿があった。
職人はふらつく足取りで荷車に乗せられた骸を河原に積んでいる。
猛暑の頃だったので、腐った骸の臭気が凄まじく、吐きそうな位であった。
「来るんじゃない!」
二十歳を過ぎたばかりの職人は、真魚の姿を見つけるなり、厳しい声で叫んだ。
「わんずかさにかかるぞ!身分の高い人が来るところではない」
「あなたの木工座はどうなったのです!?」
真魚の問いに職人はもう泣く気力も無い、という風に背を丸め、
「ほとんどわんずかさで死んだ…女房子供もだ。
お役人は骸に触れる事を恐れ、俺たちに処理を押しつける始末だ。
死人ばかりで都の建築どころではない。真魚どの、やはりタタリというのは恐ろしいな…」
タタリというのは、四年前、長岡遷都翌年に死んだ早良親王の祟りの事を言うのであろう。
長岡京の建設責任者を任されていた藤原種継が暗殺され、
その首謀者として今上帝の弟で皇太子の早良親王が廃太子となり、流刑地に向かう途中の寺の中で死んだ。
無実を証明するために一切の食を絶ち、憤死という凄まじい死にざまだったという。
それ以来、忌みごとが起こるたびに都では、親王様のタタリだ、と片付けてしまうのが当たり前になってしまっている。
「…いいえ、疫病はタタリではありません!わんずかさにかかる原因は、病者の肌のふくれ(膿胞)から出る汁に触れるからです。
おそらく汁の中に、小さく強い毒が含まれているのでしょう。骸を河原に棄てては河が毒で汚れてますます病者が増えます。
犬が骸を食うた牙に毒が付き、何処かで人を噛み、そこから病が広まるでしょう」
天然痘の原因であるウイルスの存在も知られていないこの時代に、真魚はあらゆる病の元であるウイルスや細菌を「小さな毒」として自分なりに認識していたのだ。
真魚の話を聞いて、職人ははっとして顔を上げた。
「じつは…俺もそうではないか?と骸の処理を続けて思っていたのだ。なあ真魚どの、適切な骸の処理法は?」
「穴を深く掘って埋めるか、火で焼いてしまう事です。処理に当たった者はいちいち体を洗って衣も変えなければ。
あなたもこの河原から出て、湯で体を洗うべきです!速く!」
と真魚が叫ぶと職人は笑って首を振り…自分の肩に出来た膿胞を見せた。
そんな…!!
「俺も病にかかった…真魚どの、すぐにここから離れろ。
そしてその賢すぎる頭で俺みたいな病者やこの骸の山を減らす方法を考えてくれ、頼む!」
早く行けえっ!と声を振り絞る若者の叫びを背にして、真魚は泣きながら走り出した。
お上が民にさせる事は…なにもかもあべこべじゃないか!
木工職人の若者も十日後に天然痘で死に、河原に棄てられる運命となる。
後記、
少年時代の空海、真魚を「記憶力がいいだけの気弱な少年」に設定にしたのは、
膨らみ過ぎた虚像を取り払う為です。
