
#こども基本法 17日目 第十五条 こども基本法と子どもの権利条約の周知
こんばんは、勝手にこども基本法リレーも17日目を迎えました。
リレーで17人もつづくのって聞いたことないですが、私の母校(中高)の体育祭では、走る距離が50m. 100m、200mと伸びていって400mになっていくリレー(名前忘れた)や、「足の歴史」という名のリレー競技がありました。「足の歴史」は3人4脚、2人3脚、2人2脚となり、最後1人1脚(ゴムバンドで両足を縛って飛んで進む)というもので「あしれき」と呼ばれていました。ちなみに私は障害物リレーに出ていて、こちらは8S(ハチエス)と呼ばれていました。と振り返ってみるといろんなリレーがあった体育祭だったことに今さらながら気づき、リレーとのご縁を感じます(なんのこっちゃ)。
さて本題です。十五条は以下です。
こども基本法
(この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知)
第十五条
国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。
まずこの条文に、こども基本法だけでなく「児童の権利に関する条約の趣旨及び内容」も周知を図る対象になっていることが、大きな意味があります。実は、子どもの権利条約を批准した時点で、国はその周知の義務が発生していたのですが、必ずしも「積極的」とは言い難い状況が続いています。実際、子どもの権利条約を「聞いたことがない」子どもは3割、大人は4割という調査結果もあります。この調査結果をみると「広報の義務を果たしている」とはなかなかいいづらいですね。

3万人アンケートから見る 子どもの権利に関する意識(2019年)
(画像をクリックすると元ファイルにとびます)
そんな中!
こども基本法については、どうなのか?というと、こども基本法については以下のウェブサイトでこども家庭庁が発信をしています。パンフレットや動画が、ふつう版とやさしい版と2種類づつ用意されています。

やさしい版の動画は「ボクはこども基本法!」っと擬人化されたキャラが出てきます!
他のこどもに関する法律について、このように「やさしい版」が作られたケースがあったのかわからないのですが「こどもにわかるように伝えたい」という意図がくみとれる動画になっています。
そして最後は
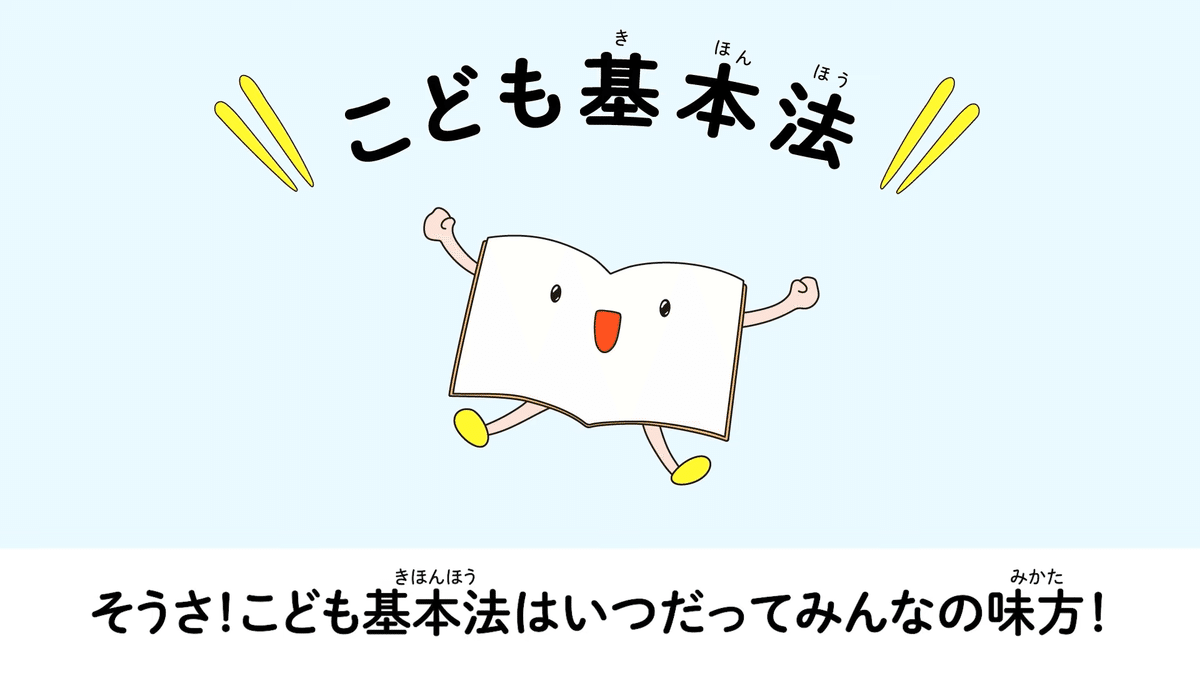
という画面も出てきます。
「こども基本法がみんなの味方」に本当になれるように、ここに書いてある内容を実現していってもらいたいですね!まだまだ試行されて17日しかたっていないこども基本法。法律って時間がたつと成長したり熟したりするものではないのかもしれませんが、一緒に育っていきたい、そんな気もしてきますね!
一報、子どもの権利条約(政府は児童の権利に関する条約 という名称を使ってよんでいます)の広報はどうかな????と「児童の権利条約 政府広報」と検索してみると・・
外務省ウェブサイト:
以下は全文がのっているウェブサイトだったり

外務省の人権外交のページだったり

文部科学省のウェブサイトも以下のような感じ

なんというか「こどもに伝えよう」という気概を一ミリも感じないウェブサイトしか出てこないですね。また、文部科学省のウェブサイトには当時批准した際の「通達」が出ています。意見表明についても書かれているのですが何と書いてあるかというと。。
4.本条約第12条から第16条までの規定において,意見を表明する権利,表現の自由についての権利等の権利について定められているが,もとより学校においては,その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒等に対し,指導や指示を行い,また校則を定めることができるものであること。
校則は,児童生徒等が健全な学校生活を営みよりよく成長発達していくための一定のきまりであり,これは学校の責任と判断において決定されるべきものであること。
なお,校則は,日々の教育指導に関わるものであり,児童生徒等の実態,保護者の考え方,地域の実情等を踏まえ,より適切なものとなるよう引き続き配慮すること。
「校則は学校が決めるものなので子どもの意見は聴かなくていい」みたいに読めてしまうこの通達。。こども基本法が施行された今、こども基本法の施行にあたっての通達も、出してほしいですね。こども基本法の基本理念を学校現場でも実践してください、と文部科学省から呼びかけてほしいです。
政府が主体となった子どもむけの子どもの権利条約の広報ツールがすぐ出てこず希望を失いそうになったところで、法務省も子どもの人権SOSミニレターなどの取組をしていることを知っていた私は、法務省のウェブサイトを見に行ってみました。ありました!


ちょっと探しただけなので、もっとよく探せばもっといろいろ出てくるのかもしれません。ただ、こども基本法の広報の力の入れようと比較してしまうと、子どもの権利条約のほうがずっと前から批准されているのに、「伝えよう」という意志が感じられず、ちょっと悲しくなってしまいますが、今後こども家庭庁でも子どもの権利条約に関する周知を行っていってくれるのかどうか含め、こちらも見守っていきたいと思います。
今日は #こども基本法 17日目 第十五条 こども基本法と子どもの権利条約の周知についてのお話でした。
読んでいただきありがとうございます!
以下にあるnoteの♡マークはnoteに来たのはじめての方、登録するなどは面倒!という方でも、ポチッと押すことができます。読んでよかった記事に、♡を押していただけると嬉しいです。(2023年4月1日~4月22日まで毎日更新予定です
