
サウンドマーケティング入門①~聴覚の特性について~
今回から3回にわたって、サウンドマーケティングの世界について紹介していこうと思います。
3話の構成としては以下の予定。
①聴覚の特性について (今回)
②音を利用したブランド戦略 (次回)
③サウンドスケープの重要性 (次々回)
今回のブログを書くにあたって、主に参考にさせて頂くのはこの本。
なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるのか ~サウンド・マーケティング戦略~
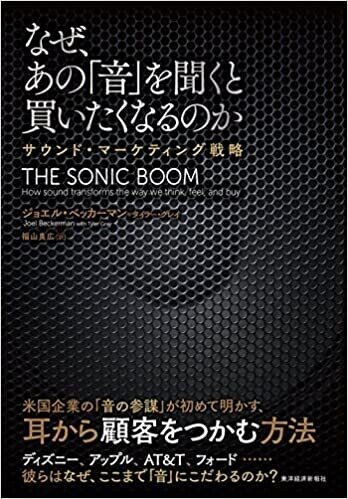
英語版のタイトルは THE SONIC BOOM
反射的にこんな画像が脳内に投影された人は、おそらく同世代ですね。(ちなみに私は1976年生まれです。)
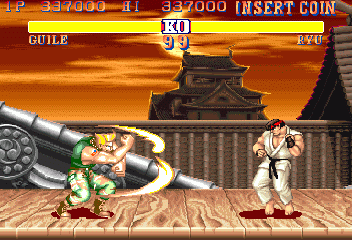
ご存知、カプコンの対戦格闘ゲームの名作「ストリートファイター」のキャラクター アメリカ空軍少佐ガイルの必殺技「ソニックブーム!」
← タメ → +P のコマンド入力に慣れるまで苦戦した記憶、やり込み過ぎて手に「ストⅡダコ」をつくっていた悪友の顔が、背景の日本ステージで流れる「リュウのテーマ」と共に蘇る人も多いのではないでしょうか?
(ご存知でない方、本当にすみません<m(__)m> 話を戻しますが、実はこれは「音楽は記憶と結びついて、何らかの感情を誘発するトリガーに成り得る」という話の布石でもあるのです。)
さて、「ソニックブーム」のそもそもの意味は『音速以上で飛行するジェット機などの衝撃波によって生ずる爆発音』by デジタル大辞泉 ですが、
本書のタイトル “THE SONIC BOOM”は、「音で感情を揺さぶる”ブームモーメント”をいかに誘発するか」というニュアンスで使われており、英語原題 には次の副題が添えられています。
How sound transforms the way we think, feel, and buy
直訳すると「音は如何にして私たちの思考、感覚、購買を変形させるか」、意訳すれば、日本語のタイトル『なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるのか』につながります。
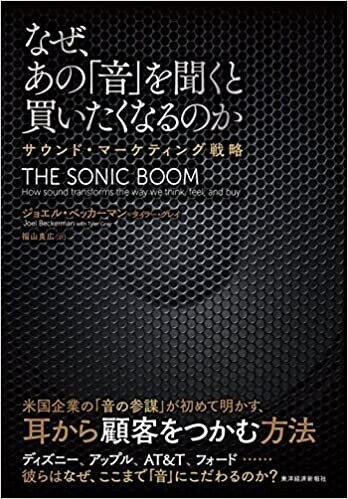
さて、ここから本題に入ります。
本書は、「音」を使ったマーケティング戦略 「サウンド・マーケティング」の世界を紹介した本です。
私は昼はジャズピアノの音楽講師、夜は銀座のラウンジピアニストを生業とする職業的音楽家ではありますが、本書を読んだ素直感想は次の通り。
まずは自分自身に対して、「音や音楽の秘める可能性について、あまりにも不勉強だった!」という反省。
同時に世間一般に対して、「音・音楽はマーケティングツールとして現状では存分に活用されているとは言い難く、まだまだ無限の可能性が残されている」という希望。
これから、本書から私が得た知見を、※他のサウンドマーケティング系の本も援用しつつ、皆さまにできるだけ分かりやすくシェアしてみようと思います。(※「サウンドパワー」、「心を動かす音の心理学」、「ドビュッシーはワインを美味にするか ~音楽の心理学」など)
「聴覚」についての脳科学的ファクト
今日はこれについてお話します。
人間には五感(視覚・聴覚・味覚・臭覚・触覚)がありますが、実はそれぞれの刺激に対して脳が反応するまでの速度は異なります。
この中で、人間の脳は音刺激に対して最も早く反応します。
具体的な刺激から反応までの速度は次の通り。
聴覚 0.146秒
触覚 0.149秒
視覚 0.189秒
味覚 0.5秒
嗅覚 0.5秒
ここで重要なのは人体のメカニズムとして、本能的に一番早く反応するのは「音」であるというファクトです。
また反応速度だけでなく、情報処理能力の面からも、聴覚は視覚を遥かに上回ります。
視覚の情報処理能力・・・1秒間に25コマ程度(一般的なアニメーションが1秒間に24コマでつくられるのもこれが理由)に対して、
聴覚の情報処理能力は・・・1秒間に200コマ
我々の「聴覚」が如何に優れ、我々が無意識にどれだけ「聴覚」に依存しているか、だんだん伝わってきたでしょうか?
この「聴覚」の特質を上手く活用している芸術が「映画」です。
有名な所ではヒッチコック映画「サイコ」のシャワーシーン。

映画を観た方であれば、バーナード・ハーマンが作曲した不気味な不協和音を連想するでしょう。
ここでお時間がある方は、ぜひ実験してみて欲しいのですが、上の動画の50秒あたりから「音声ミュート」の状態で観て欲しいのです。
たぶん・・・
あんまり怖くないと思います。
さらに、この映像をバックに別のノリノリの曲をアテレコしてみてください。
むしろ、笑えるかもしれません。
実は、人間の感情は五感の中では「聴覚」による影響を最も受け、視覚と聴覚が矛盾した情報を受け取る時、脳は「聴覚」を優先する事が多いです。
脳神経科学の世界ではこんな仮説もあるそうです。
「人間を本当にびっくりさせるのは 1)音を聞いたり 2)何かに接触したり 3)バランスを失ったとき の3つに限られる」
この3つに「視覚情報」は含まれず、本能的な観点で言えば視覚は副次的なものに過ぎないという事ですね。
映画音楽作曲家のハンス・ジマーもこんなニュアンスの事を言っています。
「ホラー映画の怖いシーンで目をふさぐ人がいるだろ。でも、あれは間違ってる。本当は耳をふさぐべきだ。」

映画音楽の巨匠 ハンス・ジマー (パイレーツ・オブ・カリビアンのテーマなどで有名。映画音楽におけるサウンドの役割を知り尽くし巧妙に使いこなす音の魔術師)
映画音楽の話の流れから、音や音楽の重要な特性についてお話します。
それは「音や音楽は記憶や感情と強く結びつきやすい」という特性であり、これは「音や音楽による刷り込みが可能」である事を示唆しています。
それゆえ、「特定の音や音楽をトリガーにして、聴き手に意図通りの記憶や感情を誘発させる」というのもできない話ではありません。
たとえば、次の音楽を想い浮かべてください。
ロッキーのテーマ
・・・体の奥底からファイティングスピリッツが湧いてきませんか?
My heart will go on
・・・タイタニック号の舳先で、両手を広げたケイト・ウィンスレットを抱えるレオナルド・ディカプリオのビジュアルが浮かびませんか?
音楽にはこうした力が備わっており、音楽のこのような特性を利用すれば、素晴らしい顧客体験の創造や、効果的なブランド戦略に活用することもできます。
この話の続きは次回ブログ「サウンドマーケティング入門②~音を利用したブランド戦略」であらためて。
最後まで読んで頂きありがとうございます。次回もお楽しみに!(^^)!
eラーニング+リアルレッスンで効率良く学べる音楽教室
代表 岩倉 康浩
