
ルソー『エミール』解説(5)
はじめに
新刊『NHK100分de名著 苫野一徳特別授業 ルソー「社会契約論」』出版記念として、前回に引き続き、ルソー『エミール』の解説第4弾をお届けします。
苫野一徳オンラインゼミで、多くの哲学や教育学などの名著解説をしていますが、そこから抜粋したものです。
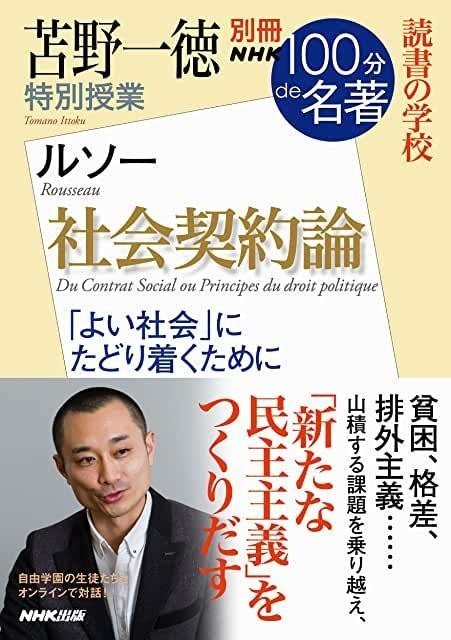
成人したエミールは、恋をして、結婚をして、そして父になります。
結婚を機に、ルソーとエミールの関係はここで一区切り。
本書後半で、ルソーはエミールに次のように伝えます。
「これで、わたしの長いあいだの仕事は終わって、別の人の仕事がはじまる。わたしはきょう、あなたがわたしにあたえていた権威を捨てる。」
本書前半では、エミールの恋人となるソフィーについてが語られます。
ソフィーを通して、ルソーは女子の教育について論じるのです。
現代のフェミニストが読めば、いくらか女性差別的に見える言葉もないわけではありません。
しかし、今よりずっと女性の地位が低かった当時のことを考えるなら、ルソーの女性観や女子教育の思想は、むしろきわめて先進的なものだったと言えるのではないかと思います。
本書冒頭で、ルソーははっきりとこう言っています。
「共通にもっているものから考えれば、両者は平等なのだ。ちがっている点から考えれば、両者は比較できないものなのだ。」
男女は平等である。ルソーはまずはっきりとそう宣言するのです。
しかし当然、差異もある。女子教育を行う際には、その「自然」な差異をしっかりと理解しておかなければならない。
どこまでも「自然」に従うこと。
これが、やはりルソー教育論のアルファにしてオメガなのです。

1.男女の平等と差異
男と女について、ルソーはまず次のように言います。
「性に関係のないあらゆる点においては、女は男と同じである。同じ器官、同じ必要、同じ能力をもっている。」
では「性」の側面から見れば、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
ルソーは、「お互いに気に入られようとする」点は同じだけれど、その流儀が違っているのだと言います。
自然を観察すれば、男はその強さによって、女はその魅力によって、「お互いに気に入られようとする」のだと。
そして続けます。
「強さ」において、女は確かに男にかなわない。しかし実は、女性こそがその「魅力」によって男を支配しているのだと。
「攻めるほうが勝利を得るためには、攻められるほうがそれを許すか命令するかしなければならない。」
「恋の駆け引き」について、ルソーは次のように言っています。
「自然は、女性には容易に欲望を刺激する能力をあたえ、男性にはそれほど容易に欲望を満足させる力をあたえないで、男性をいやでもおうでも女性の気分に依存させ、男性もまた女性の気に入るようにして、自分を強者にしてくれることを相手が承知してくれるように努力しないわけにはいかなくしているのだ。そこで勝利を得たばあい、男性にとってなによりも快く感じられることは、弱い者が力に負けたのか、それとも相手は意志によってなびいたのか、よくわからないことだ。だから女性がいつもつかう巧妙な手は、自分と相手とのあいだにそういう疑問をいつでも残しておくことなのだ。」
2.女子教育について
以上のような「性」の違いを考えれば、女子教育と男子教育は異なってしかるべきだとルソーは言います。
まず、女子には教育など必要ないという当時の一般的な風潮について、ルソーはこれを明確に否定します。
「あんなに快い、あんなに微妙な才気を女性にあたえている自然は、そんなことを命じてはいない。はんたいに、自然は、考えること、判断すること、愛すること、知ること、顔と同じように精神をみがくこと、そういうことを女性に望んでいる。」
では女子教育はどうあるべきか。
女性を、とりわけ男から「尊敬」される人間になるよう育てなさい。そうルソーは言います。
「女性の教育はすべて男性に関連させて考えられなければならない。男性の気に入り、役に立ち、男性から愛され、尊敬され、男性が幼いときは育て、大きくなれば世話をやき、助言をあたえ、なぐさめ、生活を楽しく快いものにしてやる、こういうことがあらゆる時代における女性の義務であり、女性に子どものときから教えなければならないことだ。」
フェミニズムの観点からすれば、これは捨て置けないセリフのようにも思えます。
ただここでも、時代の時代性をしっかり認識しておきたいと思います。
当時の一般的な男性の考えは、ルソーの言葉を引用すれば、「女性はどんなことについても無知でいるように育てるべきだ、ただ家事のつとめだけをさせておくべきだ」というものでした。
その意味では、女性が男性から尊敬されるよう女の子を教育せよというルソーの言葉には、むしろ女性への敬意が読み取れるようにも思います。
ルソーにとって、当時の男女不平等は許容しがたいものだったのです。
さて、では女子教育は、具体的にはどうあればよいのでしょうか。
まず、女の子は男の子以上に人目を気にするものだとルソーは言います。
「ほとんど生まれたばかりの小さい女の子でも、身を飾るものを好む。かわいらしい子であるだけでは満足しないで、かわいらしい子だと思われたいと思う。ちょっとしたしぐさにも、そういう気持ちがもう女の子の心に宿っていることがわかる。」
しかし、大事なことは装うことではなく自分自身の美しさでありやさしさであることを分からせよ。そうルソーは言います。
「女子の教育はこの点においては完全にまちがっている。人は女の子に褒美として身を飾るものをあたえる約束をし、凝った衣裳を好ませるようなことをしている。女の子が花やかな衣裳をつけると、「なんて美しいんでしょう!」と言う。まったくはんたいに、いろいろとある身の飾りは、欠点を隠すためにあるにすぎないということ、そして、美しいひとのほんとうの勝利はそのひと自身の美しさによって輝かしく見えることだということを、彼女たちにわからせなければなるまい。流行を好むのは悪い趣味だ。」
と言って、修道院で老婆のような生活をさせるのももってのほかだとルソーは言います。
「幼い娘はおばあさんと同じような生活を送るべきではない。いきいきと、快活に、好きなように、遊びたわむれ、歌をうたい、ダンスをし、その年齢にふさわしいけがれのない楽しみを味わいつくさなければならない。」
尊敬される女性になるためには、制度や礼節についての教育も重要です。
ただし、もしそれが、彼女自身の「良心」に反するものであったなら、従うべきは「良心」であることも教えよとルソーは言います。
3.恋の駆け引きについて
女性の恋の駆け引きや技巧についても、ルソーは多くのページを割いて論じています。
ルソー自身の経験がふんだんに反映されていて、なかなか面白いところです(笑)。
まずルソーは、社交界というのは八方美人の世界だが、女性は、その中に誘惑すべき相手を見つけると、彼だけを特別扱いするようになると言います。
しかも、皆の見ている前で特別扱いをして、彼の虚栄心を満足させるのだと。
ただその塩梅は難しいところで、そこが女性の腕の見せ所になっているとルソーは言います。
「気まぐれは、うまく手加減しなければ、相手を失望させるだけだろう。それをたくみに按配することによってこそ、男をひきつけようとする女は、その奴隷となる者をつなぐこのうえなく頑丈な鎖をつくりあげるのだ。」
しかし結局のところ、それは相手ではなく自分を満足させることしか考えていないのだとルソーは言います。
「男はそれぞれ、自分にあたえられたものに満足して、彼女はいつもおれのことを気にしていると思うのだが、じつのところは、彼女は彼女自身のことだけを気にしているのだ。」
ちなみに、このような技巧は、学ばれたものというよりは女が生まれつき持っているものだとルソーは言います。太古の昔から、それこそが女性の生存にとってはきわめて重要なものであっただろうから、と。
続いてルソーは、女性は抽象的な思考や科学には向かないと主張します。
「抽象的、理論的な真理の探求、諸科学の原理、公理の探求、観念を一般化するようなことはすべて、女性の領分にはない。女性が勉強することはすべて実用にむすびついていなければならない。男性の発見した原理を適用することが女性の仕事であり、また、男性を原理の確立に導く観察を行なうのが女性の仕事である。自分の義務に直接関係ないことにおける女性の考察はすべて、男性についての研究か、趣味だけを目的とする楽しい知識にむけられなければならない。」
現代の観点からすれば、これも批判を免れない発言かもしれません。
女子教育について、ルソーは最後に改めて、尊敬される女性を育てなさいと読者に訴えます。
すぐれた文明を持った人びとは、スパルタにせよローマにせよ、皆、女性を尊敬していた。そもそも、「女性に軽蔑されたいと思っている者があろうか。世のなかに一人もいない。」
だから、賢い女性を育てなさい。そしてその際は、ただ賢くなりなさいと言うだけでなく、それがどのように有用であるかを教えなさい。
たとえば、スパルタの賢い女性は、男性を次のようにして支配することもできました。
「愛を敬意によって支える女性は、ちょっと合図をするだけで男性たちを世界のはてへ、戦場へ、光栄の庭へ、死へ、どこへでも彼女の好きなところへ、おもむかせる。」
3.ソフィー
エミールの恋人となるソフィーは、上のようにして育てられた、ごく普通の少女です。
ルソーはソフィーを次のように描写します。
「彼女は、正確な精神というよりも鋭い精神をもち、気立てはやさしいが、むらがないわけではなく、容姿はふつうだが好感をあたえ、顔だちにはしっかりした人間を予告するいつわりのないしるしが見られる。人は彼女に近づくときには無関心でいられるかもしれないが、彼女から離れていくときには感動せずにはいられない。」
「ソフィーは美人ではない。けれども、彼女のそばにいると、男性は美しい女性たちのことを忘れてしまうし、美しい女性たちも自分に不満になってくる。一見したところでは、彼女はきれいだともいえないくらいなのだが、見ているうちにだんだん美しくなってくる。ほかの多くの女性たちが失うところで、彼女は獲得する。そして、獲得されたものはもう失われない。」
「ソフィーは豊かな趣味をもっていて、じょうずに身じまいをする。けれども、ぜいたくな衣裳はきらいだ。彼女の衣裳にはいつも簡素なものに結びついた優雅なものが見られる。彼女ははでなものは好まない、よく似合うものを好んでいる。流行の色はどういう色かということは知らないが、自分をひきたたせてくれる色はじつによく知っている。」
さらに、人の陰口は叩かない、特に同性の悪口は言わない、といった人となりが語られます。
ソフィーの両親は、当時としては驚くほど自由主義的な人で、結婚はソフィーの自由意志によってなされるべきだと彼女に語ります。
ただし、彼女の判断力がまだ十分ではない可能性があるので、その人が本当によい人であるかどうかは自分たちが判断する、と。
「ソフィー、あなたの権利をもちいなさい。自由に、賢明にもちいなさい。あなたにふさわしい夫はあなたが選んだ人でなければならない。わたしたちが選んだ人であってはならない。けれども、あなたはまちがってふさわしい人だと思っているのではないか、それとは知らずに、心に願っていることとは別のことをしているのではないか、それを判断するのはわたしたちなのだ。」
4.結婚について
本書には、ルソーの結婚観や恋愛観も綴られています。
まず、男性はあまり美人な女性とは結婚するなとルソーは言います。
他の男にちょっかいを出されないかと、いつも心配する羽目になるからと(笑)。
エミールとソフィーは、出会ってすぐに恋に落ちました。
でもだからと言って、ソフィーは自分を着飾るようなことはしません。エミールには、自分自身の美しさを理解してもらいたいからです。
一方の恋するエミールにとっても、彼女が何を着ているかなどどうでもいいことです。
ソフィーが他の男に優しくすれば、エミールは人並みに嫉妬します。でも、過度の嫉妬はせずに、自分の人柄でソフィーを振り向かせることに注力します。
自然において、嫉妬は多くの場合「性」に結びつけられているとルソーは言います。
でも、もしも人間が性の相手を奪い合う存在であるとするならば、際限のない戦いが繰り広げられることになるでしょう。
ひるがえって、人間をそのありのままの姿において考えてみると、そのような際限ない戦いが起こらないよう、一夫一妻制が「自然」なことになっているようだとルソーは言います。
「人間をその素朴な原始状態において考えてみると、男性のかぎられた能力をみても、その欲望に節度があることをみても、かれはひとりの女性で満足するように、自然によってきめられている、ということは容易にわかる。」
世界には、確かに一夫多妻の社会もある。しかしそれは、やはり争いの絶えない社会ではないかとルソーは言います。
5.エミール、ソフィーと別れ社会を学ぶ
さて、ルソーはここで、エミールに残酷なことを提案します。
恋に落ちたエミールとソフィーですが、ソフィーはまだ18歳に満たず、エミールは22歳になったばかり。結婚にはまだ早い。
これから一人前の市民になることが求められるエミールは、ヨーロッパを旅して周り、よい国家とは何か、よい市民とは何かについての洞察を得なければならない。
だから、ソフィーと一旦別れなさい。そして一緒に旅に出よう。
断腸の思いで、エミールはルソーに従います。
そして2年間、ヨーロッパを旅して周り、ついにあるべき国家の洞察を得ることになります。
その内容は、『エミール』と同じ1762年に出版された、ルソーの『社会契約論』と全く同じです。
すなわち、社会は「社会契約」に基づいて作られるべきこと。
その契約の内容は、「一般意志」による統治。
詳細は、ぜひ拙著『NHK100分de名著「社会契約論」』をお読みいただけると嬉しいです。
これらのことを十分に学び取ったエミールは、晴れてソフィーの元へ戻ることになります。(ついでに彼は2〜3の外国語も修得しています。)
6.結婚
こうして二人は結婚することになりました。
結婚に際して、ルソーはこんな可愛らしいアドバイスを二人にします。
結婚生活における愛の冷却をふせぐためには、「夫婦になってからも恋人同志でいる」ことが大切だ、と。
そんなことは簡単です、と笑って言うエミールに、ルソーは言います。実はそんなに簡単なことではないのだよ、と。
大事なことは、お互いに何かを強いるのではなく、楽しむことです。
「紐をあまり固く結ぼうとすると、紐は切れる。結婚の絆にも、それにふさわしい力よりも大きな力をあたえようとすると、そういうことが起こる。」
それは性においても同様だとルソーは言います。
「結婚によって心は結ばれても、肉体はしばられはしない。あなたがたはおたがいに忠実でなければならないが、御機嫌をとる必要はない。二人とも相手とは別の者に体を許すことはできないが、どちらも自分の気のむいたときでなければ相手にも体を許すべきではない。」
「だから、エミール、あなたがほんとうに妻の恋人でいるつもりなら、このひとはいつでも、あなたの主人、このひと自身の主人でなければならない。しあわせな恋人であれ。しかし、つつしみぶかい恋人であれ。すべてを愛によって手に入れるがいい。義務の名においてなにかをもとめてはならない。」
なかなか含蓄のある言葉です。
こうしてルソーは、冒頭でも紹介した次の言葉を述べて、エミールとの関係を改めることを宣言します。
「これで、わたしの長いあいだの仕事は終わって、別の人の仕事がはじまる。わたしはきょう、あなたがわたしにあたえていた権威を捨てる。」
数ヶ月後、エミールはルソーの元を訪れこう言います。
「先生、あなたの子を祝福してください。あなたの子はまもなく父親になろうとしているのです。」
本書は次のエミールの言葉で終わります。
「若い教師たちの先生になっていてください。わたしたちに助言をあたえてください。わたしたちを指導してください。わたしたちは素直にあなたのことばに従うでしょう。生きているかぎり、わたしはあなたを必要とするでしょう。いま、わたしの人間にふさわしい役目がはじまるとき、わたしはこれまでのどんなときよりもあなたを必要としている。あなたはあなたの役目を果たした。あなたを見ならわせてください。そして、休息してください。もうその時が来たのです。」
これで、5回にわたってお届けしてきた『エミール』解説も終わりです。
折に触れて読み返したい名著。ぜひ、機会があれば直接手にとってお読みいただけると嬉しく思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
