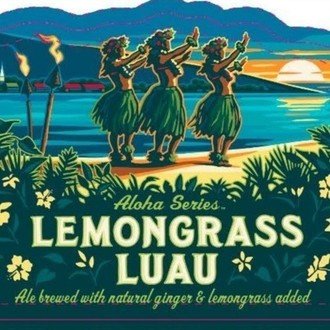あなたの書いたそれは、あなたを映す鏡か、それとも窓か
小説のパイロット版を書いているうちに、これはあまりに凡庸なのではないかと感じて、1週間ほど手付かずになっている。
どこに問題があるのかを注意深く分析してみたら、いちばん大きな原因は僕自身が悪意と悪人を書くことを避けていることにあるのだと気がついた。
周りから見ると、僕は自分の心の内を晒け出さないように見えるらしい。
自覚はないのだが、これまで何人かの友人が同じように言ったのだから、大なり小なりそういうところがあるのだと思う。
弱点だらけ、欠点だらけなのはとうに知られていることだし、そんなものを知られたところで痛くも痒くもない。弱みを見せたくないとか、欠点を知られたくないという感情もない。
心の闇と言うのはいささか大げさにしても、誰しもいくばくかの悪意は持っているものだ。悪意が剥き出しで露出したり、行動に直結してしまうのは問題だけれど、ほとんどの人たちは心の悪意を外に出すことはない。漏れ出るにしても社会生活に支障をきたさない程度に抑えるようにするものだ(得てしてその自己判断が社会とズレていて、人間関係をややこしくしたりするわけだが)。
そう思っているだけに、僕が無意識に悪意や悪人を描くのを避けようとしているのだとしたら、僕は誰に何を隠そうとしているんだろうか、と考えてしまうのだ。
「鏡と窓(Mirrors and Windows)」は、かつてMoMAで開催された写真展のタイトルだ。
エドワード・スタイケンの後を継いでMoMAの写真部長に就いたジョン・シャーカフスキーが企画した写真展として知られている。
趣味で写真をやってる人はともかく、大抵の写真家ならば知っていてもなんら不思議ではない、いわば「常識」である(とはいえ、昨今はロラン・バルトもソンタグも知らない「写真家」が結構いるそうだから、「鏡と窓」も知らない人が多いのかもしれない)。
シャーカフスキーは、写真は「己の内面を映す鏡としての写真」と「社会(外界)をより深く知るために覗く窓」のどちらかに分類されるしかないと考え —— 実際には「鏡と窓」に分類することなどできないということを明示するべく —— 当時(1960年代)のアメリカの写真家を「鏡派」と「窓派」に分類して展示を行った(シャーカフスキーの序文を誰かが訳したもののコピーを持っていたのだが家の中で行方不明で、正確にどう書かれていたのかははっきりしない)。
雇った可愛いモデルさんにポーズを付け、ポートレイトと称した写真を撮って悦に入っている人がいれば、その人の写真からは容易に趣味嗜好が読み取れる。
街中でのスナップショットがメインの人であれば、その人が街を歩いているときに何に目を向けるのかが一目瞭然だ。歩く人の足首かもしれないし、道端に落ちているゴミかもしれない。
整った綺麗な風景の写真ばかりだとしたら、その撮り手は醜い現実社会よりも見栄えの良い方に惹かれる人なのだとわかる。
誰が何を撮るにせよ、写真にはその人自身が否応なく現れてしまう。
写真を撮る、写真を見せるということは自分が丸出しになるわけで(隠そうとすれば、隠そうとしていることが丸出しになる)、それなりの覚悟がいる(アマチュアの写真家の場合はこうした意識が良くも悪くも希薄なので、余計に丸出しになる)。
小説を書くにあたって、悪意や悪人を書けないというのは、写真における「鏡と窓」と同じなのではないか。手が止まってしばらくして、そんな考えが頭に浮かんだ。
僕の中に悪意がないわけがない。内側の悪意は小説を書けば間違いなく露見する。
小説がどれだけフィクションであっても、どれだけ類型的な悪意を選んで書いたとしても、選択したという一時だけでも僕の中に巣食う悪意は形を持つようになる。
僕はそれを恐れているのではないか。
隠すための最善の方法は書かないことだ。最良にして最も確実な唯一の方法は書かないことなのだ。
もちろん書かずにいられるわけがない。
眠るな、食うなと言われているのと同じだ。書きたいことがあるから書くのではない。書かずには自分を保てないから書いているのだ。
となれば、残る道はただ一つ。悪意であれ本性であれ、見破られるのを承知で書いてしまうしかない。
やっぱり「表現」と呼ばれるものはどれも同じだ。覚悟するしかない。
いいなと思ったら応援しよう!