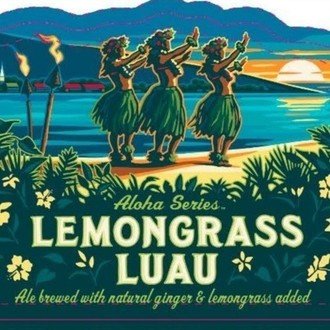断片小説集 7
駅のホームにある狭い待合室が僕の読書席だ。
学校の帰り、賑やかに喋りながら下校する同級生たちが電車に乗り込んで行くのを見送りながら、僕は毎日、日が暮れるまで小説を読む。規則正しい毎日の習慣だ。
誰かから話しかけられることもなく(最初は同級生たちがうるさかったけれど、じきに誰も喋りかけなくなった)、夏には冷房が、冬には暖房がちゃんと入る。ベンチの座り心地は良いとは言えないけれど、贅沢を言えばきりがない。定期券で出入り自由で、冷暖房完備で、集中して小説が読めるのだから、鉄道会社には申し訳ないほどだ。
「何を読んでいるの?」
僕の学校は男子校なのだから、女の子から声をかけられるはずがない。
声がした方に同じ駅を使う私立の女子高の制服を着た女の子が立っていた。
「君、毎日ここで本読んでるでしょ? 毎日、何を読んでるんだろうなって思っていたのよ」
彼女はそう言いながら僕の前に立った。
僕は上目でチラチラと見ながらも平静を装って、本を彼女に見せた。アーウィン・ショーの短編集だった。
「兄のものだったんだけど、何度も読んで気に入っていて、それでもらった。だから今は僕の本です」
彼女は手にとって、適当に開いたページをゆっくりと読み始めた。普通はパラパラとページをめくるだけなのにと僕は思った。
ブレザーの制服のフラワーホールには校章と3年生を表す学年章がついていた。この人もたくさん読んでいるのかもしれない。
「ねえ、私の本と交換しない?」
彼女はカバンを肩から外して、中から1冊の本を取り出した。
「私の本も、もう何度も読んでいて、帰りは別なものを読みたいと思ってたところなのよ。ね、どう?」
アーウィン・ショーの短編集は古本屋で見つけるたびに買っていて、彼女と交換してもまだ予備がある。それに彼女がどんなものを読むのかに興味があった。
「いいですよ。交換しましょう」
「じゃあ、私の本はこれね」
彼女が差し出したのはレイモンド・カーヴァーの『必要になったら電話をかけて』だった。
「ありがとね。じゃあ、また会ったときに」
やがて電車の到着を知らせるアナウンスが聞こえ、彼女は電車に乗り込んで行った。
以来、毎日、駅で本を読んでいても彼女が姿を見せることはなかった。
同じ学校の生徒に聞こうとしても、名前を知らない。電話をしようにも、電話番号を僕は知らなかった。
短編小説の結末としては上出来だ、と僕は思った。
(「短編小説の幸福な結末」)
* * *
人生は岐路の連続でできあがっている。振り返るほどに長く生きてくれば、誰もが気づくことだ。
「だから人は常に肯定的な選択を続けなければならない」
とあるミュージシャンがそう言っていた。俺がまだ10代の頃、たまたま買った音楽雑誌でそのインタビューを読んだ。
岐路には様々なサイズがある。大きな分岐や小さな分かれ道、突き当たりを右に行くか左に行くかを選ばなければならない丁字路。その都度、俺は肯定的な選択をすることだけに集中してきたと思う。肯定的な選択さえできていれば、少なくとも後悔する度合いは低いに違いないと思っていた。それは間違いだったけれど。
毎夜、眠りに落ちるとき、これまでにしてしまってきた大きな選択ミスのことを思い出す。「あの時ああしておけば」と後悔するのではない。あの時、もう一つの道を選んでいたらどうなっていただろうかと想像するのだ。
俺の中には永久に忘れることのない選択がある。
俺はその時に間違った選択をした。
生命の危機でも経済的な損失でもなく、もちろん社会的な立場を失うようなことでもない。それは俺にとっては生きるために必要なのはどちらなのかを選ばなければいけない場面だった。打算も将来予測もなく。
そしてどちらを選ぶかを決め、俺は片方を選んだ。でもそれが肯定的だったのかどうかは自分ではわからない。コインを投げて決めてしまったような安直さだった気もする。
やってこなかった未来をいまになって想像し、頭を抱えて泣き叫んでしまうのをどうにか抑え込んで、俺はまた眠りにつく。
「お客さん、起きてください。終点ですよ」
肩を揺さぶられて目を覚ますと、そこは電車の中だった。制服を着た車掌が顔を覗き込んでいた。電車の中の照明が眩しい。
他の乗客は誰一人残っていない。いつから眠り込んでしまったのか覚えていない。ひどく眠かった気はするけれど、終点まできてしまうほど深く眠り込んでしまうとは思わなかった。
外を見ようと窓に顔を近づけると男の顔が映った。あちこちに皺の刻まれ、髪はすっかり白くなったその男は間違いなく自分だった。自分だが自分ではない。私はまだ33歳なのだ。
ともかく電車を降りてから考えよう。シートから立ち上がろうとすると、足にもたれさせてあった杖が落ちて音を立てた。金属の軽い音が自分の杖のものだと理解するまで少しだけ時間がかかった。
何がどうなっているのか。33歳の私は一体どこへ行ってしまったのか。
痛む膝を杖で支えて、私はどうにか電車から降りた。終着駅のホームには仕事帰りらしきスーツ姿の男が数人いるだけだった。
私はベンチに腰を下ろした。
「いい加減起きなさい! 学校に遅れるわよ!」
大きな声とともに布団を引き剥がされて、僕は身震いをした。
枕元の時計は6時38分で止まっている。
「いま何時?」
「8時5分前。学校サボる気?」
「えっと、ねえ母さん、僕、いま何歳だっけ?」
「あんた寝すぎてバカになっちゃったんじゃないの? 高校2年は17歳に決まってるでしょ。ほら、さっさと起きてちょうだい」
母は僕が寝ているのもかまわず、シーツをつかんで引っこ抜いた。
僕はベッドの反対側に転げ落ちた。
もう目は覚めなかった。
(「眠る前にはいつも」)
* * *
いいなと思ったら応援しよう!