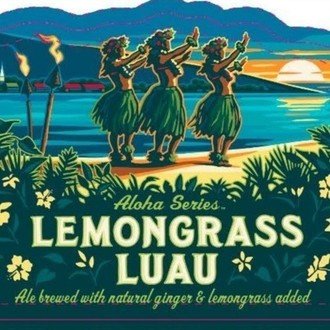さよならチャーリー
初めてローリング・ストーンズのライブに行ったのは1990年のバレンタイン・デー。
東京は雨模様だった。
コネクションをフルに使って手に入れた初来日初日のシートはステージに向かってやや右寄りの前から5列目。東京ドームをロックバンドのライブに使うのも、この日が初めてだった。
客電が落ち、キースのオープンGのリフが響くと同時にステージ前から火柱が上がり、ライトが照らされる。
最初に目に入ったのは「Start me up」のリフを弾くキースと、その後方でドラムを叩くチャーリー・ワッツの姿だった。
ストーンズを初めて聴いたのは10歳の時のことだ。
生まれて初めて買ったLPレコードは「It’s only rock’n roll」だった。
駅前の小さなレコード店だった。
店主の顔には「こんな小さな子が本当に聴くのか?」という疑問がわかりやすく貼り付いていた。
彼らが初めて来日したのは、それから16年後のことだった。
「若さにしがみついてるオッサンのバンド」
「商業主義」
「年寄りの冷や水」
「50歳近くでロックなんて気持ち悪い」
ファン以外の人間たちの言うことの中にはそんなものもあった。
でもそんなことはどうでも良かった。
ミック・ジャガーが、キースとロニーが、チャーリーが、ビル・ワイマンが目の前で音を出す。動く。それを目にすることができる。それだけで十分だった。
それまではアルバムリリースのたびに行われるワールドツアーを、指をくわえて見ているしかなかったのだから。
1981年8月24日。
アルバム『刺青の男』がリリースされた日だ。
僕はまだ17歳で、毎日に倦んで、今よりも窮屈になりながらこの先もずっと続く毎日に耐えられるのだろうかと途方に暮れていた。
発売初日のレコードをターンテーブルに乗せ、針を落とした瞬間に響いたのは1曲目の「Start Me Up」の乾いたギターのリフだった。
今になってみれば理由がさっぱりわからないのだが、17歳の僕はあのリフに救われた。
あの日から40年。同じ日にチャーリーは逝った。
80年代の中頃、キース・リチャーズがインタビューで年齢のことについて聞かれ、こう答えている。
「ロックは年齢を重ねるうちにソティスフィケートされて、エレガントになって行くんだ。年とってロックンロールバンドをやるなんて信じられないってやつには、ローリング・ストーンズを見ろよって言ってやれよ」
ファン手作りの「Greatest Rock'n'Roll Band in the world」の旗がひるがえる中、ステージの誰とも違って、チャーリー・ワッツはただ一人ジャズメンだった。その異質さがバンドの音の基盤となっている奥行きの広さが、ローリング・ストーンズをローリング・ストーンズたらしめていたのだと僕は思う。
半世紀以上もの間、ロックの代名詞のようなバンドにあってなおジャズメンであり続けたチャーリーは、また誰よりもエレガントだった。
さよなら、チャーリー。
いいなと思ったら応援しよう!