
経営管理部の2022年の取り組み
こんにちは。朝日インタラクティブ株式会社 経営管理部の石澤です。
今年も年の瀬が押し迫ってまいりました。今年はどんな1年でしたか?
世の中は激動の1年でしたが、私個人としては、特に大きな変化や事件もありませんでした。2倍速で動画を沢山見た年だったなという印象です。そういえば、夏前に仕事中ハードグミを食べていたら10年物のセラミックの奥歯が割れました。秘孔をついてしまったのでしょうか?歯が瓦のように割れて驚きました。
私個人は平凡な一年でしたが、今年も経営管理部は様々な事に取り組みました。経営管理部でこの1年間に取り組んだことを、簡単に振り返りたいと思います。トップの写真は、会社のベランダから撮影した夕日です。オフィスで一番好きな場所です。
2021年に取り組んだこと(振返り)
私たち経営管理部はどのような組織でしょうか?詳しくは、こちらのエントリーをご覧ください(長いです)。今年も3名の主力メンバーを中心に、日々の細かい改善や工夫を検討しながら、バックオフィスの視点から「いい会社」を作るための取り組みを進めました。
2022年に取り組んだこと
会計システムの変更
今年、経理での最大の変化は「会計システム」のリプレイスでした。
当社は今年度(4月)から改正電子帳簿保存法に対応し、決算関係書類含め帳簿類を適切にクラウド上で保管することを開始しました。電帳法対応の最終仕上げが会計システムの変更でした。

旧会計システムで本決算を完了(帳簿の締切り)した後に、新システムへ期末残高のインポートを行い、新年度の開始仕訳をスタートさせました。
経理にとって、会計システムのリプレイスは一大事です。
新しい会計システムの準備は約3カ月前から本格的にスタートしましたが、本決算直前の3月に本社の移転があり、そこに年始年度末の慌ただしさも重なり、事前の運用確認は十分ではありませんでした。新しい会計システムを使った4月度決算は、予行練習なしの一発勝負の状況で、決算完了直前まで決算書のレイアウト調整を行っていたほどです。
しかし、経理メンバー(2名)は、それぞれ積極的にマニュアルを読み込み、不明点はシステムベンダーへ問い合わせ、システムの理解を深めました。担当範囲の運用方針やルールを能動的に短期間で決めていき、無事に4月決算を乗り越えました。さらに、通常の記帳や決算ができるようになっただけでなく、その後数カ月をかけて効率化を目指し、次のような事にまで取り組んでくれました。
毎月必ず発生する伝票の自動仕訳機能の活用
銀行口座と接続し入金明細の自動取得による債権消込の効率化
仕訳チェック機能を使った記帳ミスの自動検知
売上システムと新会計システムの連携ツール(VBA)改修
連結決算システムへのデータ連携用財務諸表の作成
新しい会計分析書類(C/Fや資金繰り表)の整備
これらは本当に素晴らしい事ですよね。頭が下がります。
経理や会計に精通している方はご存じの通り、企業会計には、厳守しなければならない「企業会計原則」と呼ばれる7つの大原則があります。
システムが変わろうとも、過年度に採用していた会計方針を安易に変更することはできませんし、明瞭性、単一性、継続性を維持確保する必要があります。真実性や保守主義の原則も守りつつ、業務の効率化を図っていく必要があります。
先ほど述べたように事前の運用確認は不十分でした。しかし現在では、新しい会計システムにも慣れてきて、「期初にこのように設定しておけばよかった」という反省もいくつか判明してきました。来年も新しい会計システムを使い倒し、業務改善や会計分析の強化が図られていくのではと確信しています。
人事労務管理システムの導入
人事労務分野で今年一番大きな変化は、「人事労務管理システム」を導入したことです。人事や労務には色々な業務が含まれますが、今回導入したシステムは下の図の赤枠部分に対応するものです。この部分がクラウドシステム化されました。

これまで、従業員のライフイベント(入社、退職、引越し、ご結婚、ご出産など)に応じて、様々な申請書(PDF)が提出され、それをもとに情報をエクセルファイルで管理していました。必要な届出や申告があれば自治体や社会保険事務所へ提出し、導入済みの給与システムなどには手動でデータを反映していました。おおよその流れと悩みは次の通りでしょうか。

人事労務管理システムの導入により、従業員はブラウザから申請を行い、その情報が直接、従業員データベースに反映され、常に最新の状態に保たれるようになりました。また、給与システムとの自動連携もされ、社保手続きが必要な場合は、システムが必要なフローや書類・ヘルプを提示してくれるので、処理担当者の手助けになります。
導入を進めた担当者は、慣れないシステムに苦戦しながらも、システムベンダーへの問い合わせや社会保険労務士への確認(上司を介して)を行い、システムのセットアップを完了してくれました。そして、従業員の助けとなるよう、マニュアルも備え付けてくれました。
人事労務は、定型業務と非定型業務のバリエーションが豊富で、慣れるのに難しい部分があると感じます。それは人間に向き合う仕事であることと、常に発生するものではない為です。また、法令や行政等への手続きも稀に変更があるというのも要因と考えています。私は経営管理部に来て2年が経ちますが、人事労務に関しては、毎月何かしら新しいことが発生しているような感覚です。発生の度に、Webや過去資料から法令や手続きを検索し、必要な書類を整理し、作業のタイミングを忘れないよう、管理表と自分宛てのリマインドに設定するというような工夫をしてきました。
こういったシステムを導入しておくことで、法改正にもスムーズに対応できますし(システム側でアップデート)、過去の履歴も一元的に管理ができるようになります。さらに、従業員もパソコンやスマートフォンから社内申請ができるので分かりやすくなります。
今年は導入に注力したので、改善の余地はまだまだあるかもしれません。来年以降もこの人事労務管理システムをさらに活用できるよう研究を進めて行き、これまでDB化できていなかった従業員の様々な情報も登録管理をしていこうと考えています。
戸締りさん
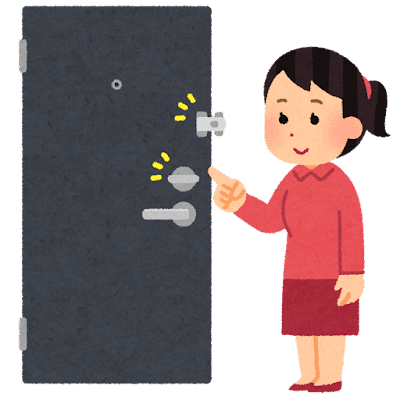
皆さんの会社にも、オフィスの最終退出者が電気や火気・戸締りを確認してサインを残すノート(やシート)が備え付けられていたりしませんか?大きな会社や24時間警備が入っているところでは無いかもしれません。
もしも、そういったノートが準備されているとしたら、それは、会社の防火管理者が消防署に提出した消防計画に基づいて備え付けられた「自主点検チェック表」かもしれません。
当社は今年3月に本店移転(引越し)をしたので、改めて管轄の消防署に中規模消防計画を策定し提出をしました。
消防計画上、「自主点検チェック表」は必要ですが、新しいオフィスに紙のシートを設置するのはかっこ悪く、紙で記録するのも時代遅れです。
そこで、Googleフォームを使ったデジタルなチェック表を作成しました。さらに、Googleフォームからの送信をトリガーにして、Slackのチャンネルに最終退出者のメッセージを投稿するように設定しました。これを通称「戸締りさん」と呼んでいます。

Googleフォームを利用したデジタルなチェックリストにしたことで、紙の自主点検シートを用意し保管する手間を省略することができました。また、以前は最終退出者を特定するために少しレガシーなシステムのログを検索する時間が必要でしたが、現在は「戸締りさん」がSlackに最終退出者を教えてくれるので、特定が容易になりました。
さらに、小さな工夫として、オフィス出口にGoogleフォームのURLをQRコードとして設置しました。最終退室者は帰宅を急ぎたいと思っているのに、手間をかけてマニュアルなどからURLを探すのは面倒です。そのため、ちょっとした「ナッジ」としてQRコードを設置することで、少しでも手間を省略することができるといいなと考えました。

今年は、「戸締りさん」をはじめとして様々なペーパレス化を推進しました。意図や目的を明確にして仕組みを改善することはそれなりに面倒ですし、個々の変化は大きなものではありません。しかし、小さな取り組みを積み重ねることで、大きな成果を得ることができます。今後もこのような取り組みを継続していきたいと思っています。
勤怠チェック君
以前、このエントリーで書いた通り、当社では労使間で「特別条項付き労使協定(36協定)」を結び、特別条項通知の運用をしています。
月中で、月初からの勤怠を確認し、残業時間に超過の兆しがある従業員へ部門長から通知を送る運用です。きちんと対象の従業員を見極めるためには、この月中の勤怠確認が非常に重要です。
そこで、「勤怠チェック君」という名前のツールを作成しました。このツールは、勤怠システムの打刻データをもとに、勤怠を分析し、特に確認が必要な勤怠が見つかると、Slackの個別DMで本人へ通知を送るものです。

実装方法は次のようになります。Google Apps Script(GAS)がGoogleカレンダーを監視し、定刻になるとAKASHI(勤怠システム)のAPIからデータを取得し分析を行います。おかしな勤怠が見つかった場合には、Slackで本人へDMを送信します。勤怠に問題がない人には送信されません。それほど難しい実装ではありません。

AKASHIには、標準機能として「アラート機能」があります。「【勤怠アラート】」という件名のメールを振り分け設定することで、注意が必要な勤怠を簡単に確認することができます。また、AKASHIにログインするとダッシュボード画面からもアラートを確認することができます。そのため、「勤怠チェック君」にはあまりニーズは無く、意味が無いかもしれないと思われました。正直なところ、気分転換を兼ねた実装でしたが、公開してみると意外に好評でした。きっと、タイミング良くサマリーを送ってあげることが重要なのかもしれません。
AKASHIのAPIでは取得できるデータ種類には仕様による限界があり、分析処理も簡単な事しかできません。現在は、より細かく分析してイレギュラーな勤怠を抽出するために、CSV方式(AKASHIからCSVを取得する)に改造中です。
この勤怠仮締め作業は従業員の事務負担であり、あまりインセンティブがあるようなものではありません。引き続き、ガバナンス、フェアネス、働き方改革、法令順守、正確性などをテーマに、勤怠管理についてはいろいろ考えをめぐらせ、負担を下げても目標達成ができる仕掛けを検討していきたいと思います。
その他の取組みと2023年に向けて
他にも、今年は次のような取組みもしました。
来年10月から始まるインボイス制度への準備や対応
在宅勤務手当新設への対応
産後パパ育児休暇新設への対応
人事評価制度改定に伴う対応
Pマークの更新&脱PPAP対応
年一回実施の個人情報保護教育テストのペーパレス化
自販機の導入など快適オフィスプロジェクト
※一番下に関連する記事へのリンクを貼りますね。
今年も本当に、いろいろな事に取り組めました。
昨年のエントリーでも書きましたが、経営管理部にはミッションステートメントがあります。メンバーはそれを胸に、日々の定型業務をこなし、イレギュラーな要請にも対応し、会社が抱えている課題に対してバックオフィスの観点から解決を試みます。前向きで真面目なメンバーたちが様々な挑戦をしてくれている結果、いろいろな事に取り組めています。
プレッシャーがかかる仕事も増えてきているため、適度に分散してあげなくては、というのは私の課題です。
しかし、それだけではありません。他部署の協力があるということも、私たち経営管理部にとって非常に重要で大切な事です。
編集部、営業部、技術・制作部に所属する各従業員は、日々専門性を発揮し、それぞれに重要な役割を果たしています。そんな忙しい中でも、経営管理部からの事務処理要請に真摯に対応をしてくれます(もちろん、たまに抜けやミスがあったりもしますが、総じて協力的です)。カッコいいですよね。他部署のメンバーの本来はミッションに無い、事務処理や間接業務を減らし、生産性の向上をしてあげたいと経営管理部は思うわけです。
その為には、他部署の事情や実状にもっと目を向けていく必要があります。他部署とコミュニケーションを増やし、リレーションシップを強化することで、より効果の大きい業務改善や課題の仕組化についてアイディアが出てくるかもしれません。というわけで、来年は部門横断(や部門連携)での取り組み(アクションプラン)も企画していきたいと考えています。
今年も簡潔にまとめられず長々と書いてしまいました。申し訳ございません。お付き合いいただきありがとうございました。
それでは、皆さま、良いお年をお迎えください。来年もまたよろしくお願い致します。
年明け1月20日(金)にデジタル戦略に関するオンラインイベントを行います。もし、ご興味があれば無料ですので是非ご視聴ください。
