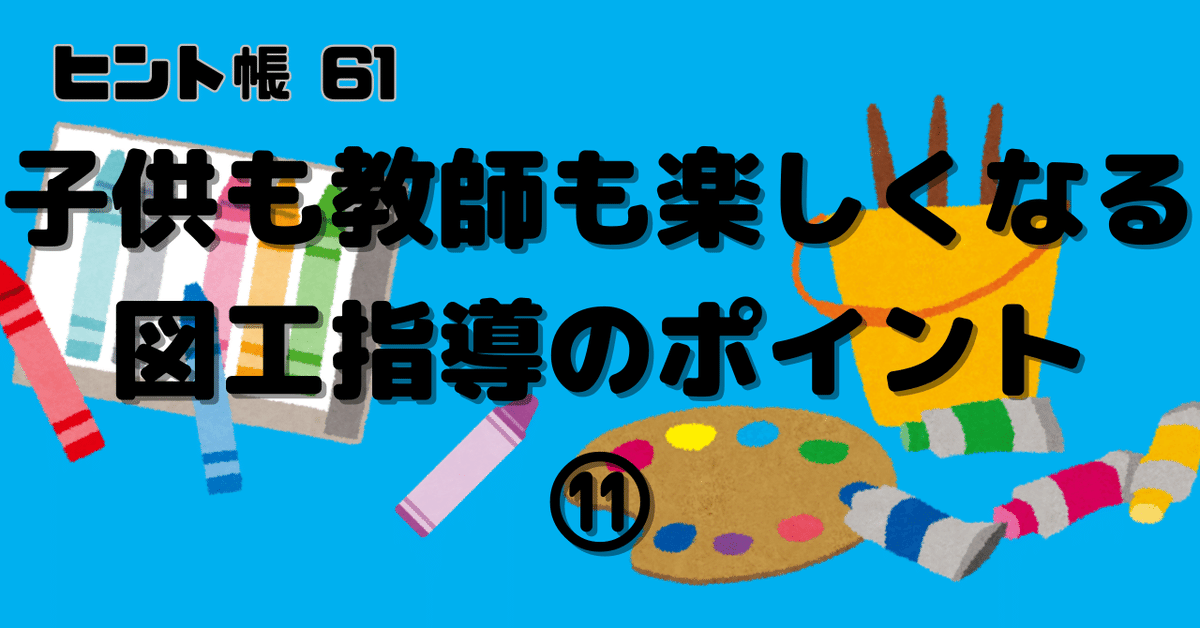
図工 子供に「竜」を描かせるか? 題材賛否両論
この「ヒント帳58」で、東洲斎写楽の役者絵の模写は、小学校の図工での題材としてどうかという疑問を述べたが、私には、これまでしばしば図工の教師仲間の中で、議論が分かれた描画の題材がある。
今回は、その中の代表的な二つの題材について紹介したい。
読者の皆さんは、この題材を子供に描かせることについて、賛成、反対のどちらだろうか。
「竜」は題材になるか
図工の絵画指導において、何でも題材になるわけではないということは、誰もが納得するだろう。
では、「竜」が出てくる民話は、題材として適切か不適切か。
竜というと、私の世代ならば、かつてテレビ放映されていた昔話のアニメ番組のオープンニングが思い出される。
展覧会などでも、「竜」がうねうねと空を動き回っている絵を見たことがある。
だから賛成派は、「描かせて良い」と主張する。「描かせている指導者がいるではないか」「著名な芸術家だって、昔から描いているんではないか」とうわけだ。
だが、私は反対だ。子供は「竜」を見たことがない。見たことがないものを描けるわけがないからだ。
もちろん、見たことがないもの、この世の中に存在しないものを描かせることで、子供たちが想像を広げ、楽しんで描くという場合もある。以前紹介した「不思議な壺」は、その好例だ。
だが、「竜」はそれとは異なるだろう。
想像して勝手に描くわけにはいかない。この世に存在しなくても、「竜」のイメージは人々に共有されているからだ。
「馬」や「熊」を絵に描かせる場合がある。SLが宇宙空間に走っている絵に取り組ませる場合もある。
こういう時は、子供は図鑑を使う。日常生活でよく見ていないからだ。
では、「竜」も、何かを見て描けばいいのか。
残念ながら図鑑には載っていない。
そこで、子供たちは「マンガ」や「絵本」を見ることになる。
その結果、子供の絵が「マンガ」または、挿絵を写したものになってしまうのである。
だから、「竜」は題材として不適切であると考える。
さて、この記事をお読みの方は、賛成、反対のどちらだろうか。
絵画指導における題材選定の原則が、そこにありそうだ。
「校歌」は題材になるか
では、「校歌」はどうか。
「校歌」を絵に描かせるなんて聞いたことがないとおっしゃるだろうか。
私は、賛成である。
これまで、6年生に題材として与えてきた。
6年間通い続けてきた学校、歌い続けてきたその校歌を絵に描かせることで、改めて校歌に向き合わせたいのだ。
だが、反対派教師は言う。
「難しい!」
と。
確かに難しい面もある。
具体物が登場しない抽象的な語句だけが並んでいる校歌の場合は、難敵だ。
だが、ある程度の具体物が歌詞にあるならば、「絵になる」。
また、かつての教え子の中には、「ともにつどい、ともに学び」といった類の、やや抽象的な歌詞であっても、イメージを広げて、「友達と遊んだり、学習したりしている場面」を描いた子もいた。
抽象的な校歌でも、指導方法の工夫によって描ける場合があるのである。
私は、「校歌」の絵に賛成である。
チャレンジしてくださる先生がいらっしゃったら幸甚だ。
