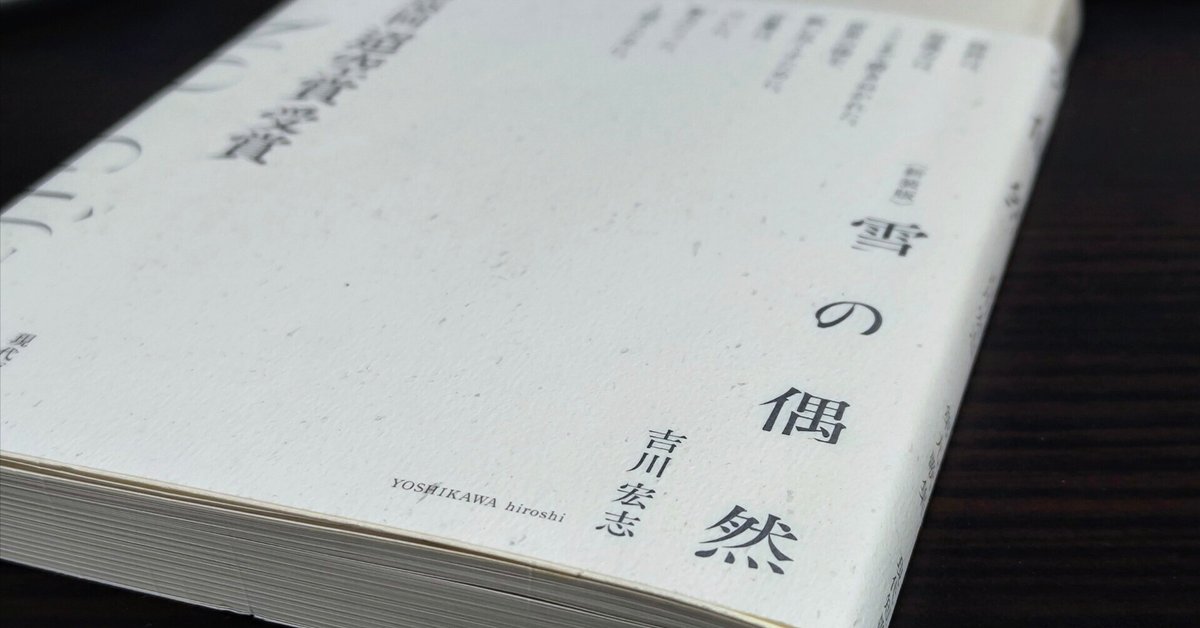
吉川宏志『雪の偶然』から(読む会を経て)好きな10首+α
2024/12/8 〈『雪の偶然』を読む会〉に参加しました。「卓越した修辞で知られる」とよく聞く吉川さんの作品、まだ十分インプットできていない段階ですが、読む会を通じてかなり視点が定まった気がしますし、「今いちばん真似したい方向性」のひとつでは確実にあると思っています。批評会で引かれた歌が多いですが、好きな10首を挙げました。
1
言葉より狂いはじめし世にありて紅葉は何の内臓ならむ
四句目をあえて定型の「もみじ」ではなく「こうよう」と読むことによって色々な仕掛けが見えてくる、というのを堀田季何さんの解説で聞いて、にわかに好きになった一首です。
・「言葉」と「紅葉」が縁語
・「ことば」「くるい」「こうよう」k音の呼応
・「なんの」「ないぞう」「ならむ」n音の呼応
・「こうよう」と「ないぞう」の反響
このような細かい仕掛けを丁寧に組み立てていく歌を作りたい。
意味的にも紅葉の「赤」が何の「内臓」(心臓を連想する)なのだろうか、という問いかけにはさまざまな答えがありそうです。吉川さんの歌には「疑問文」がけっこう多くて、無邪気なものもあれば、突きつけるようなものもあり、この一首の「ならむ」は含むものが多い感じがします。
2
ゆうぐれはどくだみの香の濃くなりて蛇腹のような石段のぼる
これは堀田さんの「嗚呼うまいなぁ」の一首目に来ていた歌で、
・「どくだみ」と「蛇腹」が縁語
・「香の」「濃くなりて」のk音
・「どく」「だみ」「じゃばら」いし「だん」の濁音
といった構成は一つ上に引いた歌と構造が似ています。緻密。「濁音の歌」と紹介されていて、初二句のひらがな表記と相まって強く記憶に残ります。
「どくだみの香の濃くなりて」に、石段を一歩ずつのぼるさなかに徐々に香りが強くなっていく、嗅覚的な時間経過をみることができ、それがとてもうまいと思います。
3
ゆうぐれの鳥啼く下に墓石の文字を読みおり文字とは傷だ
大森静佳さんが数えたら『雪の偶然』収録歌の20%は四句切れ(年を追うごとに比率が増えている)だそうですが、あまたある四句切れの中でも印象の強い一首でした。四句目までは墓石の文字を見ているという景の描写であり、結句7音でぐっと転換して「文字とは傷だ」という主張をバシッと提示する。大森さんが四句切れの効果として「結句での捉えなおし」と表現されていたのがまさにそうだと思いました。「四句切れ、結句で捉えなおす」というアプローチは真似てみたいです。
あとは「ゆうぐれの鳥啼く」で空に向いた目線を「墓石」まで下ろしていく視線移動も印象的です。
4
青鷺は小岩に立てり直文のまなざし残る座看の庭に
島田幸典さんの基調発言で「そうやって解釈するのか」と読み方がわかって強く印象に残った一首。明治期の歌人、落合直文の生家・煙雲館を気仙沼に訪れたときの一連にあり、作者が庭で小岩に立つ青鷺を見るとき、その家に住んでいた直文の「まなざしを追体験する」という構造(そして我々読者も作者の目を通じて直文のまなざしを追体験する)がある。「誰かが見ているものを、言葉を手がかりとして自身も再生する」という島田さんの解説は腹に落ちました。吉川さんの歌には「視線」が丁寧にコントロールされているものが確かに多いように思います。
座看の庭、という表現に言及はなかったと思いますが、禅語「行到水窮処 坐看雲起時(いきていたるみずのきわまるところ、ざしてみるくものおこるとき)」から、大手結社「塔」の主宰を継いだ吉川さんが、初めての短歌結社とも言われるという浅香社を起こした直文の視座を「雲の起こる時」として重ねて見ている、ということでしょうか。密度が濃い!
5
雪山に死にたる人の眼球は凍っているのか 夜を見たまま
吉川さんの短歌に通底する「死」というテーマ、四句切れ、そして「眼球」というディテールへの着目など要素盛りだくさんな一首です。読み手である私も「雪山に死にたる人」になって、夜を見ながら凍りついていくさまを感じられるように思います。目を見開いたまま死んでいく……。
6
死が見ている夢のごとくに雪深き谷を尾灯の赤走りゆく
5番の歌と「死」と「雪」が(『雪の偶然』らしく)重なりますが、この歌では「尾灯の赤」が走っていく印象的に様子が描かれます。救急車のブレーキランプでしょうか。
「死が見ている夢のごとく」という直喩も印象的です。吉川さんはよく「比喩がうまい」と紹介されるのを耳にしますが、本書に登場する直喩にはけっこう「暴力的なモチーフ」を合わせた表現が多い印象です。鈍器のごとく(p43)、手籠めのごとき(p23)、針穴が無数に穿たれたるごとき(p48)。いろいろな社会詠の歌で描かれる戦争や暴力的な事件と日常が、比喩を通じて相互に写されている感じです。
吉川宏志さんの短歌は第一歌集『青蝉』の頃から一貫して「死」というテーマが通底してると言われていて、一方私は目下「死」というテーマを歌いたい欲求は弱いです。職場詠は好きだけど社会詠・時事詠にあまり意識が向かないのは、そのあたりのアンテナ感度によるのかも(吉川さんの社会詠には「死」の絡むものが多い)。いざそのあたりのテーマに取り組もうとする時には、ここに大きな先人がいることを強く記憶します。
7
韓国を蔑して盛り上がる男たち 黒き磁石にむらがるように
「黒き磁石」という黒々とした直喩。磁石にむらがる、なので砂場の砂鉄のイメージかなと思いますが、死体に群がるゴキブリのような薄気味悪さが出ています。
菅原百合絵さんの発表では「滞留とおそれ」と題して、『ためらいを滞留させること、どちらかに決めてしまわないことは、実は楽なようでいてエネルギーを必要とする』とし、吉川さんは敢えてその「曖昧な状態」にとどまろうとしている、と分析されていました。この歌はその文脈では出てきていませんが、職場の同僚を「黒き磁石にむらがるよう」と嫌悪しながらも、その一群の末席に居る作者自身を客観的に冷ややかに見る部分が残っているように思います。
この一首を含む一連「美馬牛(びばうし、北海道美瑛町の地名)」は、冒頭とても暗く孤独な職場の飲み会風景から始まり、雪山へと移動し、最後はまた「ジュゴンの死」で終わりますが、なかなか息の詰まる連作です。
あと韻律の点では、「盛り上がる」という言葉に合わせて二句目を敢えて「なみしてもりあがる」9音と溢れさせているのも効果的だと評されていました。字余りは「余らせるべきところで意図的に余らせる」ようにしていきたい。
8
ここは三条麩屋町あたり ゆうやみの繋ぎ目として外灯が立つ
地名の効果について。これも堀田さんが『京都に詳しい作者が三条麩屋町「あたり」というのはなぜなのか→下句で「ゆうやみ」(夜)だから』という謎解きをしてくれました。初期作品から多いとされる「二句切れ」の構造で、情+景セットに区分されるのでしょうか。三条麩屋町に何があるのか、読み切れていませんが色々込められていそう……
9
好感のやすやすと作られゆく昼を鍋にななめに乾麺を挿す
この歌は会で引かれていませんでしたが、日常詠の中でもかなり好きな一首です。ランチにパスタを茹でる風景。「やすやすと」に込められた皮肉な感じ。「なべに」「ななめに」「かんめん」といった下句に密集した音の呼応。「昼を」で三句目で切れて(一字空けはなく)少しひねった景の描写が続くのも歌の構造として「ななめ」な感じがしていいなと思います。
10
夕影の貼りつく襖を抜けてゆく ふりかえったら母がいない
最後に、これも引かれていませんでしたがとても印象深い一首で、きわめて珍しい結句6音字足らずです。「母がいない 」の最後「ふっ」と姿が消えるような感覚が、これはほとんどが定型でここだけ狙い澄まして字足らずにしているのが効果を生んでいるのだと思います。
「夕影の貼りつく襖」という薄暗い光景も、死という通奏低音と不気味に呼応しつつ、美しい景を描き出しています。亡くなられたお母様に関わる歌の中でも、強く喪失感が滲んでいる歌だと思います。
+α
湯を細め珈琲淹るる ふいに来て前からずっといたような秋
+αとして一首だけ、第十歌集『叡電のほとり』から。私は5年くらい一乗寺に住んでいたので、「叡電のほとり」での暮らしには思い入れがあります。そしてこの落ち着いた生活詠。二句切れ景+情、後半の「ふいに来て前からずっといたような秋」というさらっとした秋の空気感の描写はとても心地よいです。吉川さんの歌にはこんなにやわらかい直喩もあるのですね。
京都に住んでいると塔界隈などで意外にお見かけする吉川さん。これまでの歌集を含め、さらに勉強していきたいと思っています。
いいなと思ったら応援しよう!

