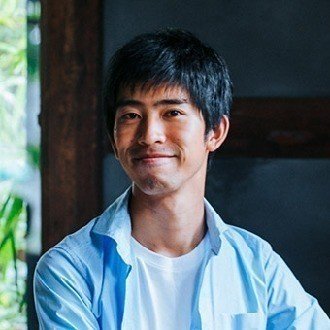阿波野巧也『ビギナーズラック』から( #ビ批評会 を経て)好きな10首+1
2024年10月19日、阿波野巧也さんの第一歌集『ビギナーズラック』批評会に参加しました。1冊の歌集をここまで深く読み込むことも、「批評会」という場に臨むことも初めての経験でした。事前に書きかけていた「私の好きな10首」に、批評会の復習を加えた形でお送りします。
1
四角いケースを背負った女の子のたぶん楽器だな、抜けていく改札
この歌が一番好きです。「たぶん楽器だな、」が不思議な位置に挿入されていて、かぶせるような独白で描く改札口の風景。四角いケースを背負った女の子と言えば「地下鉄に乗るっ」小野ミサのイメージで京都市営地下鉄、国際会館駅辺りの記憶を重ねて読んでいました。学生の多い都市を象徴するような景。パネリスト島田幸典さんがまず挙げていたように、阿波野さんの歌は「町のうた」が多く、都市を転々としてきた私にとっては共感しやすい描写がたくさんあります。
この歌、「切れ方」がずっと分からなかったんですが、
しかくいけーすを/せおったおんなの/このたぶん/がっきだな、ぬけ/ていくかいさつ
8-8-5-7-7(下句句跨がり)で読むということを把握しました(「たぶん楽器だな、」の中で分割があるのがポイント)。
この歌は批評会の会場発言で河野美砂子さんが取り上げてくださり、机を叩いてリズムを取りながら「小節線」という音楽的な表現で韻律を解釈していたこと、その前に大井学さんが「3句目の五音が大事」と言っていたのが印象的でした。
トップバッターのパネリスト奥村鼓太郎さんは「韻律⇔ムード」を中心に整理されていましたが、本書の「韻律感覚」は、批評会全体の大きなテーマでした。初句7、句またがり、頭韻……
好きな韻律発表ドラゴンが
— 阿波野巧也 (@tkyawnss) July 5, 2024
好きな韻律を発表します
初句7
句またがり
頭韻
下の句3分割するやつ
2
きみがケトルでココアをお湯に溶かしてる 瞬間はなみだの加加速度
7-7-5-7-7(しゅんかんはなみ/だのかかそくど)。「加加速度 (jerk, 躍度)」という単語の選択がとてもユニークです(合目的的とか、そういう言葉がとても好き)。一首を通じて「き」「ケ」「コ」「かか」のk音の重なりがまさに加速する感じのリズムで、ココアをお湯に溶かす渦のぐるぐると重なって気持ちの良い流れを感じます。
阿波野さんのテキスト『口語にとって韻律とはなにか』では、岡井隆の『短詩型文学論』から、韻律を理解する上での「5つのリズム」をベースとした上で、口語における「定型拡張」について掘り下げられています。このあたりの話を把握するまで、私は「57577でなければ、破調」と単に捉えていたのですが、一定の制約とねらいの中で定型から「拡張」された韻律について、こうして言語化されることで、理解が深まりました。
3
秋の光をそこにとどめて傘立てのビニール傘をひかる雨つぶ
助詞について。四句目、ビニール傘「を」という助詞の選択がユニークな歌です。河野美砂子さんは「文語的な助詞の選択だ」と表現していました。ビニール傘「に」とすれば比較的自然なところ、「を」を選んだことにより、雨粒がビニール傘の表面を「伝っていく」という省略された動きが圧縮されていると受け取りました。
口語短歌の制約として「助詞のバリエーションの少なさ」があり、そのカウンターとして韻律の定型拡張があるという話が上述のnoteにありました。数少ない助詞の候補のどれを使うか、たった一文字の選択。助詞を迷う局面で思い出すことの多そうな一首です。
4
ストローを刺してあふれるヤクルトの、そうだよな怒りはいつも遅れて
この歌は1番の「たぶん楽器だな、」とも共通する「、そうだよな」の挿入と言い方がユニークだと感じました。ヤクルトにストローを刺しても溢れなくない?と思いつつ、こぼれるヤクルトに遅れて怒りがやってくる、その遅延する時間感覚が「いつも」であるという把握には共感します。5-7-5-9-7、四句目「そうだ怒りは」なら定型のところ、「よな」がもたらす余韻、広がりがいいなと思います。
あと、この「そうだよな」という表現に関連して、岡井隆・河野裕子という名前が確かちょろっと挙がっており、このへん、未履修なのでがんばらねばと思いました。
5
砂利道の上にもみじが散っていてしゃがんできみは撮る それを撮る
会場発言で笠木拓さんの評を聞いて好きになった歌。
「砂利道の上にもみじが散っていて」←寄り
「しゃがんできみは撮る」←やや引き
「それを撮る(主体)」←最も引き
という三段階ズームを、近い方から丁寧に順に引いていくカメラワークが誠実なアプローチです。
6
三匹の犬がこっちを見つめてる 茶色いやつがいちばん見てた
魚村晋太郎さんの評を聞いて好きになった歌です。「三匹の犬がこっちを見つめてる」現在形の光景描写から、「茶色いやつがいちばん見てた」と過去形になり、主体の回想へと視点が切り替わる。この、時間軸の緻密なコントロールが阿波野さんの特徴的な技巧とされますが、こうした丁寧な時間の切り取り方ができるようになりたい。
千種創一さんも上記noteで「認識の時間幅を拡大する試み」としてこの歌を引いていました。
7
マジっすか、やばいっすねと応えつつこころは雨の花へ寄り添う
その千種創一さんの〈煙草いりますか、先輩、まだカロリーメイト食って生きてるんすか〉(『砂丘律』)を上句から想起しました。「若者言葉の導入〜」という感じで目に留まりましたが、いっぽう下句「こころは雨の花へ寄り添う」で、視点が応えた相手から主体自身のほうにぐっと寄っていく視点移動のダイナミックさがいいと思いました。
8
酎ハイを手に平野部は心まで広がっていくみたいな夜だ
珍しい直喩の歌、「平野部は心まで広がっていくみたいな夜」はぶわっとイメージが喚起され、飛距離がある比喩だと思いました。二句目「平野部は」というフレーズだけ突然テレビの気象予報士の声で再生される気がしませんか?
9
王将で打ち上げしよう7月の終わりのTOEICおわりの光
「7月の終わり」(おわり ̄)と「TOEICおわり」(お\わり)の差を、パネリストの服部真里子さんは「位相の違い」と呼んでいましたが、位相を変えたリフレイン、非常にかっこいいなと思います。「TOEICおわり」に「王将」と来るのも、とても都市的。
10
うまそうすぎて馬になる、ってメッセージにつづいてとどく絵文字の馬は
リフレインといえばこれ、ダジャレのような「うま」のリフレインがかわいらしくてとても印象に残っている一首です。そして連作タイトル「こしあんと思案」の「しあん」の韻。リフレインをうまく使いたい。
ちょっと終盤力尽きてきました!最後に……
+1
吉田歯科の〈歯〉の字が少し凝っている 歩いていけば明け方になる
最後にビギナーズラックじゃないところから一首。夜遊びの果てに歩いて家に帰る深夜に、歯医者の看板に目が留まった一瞬を描いた歌で、そういう時にそういう細かいところが気になるのが「わかるー」という感触です。
書肆侃侃房の短歌ムック「ねむらない樹 vol.11」(現時点の最新号、第六回笹井宏之賞、榊原紘特集)は、私がはじめて買った短歌雑誌で、ここに載っていた連作「Tribology」がいいなと思ったのが阿波野作品との出会いです。
作歌を始めてから長らく「どの歌人の影響を受けているのか」がいまいち言語化できていなかったのですが、景の描写、韻律、時間のとらえ方など、いま一番強く作風の影響を受けているのは阿波野さんからだと思います。
引き続き勉強していきます。
いいなと思ったら応援しよう!