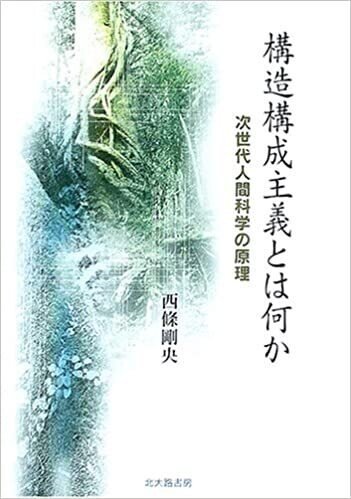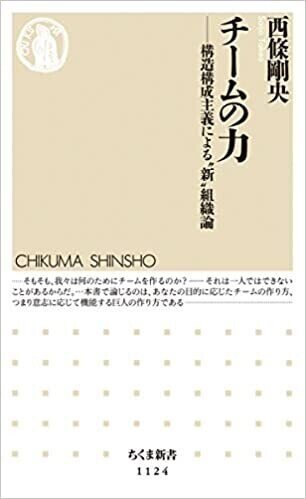私の羅針盤
ここ最近、zoomやstand.fm などのメディアで、さまざまな分野の方々とお話をする機会が増えました。おかげさまで、とても楽しい時間を過ごしています。
その中で、写真のお話、写真以外のさまざまなお話をするたびに、「背景となる考え方を共有していたら、もっと話が伝わるし、深いところまで共有できるのになー。」と、密やかに思っておりました。
一方、話す練習をしようと、心理学のお話を題材に音声メディアで話を始めたのですが、これが、むずかしい。。。話し方も、説明の順番、言葉選びも、すべてがむずかしい。。。伝わっているのかどうか、とてもあやしそう。。 うーむ。
ということで、私が羅針盤としている書籍を紹介することにしました。
他力本願極まりないですが、これが確実でしょう。もしご興味ありましたら、ご覧くださいませ。
1.統一場心理学
私が採用している心理学は「統一場心理学」です。吉家先生が確立されたメタ理論で、心理学としてはマイナーですが、理解できると非常にスッキリと世界を捉えることができますし、何より、理解しただけで心の中が整います。メタ理論なので、他のさまざまな心理学と喧嘩せず、親和性が高いのもいいと思います。
書籍は、「統一場心理学の考え方」がありますが、今年 集大成の書籍を出版予定とのことで、ご興味あるかたは、買わないでしばしお待ちいただいた方がいいかなと思います。
2.構造構成主義
その、吉家先生も参考にしているのが、こちら「構造構成主義とは何か」です。さまざまな分野、異なる文化を背景とする人とのコラボレーションを可能とするための認識論です。
異なる宗教・文化を持つ人々が話し合いを行う場合、ここを起点として始めるしかないのではないかと思っています。私も、改めて読み直してみようかな。
3.チームの力
上記の書籍を出版された西條先生は、東日本大震災のときに「ふんばろう東日本支援プロジェクト」という日本最大級のボランディア組織を立ち上げて、率いた方でもあります。
「構造構成主義」をベースに、ふんばろうでの経験を含めて、チームのための新しい組織論を論じたのがこちら。「チームの力:構造構成主義による”新”組織論」です。
チーム作り、リーダーシップ論、戦略の立て方、モチベーションを維持してもらう方法、トラブル解消法など、チームの力を最大限に伸ばす原理と方法が書かれています。
ビジネス上の組織やチームから、コミュニティ、ボランティア、人が何かしらの目的を持って集まった集合体であれば、あてはまる原理だと思います。
◇ ◇ ◇
3冊に共通しているのは「原理」を探しにいく「メタ理論」ということでしょうか。最初に経験則をベースとした考え、理論からはじめると混乱を極めますが、はじめに原理を理解した後なら、さまざまな経験則を適切に扱うことができると思っています。
そもそも、私は「本当のこと」「本質」を探したいんですよね。
背景となる文化によらず、だれもが合意することのできる理路を探す。
それは、科学でもあり哲学でもありますね。
そして、だれもが合意できる理路を持ってしてでも統合することの難しい概念を、一発で統合して見せるのが芸術の力だと考えています。
いいなと思ったら応援しよう!