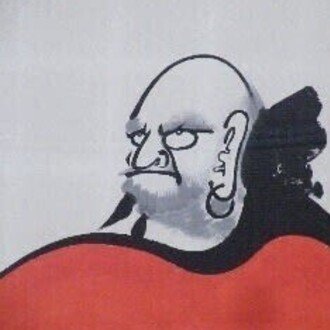「祝日」を注視すると、何かが見えてくる 今日は「建国記念日」 If you look closely at "holidays", you can see something. Today is "National Foundation Day".
今日は2月11日、「建国記念日」。祝日である。 筆者は、毎日が日曜日なので「祝日」も忘れてしまっている。たとえ、祝日は知っていても、 “今日はなんの日?” といってしまうほど世間とのずれが生じているのも否めない。筆者だけの話ではないかもしれないが、「祝日」の意味や認識が時代とともに薄らいでいるような気がするが・・・。
Today is February 11th, "National Foundation Day". It's a holiday.
For those who are Sundays every day like the author, they have forgotten the "holidays" as well. Even if you know the holidays, it is undeniable that there is a gap with the world that makes you say, "What day is it today?" It may not be the story of the author alone, but I feel that the meaning and recognition of "holidays" are fading with the times.
昨日、インスタグラムである方が元号を墨で書かれていたのが目に留まった。いままでにまとめて元号が書かれているものを見たことがなかったので感動を覚えた。その方曰く、つないだら3mを超えたというコメントが添えてあった。大化の改新のときの「大化」から元号が始はじまり、いまの「令和」まで248元号ある。その一つ一つが丁寧に書かれてあった。
Yesterday, I noticed that the era name was written in ink on Instagram. l was impressed because l had never seen the era name in one place. According to that person, there was a comment that it exceeded 3m when connected. The era name started from "Taika" at the time of the Taika no Kaishin(Reform), and there are 248 era names up to the present "Reiwa". Each one was carefully written.

kawa_k2316(インスタ アカウント名)の書と写真 掲載了承
元号についてウィキペディアでは下記の内容のことが表記されていたので、一部省いているが転載しているので参照ください。
元号(げんごう)は、古代中国大陸で創始された紀年法(年を数えたり、記録する方法)の一種。特定の年代に付けられる称号で、基本的に年を単位とするが、元号の変更は年の途中でも行われ、1年未満で改元された元号もある。
現在、世界では日本のみで制定、使用されている。日本における元号の使用は、西暦645年に孝徳天皇などの宮とする難波宮で行われた大化の改新時の「大化」から始まった。短期間でいったん廃止されたが、元号が実際に連続的に使用されたのは「大宝」からである。「大化」の年号と前後して、「日本」という国号の使用も始まったが、7~8世紀の日本の正史における用例は極めて限定的である。日本やベトナム(越南)では、元号は年号の称号で呼ばれることが多かった。公称としては、日本では江戸時代(慶応)までは「年号」が多く使われ、明治以降は一世一元の制が定着し元号法制定以後、「元号」が法的用語となった。
About the era name Wikipedia describes the following contents, so please refer to it because it is reprinted although it is partially omitted. The era name is a type of calendar era (a method of counting and recording years) that was founded in ancient mainland China. It is a title given to a specific age, and is basically in units of years, but the era name is changed in the middle of the year, and some era names are changed in less than a year.
Currently, it is established and used only in Japan in the world. The use of the era name in Japan began in 645 AD when the Taika Reform was carried out at Nanbakyo, which is the palace of Emperor Kotoku and others. Although it was once abolished in a short period of time, the era was actually used continuously because of "Taiho". Around the time of the year of "Taika", the use of the national name "Japan" began, but its use in the official history of Japan in the 7th and 8th centuries is extremely limited. In Japan and Vietnam, the era was often referred to by the title of the year. Nominally, in Japan, "year" was often used until the Edo period (Keio), and after the Meiji era, the system of one-generation era was established, and after the enactment of the Era Name Act, "era" became the legal term.
三世を生きている筆者には昭和と平成は激動の時代であったが、この令和は誰もが同じコロナ感染症時代に直面し生きている。時代によっていろんな状況に違うが、今日のような「祝日」の意味をもう少し掘り下げてみると、一年ごとではあるが社会や生活、そしてそれぞれの暮らしの変化が見えてくる。そしてその変化が次年へのステップアップにつながっていくような気がする。
Showa and Heisei were turbulent times for the author who lives in the third generation, but this Reiwa lives in the same era of corona infectious diseases. There are various situations depending on the times, but if you dig a little deeper into the meaning of "holidays" like today, you can see the changes in society, life, and each life, albeit year by year. And I feel that the change will lead to a step up to the next year.

つなぎ合わせると3m以上に (kawa_k2316さん)
リポート/ 渡邉雄二 写真&書/ kawa_k2316 Reported by Yuji Watanbe
いいなと思ったら応援しよう!