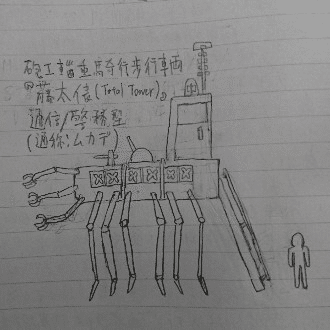創作(2022/2/20 10:00)『人事天命』Part3
原作『堕天作戦』

感想フォーム(あらかじめ)
感想は以下でも受け付けております。
Peing質問箱 :
マシュマロ :
Googleフォーム(詳細な感想の場合こちらを推奨) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScApO3Fh8282CriZXHY6Lib0gA1poCrKhT6H0JkgTH5eBH7AA/viewform
『人事天命』Part3
『漸悟頓悟』
死地で、ふと、そんなことを思い出していた。
キューティの言ったことは、正直、未だ完全には理解できないままだ。
が、大事な話だったことくらいは分かる。
いずれにせよ自分にはできなかった。
自分はきっと、最期まで、長たる分際の者でも、人と呼びうる者でも、己のすべきをなしうる者でもなかった。
自分はこれから、本来の道標に到達できずに、志半ばで死ぬ。
それは、かけがえのないヘリオスの死や、前途有望な若者であったシバの途絶によるものだ。
疑いようもなく、彼らは、自分にとっての輝きだった。
その輝きが失われたからこその、星への道であり。
またそれを投げうっての、これが最期のゼロ旋風なのだ。
悔いはある。
だが、これは多くの人が噛み締めて死んでいくものだ。
自分は彼らをそのように殺してきたのだし、正にこうやって殺しているのだ。
その自分も、そのように、救済されずに死ぬ。それだけの話だった。
これは、人倫と応報ではなく、単に確率だ。
自分だけがそこから外れられる道理はない。
当たり前のことだ。
それを、いいとは言わない。私情から見れば、悪い結末だ。
人生も人間性も完全からは程遠かった。
苦い思いが、胸の奥に濁りを残す。
***
だが、もはやそこに対する執着も、刻一刻と薄れてきている。
自分にしては珍しい。
(これが、死を迎える、ということか。)
何か、未知の人間らしさの断片を、理解しかかるような気がした。
言語化しづらい、曖昧な回路のつながり。
「いい加減でいい。」
という、キューティの言葉に関係がある何か。
それは、淡雪のように消えはせずに、脳の中にうっすらと積もっていた。
微妙に分からないまま、歩いていた。
脳がむずがゆいような違和感がある。それがどうしても溶けてくれない。
何度考えても、これを解く思考が、うまく形を結んでくれない。
一歩ずつ進むごとに、少しずつ投げやりな気持ちになりつつあった。
***
そして、ふと、気付いた。
(よく考えたら、今の私が、正にそういう風に、いい加減になっているではないか。)
目的を失い、なおも生きている。歩いている。
おそらく、目的はなくとも、人は死ぬまで、そうやって生きて、歩いていられるのだ。
ならば、これから死ぬまで、目的がなくてもいいのだ。
少なくともこうやって生きているし、歩けるではないか。
だから、単に死ぬまで生きて、そして歩けるだけ歩けばいいのだ。
価値がなくても。
意味がなくても。
やりたくなくても。
最早、ただ歩くことしかできなくても。
それを、全うしよう。
無目的なままで行こう。
ひょっとしたら、見たことのない光景が、待っているかもしれない。
死ぬ前に、自分はいったい、何を見られるのだろうか。
歩けるだけ歩いて、見られる景色を見て、死期が訪れたら、そのまま死ねばいいのだ。
きっと、自分の作り出した、白一色の氷地獄だけが広がっているのだろうが。
それはそれで、よしとはしないが、文句も言うまい。
***
意識の混濁に、すっと、透明な空気が流れた。
なるほど。
分かるということは、素晴らしい。たいしたものではないか。
もう少し検めて見れば、もっと大切なことが分かるような気もした。
が、
(今の私が触ったら、吹き飛んでしまうな。)
死を前にして、果たされていない執着を、手放してもいい。
何の戸惑いもなく、そう思った。
一つ、分かっていなかったことが分かった。
なすべきことの力ある呪いが、自分をここまで旅立たせ、こうして自分から解き放たれた。
それで、十分だ。
***
己の目的を果たした後、こうしてシバも、死ぬまで無目的に歩いていたのだろうか。
ある意味では真に自由なひとときを、このようにして過ごしていたのだろうか。
途方もない奇蹟。獣では味わえない喜び。人の境地。
そんなことを、シバに語ったような記憶がある。
これもそういうものの一つなのか。自分にもよくは分からない。
単純に、幸せかどうかでいえば、これはそれとはまるで異なるものであろう。
が、自分がシバに与えられなかった、得難い人生の時間だ。
少なくとも、得られないより、ずっとましなものであろう。
***
自分もこうして。
氷柱のように硬く真っ直ぐな呪いから解き放たれて。
雪解け水が滴るように。
のろのろと。
無為に。
歩いている。
***
自分は、望むことを、何も成し得なかった。
ただの思い出しか残らなかった。
それで、何が悪い。
大人しく、そんなちっぽけな淡雪に抱かれて、心安らかに死ねばいいではないか。
そうして死ねるだけ、恵まれているであろう。
それでよしとしても、少なくとも自分は構わない。
もはや、混乱も動揺もしていない自分がいた。
自分はここまでだ。
後は彼らに任せよう。
成功も失敗も、彼らのものだ。
最早、自分の手の及ぶ所ではない。
無責任なことを言うようだが。
そして、この最後のゼロ旋風が尽きても。
自分は、最期まで、行けるところまで行こう。
ヘリオスやシバと同じく、自分も、生の果てまで、自分の足で歩こう。
そうして、全てが尽きたら、全て受け入れて、そのまま逝こう。
***
『死出之旅』
『多くの敵を地獄に送った。
星に行くのは叶わなかった。
不死者にも出会えなかった。
育ての親として心に寄り添うこともできなかった。
申し分のない地獄が広がる。』
これがコサイタスにできる全てだ。
『夜が明ける。』
***
曙の先に、この世ならざるものを見た。
槍を携えた、蠢く蔦をまとった影。
不死者。
目を疑った。
まさか。
あれは。
ヘリオス。
***
『「ああ……あ、ああああッ!!」』
気がつくと、コサイタスは絶叫していた。
『遠くて見えない、
声も届かない、
積雪が歩みを阻む。
結露で曇ったヘルメットを外すと、残余の寒気が老体を襲った。
他者に向けて放ち続けた致死の苦痛が、直ちに自身を凍らせ始める。』
姿も見えない。
声も届かない。
足が届かない。
自分は、ヘリオスの影には届かない。
だから、ありったけの全てを振り絞って。
『残る魔力は念波に――』
想いを届けるために。
***
『「ヘリオス!!」
「聞こえるか!? 私はここだ!!」
「信じていた!! いつか必ず降臨すると!!」』
心は軽く、そして体はどこまでも重く。
自分が、身勝手にも、救われていくのを感じる。
『「見てくれたか!? クメルの大軍を、撃退した!!」
「お前が授けてくれた、ゼロ旋風……」』
息が上がる。倒れる。
分かっている。自分はここまでだ。
伝えるべきことを、伝えられない哀しさ。
それは、もう、二度と繰り返さない。
これが自分の最期にやるべきことだった。
もう、間違えない。
雪空の如く混濁していた人生の中で、疑いようもなく、この時が最も清明な意識だった。
『「ギョーマンは死んだ。恐らくシバも。オスカーは年老いた。」
「でも大丈夫だ。党は何倍も大きくなった。戴天党は不滅だ!!」
「アマチがロケットは造れると断言した。お前が選んだ頼れる人間だ。」』
ヘリオスの知る者たちの話をしなければならない。
そして、ヘリオスの知らない者、それもヘリオスの夢に関わる者の話もしなければならない。
『「心強い仲間も得た。幼体成熟のレコベル!」
「不屈の知性で、必ず星へと至るだろう。」』
ヘリオスの影が近づく。
何か言っているような気がする。
聞こえないのが残念だ。
恐らくは、あの頃のように、
「そいつはすげえ! やったじゃねえか。」
と陽気に大はしゃぎしているのではないか。
それが察せられるだけで、コサイタスには十分だった。
相手に伝えるべきことは済ませた。
後は、言葉が、勝手に出て来た。
『「……何年経とうと、
全部覚えている。
顔を剥いで、
暴れ回って、
バルコニーで、荒野で、
ホテルの部屋で語り明かして、
ピザを食べて、
私を救ってくれたことも、
私を赦してくれたことも、
私の人生そのものだった……
ヘリオス……」』
***
そして。
顔を上げると、ヘリオスの影が、立っていた。
数歩先。
コサイタスにはもうたどり着けない。
手も届かない。
だが、ヘリオスの影がそこにいる。
朝日を背負って。
コサイタスにとっての全てが、コサイタスを迎えにきた。
クメル方面軍の死のために、夜空を仰いだコサイタスの手が。
コサイタスにとっての全てを、こちらからも迎え入れようとする。
己の人生の全てを全うさせて終わらせる死を、自ら望んで受け容れる。
***
ふと、あの子と共に、太陽が沈むのを見ていたことを思い出す。
夕焼けの綺麗さが、自分には分からなかった。色が変わっただけに見える。
敢えて何かを言うのであれば、あれは頭上にあるべきだろう。
ヘリオスとは太陽の旧い呼び名なのだそうだ。
だとしたら、それは天上の存在に他ならない。
その程度の認識しかなかった。
コサイタスにはそんな審美的感覚しか備わっていなかった。
分かっていたことだった。
自分はそういう者なのだ。
党を采配する実力や、ヘリオスへの激情に比べると、こんなものは正直言ってどうでもいいことだった。
だから、これについて悩んだことは、これまで一度もなかった。
だが、朝日が自分を迎えにくるのも、いいものだ。
そう、初めて思った。
自分に、外界の風物の良し悪しが分かるようになるとは、思ってもみなかった。
最期の最期で、ヘリオスだけでなく、あの子からも、大事なものを受け取った。
そのように思えた。
『「朝日なら、
綺麗かもしれない、
シバ……」』
穏やかな朝がきた。
ヘリオスの世界だ。
存外な幸せ。法外な悟り。
これに焼かれて、自分は逝く。
何と素晴らしいことであろうか。
大空を仰いでいる。
清々しく光り輝く白に、何もかも、混ざっていく。融けていく。
背後の彼方の戴天党に、静かに、別れを告げた。
ヘリオスがコサイタスの呼吸器を外す気配があった。
コサイタスの呼吸は最早止まっているが、涼しさを感じたような気がした。
優しいな。ヘリオスは。
何もかも、清澄だ。
(続く)
いいなと思ったら応援しよう!