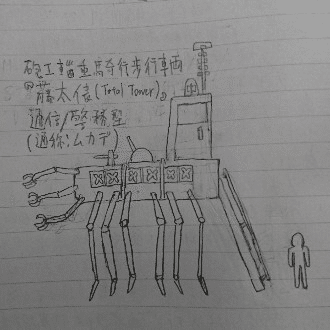随筆(2020/10/25):「共感と問題解決」というモデルは、「存在と真理」というモデルに、さらに単純化できる(1)
1.「分からないもの」には、「あるがまま受け入れてよい時」と、「扱い方が分からないと安全でない時」がある。これらは混同してはならない
よく(男女論と絡めて論じられる)「共感と問題解決」というモデルが、あるじゃないですか。
あれについて時々考えるんですけど、今日あることに気付きまして。
***
なんか驚嘆すべきものに触れた時に
「なんだこれは!? オレはこんなのはじめてみるぜ」
ってなるじゃないですか。

***
そういうときに横で
「これはこのような謂れがあって云々」
と説明されると、
「おい、オレはシンプルに驚いているんであって、そのシンプルな驚きは、説明したら、ウイスキーを水で割ったように、味が変わるんだ。やめろ!」
とは、まあなっちゃうんですよ。
***
なんらかのコンテンツでネタバレ禁止をしたがるの、まあ分かるんですよ。
それをやると驚きは薄められ、なくなる。驚きをあるがままに味わえ。そういうことです。
「面白いものは、解明されても同じだろ」という、よくある理屈は、本当は違う。
歯車で動く時計を見て、そのままあるがままに楽しむことと、内部構造を見て楽しむことくらいには。
後者がより楽しめるものの見方だという話は、万人においては別に成り立たない。万人に後者を強いてはいけない。
***
「隠されているということは、騙されているということだ。
それによって不利益がもたらされることもある。超許せねえ」
という、ある種の誠実の倫理的価値観、もちろんある(俺もかなりそうだ)。
だが、内部構造まで見ないと安心できないの、よくないですよ。
ふつうはそうではないし、あるがままに受け取ればそれで足りることも多々ある。
そういう時に、
「ウルセーぞ。俺の納得と安心のために、はらわたを解剖されろ。お前は人間じゃない。カエルだ」
と言ったら、そりゃあまあ、揉めるに決まってる。(どういうたとえだよ)
***
単に、あるがままに受け止めて投げ返すことで、「共感」をもたらすモードが成立するなら、そっちをやった方が、コミュニケーションは円滑なんですよ。
特に、問題がないんなら、「問題解決」モードなんか、採用する余地、ある訳ないでしょう。
問題解決は問題がある時にやりなよ。
問題がない時に行われる問題解決って、つまりは「これは問題だ」「否定されるべきものだ」と言っているに等しい。
そもそも「共感」モードの元となるものを、否定なんかしたら、
「これによって、何らかの否定的ではない感情を覚えたお前は、これといっしょくたに、今から否定される。自分に。有難く思え」
という意味合いになる。
揉めるに決まってるだろう。そんなの。
だから、問題のない時に、問題があると決めつける、問題解決、本当にダメなんですよ。
(今回も複数回の連載になります。長くなっちゃったので…続きます)
いいなと思ったら応援しよう!