
13-3.スクールカウンセリングの“技”を磨く
(特集 心理職として技を磨く)
黒沢幸子(目白大学教授)
Interviewed by 下山晴彦(東京大学教授/臨床心理iNEXT代表)
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.13
1.はじめに
臨床心理マガジン13号は,「心理職として“技”を磨く」特集です。前回の13-2号では,「心理職の技能向上のための主体的意識と経験とはどのようなものか」をテーマとし,黒沢幸子先生をゲストにお招きして「ブリーフセラピーの“技”を磨く」お話を伺いました。
黒沢先生は,当初アートセラピーに関心をもち,精神科病院での研修を始めました。しかし,アートセラピーをきっかけに思春期の患者さんに多く出会うことになった黒沢先生は,次第に思春期を対象とするということでスクールカウンセリングに実践の場を移していきました。そして,解決志向ブリーフセラピーの“技”を磨きがならスクールカウンセリングの実践を展開されてきました。
前回は,その解決志向ブリーフセラピーの“技”の基礎となるクライエントさんへの承認と敬意,ジョイニングの重要性をお話になられました。また,「例外の発見」や「ミラクル・クエスチョン」などの“技”を適切に実践するためには「発想の転換」が必要といった実践の“コツ”もお話をいただきました。
全体を通して,心理職として“技”を磨き,キャリアを発展させるためには,単に“技”を受身的に学ぶだけでは十分ではなく,自らの興味や関心を大事にし,現場での試行錯誤の経験から自分がやりたいことや自分に適したことを見出し,それを実現するために学習や実践を広げていく積極的な努力が必要であることが示されました。
今回の13-3号では,前回のお話を受けて,スクールカウンセリングの活動を展開し,発展させていくための“技”の使い方や磨き方を,黒沢先生に伺います。
『明解!スクールカウンセリングー:読んですっきり理解編』
https://www.kanekoshobo.co.jp/book/b184001.html
黒沢幸子・森俊夫・元永拓郎(著)金子書房
『解決志向のクラスづくり 完全マニュアル:チーム学校,みんなで目指す最高のクラス!』
https://www.honnomori.co.jp/isbn978-4-86614-104-6.htm
黒沢幸子・渡辺友香(著)ほんの森出版
本号の記事は,2020年11月13日に実施したオンラインインタビューの後半の記録に基づいて構成しました。インタビュワーは下山が務めました。Zoomの運営管理と記録作成は,北原祐理(東京大学特任助教)と井上薫(東京大学特任研究員)が担当しました。

2.スクールカウンセリングの活動5本柱
──前半では,黒沢先生がどのようにしてブリーフセラピーに出会い,“技”を磨いてきたのかについて伺いました。特に解決志向ブリーフセラピーの“技の磨き方”のポイントについてもお話をお聞きしました。そこで,次に黒沢先生の実践の原点であり,メインテーマであるスクールカウンセリングの“技”についてお聞きします。まずは,黒沢先生が大切にしているスクールカウンセリングのビジョンをお聞かせください。
スクールカウンセラーは,日本の公教育に1995年から導入されています。しかし,現在でも週1日勤務がベースになっています。週1日勤務では,十分な活動ができない面があると思います。文部科学省は,「チームとしての学校」を打ち出し,SCの常勤化も視野に入れもっと活動日を増やすビジョンを出しています。しかし,すぐに実現というわけにはいかないようです。
スクールカウンセリングでは,個別相談をしっかりできる技能が必要です。しかし,スクールカウンセリングはコミュニティ臨床です。そのため,個人相談以外に,コンサルテーション,心理教育,危機介入の技能も必要です。それから,システムに介入する技能も必要となります。子どもの心の教育や発達の支援は,スクールカウンセラーが一人で頑張ってもできることは限られます。ですので,学校というシステム,さらには学校だけでなく地域も含むシステムに関わるという発想をもち,支援システムを構築することに目を向けないといけません。
私たちは,これを5本柱と呼んでいます。①個別相談,②コンサルテーション,③心理教育,④危機介入,⑤システム構築です。スクールカウンセリングは,これらを学校のニーズや状況に応じてバランスよく実践していく仕事と思っています。5本柱を実践するためにブリーフセラピーの技能が必ずしも必要というわけではありません。しかし,ブリーフセラピーの“技”を身に着けていると,この5本柱に有効なかかわりができて便利だと思っています。

3.現場のニーズから活動を組み立てる
──スクールカウンセリングの5本柱は,コミュニティ臨床という観点からその重要性はよく理解できます。しかし,スクールカウンセリングの発展過程において,個人カウンセリングや心理療法を重視する派閥や伝統の影響を受けて個別相談に特化し,5本柱を軸とする活動に広がっていかない傾向があったと思います。その中で黒沢先生は,5本柱を意識してスクールカウンセリングを展開してこられました。それは,ブリーフセラピーの視点をもっていたことが大きかったのでしょうか?
いや,どうでしょうか(笑)。最近は黒沢といえばブリーフセラピーと言われたりしています。それで,このような企画もできるようになったわけです(笑)。しかし,以前は,ブリーフセラピストと言われることに抵抗があった時期がありました。私自身がブリーフセラピーを理解できてなかった時代があったからです。伝統的な心理療法を学んでいるときには,ブリーフセラピーは奇をてらっている印象をもったこともありました(笑)。
でも,私としては,臨床ありきで,現場でどう役立つかということでやってきました。ただし,それは,ブリーフセラピーなど,自分が好むモデルや方法があって,それをいかに現場に応用するかということではありません。ブリーフセラピーが先で,スクールカウンセリングの現場が後,としてとらえられるのは嫌で,「それは違う!」と思います。
たとえば,認知行動療法のモデルに基づいて「うつ予防プログラム」を作り,それを中学校に適用してやってみたという研究がありました。その前後で尺度をとって,プログラム実施によって「生徒はうつの知識を得ることができた(有意差有り)」といった研究となっていました。以前に日本心理臨床学会で,そのような研究のコメンテーターをさせていただいたことがありました。
発表者に「これは,先生と子どもにどのような状況があり,学校にどんなニーズがあって,このようなプログラムを実施したのか?」と尋ねたのですが,発表者は答えられませんでした。発表者の答えは,「ニーズに基づいて実施したのではなく,こちらの研究目的でやらせてもらった」というものでした。研究としては必要だとは思います。しかし,実践では,現場のニーズや状況に意識が行っていないといけないと思います。大変失礼かもしれませんが,「認知行動療法」をどのように現場に適用し,応用できるかという発想に立ってしまっていると感じ,その現場のニーズを後回しにしている発想をもっと疑ってみてほしいと思いました。

4.対話を通して学校にジョイニングする
──まずは現場のニーズがあり,それを受けてどのように現場で役立つ活動を組み立て,展開していくかが,何を置いても重要となるわけですね。この点に関して,先程の5本柱をどのようにスクールカウンセリングの実践の中に組み込んで行ったのかに関して,そのプロセスや経緯について教えてください。
現在のスクールカウンセラー制度が導入される以前の1980年代に,私は非常勤のスクールカウンセラーとして週に数日,学校に入っていました。そこでは,先生方からの相談を受けて,生徒のことについて話し合うことはしばしばありましたし,実施した心理テストのフィードバックなど,心理教育に相当することを日常的にしていました。スクールカウンセラーとして何をすればよいのかを管理職や養護教諭ともよく話し合い,教員の研修も行う機会がありました。また,命に関わる事件や事故もあり,緊急対応から危機後対応まで,病院臨床とは異なるコミュニティにおける危機介入も経験し,ノウハウを蓄積していきました。そのように自然発生的に5柱の全てをやっていました。
1995年に文部省(当時)のスクールカウンセラー活用調査研究委託事業があったときは,私としては,5本柱の全てを大切であると思っていました。しかし,同時に自然発生的な動きを無視して,私はこうやるという専門家中心主義はいけないと考えました。それで,当時は,コミュニティ心理学に理解あるスクールカウンセラーの皆様と一緒に,ゆるゆると学校にジョイニングしていくという発想で入っていきました。「心理教育,コンサルテーションやります!」ではなく,「何をすればよろしいでしょうか?」という入り方でした。
──“御用聞き”のスタンスで現場に入っていったということですね。
そうそう。ただ,私がスクールカウンセラーとして入った公立の学校は,教頭先生がはっきりとした考えをお持ちの方でした。「教育相談は大切だと思う。しかし,守秘義務で周囲から切り離された相談室を作ったとしてもうまくいかないと思う」と明確に意見を出されました。「おっしゃる通り!」と思いました。私も,相談室に来談したケースだけを狭義の守秘義務の下で抱え込んでいても学校の中で役に立つわけがないと思っていました。ですので,教頭先生とは意気投合しました。
──学校に行くと,予期せぬ出来事がいろいろと起こるわけですね。そこにあるニーズに対応していくと,5本柱を意識的にやろうと思っていなくても,やらざるを得なくなってくるということでしょうか。ただ,教員には,さまざまな意見をお持ちの方もおられたのではなかと思います。学校というコミュニティには,要因があり過ぎて対応できないということもあるかと思います。伝統的な心理療法の考え方を大切にする心理職の中には,関連要因が多すぎる学校現場で心の内面の作業に集中するために,面接室以外の事柄には関わらず,守秘義務ということで面接室内の情報を統制して対応するというスタンスのスクールカウンセラーもおられたかと思います。
以前には,そちらの伝統的な考え方が主流でした(笑)。
──そのような伝統的な活動の仕方を踏襲せずに,自分たちのスクールカウンセリングの活動を作っていこうとなったのは,現場での対話を重視し,現場のニーズを大切にするというスタンスがあったからでしょうか?
そうですね。初めに臨床トレーニングを受けた,学部から大学院時代に通っていた精神科の病院は,新進気鋭の精神科医の登竜門のようなところで,闇鍋食べながら医局で議論するような風土でした。そこで,何でもありということを学びました。オリエンテーションの異なる医師同士が意見をぶつけ合っていましたし,ベテラン看護師さんが,患者さんをよく理解していて,患者さんのためなら医師に意見することも厭わない気概を持ち,一生懸命コーディネートして病棟の活動を回していて,本当に多くを学びました。

5.システムを構築する“技”の進め方
──病院における医師や看護師と一緒に議論をすることを通して現場で活動を創っていく“技”を体験的に知っていたのですね。だからこそ,学校でも,伝統に囚われずに現実のニーズに即してスクールカウンセリングの活動を展開できたということですね。現場の動きを見るという点では,5本柱の最後にあるシステム構築の技能が視野に入っていたということかと思いますが,いかがでしょうか。
多分私あまり優等生じゃないのだと思います(笑)。何かの勉強を疑わずに邁進するよりも,「本当にそれしかないの?」「それ,本当に正しいの?」と思っているところがあります。それは,私の大学の恩師が霜山徳爾先生だったということもあるかもしれません。多くの優秀な教え子を戦争で失ったことを常に悔いておられ,戦後すぐにドイツに国費留学されたりしている先生で,劇的な価値観の変遷を,身をもって経験しておられました。アウシュビッツの強制収容所を生き延びた精神科医フランクルの『夜と霧』を翻訳出版されたことでも著名です。自分たちが先生から教わったのは,「Specialistになるな! Generalistになれ!」ということでした。
視野の狭い専門家になったら,クライエントが見えなくなるということでした。王道に乗るだけでは見えないものがあるという考え方でした。「いろいろな価値観があってよい」,「付和雷同するな」,「とにかく目の前のクライエントを見よ」とすごく言われました。なので,まずそれが染み付いているというところがあると思います。個人の内面を見る目だけでなく,そこにある関係性や状況を俯瞰的に見て,どうすることが,役割の異なる個々のメンバーを活かし,良い状況を継続的・持続的に作っていけるか,それがひいては個人の内面にも影響してくるという発想を持つことですね。
それがシステム作りにつながります。
──今回のテーマは,心理職としての“技”の磨き方です。しかし,霜山徳爾先生の伝えられていた「反骨精神」のような態度は,今の若い心理職に通じるのかと思ったりします(苦笑)。しかし,考えてみると,心理職の仕事は決して世の中の王道の活動ではないですね。むしろ,世の中で正しいと言われている秩序やシステムに乗らないからこそ,問題が起きてくるわけです。システムに合致しないから困ることも起きるし,困難も生じる。心理職は,その中で問題を解決し,生きていくのを支援することが課題とするならば,世の中のシステムと違う視点や価値観をもつことも大切だと思います。固まっている考え方やシステムを変えていく「反骨精神」も重要となると思います。学校は非常にオーソドックスで,世の中の秩序を体現するような場所ですね。そう考えると,反骨精神を持ちつつ,秩序を重視する学校にどのように入っていくかが,スクールカウンセラーの難しいところだと思います。職員室でじっと座って学校の秩序に従っていればよいのではないし,逆に反骨精神を発揮して秩序を壊しても困りますね。その辺りの塩梅をどう考えていくかが,スクールカウンセラーの“技”の磨き方に関わってくるように思います。
そうですね。付和雷同せず,かといって抗うのでもなく,個人で何とかしようとするのではなく,システムで動かせるようにするという視点です。どうやったらシステムの良循環につなげていけるか,です。家族療法やブリーフセラピーでもジョイニングが8割という言い方をします。うまく組織のお仲間に入れていただいて,うまく宿れたら,そこで初めて有用な活動がやっていけるということです。ジョイニングできれば8割まではうまくいくので,残りの2割はジョイニング後にやればよいということだと思います。

6.“Pace and Lead” & “One behind Lead”
──まずはジョイニングして,次に様子を見ながらニーズに即してシステムを構築していくということですね。
ええ。あとは“pace and lead”という考え方もあります。催眠から来ている技法です。相手のペースに合わせるペーシングができているときに,こちらが一歩リードすると,相手はついてきてくれるという技法です。ミルトン・エリクソンがやっている技法で,本当にいい形でシンクロできていればこちらの動き,いわば波に乗ってきてくれるということです。その考え方も発想の中にはあります。
──なるほど。先生がスクールカウンセリングで用いている考え方をお聞きしてシステム構築の“技”を教えていただいたと感じました。私などは,古い個人心理療法の考え方を叩き込まれているので,知らず知らずにその発想から抜け出せずにいたことに気づきました。スクールカウンセラーとして働くうえでは,個人療法の発想を抜けて,ジョイニングで学校コミュニティに入り,さらにペーシングしながら,少しずつ新しいシステムを構築し,コミュニティを変えていくという“技”があるのですね。
解決志向ブリーフセラピーでは,“one behind lead”という考え方もあります。これは,一歩下がってリードするという意味ですから,矛盾した言葉ですよね。普通,リードは先に立ってするのですが,この場合は後ろからするというわけです。“one behind lead”は,セラピストのスタンスと言われています。
──ジョイニングもbehindですね。
“one behind lead”を技法として使いこなすためには,先を見通せていないといけません。「クライエントの望む姿が手に入る方向に行くのがよい。でも,この人がそのことがわかるようになるために,どのように一歩後ろから,質問するのがよいか」を考えることができためには,先を見通せていないといけないわけです。クライエントさんが「こういうことなのですね」と自分で気づくところに,どのようにもっていくかですね。

7.先を見通して“技”を使う
──そこは,難しいところですね。精神分析では個人の内的世界,認知行動療法では個人の認知の偏りや行動パターンとして問題を見立てます。それに対してコミュニティ臨床としてのスクールカウンセリングでは,個人だけでなく,全体のシステムを見渡せていないといけませんね。その視野の広さが必要だと思います。このような視野の広さ,つまり全体のシステムを見渡せる“技”は,どのように磨けばよいのでしょうか。視野の広いセラピストというのは,あまりいないと思います。どうも,心理職は視野が狭いので,内輪で喧嘩ばかりしています(笑)。そのような内輪喧嘩を避けるためにも,心理職はどのようにして視野の広さを身につけることができるでしょうか。
そうですね。それは,「自分はなぜそこにいるか」ということと関わっています。もちろん「このクライエントさんの治療をするためにいる」ということにはなります。しかし,それだけだと,視野が狭くなります。「このクライエントさんはどのように生きているのか?」「家族や学校や職場はどうなのか?」「その中でどのように生活しているのか?」「どうなっていくのが,この人にとってよい生き方となるのだろうか?」「どのように生きたいのか」という視点から,「自分はなぜそこにいるか」を考えてみます。認知への介入をするとしたら,そのような視点との関連で「認知への介入はどういうことなのか」を考えます。それは,エコシステミックな見方ということになります。
──視野を広げるためには,家族,学校,職場という生活の場でどのように生きているのかという視点を持つことが重要になるわけですね。スクールカウンセリングでは,主な対象となる生徒は,学校という場で生活しています。そのような場で生活をしているクライエントさんという視点から,どのようにサポートしていくかを考えるということですね。生活をしっかりと見ていくと,確かに視野が広がります。
学校では,スクールカウンセラーは主人公でも何でもありません。スクールカウンセラーのお手柄って作っても何の役にも立たない。先生のお手柄,子どもたちのお手柄にするためにどう動いたらいいのかを考えるのが大切です。個別面接も,自分の心理的な見方や技法でその人が治療されていくだけの仕事ではありません。この人をどう理解すればクラスや教員との関係の中でいい状態に持っていけるか,そこからこの人は何を得てどのように成長していくかという,先を見通した視点が大切です。過去,現在がどうであるかだけでなく,望む状態や未来のありたい姿を見通すこと,児童生徒,教員,友人,保護者,クラス,学年,部活,学校,地域と,広く関係性や影響を見渡すこと,これら縦横の視点を柔軟に広げてもつことです。
教員に対しても,「この人をどうすべきか」ではなく,「どうすることで教員がより良い関わりができるようになるのか」という視点が大切となります。今,教員と特定の生徒のことを話しているとします。その場合,「教員が今後その子と似たような生徒に会ったときにも,上手に対応できるようになるためには,自分はどのように関わっていくのがよいのか」「先生が一定の自信を持ち自身で判断できるようになるにはどうしたらよいか」「自分でそれに気づいていただくためには何をすればよいのか」と考えます。
──伝統的な心理療法の技法を学んできた心理職がそのようなエコシステミックな考え方ができるようになるのは,意外と難しいと思います。個人心理療法では満たされていた心理職のナルシズムが満たされなくなるからです。少なくとも学校コミュニティでは,心理職は中心に居る存在ではなくなります。
そもそも心理職が中心になれる領域があると思うこと自体,心理職が何をする仕事なのかが理解できていないということではないでしょうか。先ほども話題になりましたが,心理職の仕事は決して世の中の王道の活動ではない側面があるからこそ,良い働きができるという逆説があるように思います。私はよくスクールカウンセラーのスーパーバイズをするときに,表のキーパーソンと裏のキーパーソンを見極めよ,と指令を出します。裏のキーパーソンがシステムを動かしているからです。
またスクールカウンセラーを黒子に例えることがあります。黒子は舞台上にいることをみんなわかっているけど,見えないことになっているのです。黒子の仕事が悪ければ,舞台はめちゃくちゃにもなりますよ。

8.ICT活用のスクールカウンセリングの可能性
──最後にコロナ禍におけるスクールカウンセラーのあり方についてお話をお聞きしたい。学校では,子どもも教員も不安になっています。そのような状況においてスクールカウンセラーは何ができるかということで,ある校長先生のご意見を伺いました。その校長先生は,「コロナ禍の状況は,日々変化している。その変化に対応して,学校は日々対策を考えて動いている。ところが,スクールカウンセラーは週1日しか来ない。そのため,スクールカウンセラーが来る度に,学校の状況や対策について説明をしなければならず,むしろ負担になっている。それで,県からスクールカウンセラーの増員を打診されたがお断りした」と延べていました。そのような意見を聞くと,スクールカウンセラーとしては何をすればよいのかと思います。現在,ギガスクール構想が実現に向けて動いています。そのような中で,週1日しか学校に入ることができないハンディを補うために,スクールは積極的にICTを用いた心理支援を展開してもよいのではないかと思ったりしています。この点についてのご意見を教えてください。
私は,コロナ禍で児童生徒の登校がままならなかった時期に,先生方と協力し,Zoomを用いてオンラインで配信をしました。生徒に向けてだけでなく,保護者に向けても配信をしていました。心理教育を何バージョンもやりました。生徒対象では,たとえば先生方のアイデアで「未来を始めるプロジェクト」といったシリーズ配信にスクールカウンセラーも加わったりしました。保護者対象では,「お母さんもご主人も子どもも皆で家にいて嫌になっちゃいますよね」とジョイニングしつつ,思春期の子どもの気持ちの理解と対応などのテーマを忍ばせながら,保護者に安心していただけるように配慮して,「情報が変わるので,何が正しいかもわからない。だから,自分なりの,そのときのベストを尽くしていると思いましょう」とか「ベストなことができていないという不安やイライラから自分や周りを責める気持ちもそっと認めてあげましょう」といった話を,その時に応じて同時双方向であったり,録画撮りをしたりして配信をしました。それで保護者から,その時の自分の気持ちにピンポイントで入ってきて,自分を取り戻せたとか救われたといったお手紙をいただいたりしました。
これまでは,メディアを利用した活動はあまり実施してきませんでした。しかし,これを機会にICTは可能性があると感じました。教員研修は,以前は対面でやっていました。しかし,コロナ禍への対応で忙しくて参加できない先生方もいた。それで,生徒指導や子どものケアというテーマでは,オンラインで限定配信もしました。これを機会に,コロナ禍でなくても,オンラインでの教員研修があってもよいと思いました。
──オンラインでの心理支援は,コロナ禍対策として苦し紛れでスタートしたという面はありました。しかし,実施してみると,いろいろな可能性も見えてきたように思います。ICTを用いることのマイナス面だけでなく,プラスの側面もみて,スクールカウンセリングにおいてもメディアを積極的に活用するという発想の転換が必要となっていると思いますが,どうでしょうか?
私は,もともとアナログ人間でICTは苦手でした。しかし,コロナ禍に対応する大学の仕事もあって,オンラインなどICTを使うことを否が応でもやることになりました。言われてみると,スクールカウンセリングのほうがオンラインやICTを活用する余地がたくさんありますね。現実に交流できない対面での相手がいない所でお話をするのに抵抗があるカウンセラーもおられるかもしれません。でも,今後は,ICTを使いこなすスキルを身に付け,オンラインで伝える役割を担っていかないと,スクールカウンセラーの役に立つ範囲が限られてしまうと思います。ICTが得意な方とチームを組めると,学校の資源の再発見になったりして,また関係性が広がります。
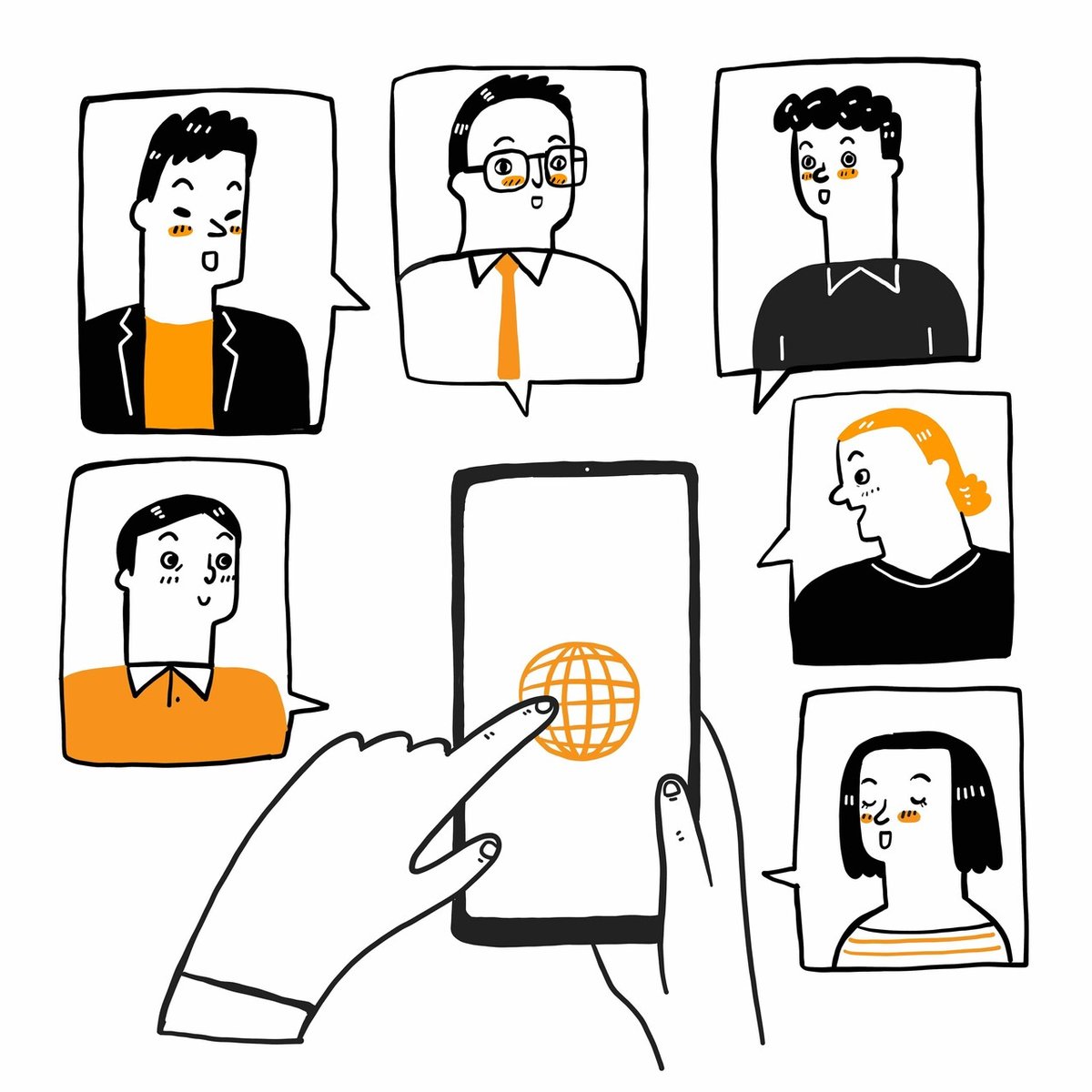
(電子マガジン「臨床心理iNEXT」13号目次に戻る)
====
〈iNEXTは,臨床心理支援にたずわるすべての人を応援しています〉
Copyright(C)臨床心理iNEXT (https://cpnext.pro/)
電子マガジン「臨床心理iNEXT」は,臨床心理職のための新しいサービス臨床心理iNEXTの広報誌です。
ご購読いただける方は,ぜひ会員になっていただけると嬉しいです。
会員の方にはメールマガジンをお送りします。
臨床心理マガジン iNEXT 第13号
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.13
◇編集長・発行人:下山晴彦
◇編集サポート:株式会社 遠見書房
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
