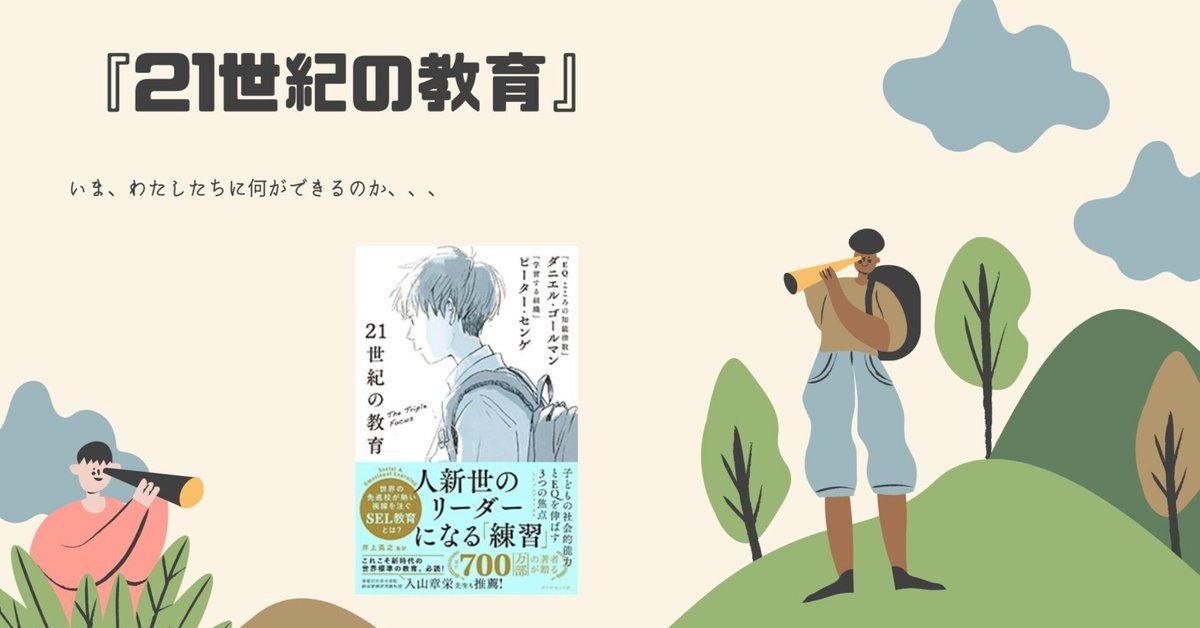
いま、わたしたちに何ができるのか、、、 vol.393
最近、巷で有名なこの本を手に取りました。
翻訳や監修は異なるとはいえ、あの有名な『EQ こころの知能指数』と『学習する組織』を書いた二人が書いた本になります。
この2冊はどちらかというと、哲学書に近いものなのでレベルは高いのですが、もしそちらを手に取れなくても、十二分にこの本を読む価値はあります。
というよりも、読んで欲しい人が見えてくる本、そっと心を押してくれる本、アンチテーゼを投げかける本、そう言った感じでしょうか。
私にとっては、やっぱりダメか、、、とも感じてしまいました笑。
SELを主軸に

この本の主軸にはSEL(Social Emotional Learning)があります。
SELについては、何度かこのnoteでもまとめているので、ぜひ読み返していただけたらと思います。
自己との対話、他者との協働、社会の中の自分、この3つを認知した時に、自分の思考をどのようにコントロールしていくか、そしてどのように行動していくか。
これがSELの目指すところでしょう。
最近ではよく目にも耳にもするものたちです。
土の時代、風の時代とか、イノベーションとか、さまざまな言い方で表現されているので、SELに馴染みのない方でも、読めばなんとなく、「ああ、これがSELってやつね」と理解できるかと思います。
本の内容はよかったですし、このような本が書店でしかも大々的に取り上げられていることに嬉しさは感じるのですが、読んで私に起きた感情は、悲しみと怒りと虚しさと、、、ってところでした。
組織としての変革

事例や一人ひとりの気持ちの持ち方、人との接し方など、納得できる部分は数多くありましたが、ネックとなるのは管理職や学校という組織。
ここが変わっていかないことには、やはりどうしようもないのかとマジマジと言われているような感覚に陥りました。
極論、そこすらもなんとかせぇと言われればそれまでなのですが、、、。
おあずけを食らってる感が強い本でした笑。
こんなにいいものがあるんだよ!
ほら、こんな結果になったんだよ!
すごいよね、やっぱりいいよね、こういう教育。
みんなもやっていこうよ!
あっ、でも上や組織が動かないと難しいよ。
といった流れ笑。
おいおいおい、そこまで行ってそこは投げやりかーいという印象です笑。
だからこそ、この本を幅広い人に読んでもらうという形で世の中に出したんでしょう。
個人として受け取ったメッセージはやはり、頭を悩ませるものです。
とりあえずやっていこうよ

ま、でも、それはさておきなんです。
今の私にとっては、正直組織はどうでもいいもの笑。
個人でできることもたくさんあるなと感じています。
例えば、朝の静かな時間を意図的に作り出す。
面談の時に、カウンセリング、コーチング、ティーチングを意識する。
社会性を意識して生徒を観る。
授業の中で実践していく。
やろうと思えばできることはたくさんあります。
いきなり大きなこと(組織を動かすこと)はしなくてもいい。
小さなことを積み重ねるから、大きなものへと行き着く。
あれ、でもやっぱりこれは一人じゃダメですね笑。
SELのスタート、自己との対話までしか行きつけていない。
やはり、次のステップは協働か、、、。
誰か、何か一緒にやってみませんか〜笑?
と、投げかけてみようかな。
