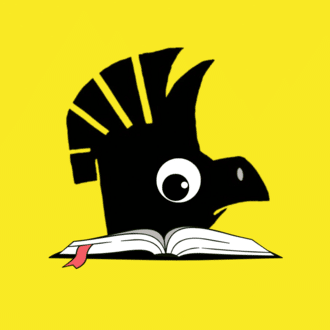ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」(第十九章)
NFTアートは、全く価値がなさそうなものに価値がつくという不思議なもの、という印象が強い。
NFTアートとして売られているものも様々だが、画像と動画にしぼって考えると、本質はメディアアートだ。
メディアアートを理解することは、NFTアートを理解することにもつながると思い、東京藝術大学の「メディア芸術史」の授業でテキストとして使用されている、ベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」という論考を読み始めた。
「複製技術時代の芸術作品」が収録されている本は様々あるが、解説付きのがほうが分かりやすいと思い『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』を使用している。
政治の芸術化(第十九章)
ついに最終章となった。
以下まとめとなる。
・プロレタリア大衆は、所有関係の廃絶をめざす
・ファシズムは、所有関係には手をふれず、大衆を組織しようとしている
・大衆に権利ではなく、表現の機会を与えることを好都合とみなす
・政治生活の耽美主義に行き着き、以下の伝統が政治の中に入り込む
・ダンヌンツィオとともにデカダンスが
・マリネッティとともに未来主義が
・ヒトラーとともにシュヴァービング(ミュンヘンの芸術家居住区)が
・戦争は、政治の耽美主義を目指す努力が、頂点に達したもの
・政治面:戦争だけが在来の所有関係を保持し、最大規模の大衆運動に一つの目標を与える
・技術面:所有関係を維持し、技術手段の総体を動員することができる
・弁償法的な思想家の目にうつる現代の戦争の美学
・生産力を利用することは、所有の秩序に邪魔される→増大する技術力は戦争に使われる
・帝国主義戦争は技術の反乱
・巨大な生産手段と、生産過程においての生産手段の不完全な利用の間の矛盾
・いいかえると、失業と販路不足
・人類の自己疎外感は、自身の滅亡を美的な享楽として体験できるほど
・コミュニズムはこれに対して、芸術の政治化を持って答えるだろう
※ 耽美主義:道徳功利性を廃して美の享受・形成に最高の価値を置く西欧の芸術思潮
※ ダンヌンツィオ:イタリアの詩人、作家、劇作家で、ファシスト運動の先駆とも言える政治的活動を行った
※ デカダンス:退廃的なこと。文化史上で、19世紀末に既成のキリスト教的価値観に懐疑的で、芸術至上主義的な立場の一派
※ マリネッティ:イタリアの詩人、作家、批評家、未来派のオーガナイザー
※ 未来主義:20世紀初頭、イタリアでおこった芸術運動で、伝統的な文化、懐古的な趣味と対立し、急速に進歩しつつあった機械を積極的に芸術に取り入れ、まったく新しい美学を打ち立てようとした
※ 弁証法:対立する物事から新しい見識を見いだす方法
まとめはこの記事がわかりやすい
特に記事内の、
礼拝的価値の基盤を失った芸術が「芸術であること」そのものに根拠を求めて宗教から政治に軸を移していく事態も引き起こす。その結果、映画を用いて「芸術のための芸術」への礼拝的価値を作り、政治の芸術化によって人々を戦争へと導くファシズムが生まれるのであった。
という箇所が、本書を読んでいて不明だった点をよくまとめられていると思う。
芸術のための芸術をもとめる→政治に軸をうつす→ファシズム誕生
という流れだ。
本書を読んでの課題
展示的価値が増してきた歴史的背景や、そこで生まれる遊戯空間に興味があるが、遊戯空間とは具体的にどんなものなのか、また、ベンヤミンの時代と現代を比較分析すると、メディアといったものがどのような変質を遂げているかを今後学んでいきたいと思う。
それにしても難しい本だった。
ドイツ語の原著でも難しい本らしく、わざわざ別のドイツ語に言い換えなければ意味がとりづらいとのことだ。
日本語訳はいくつか出ているので、別の人の訳を読んで、さらに理解を深めたいと思う。
いいなと思ったら応援しよう!